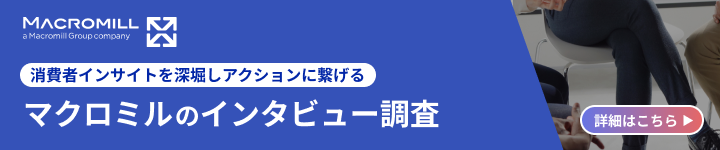定量調査と定性調査、どちらを選ぶべきか、どう組み合わせれば効果的かの判断が難しい場合もあるでしょう。この記事では、それぞれの特徴や、メリット・デメリット、代表的な手法から効果的な組み合わせ方までを解説します。
この2つの調査をうまく使い分けることで、詳しい情報と数字で示せる確かなデータの両方を基に、より良い判断ができるようになります。貴社のビジネスにおける調査の精度を高め、確かな成果につなげるための参考にしてください。
参考:定性調査とは?基本から定量調査との違いや比較・メリット・手法まで解説
- 定量調査とは?
- 定量調査のメリット
- 定量調査のデメリット
- 定量調査のおもな手法
- 定性調査とは?
- 定性調査のメリット
- 定性調査のデメリット
- 定性調査のおもな手法
- 定量調査と定性調査の違いは?
- 定量調査と定性調査の組み合わせが生む相乗効果
- 定量調査と定性調査を組み合わせる方法
- まとめ
定量調査とは?
定量調査とは、認知度や購入率、満足度といった具体的な数値を収集し、分析する手法です。回答結果が数値で示されるため客観的に理解しやすく、時系列比較などの統計的処理に適しています。信頼性のあるデータを得るには、充分なサンプル数が必要です。
定量調査のおもな目的には、市場の実態(例:商品イメージ)を把握する「実態調査」や、立てた仮説を検証する「仮説検証」があり、これらは同時に行われることもあります。
定量調査のメリット
定量調査には、ビジネスを推進する上で利点があります。おもなメリットは次の3つです。
迅速かつ低コストで実施可能
定量調査のおもな手法であるWebアンケートは費用を抑えつつ、オンラインで回答を迅速に集められます。場所を選ばず回答可能で、データも早期に把握できるのが特長です。
数値データで集計・分析が容易
定量調査は数値で表されるデータのため、集計のブレを抑え、分析がしやすくなります。そのため、誰が見ても解釈のズレが起きにくく、共通認識を得やすいのが特長です。
客観的なデータで説得力向上
定量調査では、仮説や実態を具体的な数値で示すことで、客観的な根拠に基づき、誰にでも理解しやすく説得力の高い調査結果を提示できるメリットがあります。
定量調査のデメリット
定量調査は客観的なデータを得られる一方で、いくつかのデメリットもあります。
質問以上の深掘りは難しい
アンケートは事前に用意された設問への回答が基本です。そのため、会話形式のインタビューとは異なり、個々の回答の背景や理由を詳しく追求したり、想定外の新たな情報を引き出したりするのは難しい手法です。
数値の読解力がなければ生かせない
調査で明確な数値が出ても、読み解く力がなければその価値を充分に引き出せません。数値をどう解釈し戦略に活用するか。その力がなければ、データを意思決定に生かせません。
定量調査のおもな手法
定量調査でデータを集める際には、さまざまな手法が用いられます。そのなかでも代表的な5つの手法について解説します。
ネットリサーチ(Webアンケート)
ネットリサーチ(Webアンケート)とはインターネットを介し、調査対象者へオンラインで質問票を配信、回答を収集する調査手法です。時間や場所を選ばず、広範囲の対象者から効率的にデータを集められるのが特徴です。
会場調査(CLT)
会場調査(CLT)とは、特定の会場へ対象者に来訪してもらう調査を指します。製品試用や広告視聴といった体験を経た後、その評価や感想を直接集めてデータ化する調査手法です。
ホームユーステスト(HUT)
ホームユーステスト(HUT)とは対象者に試作品などを自宅へ送り、一定期間使用後のリアルな評価を集める調査を指します。化粧品や健康食品など、継続利用してはじめて良さがわかる商品の評価に最適です。
郵送調査
質問票を調査対象者へ郵送し、回答を記入後に返送してもらうことで情報を収集する方式です。紙ベースのアンケートを用い、広範囲の人々から直接的な意見や実態データを集めるための伝統的な調査手段として知られています。
電話調査
調査員が対象者へ電話で直接話を伺いながら質問を進めます。口頭で回答をしてもらい、その場で詳細に記録し、必要なデータを集めていく調査手法です。
定性調査とは?
定性調査とは、対象者と直接対話(インタビューやグループディスカッションなど)を重ねることで、個々の意見や行動の背景にある深層心理、言葉では表現しきれない感情やニーズを深く探る手法です。
数値データでは捉えにくい「なぜそう思うのか」「何を感じているのか」といった質的な情報を収集します。
定性調査から得られるのは、消費者の生の声に基づいた「消費者理解」の深化、製品やサービス改善のための「具体的なヒント」、そして「新たな仮説の発見」です。これにより、企業は消費者が自覚していない潜在的なニーズを掘り起こしたり、自社ブランドのイメージをより正確に把握したりすることが可能になります。
定性調査のメリット
定性調査は、対象者の言葉や行動の奥にある本音や理由、そしてその背景まで深く理解できる手法です。おもなメリットは3つあります。
生の声・反応から本音を把握
インタビューや行動観察では、消費者の「生の声」や「反応」に直接触れることができます。新商品などに対する飾らない第一印象、ふとした言葉や行動といった、その場で生まれるリアルな情報から、アンケートだけでは見えない本音やニーズを理解できるでしょう。
数値化できない「なぜ」を深掘り
人の行動の「なぜ?」を深掘りできます。定性調査は、数値化できない個人の本音や価値観、動機といった深層心理を解き明かし、行動の背景にある本質を理解する手法です。
行動や思考の「背景・プロセス」を理解
時間をかけた丁寧な追跡で、個人の行動や心理の変遷を把握できます。なぜロイヤルカスタマーになったのか、あるいは離脱したのか、その「背景・プロセス」を解明し、ブランド戦略に生かします。
定性調査のデメリット
定性調査は深い洞察をもたらしますが、実施にはいくつかの課題も伴います。ここではおもなデメリットとして、以下3つの点が挙げられます。
対象者選びの難しさ
定性調査の成否は、適切な参加者を見つけられるかに懸かっています。有益な情報や意見を豊富に持つ人物かどうかは、実際に話を聞くまで不明です。そのため、的確なペルソナの設計と、それに合致する人を探し出す作業は、専門的な知見と経験が求められます。
費用と時間の負担増
調査データの種類や目的に応じた手法選択が前提ですが、費用面では注意が必要です。特に定性調査は、対象者1人あたりに要する時間とコストが大きくなりがちで、結果として全体の負担が増加します。
インタビュアーの技量への依存
インタビューの熱量や、対象者が本音を話しやすい雰囲気は、インタビュアーの技量に大きく左右されます。この属人的な要素への依存は、調査の質を安定させる上での課題です。
定性調査のおもな手法
定性調査には、対象者の深層心理や実態を明らかにするさまざまなアプローチがあります。
以下で、おもな手法をいくつか紹介します。
グループインタビュー(FGI)
グループインタビュー(FGI)とは、司会者(モデレーター)の進行の下、特定のテーマに関心を持つ複数の参加者を集め、座談会形式で意見や情報を収集する調査手法です。参加者同士の対話を通じて課題を深掘りしたり、仮説検証したりするのに役立ち、GIやグルインとも呼ばれます。
デプスインタビュー(DI)
デプスインタビュー(DI)は、選定した1名の調査対象者とモデレーターが1対1で対話し、特定のテーマについて意見や深層心理を徹底的に掘り下げる定性調査手法です。近年はビデオ通話などを活用したオンラインでの実施も一般化しています。
行動観察調査(エスノグラフィー)
行動観察調査(エスノグラフィー)は、対象者の生活の場に身を置き、その行動を注意深く見つめる行動観察調査の手法です。自宅訪問や買い物同行などを通じて、言葉にしにくい無意識のニーズや習慣を捉え、記録・分析します。
訪問調査(ホームビジット)
訪問調査(ホームビジット)はエスノグラフィーの一環で、対象者の家庭を訪問して調査します。製品が実際の生活空間でどのように利用され、どのような環境にあるかを観察する手法です。
定量調査と定性調査の違いは?
定量調査と定性調査は、目的や得たい情報に応じて使い分けられます。それぞれの調査がどのような役割を担うのか、そして調査を始める前に明確にすべき点について解説します。
定量調査は「仮説検証」で定性調査は「本音や背景の深掘り」
定量調査は仮説を数値データで検証し現状を把握するのに適した手法です。一方、定性調査は消費者の言葉や行動から本音や背景を深掘りし、隠れたニーズや新アイデアの発見につなげます。
調査目的と対象者の明確化
調査を成功させる第一歩は、「何を明らかにしたいのか」「それによって何を達成したいのか」という最終ゴールを定めることです。この目的が明確であれば、そこから逆算し、どのような情報を、誰から集めるべきか(対象者)が自ずと見えてきます。
定量調査と定性調査の組み合わせが生む相乗効果
定性調査で消費者の「なぜ」という深層心理やニーズの仮説を捉え、その仮説が「どれだけ」一般化できるかを定量調査で数値をもって検証します。このように両者を組み合わせることで、個々の手法では得られない深い洞察と客観的根拠が生まれ、戦略の質を飛躍的に高める相乗効果を発揮します。
定量調査と定性調査を組み合わせる方法
定量調査と定性調査を効果的に組み合わせるには、おもに2つの方法があります。以下で、それぞれのパターンを解説します。
定量データで課題を特定後に定性調査で原因を深掘り
定量調査で数値から課題を特定した後は、その背景にある「なぜ」を解明すべく定性調査を行います。インタビューで消費者の選択理由や潜在ニーズを深掘りすることで、仮説をより確かにして、商品の具体的な改善策や、新たな企画の種となるインサイト獲得につなげましょう
定性調査で得た仮説を定量調査で検証・一般化
たとえば、調査者と消費者のズレを防ぐため、まず定性調査で自社製品の「味が濃すぎる?」などの仮説の種を深掘りします。そこから得た消費者の実感に基づく仮説を定量調査で検証・一般化することで、より実態に即した精度の高いデータ収集が可能になります。
まとめ
定量調査と定性調査を使い分け、場合により組み合わせることで、より深く客観的なデータに基づいた意思決定が可能です。「課題を特定したい」「消費者の本音を深く知りたい」「集めたデータをどう活用すれば?」といったお悩みはありませんか?
マクロミルは、多様な調査手法(オンライン・オフライン・海外)とデータ分析、戦略立案のコンサルティングまで、貴社のマーケティング課題解決を一気通貫でサポートします。まずはお気軽に資料ダウンロード、またはお問い合わせください。貴社の課題解決に向けた最適な一歩をご提案します。