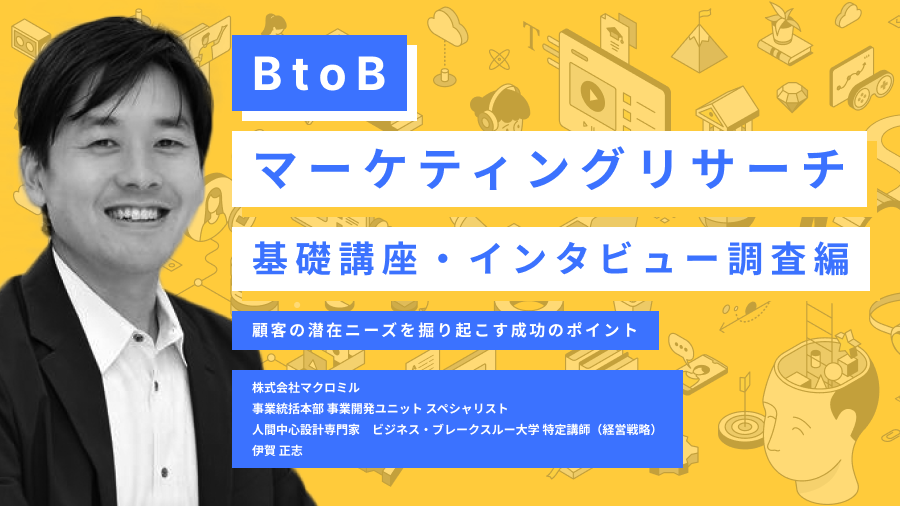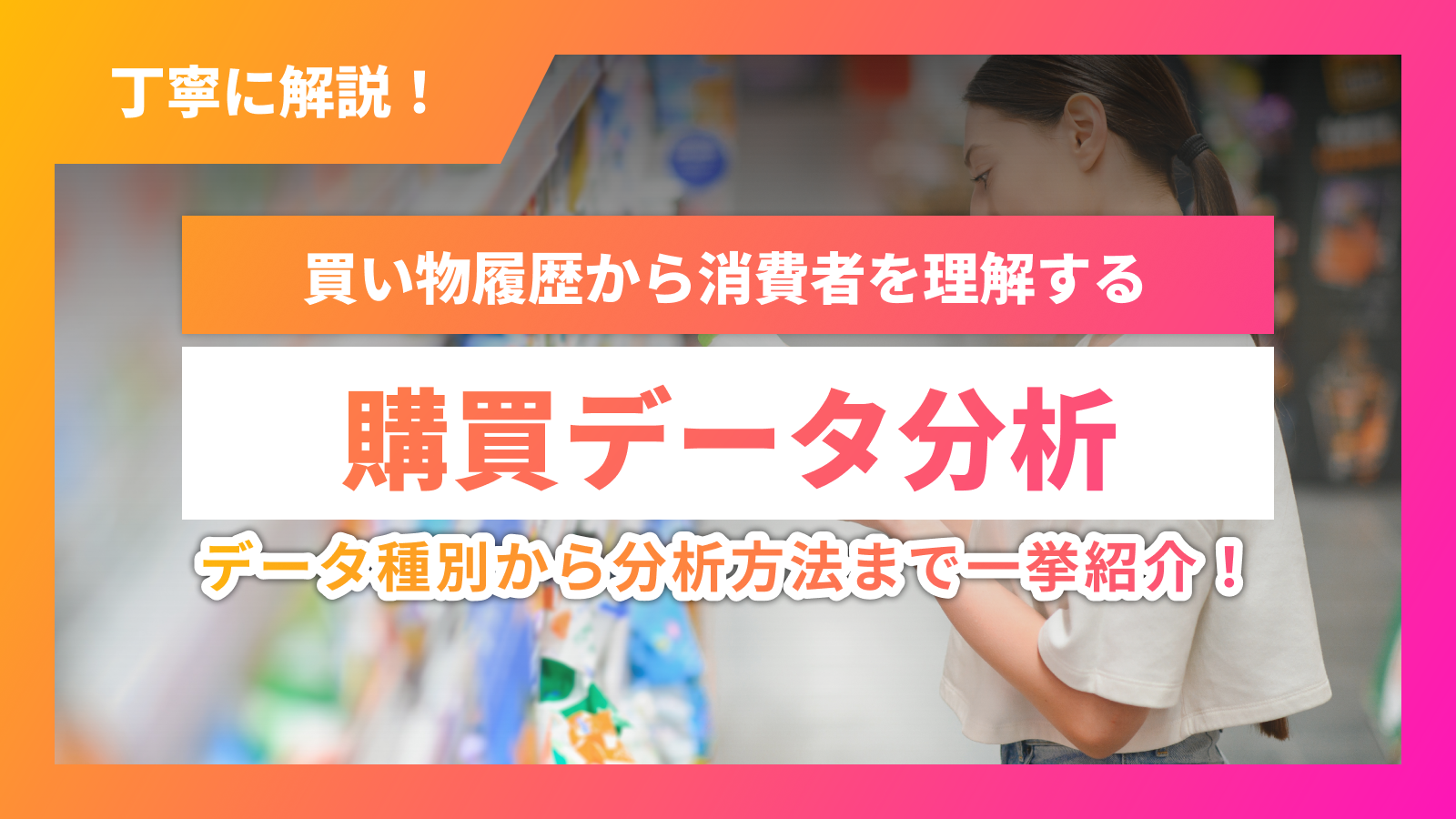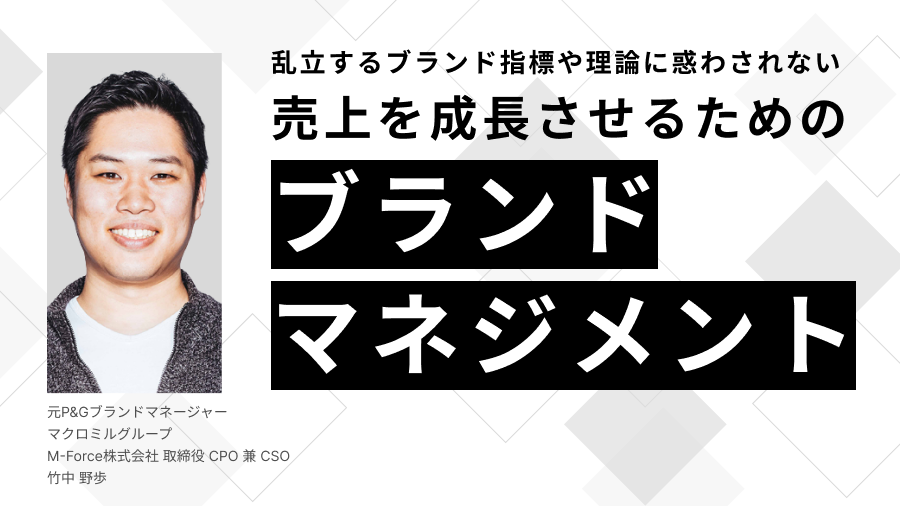スマートフォンアプリやSNS、各種Webサービスを運営するにあたって、どれだけのユーザーが継続的に利用しているかを測る指標は事業判断の要となります。その中でも「MAU(Monthly Active Users)」は、最もよく使われる基準の一つです。
MAUが伸びているかどうかは、サービスがユーザーに魅力を感じてもらい、リピート利用されているかを反映します。事業者はMAUを追いかけることで、ユーザーエンゲージメントやブランド認知、マーケティング施策の効果を大局的に把握可能です。また、投資家やアナリストが企業価値を評価する際にもMAUが注目されるケースが増えています。
本稿では、MAUとは何か、なぜ重要視されるのか、具体的な算出方法や各種マーケティング指標との関係、さらにMAUを活かしたビジネス戦略の例などを解説します。SNSやアプリ運営に携わる方はもちろん、デジタルマーケティング領域全般でMAUを理解し、ユーザーとの関わり方を最適化するヒントにしていただければ幸いです。
MAUとは
基本的な定義
MAU(Monthly Active Users)は、1か月の間に1回以上サービスを利用したユーザー数を指す指標です。たとえば、SNSであれば1か月のうちに1回でもログインまたは投稿などのアクションを行ったユーザー、アプリであれば1回以上起動したユーザーをカウントします。
この数値が大きいほど、サービスへの定着度や利用頻度が高いと推測できますが、あくまで「その月に1回以上使った」程度の条件であり、使用実態を深くは表しきれないことも注意点です。
活用されるサービスの範囲
MAUはSNSやゲームアプリなどのコンシューマ向けサービスだけでなく、法人向けの業務アプリケーション、クラウドサービスなど幅広い領域で利用されています。どのようなサービスであっても、月単位の利用者数を把握すれば、活躍しているユーザー規模が一目で分かる利点があります。
MAUが注目される背景
SNS・アプリの急成長と継続利用の重要性
Facebook、Instagram、Twitter(X)、TikTokなど多くのSNSは、いかにユーザーを獲得し、継続的に使ってもらうかを競ってきました。その成長指標として、広告主や投資家に向けて公表する数字がMAUです。同様に、ゲームアプリや音楽ストリーミングサービスなどでも、「月間に何人が使っているか」がサービスの価値や人気度を端的に示す指標と位置づけられています。
新規ユーザー獲得コストの高騰
近年、広告単価の上昇や競合の激化により、新規ユーザー獲得(ユーザーアクイジション)の費用は増大傾向にあります。そのため「既存ユーザーをどれだけ継続利用に引き留められるか」が収益性のカギとなる場合が多く、MAUはその成果を可視化する指標として注目されているのです。
MAUの算出方法と関連指標
MAUの定義づけ(アクティブユーザーの条件)
MAUを算出するには、まず「アクティブユーザー」とは何を意味するのかを明確に決める必要があります。単にログインしただけでカウントするのか、何らかの操作(投稿、視聴、購入など)を行った場合に限定するのかはサービスごとに異なる設計です。
また、1人のユーザーが複数回利用しても、ユニークユーザーとして1回しかカウントしないよう注意する必要があります。
DAU・WAUとの比較
MAUとよく比較されるのが、DAU(Daily Active Users)やWAU(Weekly Active Users)です。
- DAU:1日にアクティブなユーザー数
- WAU:1週間の間にアクティブなユーザー数
- MAU:1か月の間にアクティブなユーザー数
DAUは「1日単位で何人のユーザーが利用しているか」、MAUは「1ヶ月単位で何人のユーザーが利用しているか」を示すため、ビジネスモデルによって重視すべき指標が異なります。SNSやメッセージアプリなど高頻度利用が期待される場合はDAUを重視し、低頻度でも継続利用が重要な場合はMAUが注目されることが多いです。
その他のエンゲージメント指標(セッション数、CVRなど)
MAU単体では「月内に1回使った」程度の利用状況しか分かりません。より詳細に利用状況や収益性を把握したい場合は、1回あたりのセッション時間やCVR(コンバージョン率)、課金率などの指標と組み合わせて分析する必要があります。
例えば、「MAUは多いが課金率が低いアプリ」は広告収入に頼るビジネスモデル、「MAUは少ないがCVRが高い」なら単価重視の高額課金ユーザーが多い、といった推察が可能です。
MAUがもたらすマーケティング上の意義
ユーザーエンゲージメントの指標
SNSやアプリの成功にとって、ユーザーが単に登録するだけではなく、実際に活発に使っているかが重要です。MAUが高いほど、ユーザーがサービスに魅力を感じ続けていると推測できます。
マーケティング施策としても、新機能リリースやキャンペーンを行ったあとにMAUが増えるかどうかを見ることで、施策の効果を定量的に評価しやすくなります。
LTVや課金率との相関
ユーザー1人あたりの生涯価値(LTV)は、ユーザーが長く使ってくれるほど高まります。MAUが増え続けると、既存ユーザーのうち離脱する人よりも使い続ける人が多いという意味で、LTVの平均値が上昇する可能性が高まります。また、MAUが増えれば、広告モデルの場合は広告インプレッションが増加し、課金モデルの場合は購買機会が増えるため、全体収益が伸びる傾向にあります。
広告モデル・サブスクモデルとの相性
MAUが特に重視されるのは、広告収益やサブスクリプションに依存するサービスです。広告収益型の場合は、アクティブユーザーが広告を見るため、MAUが増えるほど広告在庫が増大し、媒体価値が上がります。サブスク型の場合も、月ごとの課金者数が重要であり、MAUを維持・拡大していくことが売上の安定につながります。
MAUを伸ばす具体策
新規ユーザー獲得施策(キャンペーン・広告)
まずは新規ユーザーを増やすことがMAU向上の第一歩です。キャンペーン(無料体験、友達紹介特典など)やSNS広告、App Store/Google Playなどでのアプリ最適化(ASO)など、新規獲得に向けたマーケティング手法を強化して認知度を高めます。しかし、新規獲得を重視するあまり、定着施策を疎かにすると離脱率が高まってしまうため、バランスが大事です。
アプリやサイトのUX改善とリテンション強化
既存ユーザーが継続利用してくれるよう、UI/UXを定期的に改善し、使いやすさや楽しさ、便利さを向上させることが重要です。プッシュ通知やメルマガなどによって再訪を促すほか、ゲーミフィケーション要素(ポイント、ランキング、実績解除など)を取り入れて、ユーザーに継続利用の動機を与える戦略もあります。
アップセル・クロスセルによる活性化
MAUが増えれば、同時に売上も伸ばすチャンスが広がります。アップセル(上位プランへの切り替え)やクロスセル(関連サービスや商品をおすすめ)をうまく実施することで、ARPU = 1ユーザーあたりの収益を引き上げつつ、サービスの利便性や満足度が高まればMAUの増加にも相乗効果をもたらします。
ただし、過度なアップセルや広告表示がユーザー体験を損なわないよう注意が必要です。
事例から学ぶMAU活用
SNSプラットフォームのレポート
FacebookやTwitter(X)、SnapchatなどのSNSは、四半期ごとにMAUやDAUを公表するレポートを出しています。株式市場や広告主は、これらの数字をもとに「どれだけサービスが成長しているか」「広告出稿の価値はあるか」を判断するのです。例えば、FacebookがMAUの伸び悩みを発表すると、株価に影響が出ることもよく知られています。
ゲームアプリのイベント施策
モバイルゲームが新しいイベントやコラボ企画を実施した際、MAUやDAUがどれだけ増えたかを測定するのが一般的です。大きなイベントでユーザーが一時的に戻ってくることがあれば、再度ゲームへの愛着を思い出して継続してくれるかもしれません。これにより、MAU増加が長期的な売上アップに繋がることが期待できます。
ECサイトにおけるリピート率とMAU
ECサイトでは、「月1回以上訪れて購入しているユーザー数」を見ることがMAUと似た概念になります。ここでMAUが増えれば、それだけリピート購入を行う顧客が多いという意味で、顧客ロイヤルティの向上を測る手がかりになります。併せて平均購入単価や購入頻度を分析することで、具体的な改善策を考えられます。
MAUが示す限界と注意点
アクティブ定義のばらつき
各サービスが「アクティブユーザー」をどう定義しているかによって、MAUの算出基準が異なる点は要注意です。例えば、SNSならログインだけでカウントするケースが多いですが、実際に投稿やコメントをしたかどうかまでは含まない場合もあります。投資家や広告主は、この「定義の差」を意識して数字を読み解く必要があります。
質的指標との組み合わせ
MAUが多いからといって、必ずしもユーザーがサービスを気に入っているとは限りません。数合わせ的にログインしているだけ、あるいはキャンペーン目的で一時的に利用しているだけかもしれません。コアなファンを獲得しているかどうかを把握するには、NPS(Net Promoter Score)®※やユーザーの定性コメントなど質的な指標とも併用することが望ましいでしょう。
チャーン率やDAUを無視できない理由
MAUだけでなく、ユーザーの離脱率(チャーン率)やDAUを同時にモニタリングすることで、ユーザーの使用頻度や長期定着度を詳しく把握できます。例えば、MAUが増えていてもDAUが減っているなら「ユーザーは増えているが、日常的にはあまり使われていない」可能性がありますし、チャーン率が上がっているのにMAUが横ばいなら「新規獲得と離脱が同じくらい起きている」などの分析が可能です。
まとめと今後の展望
MAU(Monthly Active Users)は、月単位でアクティブなユーザー数を測る指標として、SNSやアプリ、Webサービスの成功度を示す重要な数字です。
本稿で解説したように:
- MAUを把握することでユーザーエンゲージメントを定量化し、マーケティングや開発の効果を評価できる
- MAUが高ければ広告収益やサブスクモデルなどとの相性が良く、投資家や広告主にとっても魅力的な指標となる
- ただし、アクティブユーザーの定義や利用頻度の詳細を確認しないと、本当の利用状況を誤解しかねない
- DAU、WAU、チャーン率、CVRなど他の指標と組み合わせることで、より精度の高い分析が可能
- MAUを伸ばすためには、新規ユーザー獲得だけでなく、既存ユーザーを離脱させないリテンション施策やUX改善が欠かせない
今後もスマートフォンやクラウドサービスが普及し続けるなかで、MAUは引き続き多くの企業が注目する指標となるでしょう。また、機械学習やデータ解析手法が発展することで、単なるMAU集計にとどまらず、ユーザー行動の詳細を分析したスマートなマーケティング戦略が求められると考えられます。
サービス運営者やマーケターにとっては、MAUがあくまで入り口の指標である点を意識しながら、利用状況を多角的に捉えてユーザー体験を向上させる施策を展開することが、持続的な成長の鍵となるでしょう。
※NPS®、ネット・プロモーター・スコア® は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。