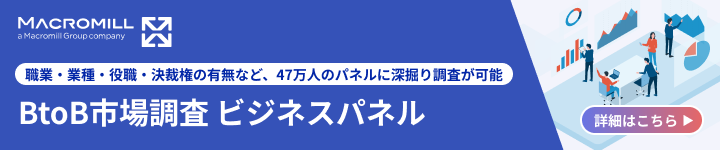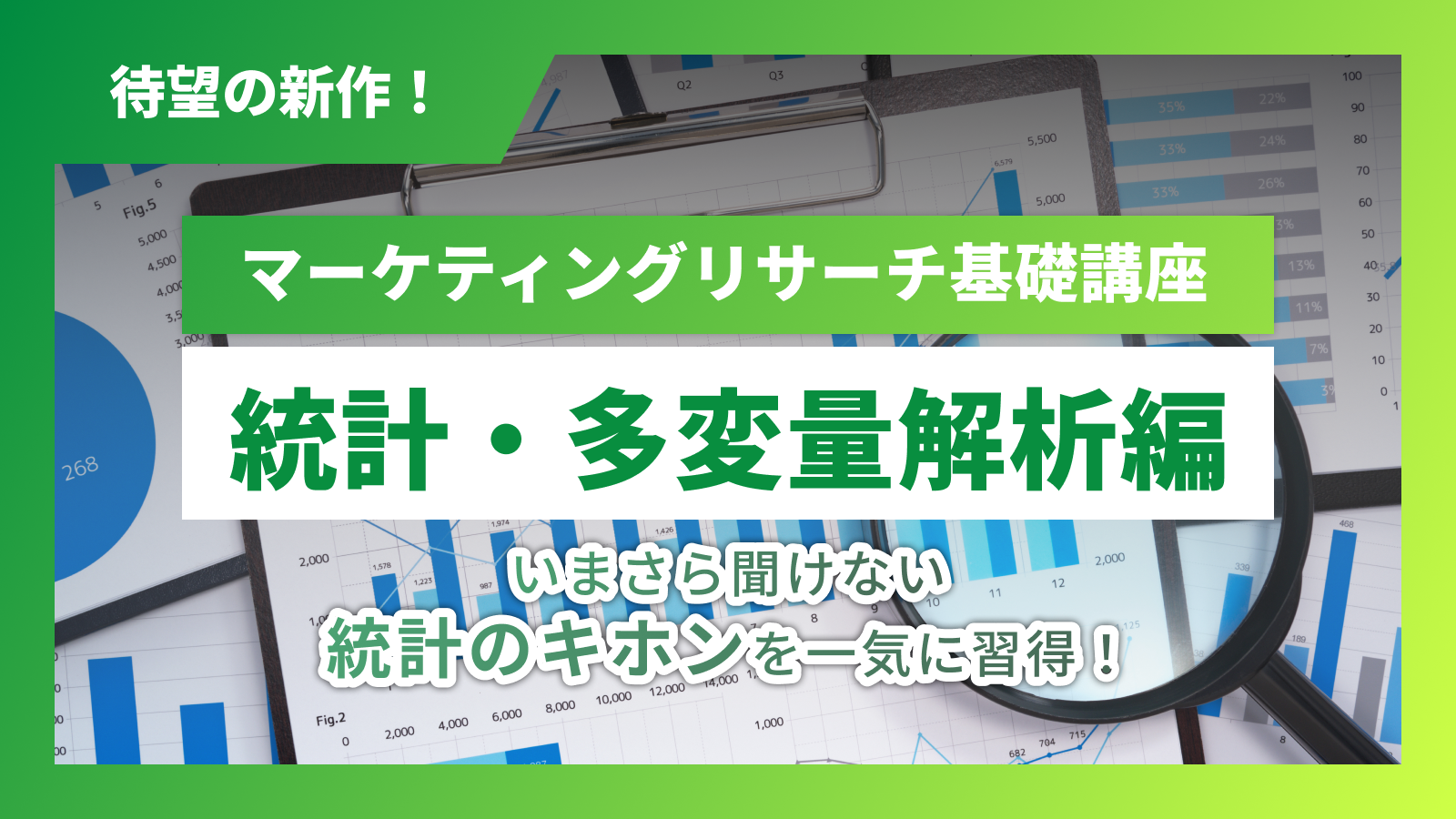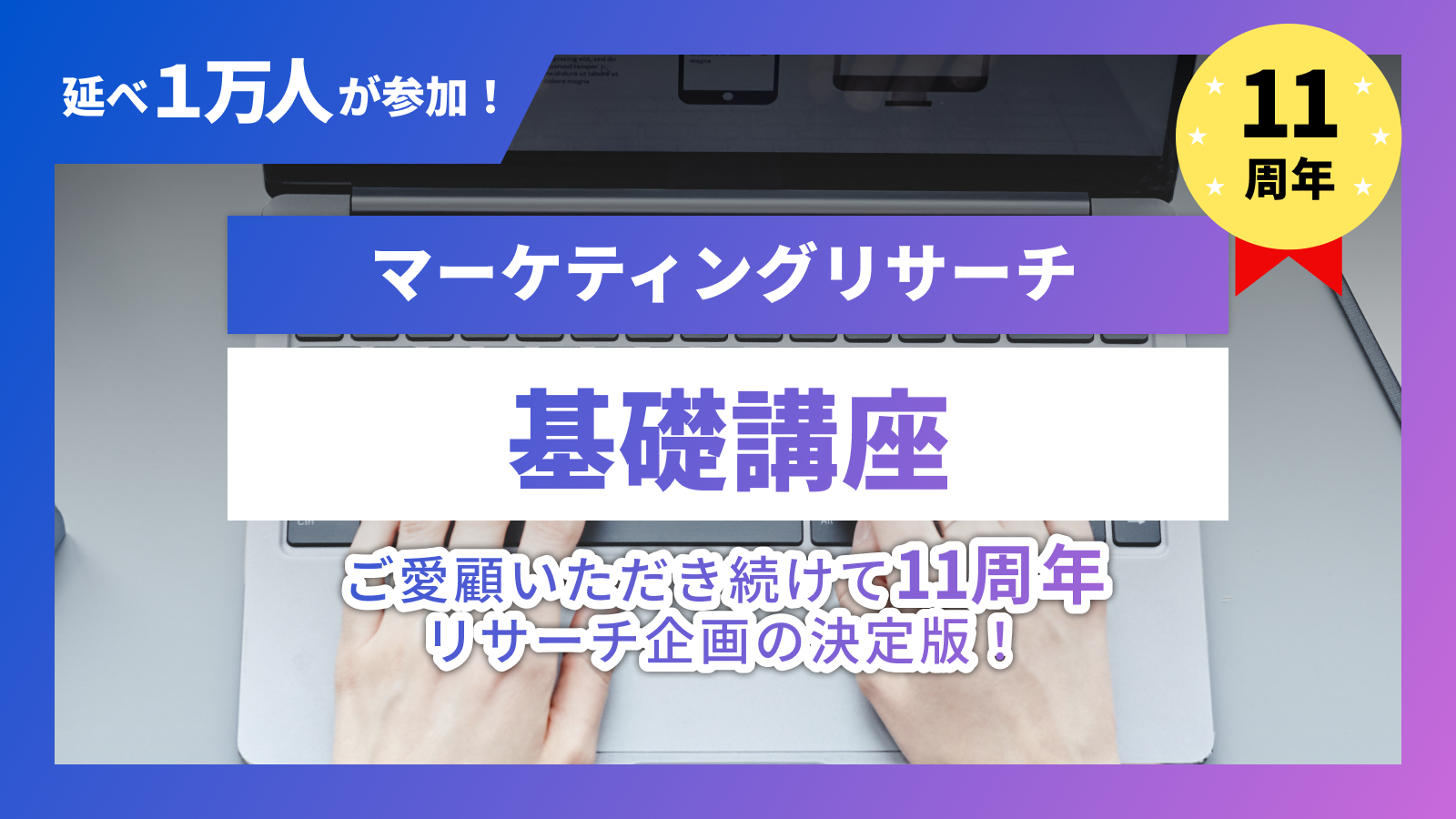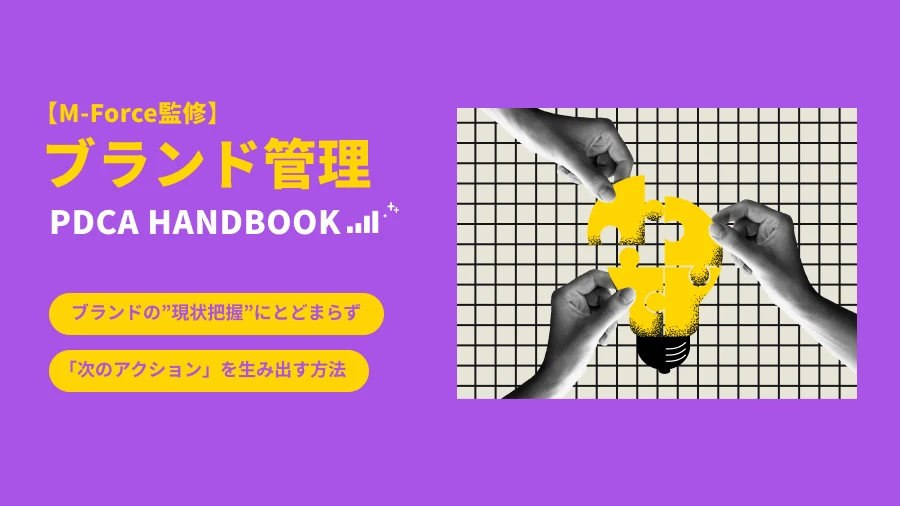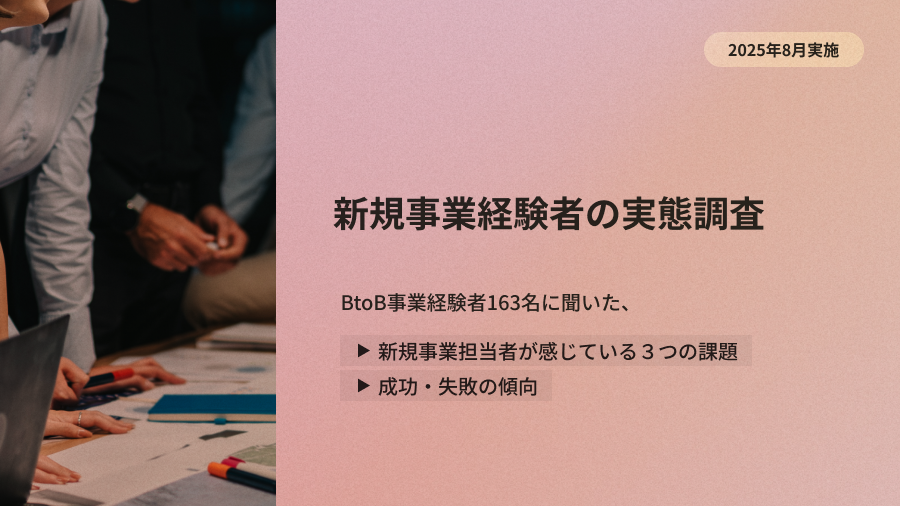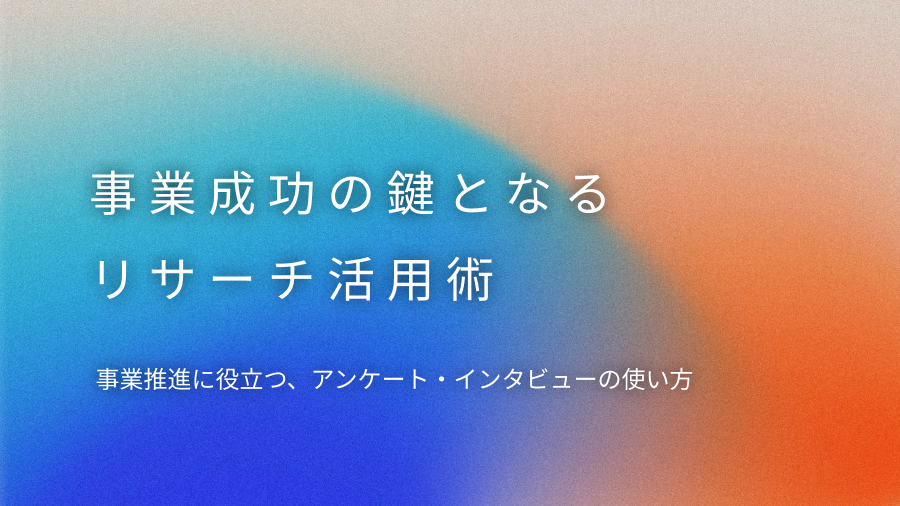マーケティングオートメーション(MA)とは?機能・導入メリット・活用法を体系的に解説
公開日 :2023/4/21(金)
最終更新日:2025/8/8(金)
営業に渡すリードが増えたのに、商談につながらない――。
見込み客はいるはずなのに、どこに何をすればいいかわからない――。
1件1件メールするにも、電話をかけるにも限界がある――。
こうした悩みは、マーケティング部門やインサイドセールスの現場では日常的に起きています。リード獲得チャネルが多様化し、顧客の行動も複雑化した現代において、“感覚と勘”に頼ったマーケティングは限界を迎えつつあります。
そこで登場したのが「マーケティングオートメーション(MA)」です。見込み顧客一人ひとりの行動を可視化し、スコアリングし、最適なタイミングで適切なコンテンツを届ける。そして、購買意欲が高まったタイミングで営業にパスする――。こうした一連のプロセスを“自動化”できるのが、MAの最大の価値です。
本コラムでは、マーケティングオートメーションの定義から導入メリット、機能、活用方法、代表的なツール、成功事例、導入の注意点までを体系的に解説していきます。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- マーケティングオートメーションとは?定義と目的
- MAでできること:代表的な機能と活用イメージ
- BtoBマーケティングにおけるMAの重要性
- 代表的なMAツールとその特徴
- MAの導入ステップと社内体制の整え方
- 成功事例から学ぶ:成果を出す企業の共通点
- MA導入における課題とその乗り越え方
- これからのMA:AI連携・ノーコード化・中堅企業向け進化
- まとめ:営業とマーケの分断を越えて、成果の基盤を築く
マーケティングオートメーションとは?定義と目的<
マーケティングオートメーション(Marketing Automation)とは、「見込み顧客の獲得から育成、営業連携までをデジタルで管理・自動化するためのツールおよび仕組み」を指します。略して「MA」と呼ばれることが一般的です。
本来、マーケティング活動には多くの“手作業”が伴います。リードの属性を確認し、過去の接点履歴を確認し、内容に応じたメールを作成・送信し、開封状況やクリック結果を見て次のアクションを考える――。こうした工程をツール上で一元管理し、自動で最適なアプローチを可能にするのがMAです。
MAの導入目的は、大きく以下の3点に集約されます。
- リードの見える化と温度管理
- 一人ひとりに最適なタイミングでのアプローチ
- 営業へのパス精度を高め、商談効率を向上させる
マーケティング部門の業務負荷を軽減するだけでなく、営業成果にも直結する仕組みとして、BtoB企業を中心に急速に導入が進んでいます。
MAでできること:代表的な機能と活用イメージ
マーケティングオートメーション(MA)は、単なるメール配信ツールではありません。むしろ、「営業とマーケの連携設計」を支える“統合プラットフォーム”と言えるほど、多岐にわたる機能を備えています。ここでは、MAでできる代表的な機能を、実務イメージとともに紹介します。
リード管理(リードデータベース)
MAの中核は、見込み顧客の情報を一元的に管理できる「リードデータベース」です。フォーム経由で取得した情報、名刺管理システムからのインポート、セミナー参加履歴などを統合し、氏名・会社名・役職・業種などの属性と、行動履歴をひとつの画面で確認できます。
活用イメージ:
「過去に製品資料をDLし、最近になってまたサイトに再訪している」リードを営業がすぐに確認できる。
スコアリング機能
リードの行動や属性に点数を付与することで、購買意欲の高いリードを“見える化”します。たとえば、「資料DL:10点」「メール開封:5点」「価格ページ閲覧:20点」など、加点・減点のルールを設けて“ホットリード”の抽出が可能になります。
活用イメージ:
スコアが80点を超えたら営業にアラートを飛ばし、すぐに商談化。
メールマーケティング/シナリオ配信
顧客の行動やセグメントに応じて、あらかじめ設定したメールを自動で送ることができます。これにより、リードナーチャリング(育成)を半自動化し、「検討中の顧客」に最適なタイミングで情報を届けることが可能になります。
活用イメージ:
ホワイトペーパーをDLした翌日にサンクスメール、その3日後に関連事例、その1週間後にウェビナー案内。
フォーム・ランディングページ作成
MAツールには、フォームやLP(ランディングページ)を簡単に作成できる機能も備わっており、資料請求・イベント申し込み・問い合わせなどのリード獲得施策を素早く設計・実装できます。
レポート・可視化ダッシュボード
各種施策の成果やリードの状態をレポート化できるのもMAの強みです。たとえば、月ごとのMQL獲得数、施策別のコンバージョン率、営業パス後の受注率など、KPIを可視化することでPDCAが回しやすくなります。
BtoBマーケティングにおけるMAの重要性
BtoB領域において、MAが注目される理由は単に「作業効率が上がるから」ではありません。その本質は、「見込み顧客との関係を持続的に構築し、購買タイミングを逃さずキャッチする仕組みをつくれること」にあります。
BtoBでは以下のような構造的課題が存在します。
- 購買までの期間が長く、検討ステージが複雑
- 複数人の意思決定者が関与する(現場・上長・経営層)
- ターゲットが限られており、数より“質”が重視される
- 営業のリソースには限界があり、全リードにアプローチできない
このような環境下で、MAは“営業の前段”を支える存在として機能します。
- 潜在顧客に認知を広げる → SEOや広告連携
- 興味段階でナーチャリング → シナリオ配信・セミナー誘導
- 検討段階で商談化を後押し → スコアリング連携・営業通知
つまり、MAを活用すれば、「誰に・いつ・どのようにアプローチすればいいか?」という“マーケティング設計の精度”が飛躍的に向上するのです。
代表的なMAツールとその特徴
MAツールは世界中で多くのベンダーが提供しており、目的や企業規模によって最適な選択肢は異なります。ここでは、日本国内でも導入実績が多い主要ツールと、その特徴を簡潔に整理します。
Salesforce Pardot(現:Marketing Cloud Account Engagement)
Salesforceとの連携性が高く、営業部門との情報共有がスムーズ。中〜大規模BtoB企業での導入が多く、スコアリングやシナリオ設計機能が豊富。Sales Cloudと統合すれば、案件管理まで一気通貫で運用可能。
Marketo Engage(アドビ)
高機能で拡張性があり、複雑なセグメントやナーチャリング設計も柔軟に対応。ABM(アカウントベースドマーケティング)との連携やグローバル運用にも強み。価格帯はやや高め。
HubSpot
中小企業〜成長企業向けに人気。CRM、CMS、SFAなどを一体で提供しており、特にインバウンドマーケティングに強い。操作性がわかりやすく、初心者でも比較的早く使いこなせる。
SATORI
匿名リードへのアプローチ機能が充実しており、「名前はわからないが行動は見えている」状態の見込み客に対してもマーケティングが可能。リードジェネレーション重視の企業にフィット。
導入時は、「連携したい既存システムとの相性」「運用者のスキル」「想定するシナリオの複雑さ」「サポート体制」などを基準に比較検討することが重要です。
MAの導入ステップと社内体制の整え方
MAは“ツールを入れれば成果が出る”わけではありません。大切なのは「導入後にどう運用するか」であり、仕組みを回す体制づくりが成功のカギを握ります。
導入目的の明確化
まずは「なぜ導入するのか?」を明確にすることが第一歩です。
例
- MQLを創出し、営業の商談効率を高めたい
- 休眠リードを再活性化したい
- 営業の属人化をなくしたい
目的が曖昧なまま導入すると、ただの「高級メール配信ツール」になってしまう可能性があります。
対象業務の洗い出しと可視化
現在のリード獲得〜営業連携までのフローを棚卸しし、「どこを自動化すれば価値があるのか」を検討します。
- フォーム入力後のサンクスメール送信
- 資料DL後のステップメール
- 特定スコアを超えたリードへの営業通知
このように、日常業務の中から“ルール化できる作業”を見つけ出すことがポイントです。
部門連携とKPIの共通化
MAはマーケ部門だけでなく、営業・インサイドセールスとの連携が前提です。「どのタイミングでリードを渡すのか」「何をもってホットと判断するか」といった定義を共有し、リードのSLA(Service Level Agreement)を設けることで組織的に機能します。
コンテンツの準備と整備
MA導入が失敗する理由として最も多いのが「コンテンツが足りない」ことです。ナーチャリングに必要なコンテンツが揃っていないと、MAを使いこなせません。導入前に、以下のような素材を準備しておきましょう。
- ホワイトペーパー、事例集、製品紹介資料
- サンクスメールやシナリオメールのテンプレート
- リードスコアの設計ルール
成功事例から学ぶ:成果を出す企業の共通点
MAツールの導入は、単なる“業務効率化”にとどまらず、組織の営業体制やマーケティング文化を進化させる可能性を秘めています。ここでは、実際に成果を出している企業に共通するポイントを紹介します。
初期は“1シナリオ”から小さく始めている
すべてのシナリオを一気に設計しようとせず、まずは「ホワイトペーパーDL後に3通のステップメールを配信」など、シンプルな施策から始めて、成果を見ながら拡張していく企業が多く見られます。最初から完璧を目指さない設計が、継続運用の鍵です。
営業と“共通KPI”で連携している
成果を出している企業では、MQL数・商談化率・受注率といった共通KPIをマーケと営業で共有し、毎月の定例会で成果を振り返る仕組みを持っています。これにより、営業は「マーケから来るリードが信用できる」と感じ、連携がスムーズになります。
コンテンツを“営業支援ツール”として活用している
導入事例、比較資料、FAQなどのナーチャリング用コンテンツが、営業提案でも活用されているケースは多くあります。MAを通じて得た“関心の強いテーマ”に基づいた資料で、提案の質が上がるという好循環が生まれています。
MA導入における課題とその乗り越え方
MAは便利な一方で、導入後に「使いこなせない」「運用が止まる」といった課題に直面するケースも少なくありません。よくある失敗とその対策を整理します。
課題①:運用担当者のスキル不足
MAツールの操作にはある程度の知識が必要です。とくに複雑なシナリオ設定やスコアリング設計では、運用ノウハウが問われます。
<対策>
初期はベンダーの伴走支援やeラーニングを活用し、「実務で使いながら学ぶ」形で徐々に運用範囲を広げていくのが現実的です。
課題②:コンテンツ不足でシナリオが作れない
MAの“中身”はコンテンツです。資料やメールがなければ、仕組みを動かすことができません。
<対策>
既存の営業資料を流用しながら、少しずつ改善。まずは「メール3通分」から始め、ユーザーの反応を見て差し替えるスタイルが現場でよく機能します。
課題③:営業との連携が取れない
「リードを渡してもフォローしてくれない」「MAを営業が見ていない」など、部門間の分断がボトルネックになることも。
<対策>
営業側に“見えるメリット”を明示することが重要です。たとえば、「このリードは過去にどの資料を見たか」がわかると、提案の切り口が見えやすくなり、営業にも利点があると実感できます。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
これからのMA:AI連携・ノーコード化・中堅企業向け進化
MAは今後さらに進化していきます。特に注目すべき3つの方向性を紹介します。
① AIによるインテント予測とシナリオ最適化
すでに一部ツールでは、AIを使った“次に読むべき資料の自動推薦”や、“どのタイミングで営業を入れるべきか”の予測が始まっています。従来は人が設定していたルールを、AIがデータに基づいて提案してくれる未来は目前です。
② ノーコード・UX重視の進化
これまでHTMLや設計知識が必要だったシナリオ構築も、ドラッグ&ドロップで直感的に操作できるUIが増えています。特に中堅企業やマーケティング専任者がいない組織でも、“使いやすさ”によってMAが広がる可能性があります。
③ SMB(中小企業)向けMAの普及
「MAは大企業のもの」という認識は過去のものになりつつあります。コストを抑えたクラウドMAや、国産のシンプルなサービスも増えており、「まずは1ステップから始める」時代が来ています。
まとめ:営業とマーケの分断を越えて、成果の基盤を築く
マーケティングオートメーション(MA)とは、単なる“業務の自動化ツール”ではありません。それは、「営業とマーケティングをつなぎ、成果に近づくための仕組み」です。
- 顧客の行動を見える化し
- 最適なタイミングで情報を届け
- 購買意欲が高まった時点で営業へパスする
この一連の流れを設計・実装・運用することで、受注率の向上、LTVの最大化、営業の効率化という成果が見えてきます。
そして何より、MAは「売り込み」ではなく、「信頼関係を積み上げていくマーケティング」を実現する手段です。仕組みを育て、顧客を育て、組織も成長させていく――その循環の起点として、MAはBtoB企業の未来を支える基盤となるのです。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル