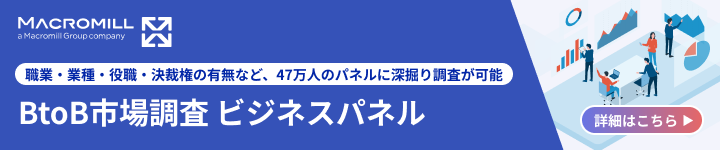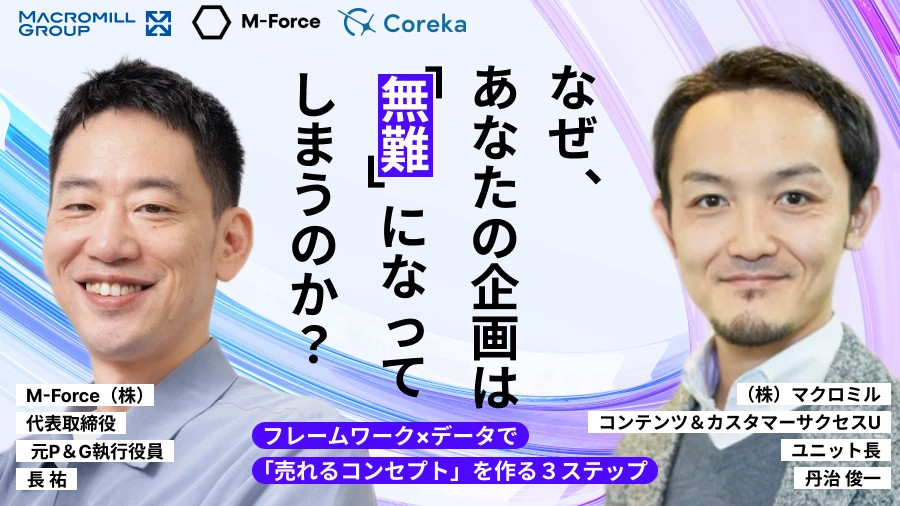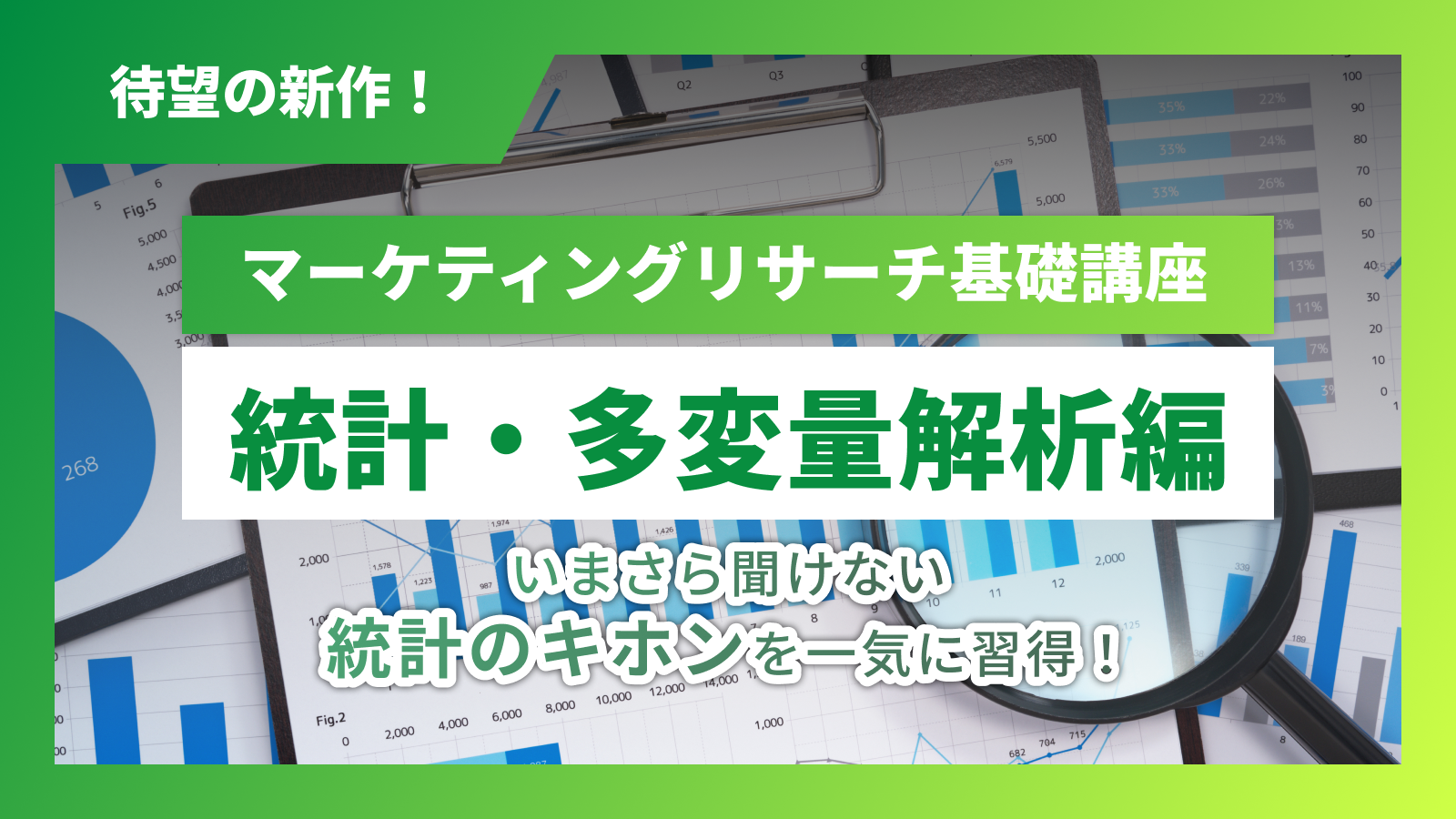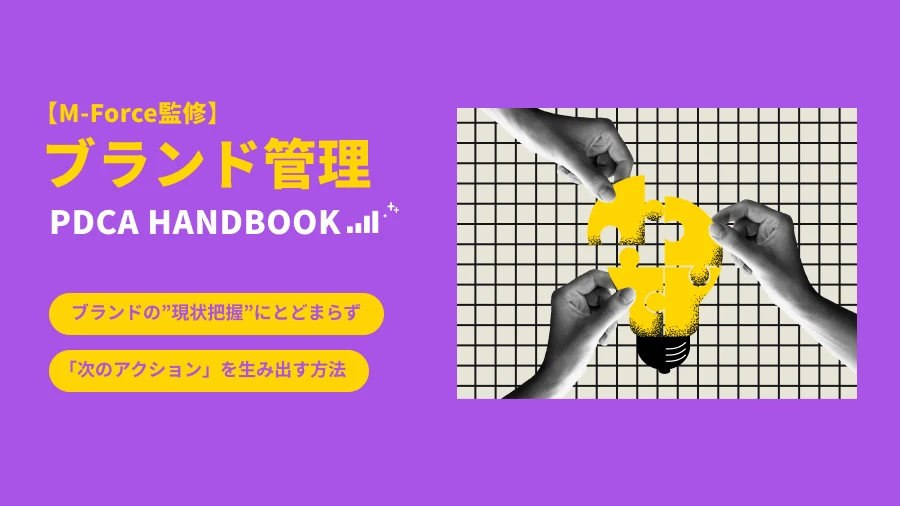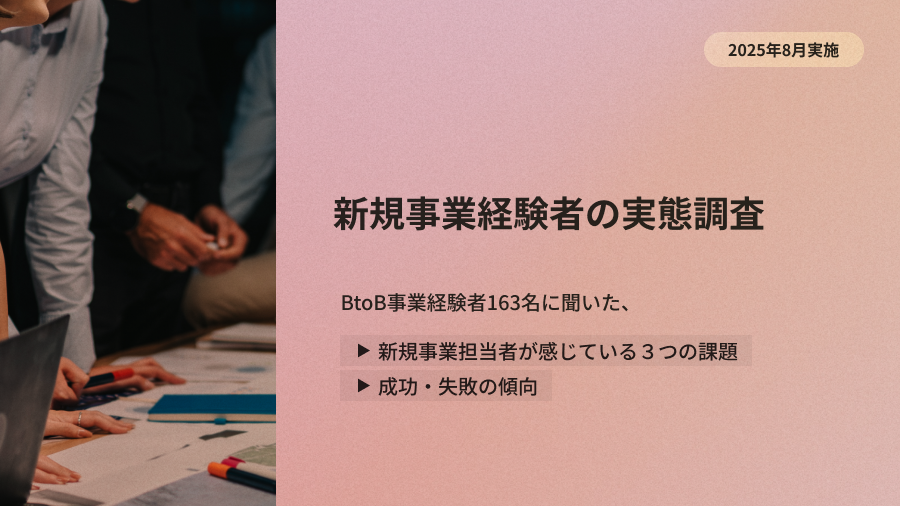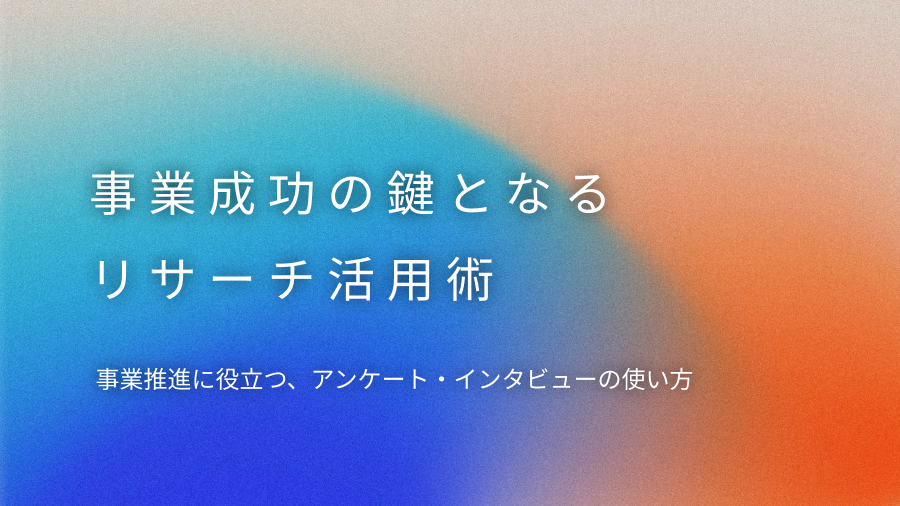どれほど優れた製品やサービスを持っていても、営業が顧客と出会えなければビジネスは始まりません。特にBtoBの世界では、ターゲット層が限られているうえに、顧客は自ら積極的に情報を取りに来るとは限らない――。この状況において、極めて重要な役割を果たすのが「リードジェネレーション」です。
リードジェネレーションとは、将来的に顧客になる可能性のある“見込み客”との最初の接点を生み出すマーケティング活動のことを指します。広告、オウンドメディア、セミナー、SNS、展示会など、あらゆるチャネルを通じて「関係のきっかけ」を生み出し、営業へとつなげる“前段”を支えるのがこの領域です。
本コラムでは、「リードって何?」「ジェネレーションってどうやるの?」という基本から、BtoBにおける戦略設計、主要施策、KPI、成功事例、そして質と量のバランスの取り方までを包括的に解説していきます。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- リードジェネレーションの定義と役割
- BtoBにおけるリードの分類とフェーズ設計
- なぜリードジェネレーションがうまくいかないのか?
- 成果を出すための5つの主要施策
- リードの“質”と“量”を両立させるために
- リード獲得から商談化につなげる設計:ナーチャリングと連携
- 成功事例から見る、成果を出す企業の共通点
- リードジェネレーションのKPI設計と改善のコツ
- これからのリードジェネレーション:インテントデータとAIの活用
- まとめ:出会いを“つくる”マーケティングへ
リードジェネレーションの定義と役割
「リード」とは、将来的に自社の顧客となる可能性を持った“見込み顧客”のことを指します。そして「リードジェネレーション(Lead Generation)」は、その見込み顧客を獲得するための活動全般を意味します。
ここで重要なのは、リードとは「まだ買うと決めていない相手」であるということです。つまり、「すぐに営業してよい相手」ではありません。製品を認知し、課題に気づき、情報を探し始めたばかりの段階にある相手を、適切な形で接点化することが、リードジェネレーションの本質です。
たとえば、以下のようなケースがリードジェネレーションにあたります。
- 製品紹介資料のダウンロードをきっかけにメールアドレスを取得
- セミナーへの参加登録で企業情報を獲得
- Web記事からホワイトペーパーのフォーム入力へ誘導
- Meta広告からLPに遷移し、無料トライアルを申し込み
いずれも“いきなり商談”ではなく、“関係づくりの第一歩”として機能するものです。リードジェネレーションの質と量が、その後のマーケティング・営業プロセス全体の生産性を決める――だからこそ、戦略的に設計する価値があるのです。
BtoBにおけるリードの分類とフェーズ設計
リードジェネレーションを語るうえで欠かせないのが、リードの“状態”の違いを理解することです。単に「見込み客」と言っても、その関心度や情報収集の段階には大きなばらつきがあります。この違いを踏まえずに一律のアプローチをしてしまうと、リードの温度感を無視したミスマッチな対応になり、せっかくの機会を無駄にしてしまいます。
一般的に、BtoBのリードは以下の3段階に分類されます。
コールドリード(Cold Lead)
製品・サービスを知ってはいるが、今すぐ導入を検討しているわけではない層。認知段階にあり、関係性は薄い。
ウォームリード(Warm Lead)
興味・関心を示しており、資料請求やイベント参加など具体的な行動を取り始めている層。
ホットリード(Hot Lead)
導入意欲が高く、予算や導入時期、比較検討も進んでいる層。営業接点を持つべきタイミングにある。
リードジェネレーションの施策は、主にコールド〜ウォームのフェーズに焦点を当てます。つまり、まだ熱量は高くないが、正しい情報と接点を通じて将来的な商談化につながる可能性を秘めたリードを「増やす」活動です。
そしてこの分類に応じて、「誰に・どのようなコンテンツを・どんなチャネルで届けるのか?」を設計することが、成果の第一歩になります。
なぜリードジェネレーションがうまくいかないのか?
多くの企業がリード獲得に課題を抱えています。しかし、その原因は「チャネルの選び方」や「広告の出し方」といった表面的なものではありません。より本質的には、以下のような構造的な問題が横たわっています。
顧客理解の浅さ
見込み客がどのような課題を持ち、どのような情報を求めているのか。そのペルソナ設計が甘いと、発信する情報も的外れになりがちです。ターゲットが“誰か”を具体的にイメージできていないまま、キャンペーンを始めても反応は得られません。
数字のゴール設定が曖昧
「月間100件のリード獲得」がKPIとして設定されている場合でも、それがどんなリードなのか、営業にパスできる品質かどうかが定義されていないことが多くあります。量ばかりを追いかけた結果、質が伴わず、営業との連携が崩れる原因にもなります。
“つながり方”の工夫が不足
今の顧客は、いきなりの営業電話や強引な資料送付には敏感です。大切なのは、「その情報を必要としている瞬間」に、「自然なかたち」で接点を生むことです。コンテンツの質、導線設計、導入ハードルなど、細部への配慮がリード獲得率を大きく左右します。
リードジェネレーションとは、単に「人を集めること」ではありません。「つながる理由をつくること」こそが、その本質なのです。
成果を出すための5つの主要施策
リードジェネレーションにおいては、多くのチャネルや施策がありますが、特にBtoBマーケティングにおいて効果が高いとされる代表的な施策を5つ紹介します。
① コンテンツマーケティング
ホワイトペーパー、技術ブログ、導入事例、業界レポートなど、検索行動や情報収集に応えるコンテンツを発信し、オーガニック流入からフォーム入力へと導きます。広告よりも“信用”が先に立つため、良質な関係性を築きやすい施策です。
② オンラインセミナー・ウェビナー
BtoBにおいて、リアルな情報提供と信頼構築ができる手段として、オンラインセミナーは非常に有効です。テーマ設定、登壇者の魅力、アーカイブ活用など、継続的にリードを生む“仕組み”にしやすいのも特徴です。
③ リスティング広告/ディスプレイ広告
「課題を自覚して検索する層」にはリスティング広告が効果的です。一方、認知目的で広く届けたい場合はディスプレイ広告を活用。バナーではなく“情報提供型”の誘導がポイントになります。
④ SNS(Meta/Linkedinなど)広告
特に海外や大企業層では、LinkedInを活用したリード獲得が進んでいます。狙いたい業種や職種に直接届けられるターゲティング精度の高さと、信頼性のあるコンテンツとの組み合わせが鍵です。
⑤ 展示会・リアルイベント
オフライン施策も健在です。製品のデモや社員との会話など、ブランドの“実体験”を通じた関係構築ができるのは大きな強みです。ただし、イベント後のフォローアップ設計が成否を分けます。
リードの“質”と“量”を両立させるために
リードジェネレーションにおいて多くのマーケティング担当者が悩むのが、「量は取れているが質が伴わない」「質にこだわると数が集まらない」というジレンマです。リードの“量”と“質”はしばしばトレードオフのように語られますが、実際には両立させるための設計と運用があります。
まず意識したいのは、“質”とは何か?という定義です。商談化率が高いリードか、意思決定者を含む組織的な引き合いか、あるいはターゲット企業リストに該当するリードか。自社にとっての「理想のリード像」を明確に定義することが、施策の精度を上げる第一歩です。
次に、“量”を担保するための設計として、以下のような考え方があります。
- ファネル上部(潜在層)には広くリーチし、低ハードルでの接点を設ける(例:メールアドレスだけの登録)
- ファネル中部では興味度をセグメントし、コンテンツの種類やCTAを調整(例:価格比較資料は関心度の高い層向け)
- ファネル下部では、具体的な検討段階にある層だけを営業にパスする
このように、リード獲得後に“質を見極める設計”を整えることで、最初から「量も質も完璧なリード」を求めるよりも、実行可能性の高いアプローチが可能になります。
また、リードソース別の比較分析を継続的に行い、チャネルごとのLTVや受注率をモニタリングすることで、最も費用対効果の高い組み合わせを導き出すこともできます。
リード獲得から商談化につなげる設計:ナーチャリングと連携
リードジェネレーションはゴールではありません。むしろ「ようやくスタートラインに立った段階」と言えるでしょう。真に重要なのは、獲得したリードをいかに“温めて”、商談につなげていくか――つまり「リードナーチャリング」の設計です。
ナーチャリング(nurturing)は、文字通り“育成”を意味します。興味・関心を持ち始めた見込み顧客に対して、定期的かつ適切な情報提供を行い、信頼を獲得しながら購入意欲を高めていくプロセスです。
たとえば以下のような手法が活用されます。
- メールマーケティング:行動履歴に応じたコンテンツを自動配信
- MA(マーケティングオートメーション)ツールによるスコアリング
- セミナーやイベントへの再参加促進
- 営業接点前のコンテンツで“社内稟議”を後押し
特に重要なのが、マーケティング部門と営業部門のスムーズな連携です。どのタイミングで、どのようなリードを営業に引き渡すのか(=MQL→SQLの定義)、そのルールと運用が明確になっていなければ、せっかく獲得したリードも営業に“捨てられる”ことになります。
言い換えれば、「営業が動きやすいリード」をつくることが、マーケティングのゴールであり、そこに至るプロセス設計こそが、リードジェネレーションの実力なのです。
成功事例から見る、成果を出す企業の共通点
リードジェネレーションの成功は偶然ではありません。多くの成果を出している企業には、いくつかの共通点があります。それは「手法」ではなく「設計思想」や「組織連携」のあり方に表れています。
顧客の“情報探索行動”を正しく理解している
あるソフトウェア企業では、検索キーワードの調査からターゲット企業の課題を可視化し、それに対応するホワイトペーパーやFAQコンテンツを設計。記事からの流入で月間300件のリードを獲得し、そのうち10%が商談化に至りました。
“1回の接点”では終わらせない仕組みがある
イベントや展示会で獲得したリードを、自社のコンテンツハブに誘導し、記事を3本以上読んだタイミングでMAから自動的に「関連資料」の案内を配信。顧客が自発的に検討を進められる“場”を整えているのが特長です。
営業とマーケの“目線”が揃っている
受注率の高い企業は、マーケティング部門が「営業にとっての理想的なリードとは何か?」を明確に定義しており、毎月の定例ミーティングで営業からのフィードバックを得ながらフォーム設計やスコアリング基準を改善し続けています。こうした事例に共通するのは、「一方的に届ける」のではなく、「顧客の文脈に寄り添う」こと。そして、社内の分断をなくして“組織全体で育てる”意識を持っていることです。
リードジェネレーションのKPI設計と改善のコツ
リードジェネレーションを継続的に改善するためには、成果を正しく測定・評価することが欠かせません。つまり、KPI(重要業績評価指標)の設計です。
代表的なKPI項目
- リード獲得数:月間・四半期での新規リード数
- フォーム通過率:LP閲覧→入力完了の割合
- リード単価(CPL):1件あたりの獲得コスト
- MQL率:全体リードのうち営業に渡せる品質と判断された割合
- SQL率:営業がアクションを起こし、商談化に至った割合
- 受注率/LTV:リードの最終的な売上貢献度
しかし、これらの数値は単体で見るのではなく、「連続したファネル」としてモニタリングすることが重要です。たとえば、リード数が増えてもSQL率が落ちていれば“質”の見直しが必要になりますし、CPLが高すぎれば施策の効率改善を検討すべきです。
改善のためのヒント
“初回接点の質”に注目する
最初に取得した情報が少なすぎると、ナーチャリングが難しくなります。逆に多すぎても離脱される。項目数、設問文、入力UXを見直すことでフォーム完了率は大きく変わります。
コンテンツ別パフォーマンスを分析する
ホワイトペーパーAとB、ウェビナーXとYで、後の商談率や営業評価に差があるかを追いましょう。「反応が良いが受注しづらいコンテンツ」を見抜くことがカギになります。
営業からの定性フィードバックを仕組み化する
「このリードは良かった」「この資料があったから話しやすかった」など、営業現場の声を定期的に吸い上げ、マーケ施策に反映させる“改善ループ”を回すことが強い組織の特徴です。
KPIは「数を追う」ための道具ではなく、「質を高めるためのヒントを得る」ための設計思想だと考えましょう。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
これからのリードジェネレーション:インテントデータとAIの活用
リードジェネレーションのあり方は、いま大きな転換点を迎えています。特に注目されているのが、「インテントデータ」と「生成AI」の活用です。
インテントデータとは?
インテント(Intent)とは「意図」や「関心」を意味します。つまり、見込み顧客が「どんなことに興味を持ち、何を調べているのか?」というデジタル行動データのことを指します。
たとえば:
- 特定のキーワードを繰り返し検索している
- 競合サイトを複数閲覧している
- 同じカテゴリの記事を数日間連続で読んでいる
こうしたシグナルをもとに、「この企業は近々購買に動く可能性がある」と予測し、優先的にアプローチをかけるのがインテントデータの活用です。従来の「手当たり次第」なリード獲得とは一線を画す精度の高いマーケティングが可能になります。
生成AIによるクリエイティブ・運用支援
生成AIの進化により、コンテンツの量産だけでなく「パーソナライズされたCTA」「行動に応じた自動応答」「フォーム改善」など、より細やかな施策が可能になっています。さらに、MAツールやCDPと連携することで、リアルタイムにスコアリングを再計算し、最適な次の打ち手を自動で提示する仕組みも登場しています。今後のリードジェネレーションは、「人の感性」と「AIの処理能力」を組み合わせて、“最適な出会い方”を科学していく時代へと進んでいきます。
まとめ:出会いを“つくる”マーケティングへ
リードジェネレーションとは、単なる「見込み客の獲得」ではありません。それは、顧客と企業が出会い、理解を深め、信頼を育み、最終的にはパートナーシップを築いていく――その最初の一歩を“設計する”マーケティング活動です。
- 顧客の思考と行動を理解し
- 適切なチャネルとコンテンツを選び
- 数だけでなく、質も意識して
- 獲得後のナーチャリングと連携し
- 組織全体で“育てる”体制を築く
そうして生まれる“ひとつひとつの出会い”が、事業の成長を支える本当の資産になります。
リードジェネレーションは、単なるマーケティング部門の仕事ではありません。営業・カスタマーサクセス・経営すべてを巻き込んだ活動です。明日、誰にどんな価値を届けるのか。そこから、マーケティング活動が動き出します。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル