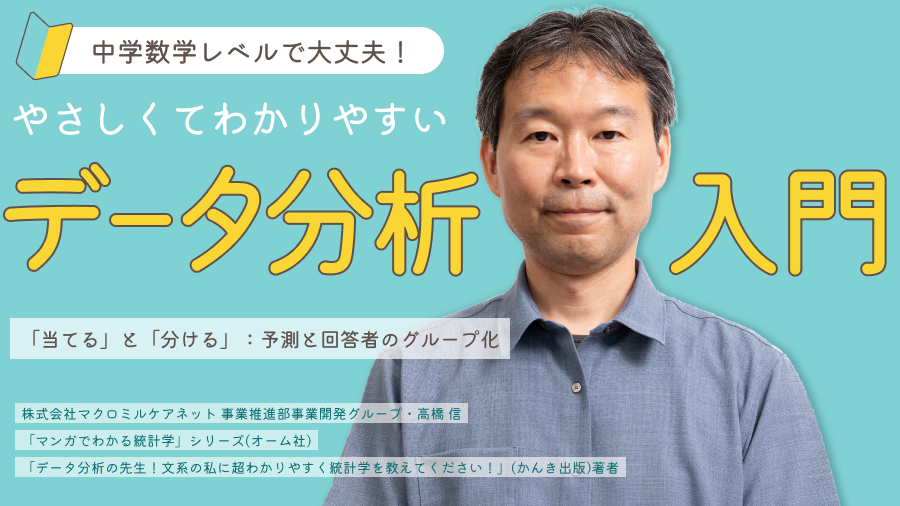インタビュー調査は、マーケティングリサーチから学術研究まで、さまざまな分野で活用される手法です。インタビューを成功させるためには、事前準備が欠かせません。むしろ、インタビューの成否は準備段階でほぼ決まるといっても過言ではないでしょう。
本記事では「インタビュー事前準備」をテーマに、調査目的の明確化、対象者の選定・リクルーティング、質問設計やインタビューガイドの作り方などを網羅的に解説します。特に近年注目されているN1分析®︎との関連についても取り上げ、どのように準備すれば高品質なインタビューが可能になるかを詳しく紹介していきます。
- インタビュー事前準備が重要な理由
- 調査目的とゴールの明確化
- 対象者(インタビューイー)の選定とリクルーティング
- インタビュー形式の選択:対面かオンラインか
- 質問設計とインタビューフローの作成
- モデレーターの役割と準備
- N1分析に向けたインタビュー事前準備
- インタビュー当日に向けた最終準備
- インタビュー事前準備のチェックリスト
- まとめ:成功するインタビューは事前準備が8割
インタビュー事前準備が重要な理由
インタビューは、対面・オンラインを問わず相手との直接的なコミュニケーションを通じて情報を得る手法です。一見すると、当日その場で話を聞くだけのように思われがちですが、実際には「インタビューの成果の8割は事前の設計と準備によって決まる」という意見もあるほどです。その理由を3つの観点から考えてみましょう。
- インタビュー調査の目的や調査課題が具体的に言語化できているかどうか。
- インタビュー対象者(インタビューイー)が適切に選ばれているかどうか。
- 質問項目やインタビューの流れ(構成)に無理や抜けがないかどうか。
これらの観点にしっかり配慮することで、当日のインタビューをスムーズに進め、質の高い情報を引き出すことができます。逆に事前準備が不十分だと、話が脱線してしまったり、聞き漏らしが発生したり、インタビューイーの本音をうまく引き出せなかったりといった問題が起こりやすくなるのです。
調査目的とゴールの明確化
インタビューの事前準備においてまず重要なのは、「そもそも何のためにインタビューを行うのか」をはっきりさせることです。商品改善のためなのか、新規サービスのアイデア発掘なのか、あるいは学術研究の仮説検証なのか。目的によって質問の内容や深掘りの仕方が大きく変わってきます。ここでは具体的な方法を紹介します。
調査テーマを設定する
「リニューアルを予定している商品Aのパッケージ案を複数評価させ、絞り込みのためのインプットを得たい」「新規コンテンツの訴求方法を探るために、ターゲットユーザーの行動特性を知りたい」など、調査テーマを簡潔にまとめます。ここで重要なのは、抽象的なテーマではなく、ある程度具体的な問いに落とし込むことです。漠然としたテーマだと、インタビュー対象者がどんな人であるべきか、どのような質問をすれば良いかが分かりづらくなります。
期待される成果を定義する
調査テーマが決まったら、「最終的にどんなアウトプットを得たいのか」を考えましょう。例えば、商品改善策の要件リストを作りたいのか、サービス利用の動機を多面的に把握したいのか、あるいはN1分析®︎を通じて一人の事例から新たな仮説を導きたいのか。期待するアウトプットのイメージを持つことで、インタビューの設計方針が明確になります。
インタビュアーの視点を整理する
インタビュアー(モデレーター)が持っている仮説を事前にリストアップしておくことでインタビューの論点がよりクリアになり、的確な深堀りが可能になります。また、仮説を整理しておくことで自分が「どのようなバイアスを持っているか」を客観的に捉えることもできます。仮説に対する先入観が強すぎるとインタビュー中に誘導的な質問をしてしまう恐れもあり、逆にまったく仮説がない場合はゴールの見えない雑談になりがちです。適度なバランスを保つ必要はありますが、事前の仮説整理はインタビューの質を向上させる有効なステップだと言えます。
対象者(インタビューイー)の選定とリクルーティング
次に大切なのは、インタビューの対象者を適切に選ぶことです。調査目的を達成するために、どのような属性や経験を持つ人から話を聞くべきかを考えます。もし対象者を間違えてしまうと、せっかく準備を万全にしても得られる情報が調査目的に合わないという結果になりかねません。
ターゲット設定やセグメントの明確化
調査テーマに関連するターゲットや顧客セグメントがある場合、まずはその定義を再確認します。例えば、ダイエット食品の利用状況を調べるのであれば、「ダイエット経験のある20〜30代女性」など大まかな属性を設定し、その中でも「リバウンドを繰り返している人」や「健康志向が強い人」といったより具体的な特性で絞るケースもあります。企業のマーケティング部門などでは、既に持っている顧客リストから対象者を抽出したりアンケート結果をもとにセグメントを定めて対象者を抽出することが一般的です。
リクルーティング方法
対象者が決まったら、実際にインタビューに応じてくれる人を探します。既存の顧客リストを使う方法や、調査会社へ委託する方法、Interview Zeroのようなパネル付きのインタビューツールを利用する方法、SNSや募集掲示板を活用する方法など、さまざまな手段があります。自社で顧客データを豊富に持っている場合は、そこから条件に合致する人を抽出し、メールで依頼するのが早いケースもあります。一方、新規サービスのコンセプトテストのように未知のターゲット層を含む場合は、幅広いリクルーティングが必要になるでしょう。
インセンティブの設定
インタビューに協力してもらうには、対象者の時間と労力をいただくわけですから、何かしらのインセンティブ(謝礼)を用意するケースが多いです。金券や商品券、または自社サービスの利用クーポンなども一般的です。ただし、インセンティブの設定には対象者のモチベーションを高めつつ、過度な誘導にならないようバランスが大切です。
インタビュー形式の選択:対面かオンラインか
インタビューの準備を進めるうえで、どのような形式で実施するかを早期に決定しておく必要があります。現在では対面インタビューだけでなく、オンラインインタビューも広く普及しておりますので、それぞれのメリット・デメリットを押さえて選択しましょう。
対面インタビュー
試用・試飲など実物を使いながらインタビューを行う場合に有効です。また、対面の場合、対象者との心理的距離を縮めやすく、表情や姿勢など微妙なサインを読み取りながら進行できるという強みがあります。一方で、会場費や移動費がかかったり、場所や時間の調整が煩雑になるといったデメリットも存在します。
オンラインインタビュー
オンラインインタビューは、地理的制約がほとんどなく、コストも抑えやすいという大きな利点があります。全国からリクルーティングができるため、募集条件が厳しいインタビュー調査も出現しやすくなります。
ただし、通信環境への依存もあるため、どちらがよいかは調査目的や対象者の属性、予算などを総合的に見て判断するとよいでしょう。
質問設計とインタビューフローの作成
インタビュー事前準備の要ともいえるのが、質問設計とインタビューフローの作成です。インタビューフローとは、インタビュアーが当日使う台本のようなもので、質問項目やインタビューの流れをあらかじめ整理しておくための資料です。以下のプロセスを参考に、しっかりと作り込むことで本番での混乱を防ぎ、漏れなく情報を収集できるようになります。
1. ブレインストーミングで質問を洗い出す
まずは調査目的と期待される成果に基づいて、聞きたいことを自由に書き出します。個人的な興味や仮説、事業上のニーズなど、関係者全員で意見を出し合い、質問の候補をリストアップしていきます。量を気にせず出しておくことで、後々必要な要素を取りこぼすリスクを減らせます。
2. 質問の整理・グルーピング
出てきた質問を大きなテーマごとにグループ分けし、優先度を検討します。ここでは、「インタビューの時間は限られている」という現実を踏まえ、質問が多すぎないように調整することがポイントです。「必ず聞きたい質問(マスト)」「時間があれば聞きたい質問(オプション)」に分類しておくと、当日の進行がスムーズになります。
3. オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け
インタビューの主役はあくまで回答者です。回答者が話しやすいように、基本的にはオープンクエスチョン(自由回答型)を中心に構成しましょう。例えば「どのように感じましたか?」「なぜそう思ったのですか?」といった問いかけです。一方で、具体的な事実確認にはクローズドクエスチョン(はい/いいえや選択肢型)が効果的な場合もあります。両者をうまく組み合わせることで、深い情報と正確な情報をバランス良く得ることができます。
4. インタビューの流れを設計する
インタビューは最初から核心的な質問を行うよりも、ウォーミングアップ(アイスブレイク)→背景情報理解→本題→クロージング、といった順序で進めるほうが回答者の緊張をほぐしやすいです。特にN1分析®︎など一人を深く掘り下げる場合は、いきなりプライベートな話題に踏み込まないよう配慮し、段階的に深度を上げていくことが大切です。
モデレーターの役割と準備
インタビューの事前準備では、質問設計やスケジュール調整だけでなく、モデレーター(インタビュアー)自身がどのように立ち回るかも非常に重要です。モデレーターの力量によってインタビューの結果が大きく左右されることは珍しくありません。
モデレーターの選定
社内の誰がモデレーターを務めるかを早期に決定し、その人が全体の進行を把握できるようにします。経験豊富なモデレーターがいる場合は任せるのがベストですが、いない場合でも「相手の発言を遮らない」「沈黙を恐れない」「発言しやすい雰囲気を作れる」人を起用するとよいでしょう。
リハーサルでスキルを磨く
モデレーター役は、質問の流れを覚えるだけでなく、回答者とのやり取りでどのように追加質問を挟むか、話が脱線したときにどのように軌道修正するかを事前にシミュレーションしておくことが大切です。声のトーン、間の取り方、相槌の打ち方など、実際にやってみると初めて気づく点が多くあります。
バイアスを意識する
モデレーター自身が強い仮説を持っていると、無意識のうちに誘導的な質問をしてしまうことがあります。客観的な視点で情報を引き出すには、自分のバイアスを自覚し、回答を誘導しない・回答者の言葉をしっかり受け止める姿勢が不可欠です。
N1分析に向けたインタビュー事前準備
「N1分析®︎」とは、サンプル数が1人(N=1)でも、その人物を徹底的に深掘りすることで新たな発見や仮説を得ようとするアプローチを指します。大規模調査による統計的有意性とは異なる価値観に基づく手法として、近年注目が集まっています。N1分析®︎を行うにあたっては、通常のインタビューに加えて以下のポイントに留意すると効果的です。
対象者の実態を把握
対象者のデータ(属性データやアンケート結果や行動ログなど)がある場合は事前に読み込んでおきましょう。
N1分析®︎では対象者の行動の背景を深掘りし、深く理解することが大切です。その準備として「普段どのような生活をしているか」「どのような意識を持っているか」といった情報をもとに仮説レベルで背景を考えておくと、当日の質問がより具体的になります。
インタビューフローの読み込み・リハーサル
作成したインタビューフローをもとにリハーサルを行います。チーム内でモデレーター役と回答者役に分かれて行う方法もあれば、外部のテストユーザーに協力をお願いする場合もあります。実際に口に出して質問すると、文字だけでは気づかなかった「難解な表現」や「回りくどい順序」などが明らかになります。修正を加えてブラッシュアップしていくことで、本番でのインタビュー効率が飛躍的に向上します。
インタビュー当日に向けた最終準備
スケジュールが決まり、対象者がリクルートされ、インタビューフローが完成したら、いよいよインタビュー当日に向けた細部の調整を行います。ここまできちんと準備しておくと、当日のトラブルを最小限に抑えられます。
会場と機材の確認
対面インタビューの場合、適切なサイズの部屋、雑音が少ない環境、録音機材やカメラの動作確認など、細かな点を見落としがちです。特に録音テストは必ず事前に行い、音質や保存先を確保しておきます。オンラインインタビューなら、インタビューツールの接続テスト、画面共有の設定、録画の許諾などを確かめましょう。
質問の最終チェック
当日に使うインタビューフローは、進行役が一目で理解できるよう簡潔にまとめておきましょう。長々と文章を書くよりも、要点を箇条書きにするなどして、フローがぱっと見て把握できる形に整えるのがおすすめです。事前の仮説整理やシミュレーションはしっかり行い、深堀りポイントについてはフローにメモしておきます。また、ヒアリング内容ごとの大まかな時間配分も記載しておきましょう。
対象者へのリマインド
対象者へインタビュー日時や場所、オンラインのアクセス方法などを再度連絡し、スムーズに当日参加できるようにします。対面の場合は、迷わず到着できるように地図や道順を案内し、オンラインの場合は接続方法や必要な機材を詳しく伝えます。
当日の流れの共有
チームメンバーが複数いる場合、誰がどの役割を担うのか、時間配分はどうするのかを明確にしておきます。モデレーターの他に、サポート役として音声録音やメモ取りに専念する人を置くと、インタビュアーが集中して質問に専念できるでしょう。
インタビュー事前準備のチェックリスト
最後に、全体を振り返る形で事前準備のチェックリストをまとめます。これらがすべて満たされていれば、当日のインタビューで大きなトラブルはほぼ回避できるはずです。
- 調査目的
- 調査課題(何のために、何を明らかにしたいのか)が明確になっている
- 対象者の選定
- ターゲット・セグメント設定、リクルーティング完了
- インタビュー形式
- 対面かオンラインかを決定し、必要な環境を整備
- インタビューフロー
- 質問項目を整理し、リハーサルで内容を最適化
- モデレーター準備
- 仮設の整理、リハーサルでシミュレーション(進行練習)
- スケジュール
- 対象者へのリマインド、緊急連絡体制、会場準備
- 機材チェック
- 録音・録画の確認、オンラインツールの動作テスト
まとめ:成功するインタビューは事前準備が8割
インタビュー調査は、相手から直接生の声を聞き出す絶好の機会です。その成功の鍵は、いかに事前準備を丁寧に行うかにかかっています。調査目的の明確化や対象者の適切な選定、詳細に作り込まれたインタビューガイド、モデレーターの事前練習などがしっかりと行われていれば、当日の進行は格段にスムーズになるでしょう。
さらに、N1分析®︎など深い洞察を得たい場合には、対象者の背景情報を早い段階で収集しておくことがポイントです。一人の回答者だけでも、その人の内面や生活を徹底的に探ることで、インタビュー中に思わぬ発見やイノベーティブなアイデアが生まれる可能性があります。
事前準備をしっかり行うことで、当日のインタビューは「ただ話を聞く場」から「新しい気づきや洞察を得るための貴重なプロセス」へと変貌します。ぜひ本記事で紹介したポイントを活用して、より質の高いインタビュー調査を実現してみてください。目的に合致した情報を的確に引き出し、次のステップ(製品改善、サービス企画、研究分析など)につなげていくためにも、「準備8割」の姿勢を大切にしましょう。
※N1分析®は、マクロミルグループが保有する商標です。ライセンス提供はしておりませんため、当社(マクロミルグループ)以外は正規の提供者ではありませんのでご注意ください。N1分析®︎のご相談は右上の「お問い合わせ」まで。
著者の紹介
株式会社マクロミル
鳥居 慧
2009年に株式会社マクロミルに入社。
10年以上にわたり定量調査から定性調査まで幅広いリサーチサービスの運用部門に従事し、10,000件以上のプロジェクトに関与。
2024年、セルフ型のオンラインインタビュープラットフォーム「Interview Zero」を立ち上げ、プロダクト責任者として従事。