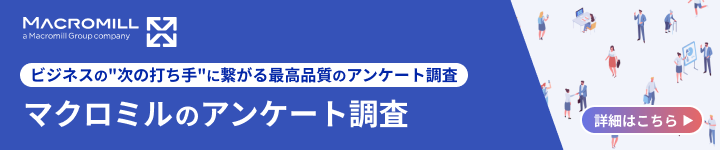ES調査(従業員満足度調査)とは?実施の目的やメリット、質問項目例も紹介
公開日 :2023/12/25(月)
最終更新日:2025/3/14(金)
ES調査(従業員満足度調査)とは、組織の課題発見や改善を行う際などに必要な調査です。人材の定着や制度の改善などのために、自社でもES調査の実施を検討している企業も多いのではないでしょうか。この記事では、ES調査の目的やメリット、実施手順などを詳しく解説します。ES調査の実施を考えている場合は、ぜひ参考にしてください。
- ES調査(従業員満足度調査)とは?
- ES調査(従業員満足度調査)を実施する目的
- ES調査(従業員満足度調査)のメリット
- ES調査(従業員満足度調査)の費用の目安
- ES調査(従業員満足度)の流れ
- ES調査(従業員満足度調査)の質問項目例
- ES調査(従業員満足度調査)を実施する際の注意点
- ES調査(従業員満足度調査)の集計・分析方法
- ES(従業員満足度)を向上させる取り組み
- ES調査(従業員満足度調査)をスムーズに実施するならマクロミル
- まとめ

ES調査(従業員満足度調査)とは?
ES調査(従業員満足度調査)とは、従業員が組織や仕事内容に対してモチベーションを感じているか、満足しているかなどを調べるための調査です。ES=従業員満足度は、企業の業績にも影響を及ぼすため、企業にとって欠かせない調査だといえます。ESを把握し、問題点を改善することで従業員のモチベーション向上などにつながります。

ES調査(従業員満足度調査)を実施する目的
ES調査を実施する目的は、大きく分けて3つです。ここでは、それぞれの目的について詳しく解説します。
優秀な人材の定着を図るため
ES調査の目的の1つに、優秀な人材の定着を図ることがあります。従業員が業務内容や労働環境など、働くうえで重要となるさまざまな部分に不満を抱えたままそれが解消されない場合、最悪離職につながってしまう可能性があります。
とくに、優秀な人材が離職して他社に流れてしまうと自社の業績に大きな影響を与える可能性があるでしょう。従業員満足度調査を実施することで、従業員の不満や業務の問題点などが明らかになるため、働きやすい環境の構築につながります。
各種制度の改善を図るため
ES調査によって、各種制度の改善を図るという目的もあります。たとえば、人事制度は従業員を正しくかつ公正に評価する必要があるため、適切な施策を検討して制度の改善を図らなければいけません。
ES調査を実施することにより、従業員の要望や制度に感じている不満などを正しく把握できます。施策を行う前と後でES調査を実施することで、施策による効果を見極めることもできるため、効率的に各種制度の改善を行っていけます。
組織の活性化を図るため
ES調査で得られたデータを組織改善に活かすことができるため、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の定着につながり、組織としての活性化も期待できます。
従業員の意欲が向上することで、従業員個人のパフォーマンスがよくなるケースもあります。結果として生産性が向上するなどのメリットも得られるため、業績アップの可能性を高められる点も大きなメリットでしょう。

ES調査(従業員満足度調査)のメリット
ES調査には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットを解説します。
ES(従業員の満足度)を定量的に把握できる
ES調査により、従業員の満足度を定量的に把握できる点は大きなメリットです。従業員の心理状態や意識などは目に見えないもののため、正確に把握することは難しいでしょう。しかし、ES調査の実施によって、従業員の現状や意識、不満などの感情的なものを定量的かつ客観的に把握できるため、改善につなげやすくなります。
組織が抱える課題を早期に見える化できる
ES調査の実施により、組織が抱えている課題を早めに発見できる点もメリットです。ES調査はさまざまな角度から調査することができるため、まだ表面化していないような課題を早期に発見できるというメリットがあります。課題を早めに見つけられるため、改善までのスピードが早まり、従業員の満足度やモチベーション向上につながります。
従業員との信頼関係構築、自社への愛着向上効果につながる
定期的にES調査を実施することで、従業員との信頼関係構築につながります。ES調査をしっかり行うと、従業員は「会社は自分たちのことを考えてくれている」と感じるようになります。そのため、信頼関係の構築や自社への愛着が向上するなどの効果が見込めるでしょう。また、ES調査によって従業員が自社に対して意見を言える機会づくりにもなります。
生産性が向上する
ES(従業員満足度)を重視している企業は、生産性が向上しやすい傾向にあります。ES調査を行うことで、明らかになった潜在的な課題の解決に努めることで、従業員の仕事に対するモチベーションが向上します。従業員のやる気や意欲の高まりにより、業務効率が向上し、組織全体の業績にも影響するためです。また、組織に対する満足度や所属意識が高いとエンゲージメントスコアが高くなることもわかっています。エンゲージメントスコアが高い従業員は、ES(従業員満足度)、労働生産性ともに高い傾向にあります。
人事戦略に役立つ
ES(従業員満足度)調査の結果をもとに、従業員の成長や成果を可視化することで人事戦略に役立てられます。調査結果によって可視化されるのは、従業員の成長や成果だけではありません。課題を抱える従業員も把握できるため、人事配置が適切であるかの見直しにも有効です。従業員の個性や強みを活かせる適材適所の人材配置は、従業員のモチベーションに大きく影響します。
従業員の生の声を把握できる
従業員の生の声を把握することで、課題の早期発見・解決につながります。ES調査はアンケート形式で実施することが多いため、従業員の心からの声を収集しやすい特徴があります。上司や管理職などとの対面との面談では言いづらい悩みや課題もES調査ならば、聞き出せるでしょう。ES調査で収集した従業員の声をもとに、直接的に職場環境の改善が可能です。

ES調査(従業員満足度調査)の費用の目安
ES調査の費用は調査方法によっても異なります。一例としてはリサーチ会社に調査を依頼する場合には、1回あたり15万円~40万円前後が相場となるようです。このようにリサーチ会社などに依頼する際は費用が大きくなりがちのため、ES調査を実施する際にはあらかじめどの程度の費用がかかるのかを調べておき、費用を準備しておく必要があります。

ES調査(従業員満足度)の流れ
ES調査は4つのステップで行います。
ES調査(従業員満足度調査)の目的を明確化する
まずは、何のためにES調査を行うのかを明確化しましょう。ES調査の目的が曖昧なままだと、適切な調査が実施しにくくなります。たとえば、「離職率を低下させたい」「従業員のモチベーション向上につなげたい」「人事施策を検討したい」というように、目的を明確にしましょう。これにより、適切な調査の実施が可能になります。
調査対象の決定と質問項目の設計を行う
調査の目的を決定したら、具体的に誰に調査を行うのかを決めましょう。たとえば、全従業員を対象にするのか、入社〇年以上の従業員を対象にするのかというように、対象を細かく設定します。また、従業員に対してどのような質問を行うのか、具体的な質問項目の設計も合わせて行っておきます。
参考:【目的別】アンケートの設問例|作成する手順や回答率を上げる方法なども解説
回答依頼・集計・分析
調査対象や質問項目などの調査方法を決定した後は、実際に回答依頼を行い、集計からデータ分析まで行います。回答を依頼する際には、なぜ調査を行うのかという目的を従業員に周知しておくと協力を得やすくなります。集計やデータ分析には専門知識やノウハウも必要になるため、リサーチ会社のサポートを受けるとよいでしょう。
参考:アンケート結果を分析する方法とは?集計方法や分析の種類、実施する手順などを解説
施策の検討・実行
データの分析によって課題や問題点を見つけたら、課題に合わせて今後の改善策の検討を行います。施策は課題によって異なりますが、研修の実施や人事制度の改善などが考えられます。施策の検討が終わった後は、経営層と従業員に報告やフィードバックを行いましょう。経営層の理解や了承が得られたら、実際に施策を実行していきます。
フィードバックする
ES調査は、結果を把握して終わりではありません。その後の施策検討とともに、フィードバックも重要です。調査に携わった従業員や経営層に調査結果をまとめた資料や、見えてきた課題などを周知しましょう。時間の経過とともに回答者の意識が変わることもあります。調査から時間を掛けずに、フィードバックを実施しましょう。

ES調査(従業員満足度調査)の質問項目例
ES調査の主な質問項目としては、以下のような内容が挙げられます。
- 基本情報(年齢や勤続年数、役職など)
- 業務内容(難易度・充足感など)
- 負荷に関する内容(残業時間など)
- 上司に関する内容(コミュニケーションなど)
- 人事評価に関する内容(待遇など)
- 組織風土に関する内容(人間関係など)
以上の項目を基本として、新たな項目を増やしたり重視する項目を検討したりしましょう。

ES調査(従業員満足度調査)を実施する際の注意点
ES調査を実施する際には、注意したいポイントもあります。ここでは、3つの注意点を詳しく解説します。
適切な質問項目を選定する必要がある
自社が抱えている課題や目的に応じて適切な質問項目を設定しなければ、必要なデータを得ることは難しいでしょう。たとえば、質問内容が細かすぎると従業員に負担がかかってしまい、回答内容が適当になってしまうなどもよくある失敗として挙げられます。そのため、適切な質問内容や量を検討することが重要です。
調査の実施だけで終わらないようにする
ES調査は実施することが目的ではありません。ES調査の内容を分析して、そこから改善のための施策の検討や実行を行うことが重要です。調査すること自体が目的になってしまっては意味がありません。従業員満足度調査はあくまでも手段です。調査内容を分析して改善施策を実施し、よりよい労働環境を構築することが目的だと意識しましょう。
継続的な取り組みが必要になる
ES調査は1回実施すればよいというものではありません。ES調査を定期的に行うことで、従業員からの信頼が高まります。また、定期的にES調査を実施することで、実行した施策の効果なども見極めやすくなります。結果として企業の発展にもつながるため、継続的にES調査に取り組みましょう。
ES調査(従業員満足度調査)の集計・分析方法
ES調査の集計・分析方法は、目的や対象などによって、適しているものが異なります。ここでは、3つの集計・分析方法を解説します。
単純集計
単純集計は、データ全体を集計し総合点を導き出す方法で、大まかな分析に役立ちます。1つひとつの質問に対し、回答比率や回答の平均値を求めます。
満足度構造分析
満足度構造分析とは、従業員満足度が高い従業員がどの項目に満足度を抱いているか、その度合いから解決策を導き出す方法です。傾向を把握、分析することで、組織の強みがわかり、重視すべき項目も明確になります。従業員満足度が高い従業員データを総合的に分析することで、従業員満足度の高い社員の傾向の理解につながります。
クロス集計
クロス集計とは、部門や職種、年齢、性別、職位などの属性ごとに従業員満足度を集計する方法です。単純集計で、全体の傾向を把握した後、次の段階として実施します。クロス集計により、単純集計で明らかになった値をさらに深堀できます。クロス集計では、どのような視点で違いを分析するのか、分析軸の設定が重要です。
ES(従業員満足度)を向上させる取り組み
ESは調査結果を踏まえて、向上させることが重要です。ここでは、従業員満足度を向上させる取り組みを解説します。
ワークライフバランスを改善する
職場環境が整っていて、ワークライフバランスが充実していると従業員の満足度は高くなります。仕事だけでなく、プライベートの時間を確保することで、従業員に心の余裕が生まれるためです。仕事とプライベートのオンオフを切り替えて、充実した生活が送れるように、従業員本人だけでなく家族も利用できる支援制度の充実が求められています。
ワークライフバランスを改善する取り組みとして、以下の例が挙げられます。
- 育児・介護休暇の取得を促進する
- 副業を自由化する
- 定時退社を推進する
人事評価制度や給与形態を見直す
ES調査の結果、待遇面や人事評価に対する満足度が低いと判明した場合は、報酬や人事制度を見直す取り組みを実施しましょう。明確な評価基準、適切なフィードバックにより、「努力が認められている」と感じ、従業員満足度が向上します。また、給与形態を見直し、報酬を改善することで、従業員のモチベーションが向上し、定着率も安定するでしょう。
人事評価制度や給与形態を見直す例として、以下が挙げられます。
- インセンティブ制度を導入する
- 各種手当を充実させる
従業員の成長を促進する施策を導入
従業員の継続して働きたいという意思を醸成するためには、従業員の成長を促進する施策の導入が重要です。スキルや能力が磨ける業務や理想とするキャリアパスに邁進できる職場環境を用意しましょう。従業員は、キャリア形成やスキルアップが見込める組織に対し、将来性を見出します。
従業員の成長を促進する施策として、以下が挙げられます。
- 社内公募制度を導入する
- 他部署への異動制度を確立する
- 資格取得を支援する制度を設ける
社内のコミュニケーションを活性化する
上司や同僚、部下など、職場内の人間関係に対する満足度も、従業員満足度に影響します。社内のコミュニケーションを活性化し、チームワークの向上、他部署間の円滑な情報共有を実現しましょう。良好な人間関係を築くための例として、以下が挙げられます。
- 社内報を定期的に発行する
- コミュニケーションツールを導入する
- 1on1ミーティングを開催する

ES調査(従業員満足度調査)をスムーズに実施するならマクロミル
ES調査をスムーズかつ適切に行いたい場合には、マクロミルがおすすめです。マクロミルでは、ES調査の支援を行っています。アンケートの告知から回答画面の作成、データ集計までワンストップでサポートできるため、ES調査のノウハウがない企業でも安心です。
実績が豊富なだけでなく、無料集計ソフトも提供しています。これにより、集計やレポートの出力などもスムーズに行えるようになるため、施策の検討などにもつなげやすくなっています。

まとめ
ES調査とは、組織や仕事に対する満足度やモチベーションを定量的かつ客観的に把握することができ、自社の課題や問題点の改善につながります。ES調査にはノウハウが必要になるため、リサーチ会社などの支援を受けるとよいでしょう。
マクロミルでは、データの収集や分析だけでなく、利活用支援も行っています。マーケティングリサーチとデジタルマーケティングリサーチを中心に、多様な社会・消費者ニーズを分析し、消費者インサイトを提供しています。マクロミルではES調査の支援も提供しているため、ES調査の実施を検討している場合はお気軽にお問い合わせください。