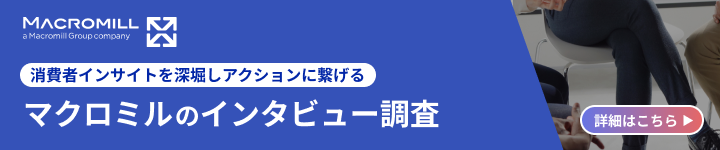定性調査をまとめることは、顧客のニーズやインサイトなどを把握するために必要です。定量調査と違い、数値化できない事象の回答を、商品やサービスの改善につなげられます。調査の結果を分析することで、新しいアイデアやヒントも得られるため重要です。この記事では、定性調査のまとめ方や分析方法などについて解説します。ぜひ参考にしてください。
参考:定性調査とは?基本から定量調査との違いや比較・メリット・手法まで解説
定性調査とは
定性調査とは、数値化できないものに対する調査です。「質的調査」とも呼ばれ、感情や価値観、行動、言葉などを調査します。また、定性調査はインタビューや観察調査を通して回答を集める方法です。アンケート調査だけでは得られない回答から、消費者の行動や思考、商品やサービスの改善点などの発見につなげられます。
定性調査と定量調査の違い
定性調査と定量調査の違いは、分析する対象です。定性調査は、行動や言動などを調べて、仮説の構築を目的としています。調査結果から得た消費者の潜在ニーズを分析することで、新しいアイデアやヒントにつなげます。定量調査は、仮説を検証するためのものです。調査結果を数値化して分析することで、実態や傾向などを把握できます。
定性調査をまとめる重要性
定性調査は、調査結果を伝える前提でまとめることが重要です。定量調査のように調査結果の数値化ができないため、結論を伝える工夫が必要です。調査に携わっていない人でも、分析した結果を理解できるようにまとめましょう。文章だけではなく、表や図などを使用してまとめることで、顧客のニーズを共有したり、理解を促したりすることができます。
定性調査の手法と特徴
定性調査の手法には、インタビューや観察調査などがあります。ここでは、それぞれの手法と特徴について解説します。
デプスインタビュー
デプスインタビューは、調査対象者と1対1で面談をする手法です。インタビューに適した人を選び、話を深掘りして回答を引き出します。デプスインタビューからは、購入に至るプロセスや気持ち、本音といった回答が得られます。調査対象の人と時間をかけて話をすることは、新しい発見や仮説の構築に有効です。
グループインタビュー
グループインタビューは、調査対象者を4〜8人程度集めて、質問に対して話し合う場を設ける手法です。司会者を中心にして調査対象者にインタビューすることで、質問の回答から意見やインサイトを見つけられます。グループインタビューでは、年齢や性別、職業などが異なる人を集めると、1度にさまざまな意見を集められます。
行動観察調査
行動観察調査は、調査対象者に同行する方法です。対象者の行動や習慣を観察することで、言語化されていない意識を可視化できます。たとえば、お店に入ってからの行動や、商品の比較検討、購入までのプロセスなどが挙げられます。行動観察調査やインタビューは、消費者の行動原理やインサイトの発見につなげられます。
訪問観察調査
訪問観察調査は、調査対象者の自宅を訪問する手法です。実際に商品やサービスを利用するところを観察し、使い方や使用環境などを調査します。訪問観察調査は、対象者本人だけではなく、同居する人の反応を調査する場合があります。たとえば、夫婦や親子同席で調査をすると、使用している人と、使用していない人の両方から反応を得られます。
定性調査のまとめ方の基本手順
定性調査は、調査対象者の発言をまとめて、レポートを作成します。ここでは、まとめ方の手順を解説します。
1.発言を書き写す
はじめに、インタビュー中の発言を書き写します。調査対象者の発言をExcelやWordにまとめた「発言録」を作成しましょう。当日に書き起こす、または音源や録画した映像などをもとに、発言を書き写します。発言した言葉はそのまま書き写す必要があるため、自動文字起こしをはじめとした、ツールの活用がおすすめです。
2.発言の内容を整理する
発言を書き写した後は、内容の整理をします。大事なポイントや共感を得たワード、共通性などをもとに整理しましょう。発言をグループごとに振り分けると、傾向やパターンをつかみやすくなります。インタビュー発言だけではなく、言葉の裏にある気持ちや考え方などをつかむことも必要です。
3.レポートを作成する
定性調査の目的をもとに、レポートを作成しましょう。主張に一貫性がある内容で、全体の文脈を統一させたレポートを作成することが重要です。レポートは関係者で共有するため、読みやすく、わかりやすいものでなければなりません。また、誰に向けてのレポートであるかを考えながら、工夫してまとめるとよいでしょう。
定性調査の結果を分析する方法
定性調査の結果は、適切な方法で分析する必要があります。ここでは、調査結果を分析する方法について解説します。
アフターコーディング
アフターコーディングとは、データにコードを割り当てることを指します。調査対象者の発言を言い換えて、コードをつけて割り振りましょう。データに番号や色などを設定して構造で整理すると、比較や関連付けができます。コーディングをすると発言がまとまって、パターンやテーマ、概念がつかみやすくなります。
上位下位関係分析
上位下位関係分析とは、項目の重要度を判別する方法です。調査結果のなかから重要と思われるものを抽出し、階層に分けて振り分けます。発言の頻度や強調の度合いなどでグルーピングすると、本質的なニーズを深掘りできます。インタビューや行動観察などのデータは、関連性や背景にある意味などの分析も必要です。
KJ法
KJ法とは、アイデアや情報などを整理する方法です。付箋やカードに情報を書き、グループごとに分けて整理します。KJ法は情報を多角的に分析することに適しており、ロジカルに整理したり、アイデアを可視化したりできます。情報をグループ化することで、大量にあるデータの関連付けやアイデアの発見などにつなげられます。
KA法
KA法は、本質的な価値を抽出する方法です。「出来事」「心の声」「価値」のカードを作成し、それぞれを関連性ごとにまとめて分析をします。大量のデータをマップ化して整理すると、問題点や解決策の発見につなげられます。カードをグルーピングする際は、色をつけたり、矢印をつけたりして関連性がわかるようにしましょう。
定性調査をまとめる際の注意点
定性調査は、本来の目的に合った情報をまとめなければなりません。ここでは、調査結果をまとめる際の注意点を解説します。
目的・仮説をもとにまとめる
定性調査は、本来の目的と仮説が重要です。目的を達成するために立てた仮説をもとに、調査した結果を分析しましょう。仮説をもとに調査すると、工程を具体的にできて、結果の質が向上します。調査結果を分析する際は、調査に関係のない情報は除きましょう。関連性の低い情報は、別のレポートを作成してまとめる必要があります。
定量的な分析を避ける
定性調査で求められるのは、数値で得られる結果ではなく、情報や質的なデータです。定量的な分析を避けて、事柄の背景や理由などをまとめましょう。多数決や割合などの判断をもとに、分析してはならない点に注意が必要です。ただし、洞察や深い理解を得たい場合は、定性と定量の分析を組み合わせることをおすすめします。
レポートの書き方を工夫する
レポートは、報告の形式で書き方を変えましょう。結果を簡潔に報告する場合は、内容を要約した「サマリーレポート」が適しています。より詳しい内容を報告しなければならない場合は、「フルレポート」という詳細な分析や知見をまとめたものが必要です。定性調査の目的によって書き方が異なるため、適切なまとめ方を選びましょう。
まとめ
定性調査は、結果を数値化できないため、まとめ方に工夫が必要です。文章だけでなく、表や図などを活用し、調査に携わっていない人でも理解できるまとめ方が求められます。目的・仮説をもとに調査結果をまとめて、消費者のインサイトや商品・サービスの改善につなげましょう。
マクロミルは、マーケティングリサーチとデジタルマーケティングリサーチを中心に、多様な社会・消費者ニーズを分析できます。クライアントに的確な消費者インサイトを提供するので、ぜひ利用をご検討ください。