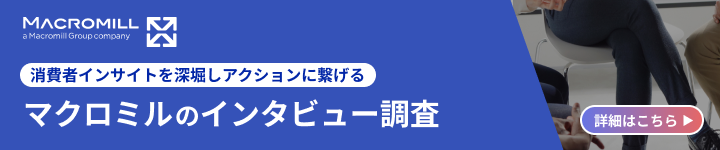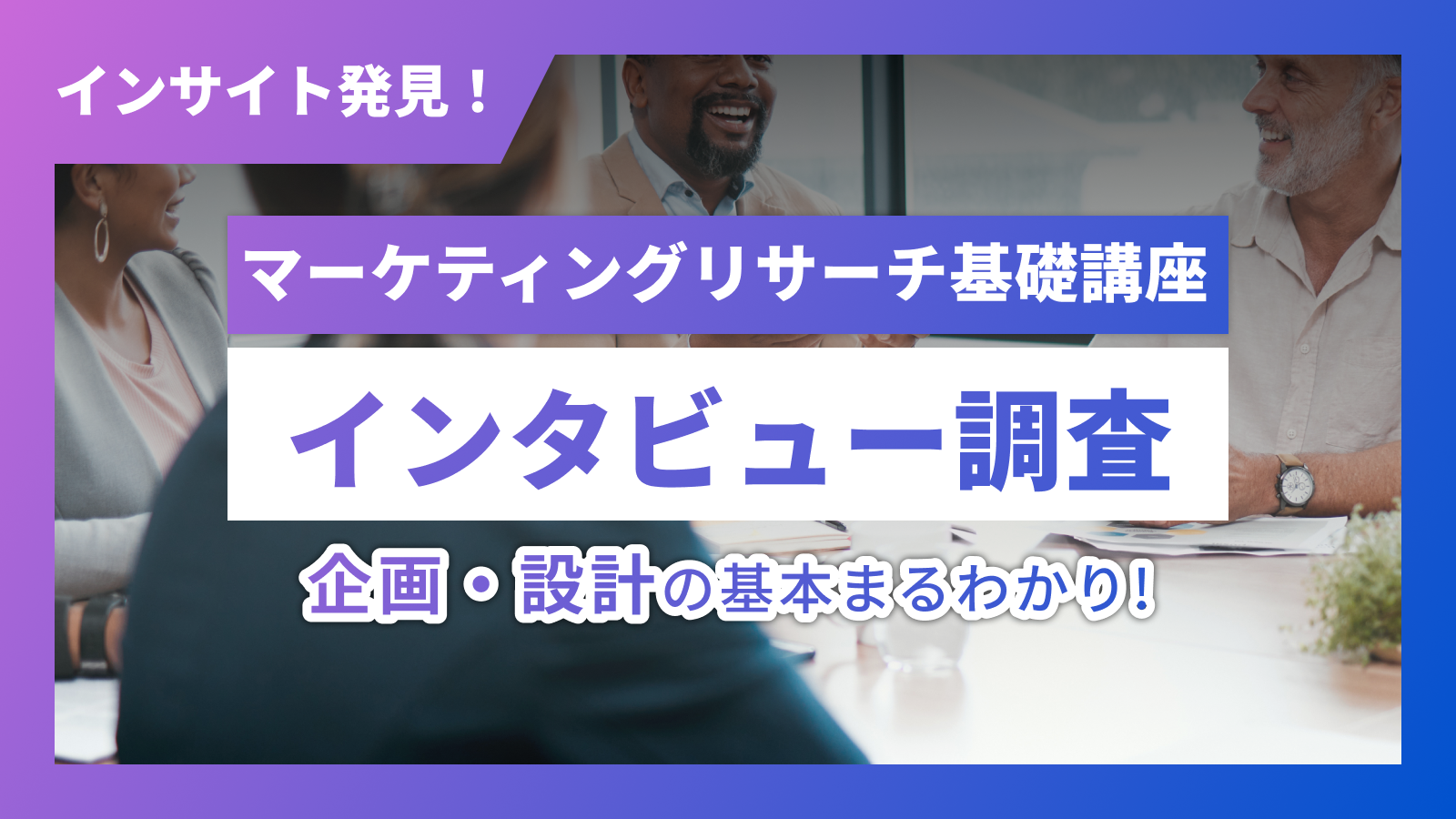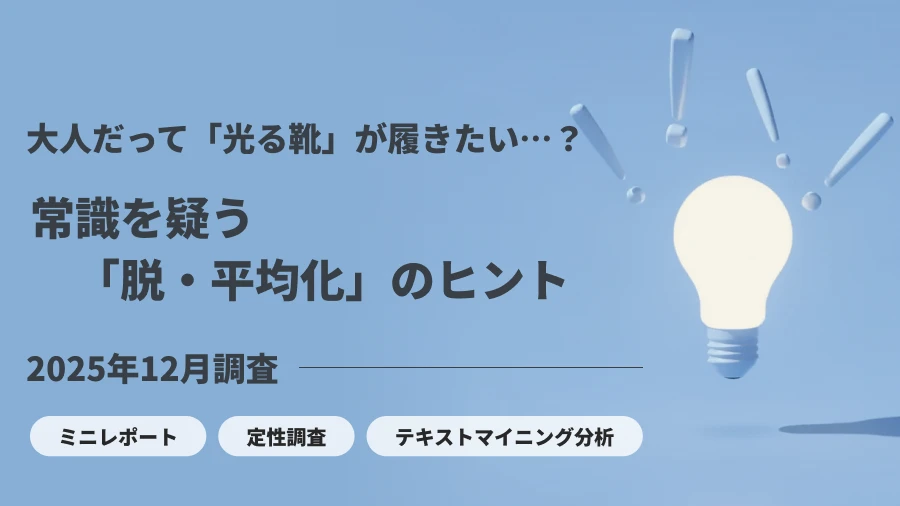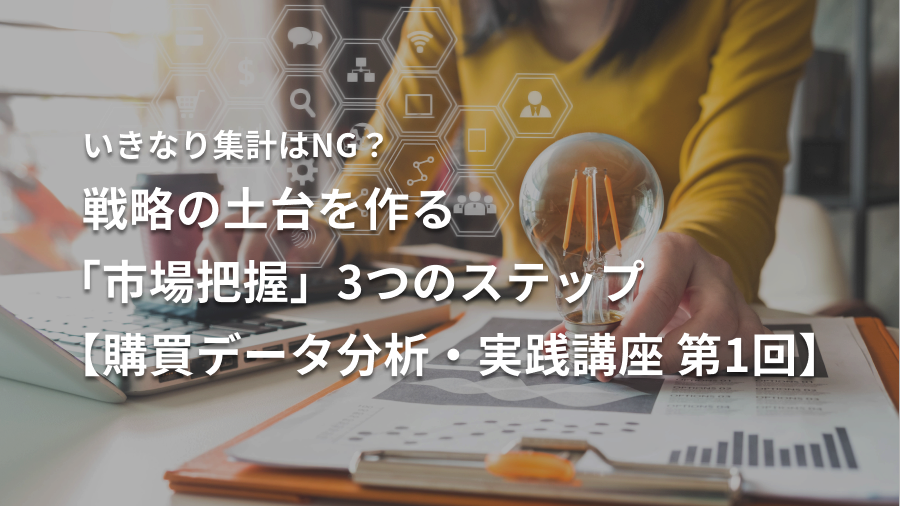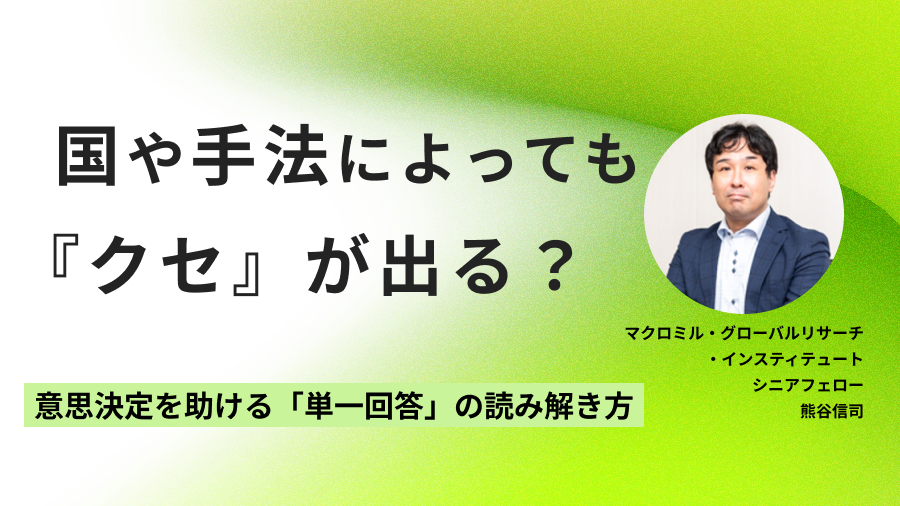グループインタビューとは? 複数の対象者から深い本音を引き出す定性調査の活用法
公開日 :2023/4/18(火)
最終更新日:2025/4/11(金)
グループインタビューとは、複数名の対象者を1つの場所に集め、特定のテーマや商品・サービスに関する意見を話し合ってもらう形式の定性調査の手法を指します。ときにはフォーカスグループインタビュー(FGI)と同義で扱われることもあり、対象者同士の対話や相互作用(グループダイナミクス)から得られるリアルな発言や感情の変化を把握できる点が特徴です。
- グループインタビューの基本概念
- グループインタビューが求められる背景
- グループインタビューの特徴
- グループインタビューと他の定性調査(デプスインタビューなど)の違い
- グループインタビューの実施プロセス
- グループインタビューの成功事例と実践的なヒント
- グループインタビューで注意すべき課題
- デジタル/AI時代におけるグループインタビューの今後の展望
- まとめ
グループインタビューの基本概念
定量調査(アンケートなど)は、数値や統計に基づき大まかな全体像をつかむのに優れています。しかし、消費者が実際に何を感じ、なぜその商品に魅力を感じるのか、あるいはどういった点に不満や不安を持つのかを深掘りするには、やはり定性情報が不可欠です。グループインタビューでは、対象者同士の発言が連鎖反応を起こし、個別のアンケートや1対1のデプスインタビューでは引き出しにくい気づきや意見が得られることが少なくありません。
一方で、グループインタビューは適切に設計しないと、一部の対象者が会話をリードしすぎたり、他の対象者の意見を飲み込んでしまったりといったリスクが存在します。モデレーターが対象者同士のやり取りを上手にファシリテートして、全員が発言しやすい空気を作ることが成功への大きなポイントとなります。また、最近ではオンラインで行うケースも増え、ファーストパーティデータやSNS広告でリクルーティングした対象者と遠隔でセッションを行う手段が一般化しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の時代にあって、ABテストやEFO(Entry Form Optimization)など定量的な観点でユーザー行動を解析する一方で、グループインタビューによる定性的視点を組み合わせる企業が増えています。
グループインタビューが求められる背景
オンライン化やSNS広告の活性化によってデータドリブンなマーケティングが盛んになる一方、Cookie規制の進展でサードパーティデータの限界が見え始めました。そのため、ユーザーとの直接的なコミュニケーションが行える場を確保し、より深いインサイトを得たいという需要が高まっています。
グループインタビューは、この「ユーザー同士が互いの意見を聞き合う」という独特の場から、新しい発見を得やすい手法です。たとえば、ある製品について「そこまで深刻に思っていなかった点が、別の参加者の体験談を聞いたことで大きな不満要因だと気づく」といったケースがよく見られます。これこそがグループダイナミクスの醍醐味であり、一対一のデプスインタビューや定量アンケートでは得にくい「発話の連鎖」を促す効果なのです。
また、グループインタビューは比較的短い時間(1〜2時間程度)で複数の対象者の意見を同時に収集できるため、コストパフォーマンスの面でも評価されることがあります。ただし、対象者間の関係や会話の流れを適切にコントロールする必要があるため、モデレーターの役割が極めて重要です。対象者が少数のリーダー的存在に発言を左右されないよう注意しながら、Cookie規制下でもオウンドメディアやファーストパーティデータを活用したリクルーティングで、多様な属性の対象者を集めて成功する例も出てきています。
グループインタビューの特徴
1. グループダイナミクス
グループインタビューの大きな特長は、対象者同士のやり取りから新たな意見が生まれる点です。ある対象者の発言がきっかけとなり、他の対象者が自分の経験を思い出したり、共感して追随したりします。この相互作用が定量調査では発見しにくいアイデアや感情の深層を明るみに出します。
2. 短時間で複数意見を得られる
通常、同数の対象者を個別にデプスインタビューするよりも、時間とコストを抑えて多様な視点を得られます。そのため、新製品の開発初期にイメージを固める段階や、コンセプトテストで大枠の方向性を決める際に有効です。
3. モデレーターのファシリテーション力が重要
グループインタビューを円滑に進めるうえでは、モデレーターが場を管理し、全員が発言しやすい空気をつくる必要があります。特定の対象者が会話を独占しないよう配慮したり、話題が逸れすぎないようコントロールする手腕が求められます。
このように、グループインタビューは「参加者同士の対話」という構造を巧みに活かして調査を進める手法と言えます。Cookie規制で企業がデータに制約を受ける中でも、参加者をSNS広告やコミュニティで募集し、多角的な意見を獲得しやすい方法となっています。
グループインタビューと他の定性調査(デプスインタビューなど)の違い
フォーカスグループインタビュー(FGI)という名称で呼ばれることもあるグループインタビューですが、1対1のデプスインタビューとの比較がよく行われます。一対一では当事者の感情を深く探れますが、対人関係による発話誘発は起きにくい側面があります。逆に、複数人が集まるグループインタビューでは参加者同士の会話が化学反応を起こし、思わぬ意見が飛び出す反面、個人のプライベートな話題や非常に感情的な内容は出にくい場合があります。
また、定量調査が数値や割合といった客観的指標を提供するのに対し、グループインタビューは主観的な語りをメインとするため、結果を統計的に一般化するのは難しいです。ただし、コミュニティやファーストパーティデータである程度セグメントを選んだうえで対象者をリクルーティングすれば、離脱率やCVRなどの数値で把握しきれないブランドロイヤリティやユーザーインサイトの内面部分を補う役目が期待できます。
フォーカスグループではさらに、企業や広告主が裏から観察できるように「ワンウェイミラー付きの会議室」で実施することが多く、実査中にチームがモデレーターへ指示を出すこともあります。より自然な発言を得るためには、対象者が企業担当者に気を使わない環境づくりが大切なので、オブザーバーは直接同席せず、隣室や映像越しで見る形が一般的となっています。
グループインタビューの実施プロセス
グループインタビューを行う際は、下記のようなステップが想定されます。
1. 目的とテーマ設定
まず、「新商品のアイデアを検証する」や「既存サービスに対する不満点を洗い出す」といった明確な調査テーマを決めます。このテーマに合致した質問項目と進行プロセスをプランニングします。
2. 対象者のリクルーティングとスクリーニング
調査対象としたい属性(年齢、性別、使用経験など)を考慮し、SNS広告やコミュニティ投稿で募集を行うなどして、複数人の対象者を抽出。ファーストパーティデータや社内顧客リストを活用すればスムーズに適正な対象者を集めることができます。
3. モデレーターガイドの作成
モデレーターが会話の流れを管理しやすいよう、導入(アイスブレイク)→主題の質問→深掘りの質問→まとめ、といったシナリオを用意。ただし、対象者同士の相互作用を尊重する柔軟さも重要です。
4. 実査(グループセッション)
通常、4〜8人程度の対象者を1〜2時間集めて行います。モデレーターは場の進行を行い、参加者が対等に話せるように留意。離脱率やCVRに直接かかわるUX・UI関連のフィードバックが出たら深掘りを促すなど、適宜方向を調整します。
5. 記録・分析・レポート作成
音声録音やビデオ撮影を行い、可能であれば逐語録(トランスクリプト)を作成。そこから共通するキーワードや発言の流れ、対立する意見などを整理し、最終的に企業のPDCAサイクルに組み込める形でレポーティングします。最近では逐語録をAIで自動化し、インタビュー終了直後に簡易的なレポートを作成するやり方も増えています。
この一連のプロセスを通じて、SNS広告や検索連動型広告だけでは見えづらい生の声を集め、ブランドロイヤリティ強化やUXの大幅改善につなげられるわけです。
グループインタビューの成功事例と実践的なヒント
ある化粧品メーカーが、新たなフェムテック領域の商品コンセプトを市場に投入する前にグループインタビューを実施しました。製品サンプルを参加者に触れてもらい、匂いや使い心地に対する感想を集めるだけでなく、SNS広告を見た感想やパッケージデザインへの印象なども議論。結果として、広告費を過度に投入する前の段階で潜在的な不満点(価格帯、デザインテイストなど)が明確になり、改良版を投入してからはCVRとユーザー満足度が同時にアップしたというケースがあります。
別の例では、家電メーカーがユーザーコミュニティの積極参加者を対象にオンラインでグループインタビューを行い、新機能のUI設計をブラッシュアップ。Cookie規制で詳細なターゲティングが難しくなるなか、ファーストパーティデータを使いリピート購入者を中心にグループを組成したことで、エントリーフォームの不備やステップメールの文面に対する率直なフィードバックも得られ、UX改善に大きく寄与したそうです。いずれの例でも、モデレーターが対象者同士の会話を適切に誘導し、ABテストなどと連携したPDCAを回せる仕組みを組み合わせていたのが成功要因として挙げられます。
グループインタビューで注意すべき課題
1. 偏りやグループシンク(集団浅慮)
グループインタビューでは、一部の参加者の意見に他の参加者が流される「集団浅慮(グループシンク)」や圧力が生じるリスクが高まります。対策として、モデレーターが全員に均等に発言を促したり、話しにくい人へピンポイントで質問を投げかけたりすることが必要です。
2. モデレーターのバイアス
質問や進行の仕方で、結論を誘導するような言動があると、調査結果が歪められます。たとえば「この機能すごく便利ですよね?」というリード質問は避け、オープンな問いや話の掘り下げに徹するのが理想です。
3. プライバシーやデリケートな話題
性や健康面などセンシティブなテーマを扱う場合、グループ環境では話しにくい対象者がいるかもしれません。デプスインタビューなどの手法を併用したり、発言が強制にならないよう配慮するなど、トピックやリクルーティング段階で対策が必要です。
4. データ分析の難しさ
定量データのように統計的な有意差を示すことは難しく、対象者全体の発言をどこまで一般化できるかは判断が求められます。複数回のグループインタビューを行い、発言の傾向が一致するか確認するなど、複数の視点から分析すると精度が向上します。
デジタル/AI時代におけるグループインタビューの今後の展望
オンラインでのビデオ会議ツールの普及により、地理的に離れた対象者を集めてグループインタビューを行う事例が急増しています。コロナ禍以降、遠隔でのやり取りが一般化したため、企業は広告費や会場費を軽減しつつ多様な地域や属性の対象者と会話できるようになりました。一方で、対面で得られる細かな空気感や身体言語を捉えづらくなるという欠点もあり、バランスを見極めることが重要です。
DXの深化とともに、マルチモーダル解析や大規模言語モデルなどのAIがグループインタビューで生成された発言データをテキストマイニングする手法も発展していくでしょう。参加者同士の発話をリアルタイムで分析し、PDCAサイクルを短期間に回すことが可能になると、コミュニティ運営やファーストパーティデータを使った高度なマーケティングがさらに加速するでしょう。
ただし、いかにテクノロジーが進化しても、人間同士がその場で意見を交換するというグループインタビュー固有のメリットは色褪せにくいと考えられます。対象者同士の連鎖反応が生み出す新しい気づきは、単なるアンケートや一対一のデプスインタビューでは得にくいものだからです。Cookie規制や広告費高騰、サードパーティデータの制限に左右されず、本音を把握する手段としてグループインタビューが果たす役割は引き続き大きいといえます。
まとめ
グループインタビュー(Group Interview)とは、複数の対象者が一堂に会して特定のテーマについて語り合う、定性調査の代表的手法です。フォーカスグループインタビュー(FGI)とも呼ばれることも多く、対象者同士のやり取り(グループダイナミクス)を活かして多様な意見や未顕在のニーズ、感情のきっかけを探ることができます。近年はSNS広告や検索連動型広告などデータドリブンの方法が充実する一方、Cookie規制で取得できる行動ログが制限される背景からも、ファーストパーティデータやコミュニティとの連動を図るうえでグループインタビューの価値が再認識されています。
ただし、一部の参加者の意見に他の参加者が流されやすい「集団浅慮」や、モデレーターのリード質問による回答誘導など、注意すべき点も少なくありません。対面とオンラインのどちらで実施するかによって、空気感や発言の深度が変わる可能性も大きいです。ユーザーにとってセンシティブな話題の場合は、グループ環境よりも一対一のデプスインタビューが適しているケースもあるでしょう。
それでも、調査費を大きく投入せずとも、複数の対象者が互いの発言に触発されながらリアルな意見を交わす場が得られるのはグループインタビューならではの魅力です。PDCAサイクルの一環として、プロトタイプや広告クリエイティブ、UI/UXのコンセプトを検証する際にも有用で、短時間で多層的なインサイトを得たい企業や組織に支持されています。今後もDX時代のマーケティングリサーチや商品開発において、グループインタビューは本音やコミュニティの声を捉える手段として欠かせない存在であり続けるでしょう。