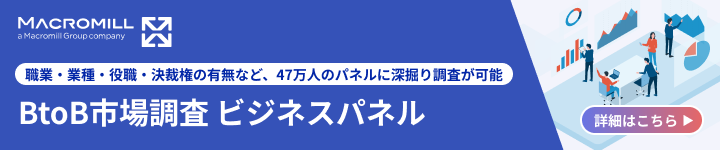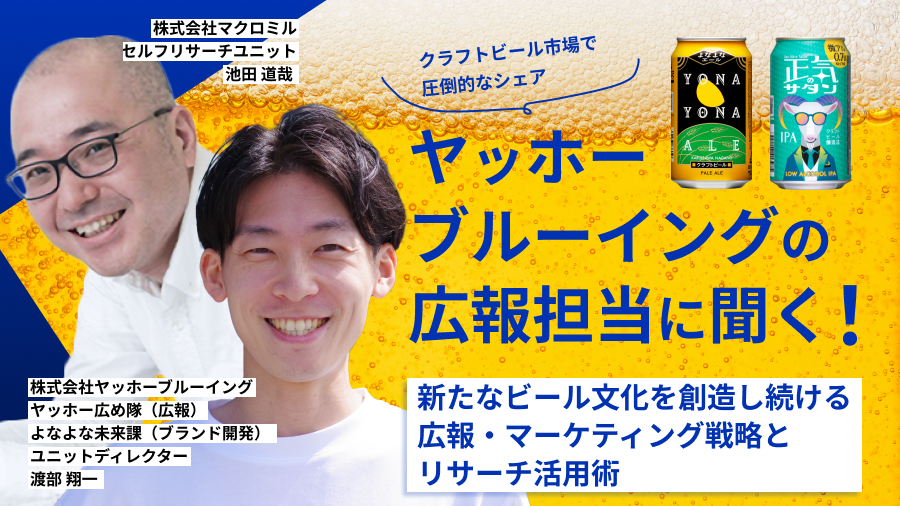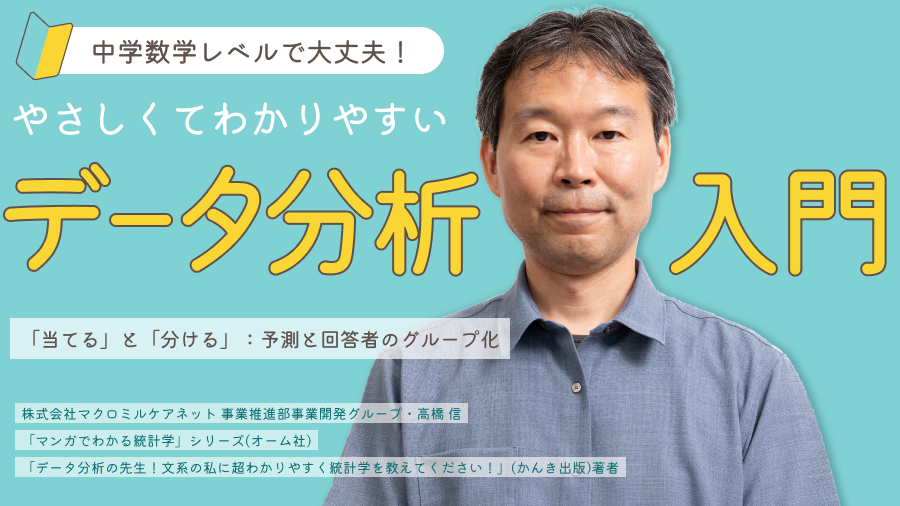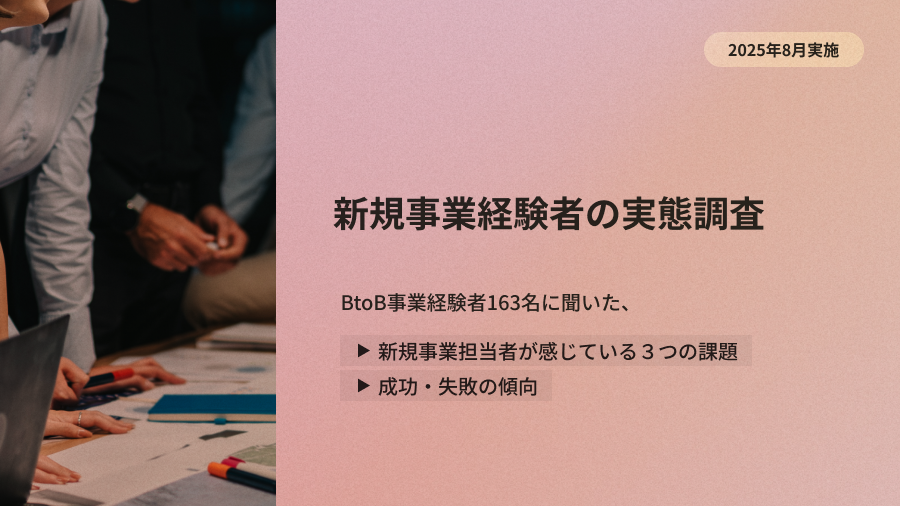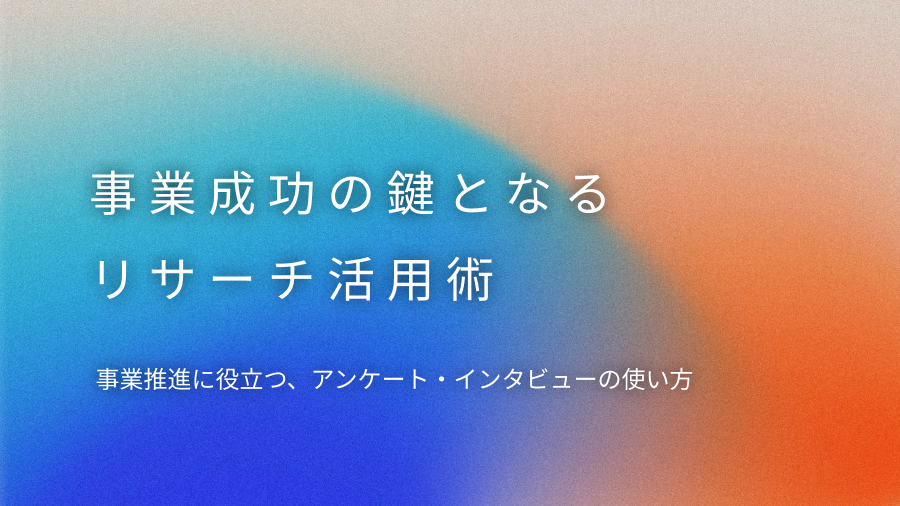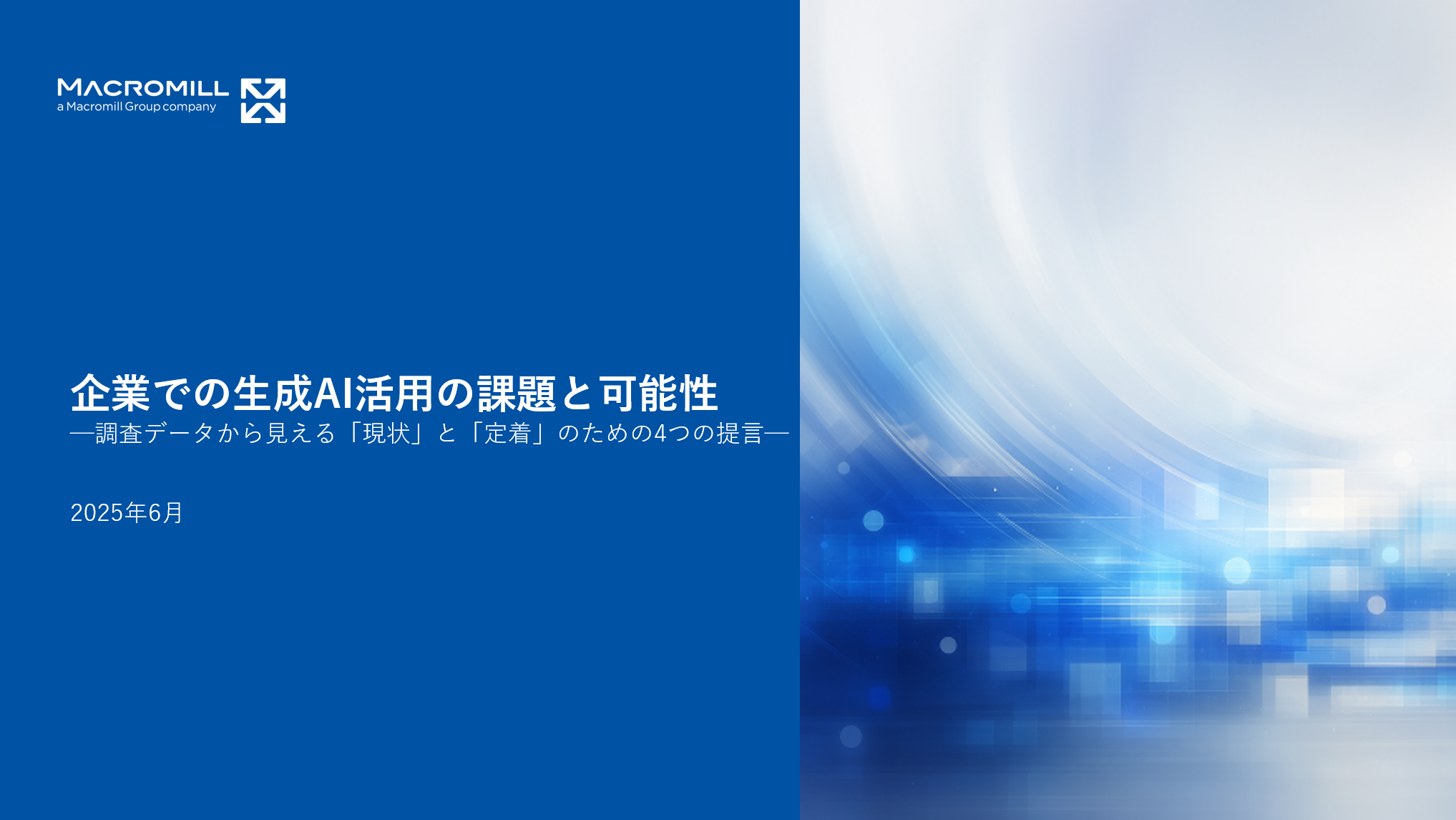「リードは増えたのに、商談化しない」
「優良顧客層へのアプローチ率が低い」
「営業が本当に欲しいリードが取れていない」
BtoBマーケティングに携わる企業の多くが、量から質への転換点に直面しています。大量リード獲得型のマーケティングでは、顧客単価が高く、検討期間も長いBtoB商材の購買行動に合致しないケースが多く、結果として“マーケと営業の分断”を生むことも少なくありません。
そこで注目されているのが「ABM(アカウントベースドマーケティング)」です。
ABMとは、「自社にとって重要なターゲット企業(アカウント)を事前に特定し、営業とマーケティングが連携しながら個社単位でアプローチしていく戦略」です。“リード単位”ではなく、“企業単位”で設計されることが最大の特徴であり、特に営業接点の重要性が高いBtoBビジネスにおいて、成果につながりやすいモデルとされています。
本コラムでは、ABMの定義から導入背景、実施の流れ、活用ツール、成功事例、従来のマーケティングとの違い、導入時の注意点まで、BtoB企業が押さえておくべきABMの全体像を解説します。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- ABMの定義と背景:「アカウント単位の戦略設計」とは
- 従来のリード型マーケティングとの違い
- ABMの代表的な実践ステップ
- ABMで活用されるツールとデータ基盤
- ABM成功事例:営業・マーケ連携の効果とは
- ABMを始める際の注意点と壁の乗り越え方
- まとめ:ABMは“顧客と並走する戦略”である
ABMの定義と背景:「アカウント単位の戦略設計」とは
ABM(Account Based Marketing)とは、従来の「リードを広く集めるマーケティング手法」に対して、「あらかじめ営業・マーケが選定した特定の企業(アカウント)に対して、個別最適化した施策を展開するマーケティング戦略」を指します。
リード単位ではなく、アカウント単位でターゲティング・コンテンツ・チャネル・営業連携を設計することで、以下のような特徴があります。
- 商談化・受注確度の高い企業だけに集中投資できる
- マーケと営業が“共通のターゲット”を追える
- 顧客との関係性が“量より深さ”で強化される
ABMの考え方は、もともと米国のテック系BtoB企業で生まれ、エンタープライズ営業における“商談の質と密度”を高める戦略として発展しました。近年では、ツールの普及やデータ整備の進展により、日本国内でも中堅企業やSaaSベンダーを中心に導入が広がっています。
従来のリード型マーケティングとの違い
ABMの特徴をより深く理解するためには、従来型の「リードベースマーケティング」との違いを明確にしておく必要があります。以下に両者の違いを表で整理します。
| 比較項目 | リード型マーケティング | ABM(アカウントベース) |
|---|---|---|
| 対象の単位 | 個人(リード) | 企業(アカウント) |
| アプローチ対象の選定 | 広くリードを集めてから絞る | 最初に企業を選び、深く掘る |
| マーケと営業の連携 | 分業型/情報連携に課題あり | 共通のターゲットに一体で動く |
| コンテンツや施策 | 汎用的・セグメント別 | 個社ごとにパーソナライズ |
| 成功指標 | リード獲得数、コンバージョン率 | アカウントごとの商談化・受注率 |
| 向いている商材 | 単価が低く購買サイクルが短い | 単価が高く複数人の意思決定がある |
ABMは、いわば「営業型マーケティング」とも言えるアプローチです。特定企業に深く入り込み、関係性を育てながら商談を創出していく。そのため、「数よりも精度」「情報よりも信頼」が重視されます。
ABMの代表的な実践ステップ
ABMは戦略であると同時に「プロセス」です。以下のようなステップで段階的に実践されます。
STEP1:ターゲットアカウントの選定
最初に行うべきは、「どの企業にアプローチするのか」の選定です。ここでは、営業とマーケティングが連携しながら、受注単価、LTV、業界、過去の受注傾向などを基にターゲットリストを作成します。
例:
- 上場しておりDX推進に積極的な製造業
- 売上100億円以上かつマーケ専任者がいる企業
- 過去に失注したが、改めてアプローチしたい企業群
STEP2:アカウントごとのインサイト収集
ターゲット企業ごとに、業界課題、事業計画、組織構造、既存ベンダーの状況などの情報を収集します。これは、個社別提案の「解像度」を上げる重要なフェーズです。
手段:IR情報/ニュース/SNS/営業ヒアリング/外部データベース(Fourin、SPEEDAなど)
STEP3:コンテンツ・提案のパーソナライズ設計
ABMでは、アカウント単位に最適化した情報提供が求められます。以下のようなアウトプットが想定されます。
- 企業別の課題仮説に基づいた提案書
- 業界特化型の導入事例集
- 経営層向けの短時間動画レター
- 担当者別のFAQシート
「その企業のために作った」と感じられる施策は、情報の価値を一気に高めます。
STEP4:営業との連携とアプローチ開始
マーケ側がアプローチの道筋を整備した上で、営業と連携してアカウント単位での接点を増やしていきます。
たとえば、以下のような施策があります。
- 担当者向けにイベント・セミナーを開催
- 経営層へは経営課題レポートを直接送付
- ナーチャリングメールをパーソナライズして配信
営業とマーケが“連携”ではなく“共闘”することが、ABMを成功させる鍵です。
STEP5:成果の可視化と改善ループ
ABMでは、単に「反応があったかどうか」だけでなく、アカウント単位での商談化率、滞留期間、意思決定速度などを計測し、フェーズごとに改善を繰り返します。
例:
- 30社にアプローチ → 15社で接点化 → 6社で商談化 → 2社で受注
- 担当者接点数 × 意思決定者接点数の関係性を分析
- 事例提示あり/なしで商談継続率を比較
ABMで活用されるツールとデータ基盤
ABMを実践する上で重要なのが、「どの企業に、どのような情報を、どのように届けるか」を設計・実行・分析できるツール群とデータ基盤です。以下に、ABMにおいて活用される主なツールと役割を整理します。
MA(マーケティングオートメーション)
ABMにおいても、リードの育成やスコアリング、セグメント別コンテンツ配信にMAツールは不可欠です。Account Engagement(旧Pardot)、Marketo、HubSpotなどが代表格で、以下のような場面で活躍します。
- 特定アカウントに対してカスタマイズされたシナリオを配信
- 営業アラートをスコアと行動履歴に基づき自動送信
- アカウントごとの反応データを営業に共有
SFA/CRM
SalesforceやMicrosoft DynamicsなどのSFA/CRMは、ABMにおける“営業連携”のハブです。担当者情報、組織構造、過去の接点履歴などを蓄積・可視化し、マーケティングからの情報を営業が受け取りやすくする機能を担います。
- ターゲットアカウントのコンタクトマップを構築
- MAと連携して行動履歴を可視化
- キーマンの反応を営業ダッシュボードに表示
ABM特化型ツール(インテントデータ・広告連携)
近年では、ABMに特化したツールも登場しています。
- FORCAS(ターゲット企業の分析・インサイト可視化)
- LinkedIn広告(職種・企業単位でのターゲティング)
- Demandbase(インテントシグナルの可視化)
- BABLE(キーマンへのパーソナライズド広告配信)
これらを活用することで、“相手が興味を持ち始めた瞬間”にアプローチすることが可能になります。
データ連携・分析基盤(CDP・BI)
CDP(Customer Data Platform)やBIツール(Tableau、Lookerなど)を導入すれば、複数のツールにまたがったアカウント単位の行動データを統合し、ダッシュボードで可視化することができます。
ABM成功事例:営業・マーケ連携の効果とは
事例①:SaaS企業A社 – 成約単価が1.6倍に向上
A社では、売上の80%を占める大手企業に対し、既存のリード獲得型施策ではアプローチが難しくなっていた。そこで、20社をABMターゲットに選定し、1社ずつ専用のセミナー、事例資料、提案書を準備。営業・マーケが週次で状況を共有。
その結果、接点化率は60%、商談化率は40%、成約単価は従来の1.6倍に向上。「営業だけではつかめなかった接点」がマーケティング支援によって広がった。
事例②:製造業B社 – 分散していたリソースをABMに集中して効率化
B社は全国にある営業所が個別に展示会やDMを実施しており、ROIが不透明だった。ABM導入後は、共通のターゲット企業を設定し、業界特化型のホワイトペーパーとウェビナーを一元化。行動データをSalesforceで共有する仕組みを構築。
結果、営業から「温まっているリードだけに注力できる」と好評で、商談リードの成約率が2倍に。費用対効果も大幅に改善された。
ABMを始める際の注意点と壁の乗り越え方
ABMは非常に効果的なアプローチですが、導入初期にはいくつかの“つまずきポイント”があります。
営業とマーケが“協業”ではなく“ただの並列”になってしまう
形だけの連携では、マーケが出した情報を営業が活用せず、ABMが機能しません。
<解決策>
SLA(Service Level Agreement)を定め、「いつ・どのスコア・どの反応があったら誰が何をするか」を明文化し、共通KPIで管理することが重要です。
コンテンツ制作に工数がかかりすぎる
1社ごとにカスタマイズした施策を行うと、負荷が大きくなることがあります。
<解決策>
個社向けコンテンツは「テンプレート+要素差し替え」で運用可能にする。業界別資料やケース別FAQなど“半パーソナライズ”でも効果は十分あります。
成果が出るまでに時間がかかる
ABMは中長期戦略であり、短期のCPA改善とは目的が異なります。
<解決策>
成果指標を「接点化率」「商談化率」「ターゲット企業との関係構築進度」などに再定義し、数値ではなく“関係の質”で価値を捉える視点が必要です。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
まとめ:ABMは“顧客と並走する戦略”である
ABM(アカウントベースドマーケティング)は、単なる手法や施策ではありません。それは、営業とマーケティングが“一社ごとの顧客に寄り添う”という、BtoBビジネスの本質に立ち返った戦略です。
- 「この企業に売りたい」ではなく、「この企業と関係を築きたい」
- 「リード数」ではなく、「関係の質」で成果を測る
- 「情報の提供」ではなく、「意思決定の支援」を行う
ABMは、短期的なリード獲得競争から脱却し、本当に価値のある顧客との“長期的な関係構築”にフォーカスします。だからこそ、マーケティングのあり方を変え、営業の成果にも直結するのです。
もし、リードの“質”や営業との連携に課題を感じているなら、ABMは“次の一手”になるはずです。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル