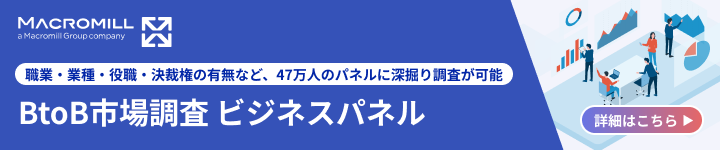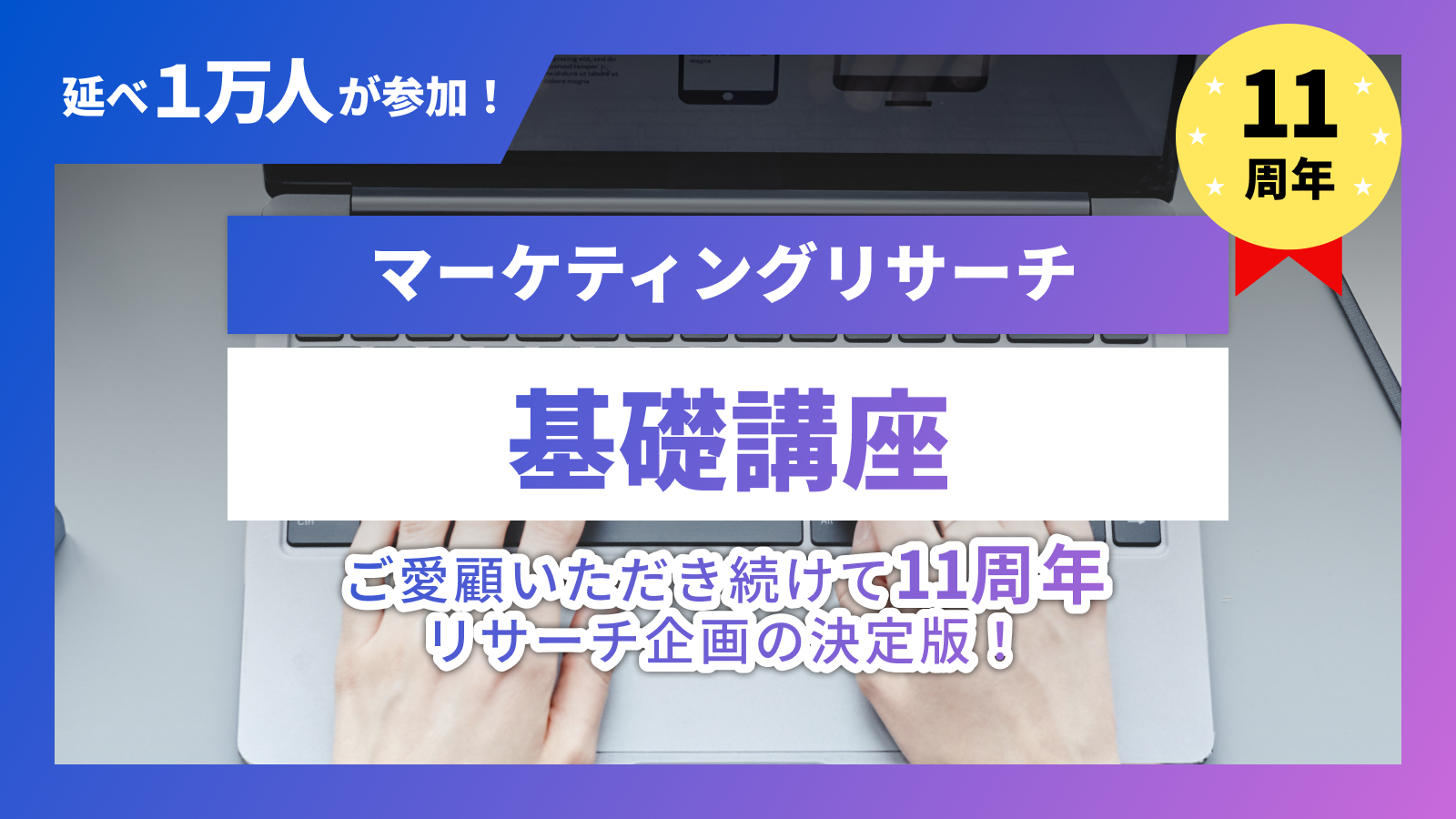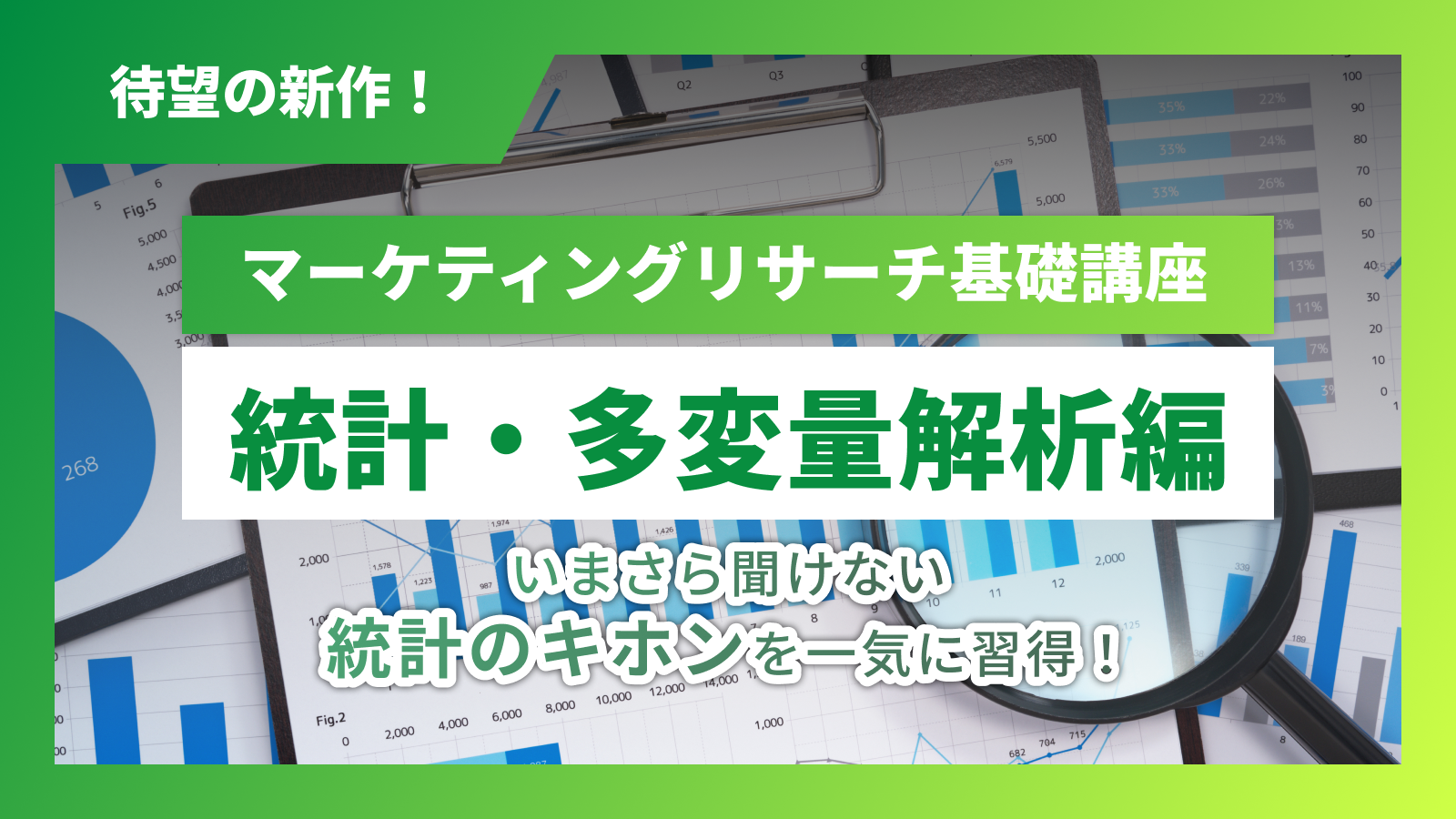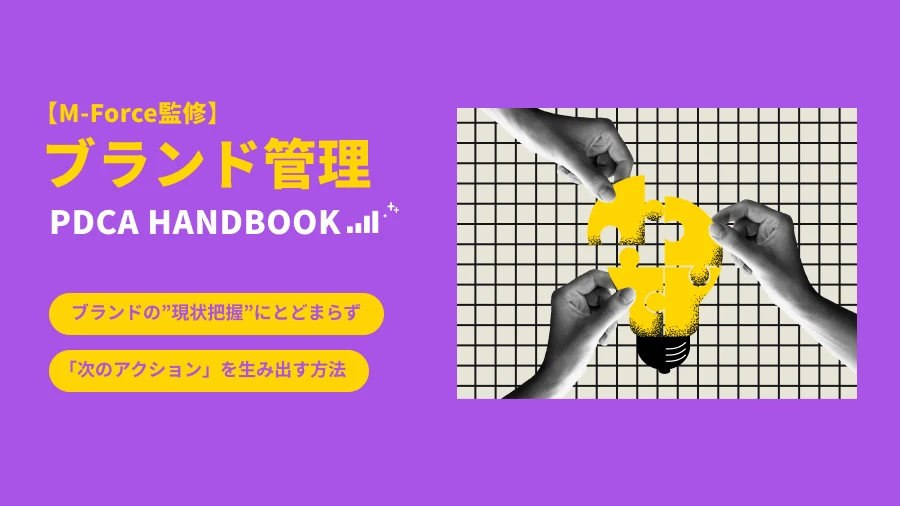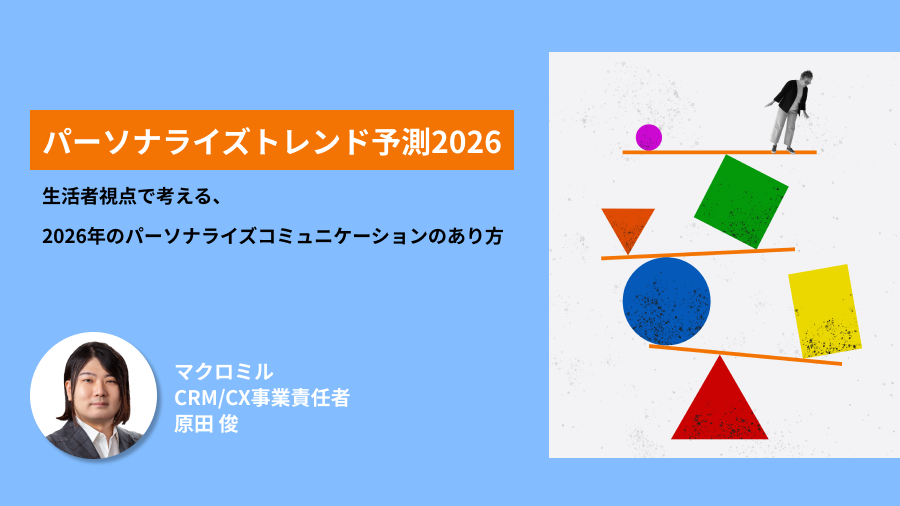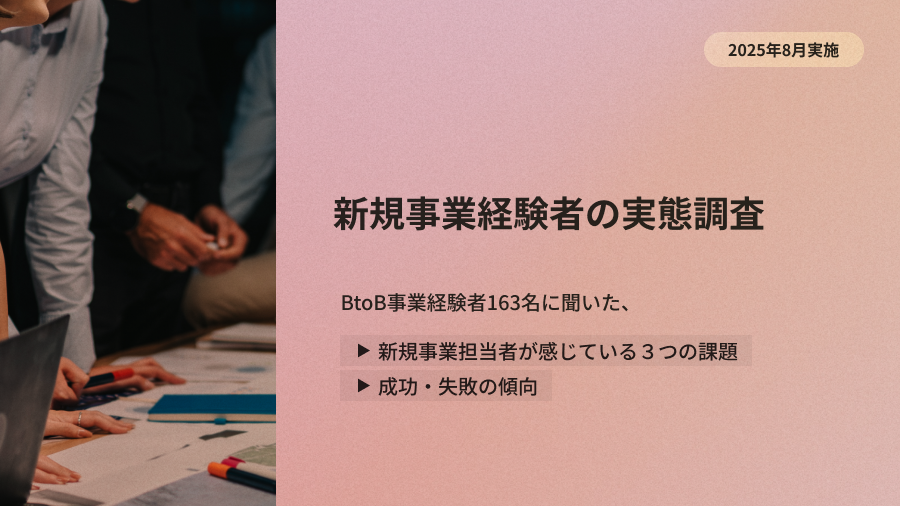「いい商品なのに、なぜ反応が悪いのか?」
「広告費をかけても、一過性で終わってしまう…」
「“売り込まない”マーケティングって、どうやるのか?」
こうした悩みを抱える企業がいま注目しているのが「コンテンツマーケティング」です。
コンテンツマーケティングとは、自社が提供する価値や専門性を“情報”として発信し、見込み客との関係性を築きながら、最終的に購買や問い合わせにつなげるマーケティング手法です。広告のように“押し込む”のではなく、相手にとって「役立つ・面白い・納得感がある」情報を届けることで、自然と信頼と関心を高めていきます。
本コラムでは、コンテンツマーケティングの基本的な定義から、BtoB企業における活用シーン、戦略設計、主要チャネル、成功事例、そして成果を出すための実践的な考え方までを、体系的に解説していきます。
【BtoB事業に関わる方必見!課題別アプローチ方法の資料を公開中】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- コンテンツマーケティングの定義と目的
- なぜ今コンテンツマーケティングが求められるのか?
- 代表的なコンテンツの種類と活用場面
- 戦略設計のフレームワーク(ペルソナ/ジャーニー/KPI)
- SEOとの関係とコンテンツ最適化の考え方
- コンテンツの流通設計:チャネルと拡散の工夫
- 成功事例:BtoB企業での実践と成果
- 継続運用の壁と乗り越え方
- まとめ:信頼はコンテンツから生まれる
コンテンツマーケティングの定義と目的
コンテンツマーケティングとは、「見込み客や顧客にとって価値ある情報(コンテンツ)を継続的に発信することで、信頼関係を築き、最終的な購買行動や問い合わせにつなげるマーケティング手法」です。
この手法の本質は、「売り込まないで売ること」。直接的な広告や営業ではなく、“課題を解決するための情報”を提供することで、顧客の購買プロセスに寄り添い、無理なくファンや顧客になってもらう仕組みです。
代表的な目的には以下があります:
- ブランド認知の拡大
- リードの獲得と育成(リードジェネレーション/ナーチャリング)
- SEOによる検索流入の獲得
- 営業支援(提案に使える事例やホワイトペーパーの整備)
- 顧客ロイヤルティの向上(導入後の活用促進)
「誰に・何を・どう伝えるか」を戦略的に設計することで、広告よりも長期的かつ費用対効果の高いマーケティングを実現できます。
なぜ今コンテンツマーケティングが求められるのか?
コンテンツマーケティングは決して新しい概念ではありませんが、ここ数年でその重要性が急激に高まっています。その背景には、顧客の購買行動と情報の取得スタイルの大きな変化があります。
① 顧客は“自分で調べてから問い合わせる”時代に
BtoBでもBtoCでも、顧客は営業に問い合わせる前にネットで製品やサービスを調べるのが当たり前になりました。実際、BtoBの購買行動の約6〜7割は営業接点前に完了しているとも言われています。
つまり、「営業が話す前に、顧客は意思決定の大半を終えている」のです。では、その過程で参考にされているのは何か?――それこそが企業の提供する“コンテンツ”です。
② デジタル広告に対する信頼の低下と情報過多
リスティング広告やバナー広告は、見られない・信じられない時代に突入しています。一方で、検索結果からたどり着いたブログ記事や、課題に直結したホワイトペーパーは「自分で選んだ情報」として信頼されやすく、コンバージョンにもつながりやすい傾向があります。
③ 営業の“提案材料”としても価値がある
コンテンツはマーケティング部門だけでなく、営業部門にとっても武器になります。たとえば、提案資料に導入事例を差し込んだり、ヒアリング後に「課題別解決ガイド」を送ったりすることで、営業の信頼性が高まり、クロージング率も上がります。
このように、コンテンツは“集客のための素材”を超えて、「顧客との関係をつくり、育て、深めるための戦略資産」へと進化しています。
代表的なコンテンツの種類と活用場面
コンテンツマーケティングでは、「誰に・どんな情報を・どのタイミングで届けるか」が重要です。ここでは、代表的なコンテンツの種類とその活用場面を紹介します。
ブログ記事(オウンドメディア)
SEO流入の起点であり、最もベーシックな施策。課題解決型・ノウハウ型・トレンド解説型など、ペルソナの興味に応じてテーマを設計します。
活用場面:潜在層の認知・リードジェネレーションの起点
ホワイトペーパー/eBook
より深い情報提供を目的としたダウンロードコンテンツ。フォーム入力によるリード獲得につながることが多く、リードナーチャリングの起点になります。
活用場面:情報収集中のリード育成、営業パス前の“関心温度”測定
導入事例(カスタマーストーリー)
「自社と似た課題を持った企業がどう解決したか」を示すことで、読み手の共感と信頼を引き出せるコンテンツです。営業時にも活用しやすく、コンバージョンへの最後の後押しにもなります。
活用場面:比較検討・社内説得フェーズ、営業支援ツール
セミナー/ウェビナー動画
リアルタイムでも録画でも、テーマ特化型で学びを提供できるコンテンツ。視聴データはMAやCRMと連携させてスコアリングに活用できます。
活用場面:課題が顕在化している層へのアプローチ、ナーチャリング中のリードの熱量測定
メールコンテンツ(ナーチャリング用)
ステップメールやセグメント別配信によって、見込み客の関心に合わせて情報提供できます。「コンテンツそのものが目的」ではなく、「リードとの接点継続」が主目的です。
活用場面:MA活用下でのシナリオ設計、定期フォローアップ
戦略設計のフレームワーク(ペルソナ/ジャーニー/KPI)
成果を上げるコンテンツマーケティングは、場当たり的に記事や資料を作っているわけではありません。明確な戦略設計に基づき、「誰に」「何を」「どう届け」「どう評価するか」が設計されています。ここでは、コンテンツ戦略に欠かせない3つのフレームを紹介します。
① ペルソナ設計:誰のためのコンテンツかを明確に
ペルソナとは、理想的な顧客像を具体的に描いたモデルです。職種・役職・業界・日々の業務・課題・情報収集の習慣などを掘り下げ、「どんな時に、どんな情報が必要になるか」を逆算することで、コンテンツの方向性が決まります。
例:
- 役職:マーケティング部 部長
- 業種:IT/SaaS
- 主な課題:リードは増えているが商談化率が低い
- 検討中の施策:MAの導入、インサイドセールス体制の強化
② カスタマージャーニー:フェーズごとの“問い”を把握
見込み客は、「認知→関心→比較→導入検討→意思決定」というプロセスを経て購買に至ります。これをカスタマージャーニーと呼びます。各フェーズで「どんな疑問を抱き、どんな情報を求めているか?」を可視化することで、コンテンツのテーマとフォーマットを的確に設計できます。
例:
- 認知フェーズ:「業務が非効率な気がするが、他社はどうしてる?」
- 比較フェーズ:「A社とB社、何が違う?」
- 決定フェーズ:「ROIや導入プロセスは?社内説得できる材料が欲しい」
③ KPI設計:成果を測る指標を定めておく
コンテンツ施策は「効果が見えにくい」と言われがちですが、KPI設計によって改善可能な仕組みに変わります。代表的な指標は以下のとおりです:
- 記事単位:ページビュー、平均滞在時間、直帰率
- ダウンロード系:コンバージョン率、資料DL数
- 全体:オーガニック流入数、MQL数、商談化数、受注率
KPIを「評価」ではなく「改善」のために使うことで、コンテンツは常にアップデート可能なマーケティング資産となります。
SEOとの関係とコンテンツ最適化の考え方
SEO(検索エンジン最適化)は、コンテンツマーケティングにおいて最も汎用性の高い集客チャネルのひとつです。SEOを意識してコンテンツを設計すれば、検索エンジン経由で“自然に見込み客が集まる仕組み”が作れます。
検索意図(インテント)を読み解く
たとえば「MAとは?」と検索する人は、次のような“背景”を持っているかもしれません:
- 最近MAという言葉を初めて聞いた
- 上司から導入検討を任された
- 他社が導入していると聞き、自分でも調べている
このように、キーワードそのものではなく、「その裏にあるニーズや不安」に対してコンテンツが答えているかが重要です。
E-E-A-Tとユーザビリティの両立
Googleが重視する「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」を高めるためには、単なる情報量ではなく、「その企業だから書ける視点」や「実務に基づいた経験」が必要です。
また、長文コンテンツであっても:
- 見出し構造が明確
- 要点が章ごとに整理されている
- 図解や表で直感的に理解できる
といった“読みやすさ”の工夫は、検索順位にもユーザー満足度にも寄与します。
コンテンツSEOは“記事単体”ではなく“サイト全体”で考える
SEOで成果を上げている企業の特徴は、「記事単体の順位」ではなく「関連キーワード群で面を取る」設計になっています。
たとえば:
- メインKW:「コンテンツマーケティングとは」
- 関連記事:「ペルソナ設計とは」「BtoBナーチャリング事例」「SEOライティングの基本」
このように、1つのテーマに対して複数の角度から深掘りし、内部リンクで結び付ける“コンテンツクラスター”戦略が有効です。
コンテンツの流通設計:チャネルと拡散の工夫
どれだけ良いコンテンツを作っても、読まれなければ意味がありません。コンテンツは“つくる”だけでなく“届ける”ことまで設計して初めて成果につながります。
プル型流通:SEO・SNS・外部メディア連携
SEO経由での流入に加えて、LinkedInやX(旧Twitter)などのSNSでのシェア、業界特化メディアとのタイアップ記事なども有効です。
- 記事公開後にSNSで要点だけ切り出して投稿
- 資料DLページをPR Timesでプレスリリース配信
- 業界コミュニティにウェビナー記事を投稿
プッシュ型流通:メール・MA・リターゲティング
ナーチャリング対象のリードや既存顧客に向けて、セグメント別にメールで届ける/MAでスコア連動して自動配信する/コンテンツ閲覧履歴から広告をリターゲティングするなど、“自分から届ける”設計も不可欠です。
営業活用:コンテンツを“営業資料”として使う
営業担当が商談前に「この事例、参考になりますよ」と送ったり、ヒアリング後に「課題整理の参考にどうぞ」と資料を案内したりすることで、商談率や信頼感が上がるという成果も数多く報告されています。
成功事例:BtoB企業での実践と成果
コンテンツマーケティングは、「リードが増えた」「CVRが上がった」といった定量成果だけでなく、「顧客からの信頼が深まった」「営業との会話が変わった」といった定性成果ももたらします。ここでは、BtoB企業の実際の活用事例を紹介します。
事例①:SaaS企業A社 – オウンドメディア経由のMQL数が4倍に
A社では、営業が取得した名刺に頼るリード獲得から脱却するために、「課題解決×検索意図」を意識したオウンドメディアを立ち上げ。1年間で60本以上のSEOコンテンツを蓄積した結果、オーガニック経由でのMQLが4倍に増加。さらに、メディア経由のMQLの商談化率は展示会経由の1.5倍に。
事例②:製造業B社 – 営業支援資料としての導入事例が受注率を後押し
B社は営業段階で「うちは前例がないと社内が動かない」と言われることが多く、営業のクロージングに苦戦していた。そこで、業種別に導入事例を整備し、PDF形式とWeb掲載の両方で展開。営業から「使いやすい」「説得力が増した」と好評を得て、クロージング率が前年比で1.4倍に向上。
事例③:IT企業C社 – スコアリングとコンテンツを連動させたナーチャリングで商談化率2.3倍
C社はMAと連携し、コンテンツごとに付与されるスコアを設計。興味度の高いテーマに反応したリードだけに、次の段階のコンテンツを自動配信するシナリオを構築。その結果、セミナー→事例DL→個別相談への導線が“自然にできあがり”、リード全体の商談化率が2.3倍に上昇。
継続運用の壁と乗り越え方
コンテンツマーケティングの本質は「資産づくり」であり、短期的な成果よりも“継続によって価値が高まる”取り組みです。とはいえ、現場では以下のような“壁”に直面することも少なくありません。
ネタ切れ問題
1年近く運用していると「もうテーマが尽きた」と感じることがあります。
<解決策>:
営業やCSから「よくある質問」をヒアリングする/検索キーワードの再調査/既存記事のリライト/顧客インタビューの導入など、“現場の声”や“過去資産の活用”でテーマは無限に広がります。
量産しても読まれない問題
せっかく書いても読まれずに終わってしまう――。これは設計・配信・タイトルの工夫で解決できます。
<解決策>:
検索意図を明確にする/構成をテンプレ化しない/SNSやメールで届ける/見出しと導入文に時間をかける。質と流通の両輪で考える必要があります。
社内理解が得られない問題
「コンテンツで売上になるのか?」という疑問にさらされることもあります。
<解決策>:
数字だけでなく、“コンテンツ経由で商談になったエピソード”を共有する。「コンテンツを見て問い合わせが来た」「営業が事例記事で提案できた」などのストーリーが、社内の理解と支持を広げます。
【BtoB事業に関わる方必見!課題別アプローチ方法の資料を公開中】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
まとめ:信頼はコンテンツから生まれる
コンテンツマーケティングとは、「情報を通じて、顧客との信頼を構築していく活動」です。
- 顧客が悩んでいることに答え
- 検討を進める材料を提供し
- 社内を動かす支援までも担う
そんな“無理のない説得力”を持つのが、コンテンツの力です。
広告のように即効性はないかもしれません。ですが、積み重ねたコンテンツは“資産”として残り続け、営業支援や採用、ブランディングなど、あらゆる部門で活用できます。
そして何より、優れたコンテンツは「この会社なら信頼できる」と思ってもらえる“接点”をつくります。
信頼から始まるビジネスは、きっと強く、長く続いていきます。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル