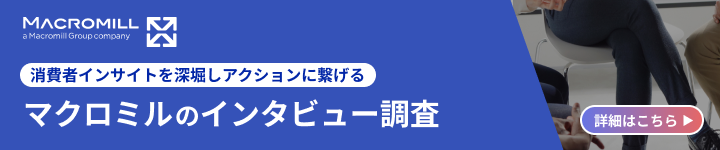NPS®は、顧客の推奨意向を数値化して把握できる指標です。事業拡大やサービス改善に活用できる一方、回答傾向や調査対象によって結果が変動する点には注意が必要です。この記事では、NPS®の基礎知識、計算方法、メリット・デメリット、実施手順や活用事例まで、導入に役立つ情報を詳しく解説します。参考にしてください。
参考:アンケートとは?目的や種類、質の高いアンケートを作るコツも解説
- NPSとは
- NPSの計算方法
- NPSアンケートを活用するメリット
- NPSアンケートを活用するデメリット
- NPSアンケートを実施する手順
- NPSアンケートの活用事例
- NPSアンケートに関するよくある質問
- まとめ
NPSとは
NPS®(ネット・プロモーター・スコア)とは、顧客の忠誠度を評価するための指標のひとつです。顧客の忠誠度とは、ある企業やブランド、商品、サービスに対して抱く信頼感や愛着を指します。NPS®を活用することで、顧客が企業や商品、サービスを他者にどの程度すすめたいと思っているかを数値化して把握できます。
NPSと顧客満足度の違い
NPS®と顧客満足度は似た指標として扱われますが、将来の行動(継続・推奨など)との相関の捉え方にあります。顧客満足度は顧客の満足度を示しますが、範囲は幅広くあいまいです。満足しているからといって、必ずしもリピート購入や売上増につながるわけではありません。
一方、NPS®は「企業や商品・サービスを他者にすすめたいか」という推奨意向を数値化するため、継続利用や口コミ行動との相関が多く確認されている点が特徴です。
NPSとeNPSとの違い
NPS®を従業員向けに応用した指標が「eNPS(Employee Net Promoter Score)」です。eNPSは「この会社を勤務先として友人に勧めたいか」を起点に、従業員エンゲージメントの一側面を把握する指標です。従業員満足の全体を直接測るものではありません。エンゲージメントが高い従業員は、顧客により質の高いサービスを提供する意欲を持ちます。
NPSの計算方法
NPS®は、顧客の推奨度に応じて分類し、スコアを算出する指標です。ここでは、NPS®の分類方法と具体的な計算方法について解説します。
推奨者・中立者・批判者のスコア区分と意味
NPS®は、顧客に「企業・ブランド・サービス・商品を周りにすすめたいか」を0〜10の11段階で評価してもらい、結果に応じて3つのグループに分類します。
- 推奨者(9〜10点):企業や商品に強い愛着を持ち、積極的に周囲にすすめる顧客。紹介客の多くはこのグループから生まれる。
- 中立者(7〜8点):満足はしているが積極的にすすめることも否定的な発信をすることもない顧客。競合に流れやすい傾向がある。
- 批判者(0〜6点):不満を持ち、否定的な口コミを広める可能性がある顧客。クレーム対応などで社内リソースに影響を与えることもある。
NPSの計算式
NPS®は、推奨者の割合から批判者の割合を差し引いて求められます。計算式は以下のとおりです。
- NPS® =(推奨者数 − 批判者数) ÷ 回答者総数 × 100
NPSアンケートを活用するメリット
NPS®アンケートを活用するメリットは、おもに3つあります。以下で、それぞれのメリットについて解説します。
事業拡大に役立つ
NPS®は、将来の収益との関連性が高い点が特徴です。得られたスコアを分析して改善策を実施することで、事業の成長や売上の向上につながる可能性があります。たとえば、推奨者のリピート率を高めることで売上を伸ばすことが可能です。さらに、定期的な調査と改善を重ねて推奨者を増やせば、事業の成長や収益の増加がより一層期待できます。
自社サービスや商品の課題を見つけられる
NPS®は国内外で広く採用されており、業界平均や競合と比較して自社の立ち位置を確認できます。業界ごとにスコアが異なるため、同業他社との比較が重要です。顧客の評価や不満点を把握できるため、商品・サービス改善や新規事業開発にも活用できます。
指標が数値化される
NPS®は、顧客ロイヤルティを簡単に数値化できる点が特徴です。設問自体はシンプルで社内で共有しやすいため、多くの企業が商品やサービス改善に活用しています。
NPSアンケートを活用するデメリット
NPS®アンケートを活用するデメリットは、おもに2つあります。以下で、2つのデメリットについて解説します。
日本では低い評価につながりやすい
日本の消費者は回答の際に、中間評価を選びやすい傾向があるため、調査結果が低めに出る場合があります。NPS®の評価基準では0~6点が批判者に含まれ、幅が広い一方で、推奨者は9~10点に限定されていることが影響しています。そのため、アンケートは継続的に実施し、自社の取り組みや競合他社との比較を通じて、相対的な立ち位置を把握することが重要です。
調査対象によって結果が大きく変動する
NPS®の結果は、誰に調査を行うかによって大きく変動します。自社の顧客を対象にするのか、調査会社のモニターを利用するのかで数値は異なるため、留意が必要です。また、経営層なのか現場担当者なのかといった回答者層も、あらかじめ設定しておきましょう。
NPSアンケートを実施する手順
NPS®アンケートを実施する際には、手順を把握することも大切です。以下で、順を追って解説します。
1.実施の目的を明確にする
NPS®アンケートでは、まず実施する目的をはっきりさせることが重要です。目的を明確にすることで、企業や商品・サービスの改善につながり、課題の発見もしやすくなります。質問内容は目的によって変わるため、「なぜ実施するのか」を事前に整理しておきましょう。さらに、顧客ロイヤルティを測定するには、顧客との接点を明確にしておくことも欠かせません。
2.質問内容を選定する
目的を明確にしたら、質問内容を選定しましょう。アンケートに盛り込みたい質問内容を検討する際は、「カスタマージャーニーマップ」を活用すると効果的です。商品やサービスの購入から利用に至るまでの行動や思考を整理・分析する手法です。
質問数は多すぎると回答負担が大きくなり、回収率が下がる恐れがあります。目安としては、5分以内で答えられる程度に絞り込みましょう。
3.アンケートの実施方法を決める
次に、アンケートの実施方法を決めましょう。NPS®アンケートは、目的や対象者に応じて方法を決めることが重要です。オンラインかオフラインかは、顧客の属性を考慮して判断します。最近はWebアンケートを簡単に作成できるツールも多いため、必要に応じて導入すると効率的です。
4.結果を分析し、課題を明らかにする
アンケートを実施するだけでは十分ではありません。結果を分析し、課題の可視化が重要です。分析にあたっては、さまざまなフレームワークを活用できます。
NPSアンケートの活用事例
NPS®アンケートを実施する際には、他社の活用事例を参考にすることも大切です。以下で、2つの事例をピックアップし、紹介します。
富士通株式会社
富士通株式会社がNPS®を非財務指標として活用した事例です。財務指標との関係を検証しながら経営判断に反映しています。2020年からは30か国共通の質問で調査を実施し、各国で分散していた取り組みをグローバルに統合し、世界中の顧客の声を分析・共有し、経営に生かしています。
さらに、各地域にCXリーダーを配置して改善活動を推進し、四半期ごとに事業責任者が集まり、課題解決のアクションと効果検証を一貫して行っています。
コニカミノルタ株式会社
コニカミノルタ株式会社がグループ全体で顧客関係の強化を進め、2012年にNPS®を導入した事例です。2017年には顧客接点ごとの調査(トランザクション調査)を開始し、2020年からは顧客の声を基に迅速に対応する改善プログラムを展開しています。
2022年以降は24カ国でCX向上に取り組んでいます。さらにNPS®に加え「製品・サービスを使い続けたいか」という継続意向を独自に調査し、週次で分析して営業活動に活用しています。
NPSアンケートに関するよくある質問
NPS®アンケートに関してよくある質問を2つピックアップし、紹介します。
NPSスコアの平均は?
NTTコム オンラインのNPS®ベンチマーク調査によると、日本人は中間評価を選びやすい傾向があります。その結果「批判者」が増え、平均値がマイナスになるのは自然な傾向といえます。
※参考:NPS®とは(ネットプロモータースコア)顧客満足度に変わる新指標 – NPS®ソリューション | NTTコム オンライン
NPSを改善するのにどのくらい時間がかかる?
年1回のNPS®スコアの変動に振り回されても意味はなく、重要なのは課題を特定し対策を優先することです。トレンドマイクロでは、原因が不明なスコア変動に課題を感じ、NPS Proを導入して年1回の調査に加え、オンボーディング調査も実施しています。
※参考:セキュリティソフトのライセンス更新におけるNPS®導入事例:トレンドマイクロ – NPS®ソリューション | NTTコム オンライン
まとめ
NPS®アンケートは、顧客ロイヤルティを数値で把握し、課題発見や改善策の優先順位付けに活用できます。継続的に調査・分析を行い、対象や質問内容を明確にすることが重要です。国内外の事例からも、NPS®を経営や営業活動に反映させることで、事業成長や顧客満足向上につなげられることが分かります。
株式会社マクロミルは、マーケティングリサーチとデジタルリサーチを軸に、社会や消費者の多様なニーズを分析し、クライアントに適切な消費者インサイトを提供しています。調査だけでなく、データ活用支援や広告・CRMなどの施策まで一貫してサポート可能です。まずはお気軽にご相談ください。
※NPS®、ネット・プロモーター・スコア® は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。