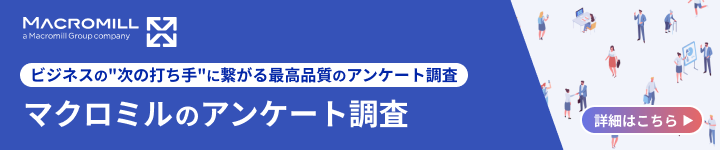製品やサービスの価格設定は企業の利益に直結します。価格調査は、市場調査において消費者の価格感度を把握し、競合他社の動向を分析することで最適な価格設定を導き出すマーケティング活動の一環です。本記事では価格調査の基本から具体的な分析方法まで詳しく解説します。
新規事業開発や商品企画に携わる方、マーケティング担当者の皆様にとって価格戦略立案の参考になる情報をお届けします。
参考:市場調査とは?マーケティングリサーチとの違いやメリット、代表的な9つの方法を解説
- 価格調査とは何をするのか?
- 価格調査はなぜ重要なのか?
- 3つのプライシングの考え方
- 価格調査の代表的な3つの分析方法
- 価格調査を実施する際の業務フロー
- 価格調査を実施する際のポイント
- 価格調査を実施する際の注意点
- まとめ
価格調査とは何をするのか?
価格調査とは、製品やサービスの最適価格を見極めるためのマーケティングリサーチです。消費者アンケートやインタビューを通じて価格感度を数値化し、競合製品の価格情報を収集・分析します。目的は、消費者が価値を感じる価格と企業が利益確保できる価格のバランスポイントを見つけることです。
適切な価格設定は販売数量の増加につながり、最終的には企業の収益向上に貢献します。
価格調査はなぜ重要なのか?
企業の想定価格と消費者が感じる価値にはギャップが生じやすく、これを埋めないと売上不振や利益率低下を招きます。消費者は「高すぎる」と購入せず、「安すぎる」と品質に不安を感じるため、この許容範囲を特定することが重要です。
また、競合他社の価格動向を把握せずに価格を設定すれば、価格競争で不利な立場に立たされる可能性があります。新製品開発では、想定価格帯から逆算してコスト管理や機能設計の指針を得られるため、製品開発の効率化にも貢献します。
3つのプライシングの考え方
製品やサービスの価格設定には3つの代表的な考え方があります。市場状況や製品特性に応じて適した考え方を選択しましょう。
ペネトレーションプライス
ペネトレーションプライスは、市場浸透を目的とした低価格戦略です。新規参入時に競合より意図的に安い価格を設定し、短期間での市場シェア獲得を狙います。価格に敏感な消費者が多い市場に効果的で、家電量販店のPB商品やサブスクリプションサービスなどでよく見られます。多くの顧客を獲得した後、徐々に価格調整や付加価値サービスの追加を行う段階的なアプローチも可能です。
スキミングプライス
スキミングプライスは、初期段階で高価格設定を行い、徐々に価格を下げていく戦略です。革新的な製品や差別化された商品の発売時に用いられ、「早く手に入れたい」初期採用者から高い利益を確保します。
最新スマートフォンなどによく見られるこの手法は、開発費の早期回収や高品質というブランドイメージ確立に有効です。
コストプラス
コストプラスは、原価に一定の利益マージンを上乗せして価格を設定する手法です。計算が単純で確実な利益確保が可能なため、多くの企業で基本的な価格設定方式として採用されています。
受注生産型製造業や原材料価格変動が大きい業界で有効ですが、市場需要や競合状況を考慮していないため、消費者の価値認識との間にギャップが生じる可能性があります。
価格調査の代表的な3つの分析方法
消費者の価格感度を測定するための分析方法は、PSM分析、CVM分析、コンジョイント分析の3つが代表的です。それぞれの特徴を解説します。
PSM分析
PSM分析は、消費者の価格感度を測定する方法です。「高すぎる価格」「安すぎる価格」「高いが購入検討できる価格」「お買い得と感じる価格」の4つの質問から消費者心理を数値化します。
データをグラフ化すると、交点から「理想価格」「許容価格帯」「妥協価格」がわかり、適正価格帯を導き出せます。新製品の価格設定時や、価格改定時に有効です。
CVM分析
CVM分析(仮想評価法)は、特定価格帯での消費者購入意向を段階的に調査します。「この商品が3,000円だったら購入しますか?」といった質問を異なる価格でランダムに提示し回答を集めます。
回答結果より各価格帯での購入確率を算出でき、収益を最大化できる最適価格の設定が可能です。通常5段階程度の価格帯で調査を実施します。
コンジョイント分析
コンジョイント分析は、価格だけでなくさまざまな属性(機能、デザイン、ブランドなど)が消費者の購買判断に与える影響を総合的に分析する方法です。異なる属性の組み合わせを提示し、どれが選ばれたかにより各属性の価値を数値化します。
「高価格・高性能」「低価格・普通性能」といった選択肢の比較から、消費者が価格と機能のバランスをどう評価しているかがわかり、市場シェアの予測も可能です。
価格調査を実施する際の業務フロー
効果的な価格調査を行うには、以下の5つのステップを順序立てて進めましょう。
1.ターゲット設定
価格調査の最初のステップはターゲット設定です。調査対象となる顧客層や市場セグメント、競合製品を明確に定義します。「20代〜30代の働く女性」などの具体的なターゲット像を描き、市場ポジショニングや競合範囲も決定します。
調査目的を「新製品の価格設定」「既存製品の価格改定」など明確にすることで、次の分析方法や調査方法の決定に明確な方向性を与え、効率的な調査の実施が可能となるでしょう。
2.分析方法の決定
次のステップでは、PSM分析、CVM分析、コンジョイント分析など、調査目的に合った分析方法を選びます。製品特性、開発段階、予算、必要精度を考慮して適切な方法を決めましょう。価格感度の把握にはPSM分析、価格と他属性の関係把握にはコンジョイント分析が効果的です。
3.調査方法の決定
調査方法の決定では、消費者からデータを収集する方法を決定します。Webアンケート、対面調査、グループインタビュー、街頭調査などから、対象者特性、サンプル数、予算、納期を考慮して選びます。
幅広い意見収集にはWebアンケート、詳細な消費者心理把握にはグループインタビューが適しています。統計的に有意な結果を得るための十分なサンプル数確保も重要です。
4.調査の実施・集計・分析
調査の実施・集計・分析では、実際にデータを収集し結果を数値化します。アンケートやインタビューを実施し回答を集計した後、決定した分析方法でデータを分析し、消費者の価格感度や最適価格帯を導き出します。集計の際には、矛盾回答や外れ値を処理するデータクリーニングも重要です。
5.分析結果より意思決定をする
最終ステップでは、調査から得られた知見を実際のビジネス判断に生かします。分析から導いた最適価格帯をもとに販売価格を決定しますが、市場環境、コスト構造、競合状況、営業部門の意見も考慮した総合判断が重要です。決定した価格から販売計画や収益予測を立て、マーケティング戦略も調整します。
価格調査を実施する際のポイント
効果的な価格調査を行うには、明確な目的設定と適切な調査方法の選択が重要です。この2つのポイントを押さえることで、調査の精度と実用性が大きく向上します。
目的に基づいた目標を設定する
価格調査を実施する際は、まず「何のために調査をするのか」という目的を明確にすることが重要です。新製品の価格設定、既存製品の価格改定、競合分析など、目的によって必要な情報が異なります。
たとえば、新商品開発なら「消費者が受け入れる価格帯の把握」、シェア拡大が目的なら「価格変更時の販売量変化の予測」など、具体的な目標設定が調査の効率と有効性を高めます。
目的に応じた調査方法を選択する
調査目的が決まったら、それに最適な調査方法を選択します。価格感度の把握にはPSM分析、価格と他の商品特性の関係を数値化するにはコンジョイント分析というように、目的に合った分析方法を選びます。
また、調査対象者の特性も考慮し、高齢者が対象ならWeb調査より対面調査、BtoBならユーザー企業へのヒアリングなど、回答精度を高める工夫が必要です。
価格調査を実施する際の注意点
価格調査では客観的な視点と柔軟な解釈が必要です。企業視点に偏らず、調査結果も絶対視しないことがポイントです。
利益追求より消費者を意識
価格調査では企業側の利益追求視点ではなく、消費者視点での「値ごろ感」を重視することが大切です。企業が原価やコストに基づいて考える「適正価格」と、消費者が提供価値から判断する「適正価格」には大きなギャップが存在します。このギャップを埋めるには、消費者視点に立った価格感覚を調査・分析し、「買いたい」と思わせる価格帯を見極めましょう。
調査結果はあくまで仮説
価格調査の結果は100%確実なものではなく、あくまで仮説としてとらえましょう。調査時点の限られた条件下での消費者の反応を数値化したものであり、実際の市場では予測と異なる反応が起こることもあります。
「購入する」と回答した消費者も、実際の購買場面では別の判断をする可能性もあるでしょう。調査結果を絶対視せず、市場投入後も柔軟に価格調整を行う姿勢が重要です。
まとめ
価格調査は製品の最適価格を導き出すプロセスです。PSM分析やコンジョイント分析などで消費者の価格感度を数値化し「売れる価格」を見極めます。調査には明確な目標設定と適切な設計が不可欠で、消費者視点の「値ごろ感」を重視し、市場投入後の柔軟な対応も大切です。
もし価格設定でお悩みなら、ぜひ1度マクロミルにご相談ください。90以上の国と地域に対応し、1.3億人のパネルネットワークと年間4,000社以上の取引実績を生かし、業界特性に合わせた信頼性の高い調査を実施します。分析結果に基づく提案で、御社の製品競争力向上をサポートいたします。