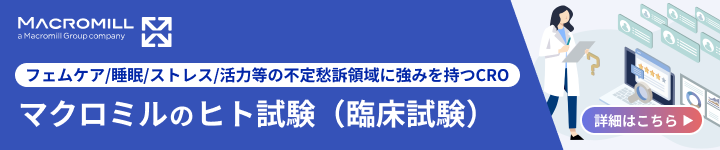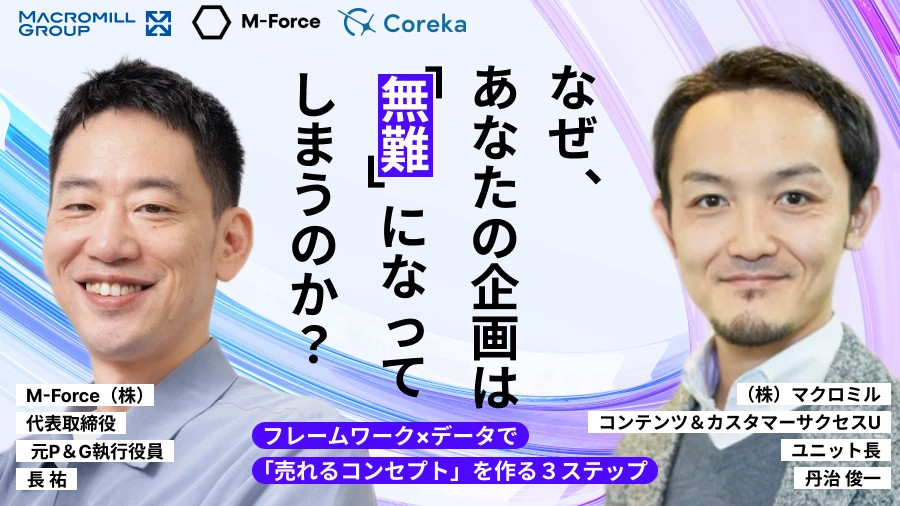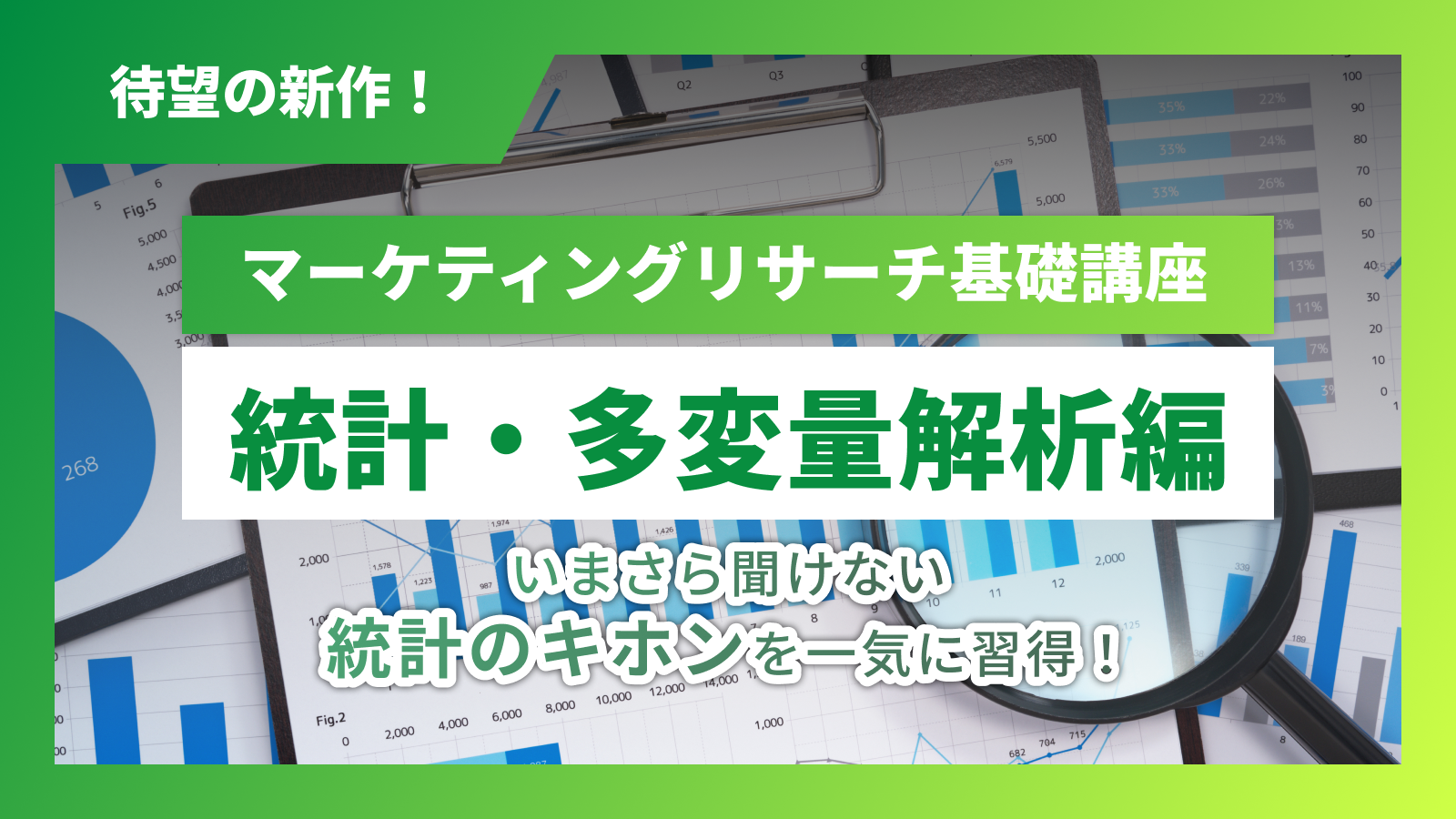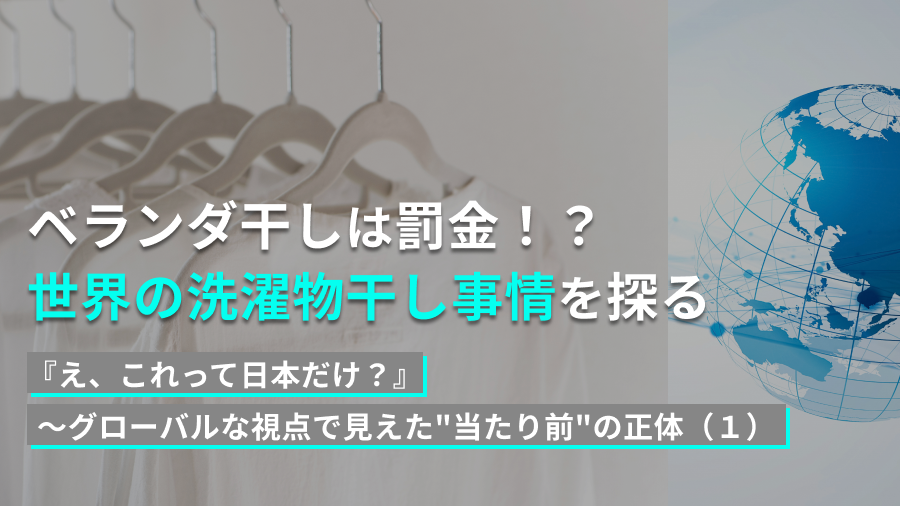ヒト試験(臨床試験)とは?実際の生活者を研究対象者(被験者)として食品やサプリメントの有効性や安全性を学術的に検証する研究手法
公開日 :2025/1/24(金)
最終更新日:2025/5/9(金)
ヒト試験(臨床試験)とは、医薬品、食品、サプリメント等の有効性、機能性、安全性を人間(ヒト)を対象に評価する研究手法です。動物実験や実験室レベルの評価とは異なり、実際の人体反応をデータとして取得できるため、製品の効果や安全性を実証的に把握することができます。臨床試験の多くは、二重盲検ランダム化比較試験(RCT)などの、データの信頼性を高める研究デザインが採用されるのが特長です。
次章以降では、その中でも食品臨床試験について取り上げていきます。
食品臨床試験が求められる背景
食品科学や栄養学などの分野が進展し、機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)などの、生活者のQOLの向上に役立つ商品も増加しています。そのような背景もあり、食品の機能性や安全性を生活者の実生活環境に近い形で検証するヒト試験の必要性が高まっています。細胞動物モデルでは予測しきれない人間特有の代謝や行動特性が存在するため、最終的な有効性や安全性を示すにはヒトを研究対象者(被験者)とした研究が重要とされているためです。
また、特定の条件を満たし実施されるヒト試験で取得したデータは、機能性表示食品の届出や特定保健用食品(トクホ)の承認申請に利用する科学的根拠(エビデンス)として利用可能なため近年は特にヒト試験の実施が増加しています。
食品臨床試験を支える要素
食品臨床試験を実施する場合、以下の要素が試験結果に影響します。
1. 倫理審査とインフォームド・コンセント
学術的ルールやガイドライン(人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等)に基づき、研究対象者(被験者)の人権保護やプライバシーを配慮した試験計画書を作成します。作成した試験計画書をもとに倫理審査委員会の審査・承認を経て、研究対象者に対して十分な説明と直接の同意(インフォームド・コンセント)を得て試験を実施します。
2. 試験デザインと統計学的設計
二重盲検法、ランダム化比較試験(RCT)、クロスオーバーなどを活用し、外的妥当性と内的妥当性を両立させます。評価項目、素材の効果を加味したうえでサンプル数や割付因子を慎重に設定し割付実施します。
3. 適格な被験者呼集と被験者管理
試験計画書の適格基準に合致し、除外基準に合致しない被験者を呼集します。試験期間中は被験者には食品の摂取や来院・調査票への回答など被験者が対応しなければいけないタスクも多数発生しますが、試験計画からの逸脱が無いよう実施側がコントロールします。
4. データ収集と解析
血液検査などの生化学指標や生理学的指標、各分野の学会でオーソライズされた調査票、オリジナルのアンケートなど多面的にデータを取得し、統計解析により有意差を検証しや研究結果報告書に反映します。
以上の要素の中でも、特に被験者呼集と被験者管理は試験データの品質を大きく左右させるため、特に注意が必要です。これらを踏まえたうえで厳密に実施運用することで、学会や学術誌の査読に耐える科学的エビデンスを確立することができます。
食品臨床試験実施時の大まかな流れ
研究機関や企業が食品臨床試験を実施するには、まず研究目的の明確化と計画書の作成を行い、倫理委員会へ提出して承認を得ます。次に、研究対象者(被験者)の募集を行い、インフォームド・コンセントを取得した上で臨床試験を開始します。
開始後は、期間中に定めた生化学・生理学検査や各種測定、アンケートを行います。同時に日誌形式で研究対象者(被験者)から体調や服薬状況を聴取し、有害事象の収集も行います。集められたすべてデータを整理し、解析対象者を明確化したうえで統計解析を実施します。
最終的に、学会発表や論文を投稿し得られた知見を次の研究や製品開発に活か場合や、機能性表示食品の届出や特定保健用食品(トクホ)の承認申請に用いることが一般的です。
食品臨床試験のメリットとデメリット
メリットとしては、実際の人間を対象にした試験結果であるため、研究成果の現実適用性(外的妥当性)や説得力が高まり、学術評価を得やすい点が挙げられます。また、研究対象者(被験者)の生化学・生理学検査に加え、主観的を含め多面的なデータを得られるため、様々考察から結論に至ることができます。
一方、デメリットとして、実施コストや期間、被験者の募集などハードルが高く、倫理面での配慮や厳密な計画が必須です。サンプル数やバイアス対策が不十分だと、学術的信頼性に疑問が生じる可能性や結果の解釈が難しくなります。
現代における食品臨床試験の役割
ヒトを対象とした臨床試験や臨床研究は、製品・素材が実際の生活シーンでどのように作用するかを明らかにする上で非常に重要です。研究成果を活用した商品の上市を目指すにあたり、データを厳密に取得して有効性や安全性を立証する過程は避けて通れません。また、取得できるデータ種やデータの取得方法が多様化し復数間のデータ解析が進むことでより高度な解析を用いた新たな知見を得ることも可能となりつつあります。
まとめ
食品臨床試験とは、ヒトを研究対象者(被験者)として食品の安全性・有効性を学術的に検証する研究手法であり、試験デザインや倫理審査、統計解析などを厳密に行うことで高い信頼性のエビデンスを得ることができます。
著者紹介
株式会社マクロミル ライフサイエンス事業本部 クリニカルトライアル部長
大出 聡馬
2019年より、機能性表示食品などの臨床試験受託サービスの黎明期を主導。単独で食品CROと連携しながら多くの試験を成功に導いた実績を持つ。
2021年にはライフサイエンス事業本部の立ち上げにおいて中心的な役割を担い、オペレーション部門の責任者として当社のCRO体制構築を主導。
2024年より現職。臨床試験事業の責任者として、試験の立案から実行までを統括し、企業の研究開発を支援する体制をリードしている。