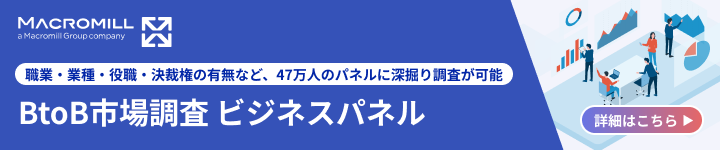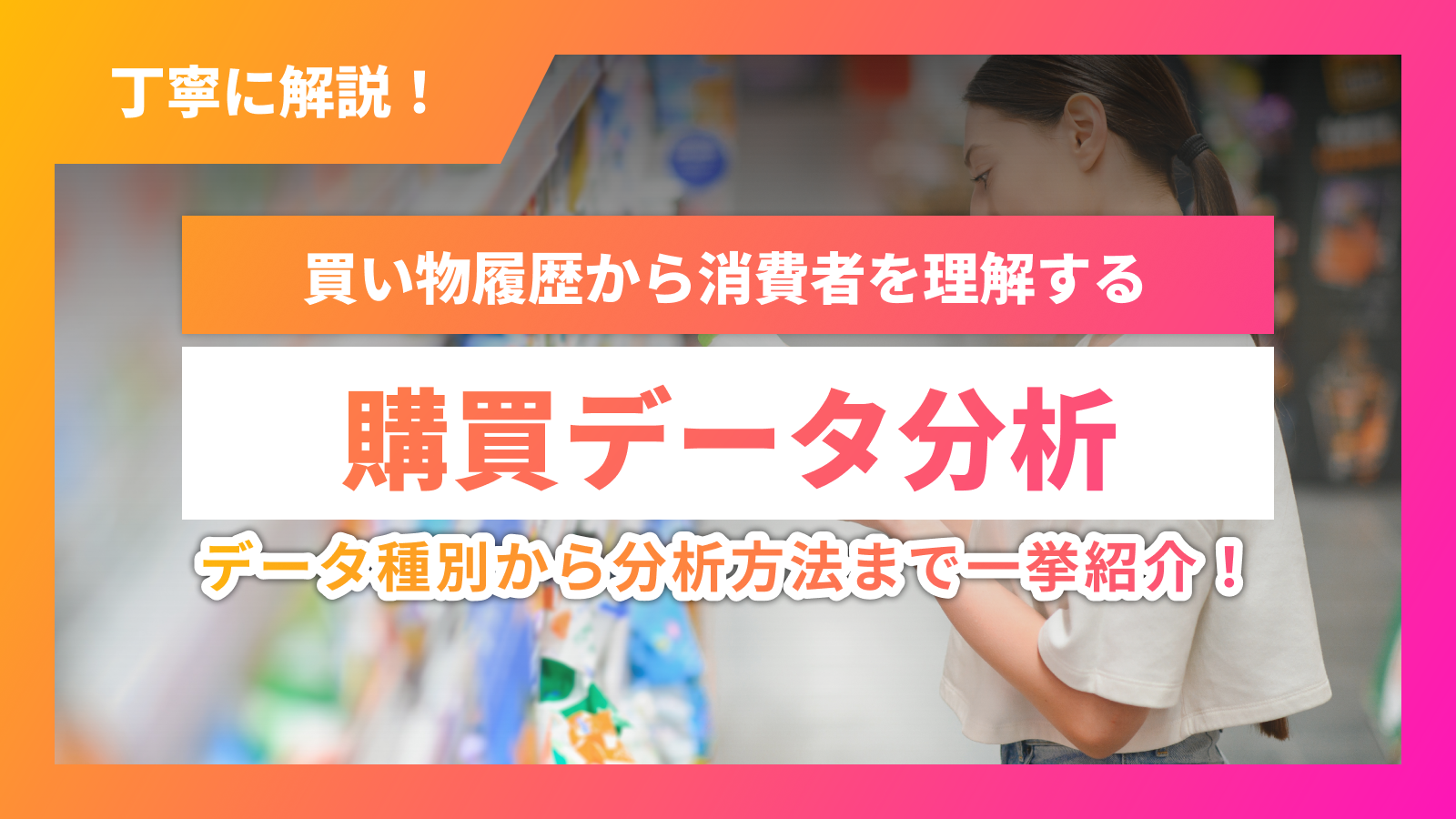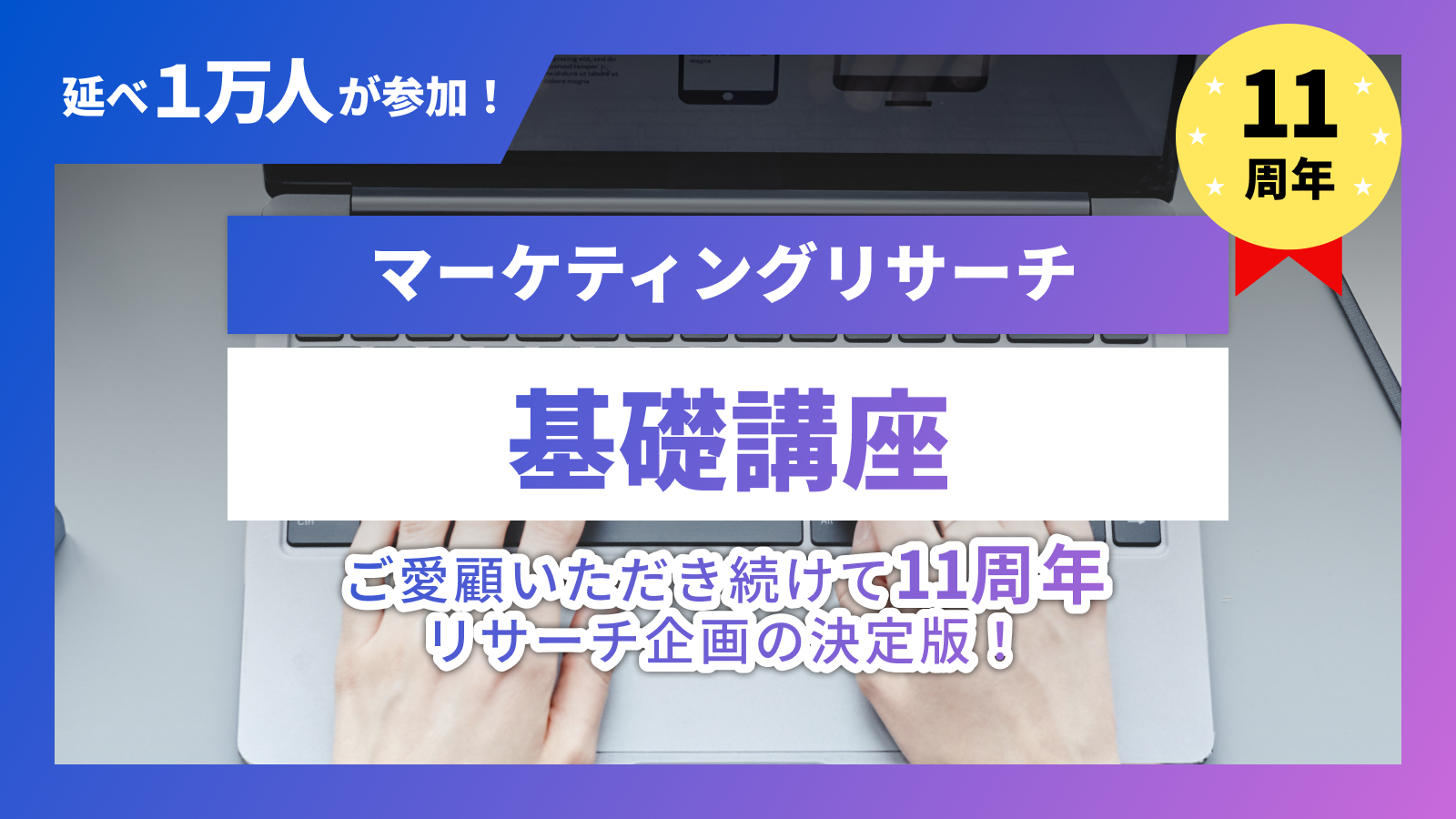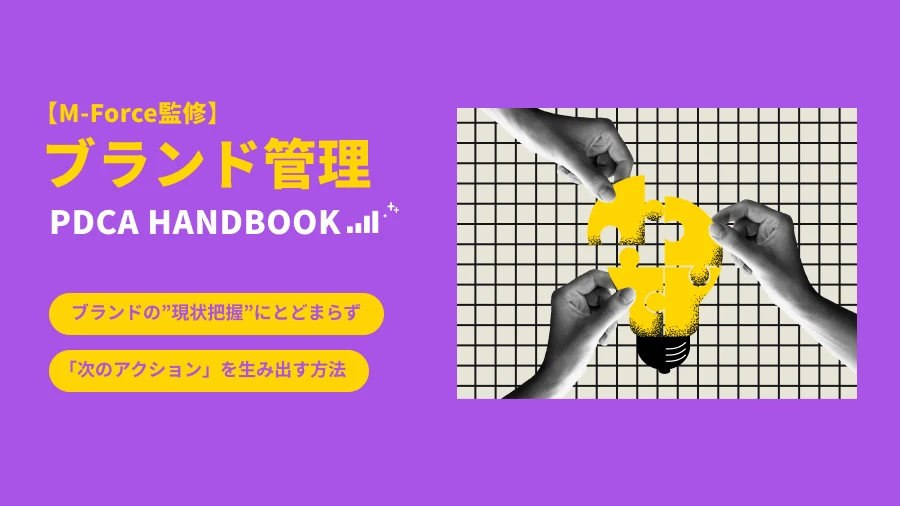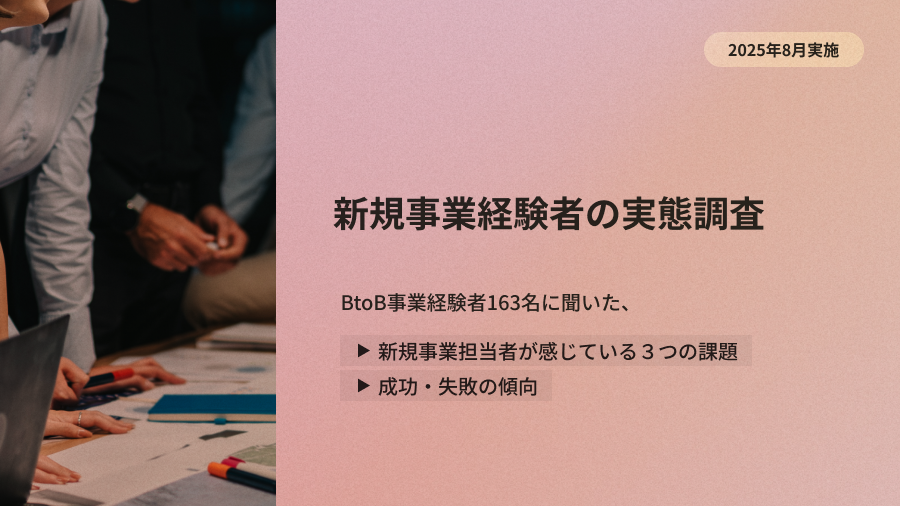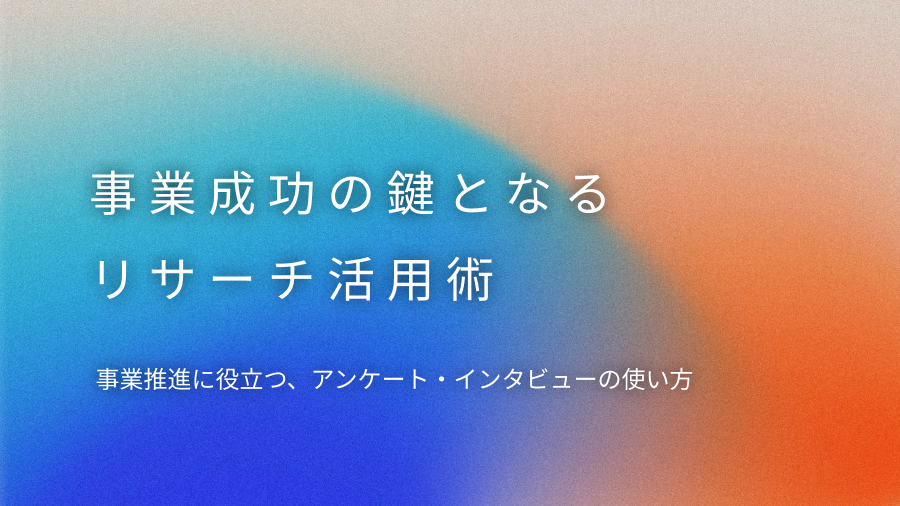リード(見込み客)とは?意味・分類・獲得から育成までを徹底解説
公開日 :2024/12/5(木)
最終更新日:2025/8/8(金)
営業にとってもマーケティングにとっても、「リード」は最も基本でありながら最も奥が深い概念です。製品やサービスに興味を示しているが、まだ契約には至っていない“その一歩手前の存在”――それがリード、すなわち見込み客です。
しかし、「リード」と一口に言っても、問い合わせをしてきたばかりの人から、資料を複数回ダウンロードしセミナーにも参加した人まで、その関心度はさまざまです。そして、その“温度感”を理解しないまま営業をかけても、成果につながる確率は低く、かえって顧客の信頼を失ってしまうこともあります。
だからこそ、「リードとは何か?」を正しく理解することは、あらゆるマーケティング・営業活動の出発点です。
本コラムでは、「リード」の定義から、分類、獲得方法、ナーチャリング、営業との連携、スコアリングによる可視化、さらには成功事例までを包括的に解説していきます。読了後には、リードという言葉が単なるマーケ用語ではなく、“事業の未来をつくる存在”であることが実感できるはずです。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- リード(見込み客)の定義とは?
- リードとその他の顧客概念(プロスペクト/MQL/SQL)との違い
- リードの分類:コールド/ウォーム/ホットの考え方
- リードの獲得方法:チャネルと施策一覧
- ナーチャリングとの関係性
- リードのスコアリングと可視化手法
- 営業との連携:リードを成果につなげるには
- 成功事例から見る「リード活用」のベストプラクティス
- まとめ:リードは“未来の売上”である
リード(見込み客)の定義とは?
リードとは、「自社の商品やサービスに対して何らかの興味・関心を示した個人または企業」のことを指します。たとえば以下のような行動を取った人が、リードと見なされます:
- Webサイトから資料をダウンロードした
- セミナーやウェビナーに参加した
- メルマガに登録した
- 営業が獲得した名刺情報
- SNS経由で問い合わせをした
重要なのは、「購入はしていないが、何かしらの接点がある状態」であるという点です。
この段階の見込み客に対して、「どのように信頼を築き、購買へと導くか」が、マーケティングと営業の腕の見せ所です。
リードとその他の顧客概念(プロスペクト/MQL/SQL)との違い
「リード」という言葉は日常的に使われますが、実務の現場では類似する用語がいくつか存在し、混同されやすいのも事実です。ここでは、特に混同されがちな「プロスペクト」「MQL」「SQL」との違いを明確にしておきましょう。
① プロスペクト(Prospect)
プロスペクトとは、「将来的に顧客になりうるが、まだ接点のない企業や人物」のことを指します。いわば“潜在的なターゲットリスト”です。業界、企業規模、役職などの属性から、自社の顧客になりそうな候補をあらかじめ定義した存在で、まだ何のアクションも起こしていない場合も含まれます。
② リード(Lead)
すでに何らかのアクションを通じて自社と接点が生まれた見込み客です。プロスペクトが“関係前”だとすれば、リードは“関係が始まった後”のステージと捉えるとわかりやすいでしょう。
③ MQL(Marketing Qualified Lead)
MQLは、マーケティング活動の中で獲得されたリードのうち、「営業に渡す価値がある」と判断された層を指します。例えば、ホワイトペーパーのダウンロードに加え、特定のサービスページを複数回訪れている、過去にセミナーにも参加している、などの行動を取っていれば“関心度が高い”と評価されます。
④ SQL(Sales Qualified Lead)
SQLは、営業部門が「このリードは商談化の可能性がある」と判断した段階です。通常はMQLを営業にパスし、営業がヒアリングを通じて課題や導入意向を確認した結果、SQLとして商談プロセスに入ります。
このように、リードという言葉は“広義”の概念であり、組織の中での扱いやステージによって、より細かく分類されるのが実態です。
リードの分類:コールド/ウォーム/ホットの考え方
リードには“温度感”があります。つまり、どれだけその人が購買に近づいているか、という関心の強さや緊急度の違いです。これを表現するためによく使われるのが、「コールド」「ウォーム」「ホット」という3段階の分類です。
① コールドリード(Cold Lead)
- 接点はあるが、今すぐのニーズはない状態
- たとえば、ホワイトペーパーを1回ダウンロードしただけ
- 情報収集段階、もしくは潜在的な興味のみ
この段階では、営業が直接アプローチするには時期尚早なため、ナーチャリングによって関心度を高めていく必要があります。
② ウォームリード(Warm Lead)
- 関心はあるが、比較検討の途中にある状態
- 特定テーマのセミナー参加や、製品ページを複数回閲覧するなど、行動量が増えている
- 担当者レベルでの関心はあるが、社内稟議や導入課題があるケースも多い
ナーチャリングと並行して、タイミングやニーズの顕在化を見極めながら営業との連携を検討する段階です。
③ ホットリード(Hot Lead)
- 明確な導入意向があり、営業がすぐにアプローチすべき状態
- 価格ページの閲覧、具体的な問い合わせ、商談依頼などが行動指標になる
- 社内決裁者とつながる段階に近づいている
この段階では、迅速に営業へパスし、スムーズに商談化を進める必要があります。逆に、このタイミングを逃すと競合にリードを奪われるリスクも高まります。
リードの獲得方法:チャネルと施策一覧
リードは“自然に集まる”ものではありません。マーケティング部門は、明確な戦略に基づいて「どこで」「誰に向けて」「どのように」情報を届けるかを設計し、能動的にリードを創出する必要があります。
ここでは、BtoB企業でよく活用されているリード獲得施策をチャネル別に整理します。
オウンドメディア・SEO
検索エンジン経由で見込み客を呼び込む王道の手法。課題解決型コンテンツ(例:「SFAとは?」「営業の属人化を防ぐ方法」など)を通じてアクセスを集め、ホワイトペーパーや資料DLフォームでリード情報を取得します。
メリット:
- 購買意図が高いキーワードからの流入が多い
- コンテンツが資産として蓄積される
広告(リスティング・ディスプレイ・SNS)
特定のターゲットに向けて、狙ったタイミングで情報を届けられる施策です。特に「セミナー告知」「業界特化コンテンツの配信」との相性が良く、短期でのリード獲得に向いています。
セミナー・ウェビナー
BtoB領域で急成長しているチャネルです。“課題を深く理解したい”層に向けて学びの場を提供し、信頼を構築しながら情報を取得できます。視聴者属性や参加後の行動によって、関心度も把握しやすく、後続のナーチャリング施策にもつなげやすいのが特徴です。
展示会・イベント
リアルでの名刺交換や製品デモを通じて直接的にリード情報を得る手段です。短期的には名刺数の確保ができるものの、フォロー体制やMAとの連携が弱いと“データの山”で終わってしまうリスクもあるため注意が必要です。
パートナー連携・共催施策
ターゲット層に近い他社との共催セミナーやコンテンツ連携も効果的です。1社ではリーチできなかった新規層へアプローチできるだけでなく、パートナー経由の信頼によってリードの質が高くなる傾向もあります。
SNS・YouTube・ポッドキャスト
自社の認知や“人となり”を伝えるコンテンツとして、SNS・動画・音声メディアの活用も進んでいます。直接的なリード獲得というよりは、ファネル上部の“関心喚起”として機能し、他の施策との連動が鍵になります。
ナーチャリングとの関係性
リードは「獲得して終わり」ではありません。むしろ、そこからがスタートです。獲得したリードに対して、継続的に接点を持ち、信頼を築き、購買意欲を高めていく一連のプロセスを「リードナーチャリング(Lead Nurturing)」と呼びます。
なぜナーチャリングが必要なのか? それは、BtoBにおいて「いますぐ買う人」はほんの一握りだからです。
ある調査では、リード全体の中で“すぐに営業アプローチすべき層”は10%以下とされています。残りの90%は、まだ検討中だったり、情報収集中だったりと、関心はあっても今すぐの導入には至っていない層です。
ナーチャリングは、こうした“将来のホットリード候補”に対して適切なコンテンツを届け、信頼を築き、育てていく取り組みです。たとえば以下のような施策が含まれます:
- ステップメールによる段階的な情報提供
- セミナーやウェビナーへの継続招待
- 行動履歴に応じたコンテンツレコメンド
- スコアリングによる関心度の可視化
ナーチャリングがあることで、営業は“温まったリード”に集中でき、商談の効率と受注率が格段に向上します。つまり、ナーチャリングは営業活動を支える“土台”でもあるのです。
リードのスコアリングと可視化手法
リードの“温度感”や“確度”を感覚に頼らず判断するために欠かせないのが、「スコアリング」です。スコアリングとは、リードの属性や行動に点数を付与し、購買意欲を数値化・可視化する手法です。
属性スコア
- 業種がターゲットと一致している:+10点
- 従業員規模が自社商材にマッチ:+5点
- 役職が意思決定者:+20点
このように、リードの“外的な条件”に点数を付け、優先度を把握します。
行動スコア
- 資料DL:+10点
- メール開封:+5点
- 製品ページ閲覧:+15点
- 問い合わせ:+30点
リードが起こした“行動”を点数化し、関心の高まりを測定します。
スコアの活用方法
- 合計スコアが◯点を超えたら営業に通知(ホットリード)
- スコアごとにメールシナリオを変更(個別ナーチャリング)
- 商談に至ったリードのスコアを分析して“勝ちパターン”を可視化
スコアリングを通じて、マーケティングと営業が“感覚”ではなく“数値”で判断し合える土台をつくることができます。
営業との連携:リードを成果につなげるには
いくらリードを獲得し、スコアリングで優先順位をつけ、丁寧にナーチャリングをしても、それだけでは売上にはなりません。最終的に“商談化”し“受注”に至るには、営業との連携が不可欠です。
マーケティング部門が抱える代表的な悩みは、「せっかくホットリードを渡しても、営業がフォローしてくれない」。一方で営業側も、「マーケティングから来るリードは質が低い」という印象を持っているケースが少なくありません。
このギャップを埋めるには、以下のような仕組みとマインドセットが必要です。
MQLとSQLの定義を共有する
「どのような状態のリードを営業に渡すのか?」を明文化し、マーケと営業が合意しておくことが第一歩です。たとえば、下記のような条件を共有するとスムーズです:
- スコアが80点以上かつ業種・職種がターゲット内
- 資料を2回以上ダウンロードし、セミナーにも参加済み
- 製品ページを3回以上訪問している
この定義が曖昧だと、営業は「冷たいリードが回ってきた」と感じ、フォローの優先度を下げてしまいます。
リード移行のSLA(サービスレベルアグリーメント)を設定する
MQLを営業にパスした後、どのタイミングで、どのような方法でアプローチするのかをルール化しておくことで、対応遅れやリードの“腐り”を防ぎます。
- MQL受け取りから3営業日以内に初回連絡
- 不通の場合は3回までフォローし、その後マーケに戻す
- 商談化した場合はフィードバックを共有
このように、両部門が責任を持って“共通の目標(受注)”を追える体制づくりが鍵となります。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
成功事例から見る「リード活用」のベストプラクティス
事例①:SaaS企業A社 – スコアリングと営業通知の連携で商談化率2.5倍
A社では、Web閲覧履歴や資料DL履歴に応じた行動スコアリングを導入し、一定スコアを超えたリードに対して自動で営業にSlack通知を送る仕組みを構築。営業は「温まったリード」だけに集中できるようになり、商談化率が2.5倍に向上。また、営業がヒアリングした内容をマーケに戻すことで、スコアリングルールやシナリオメールも改善され、成果の好循環が生まれた。
事例②:製造業B社 – ナーチャリングメールで眠っていたリードを再活性化
展示会で獲得した名刺リストが放置されていたB社では、半年ぶりに「業界動向×導入事例」のナーチャリングメールを配信。その結果、20件以上の返信と問い合わせがあり、3件が新規受注に結びついた。「放置されていたリードこそ資産だった」と社内でも評価され、以降はMAツールを活用したステップメール配信が標準化された。
まとめ:リードは“未来の売上”である
リード(見込み客)は、単なる「メールアドレス」でも、「名刺データ」でもありません。それは、自社の価値に興味を示し、いずれ顧客になる可能性を持った“未来の売上”です。
- リードの温度感を正しく理解し
- 獲得から育成まで一貫した設計を行い
- スコアリングやナーチャリングを通じて成熟度を高め
- 営業と連携して“適切なタイミング”でアプローチする
この一連のプロセスを丁寧に積み重ねていくことで、マーケティングは「リードの数を追う活動」から、「売上をつくる活動」へと進化します。
リードは、受注に至るかもしれない“可能性”そのものです。そして、その可能性をどう育て、どう収穫するかこそが、現代マーケティングにおける最も重要な問いなのです。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル