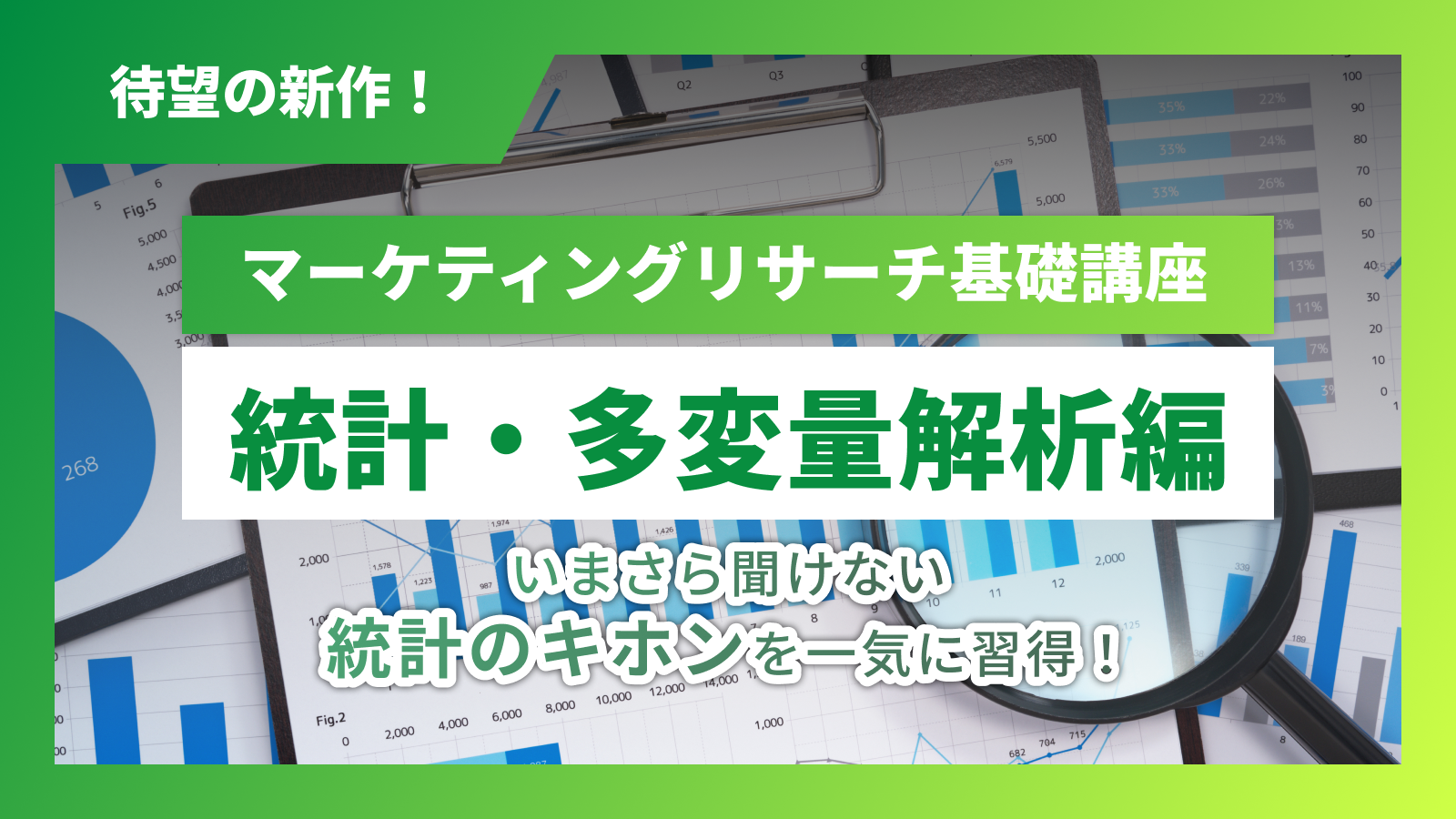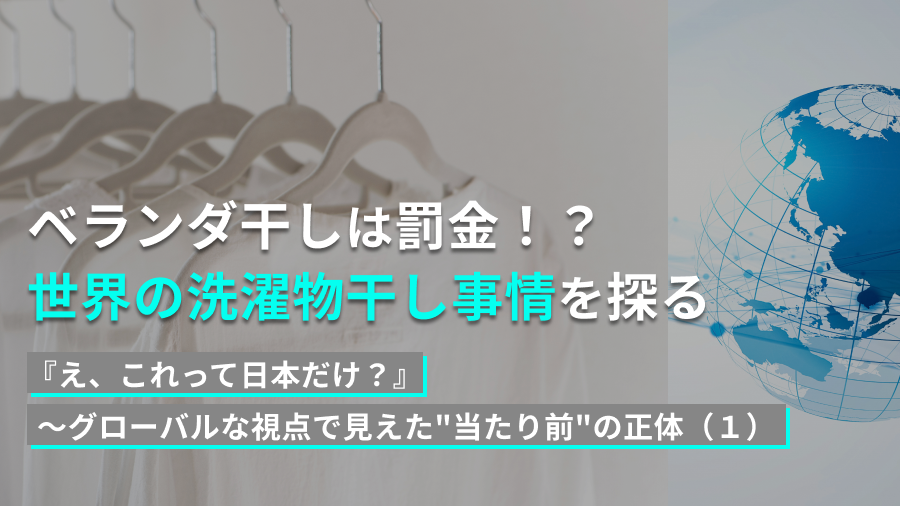ROIとは?計測するメリットやデメリット、DX時代のマーケティングにおける活用法をわかりやすく解説!
公開日 :2024/12/5(木)
最終更新日:2025/3/14(金)
ROI(Return on Investment) とは、日本語で「投資利益率」などと訳される、ある取り組みに対して投下したコスト(投資額)に対し、どれだけの利益(リターン)が得られたかを示す指標です。具体的には、(利益 ÷ 投資額)× 100% の形で算出することが多く、マーケティング施策や広告運用などにおいて、施策の効率性を測るための代表的なKPIの一つとして位置づけられています。
たとえば企業がSNS広告や検索連動型広告に費用をかけた際、得られた利益金額を投資金額で割ることで、その施策がどの程度“割に合った”ものかを把握できるわけです。ただし、ROIは単純化された指標であり、短期的な売上だけでは測りづらいブランディングやロイヤリティ向上といった中長期的な効果を見落としがちという指摘もあります。そのため、近年はCookie規制の影響でサードパーティデータの活用が難しくなる中でも、ファーストパーティデータを活かしてROI計算に補足できる指標(LTVやNPS®など)を併用する流れが生まれています。こちらも後ほど解説します。
デジタルトランスフォーメーション(DX)においては、ROIを単なる数値化だけではなく、ユーザー行動ログやコミュニティ上での反響も勘案しながら、週次・月次でPDCAサイクルを回して広告費やマーケティング投資を最適化していくアプローチが一般的です。SNS広告の費用対効果(ROAS, Return On Ad Spend)とも密接に関係し、CVR(コンバージョン率)やEFO(Entry Form Optimization)などの改善がROIを高める手段となり得る点が、多くの企業で意識されています。
- ROIと広告費最適化の関係
- ROIの計算方法とバリエーション
- ROIが注目される背景
- ROIのメリットと限界
- ROIと他の指標との組み合わせ
- ROIと定性手法(デプスインタビューなどの)との併用の重要性
- ROIの今後の展望とDX時代の可能性(短期ROIから『総合的ROI』へ)
- まとめ
ROIと広告費最適化の関係
ROIは、特に広告費の最適化を考える際に用いられる場面が多いです。なぜなら、企業がSNS広告や検索連動型広告に支出する金額をどこまで増やすべきか、あるいはどのキャンペーンが投資対効果に優れるかを判断する材料として、ROIが分かりやすいからです。具体的には、ある広告に対して投じた費用が 100万円で、そこからの売上が 400万円、利益が 200万円得られたとした場合、ROIは(200万円 ÷ 100万円)× 100%=200%となります。
ただし、この計算では広告による短期売上しか見ていないケースが多く、ブランドロイヤリティやコミュニティ形成による中長期的な利益は加味しづらいという難点が挙げられます。デジタル社会で Cookie規制が進んでいる中、ファーストパーティデータを使い、顧客のライフタイムバリュー(LTV)やリピート購入率、口コミ(WOM)効果などを総合的に把握しないと、広告費を単純に ROI のみで判断しすぎる危険があるかもしれません。
さらに、オムニチャネル環境が広がると、オンラインとオフラインを横断してユーザーが商品やサービスに触れる経路が複雑化します。ROIを広告施策ごとに分割して計測するのは難易度が上がる一方、コミュニティやSNSを通じて補完的なデータを得ることで、Cookie不使用でもマーケティング効率を捉えやすくなる可能性があります。こうした状況下でROIを的確に計算・応用するためには、PDCAサイクルの継続的な実行と、ROIだけではない多角的な指標(CVR, NPS®, LTVなど)の統合あるいは併用が不可欠です。
ROIの計算方法とバリエーション
最もベーシックな ROI の計算式は(利益 ÷ 投資額)× 100% です。ここで「利益」とは、売上から諸々のコストを引いた純利益を指す場合が多いですが、企業によっては粗利益を使うこともあります。マーケティング施策の効果検証では、以下のような計算バリエーションがしばしば採用されます。
- 純利益ベースのROI 売上 – 広告費 – 原価 – 他の関連コスト = 純利益とし、その数字を広告費(投資額)で割る方法。より厳密に実態の利益率を捉えられます。
- 売上高ベースのROI 売上をそのまま投資額で割る簡便な手法。マーケターはROAS(Return On Ad Spend)と呼ぶこともありますが、利益率を考慮しないため、採算性を見誤るリスクがあります。
- 顧客獲得コスト(CAC)との比較 ロイヤリティやLTV(ライフタイムバリュー)も合わせて見ると、短期ROIが低くとも、長期的利益が大きい施策を判断できます。
- コミュニティ視点のROI 定量的な売上に表れにくいブランドロイヤリティやSNS上の口コミ波及効果を数値化しようという取り組みもありますが、正確に測るのは容易ではありません。
このように、ROIを単純な売上÷コストに置き換えて解釈するだけではなく、企業の収益モデルや広告費、ロイヤリティ形成のステップなどに合わせた柔軟な定義づけが実践されている現状があります。
ROIが注目される背景
1. 広告費の上昇と予算最適化の要請
SNS広告や検索連動型広告など、競合企業がこぞって参入するメディアでの出稿費は年々高騰しています。単に出稿量を増やすだけではコストが膨れ上がるため、どこにリソースを配分すれば投資対効果が最大化するか、ROIを基軸に考える必要が高まっています。
2. Cookie規制やプライバシー保護
Cookie規制によりサードパーティデータの活用に制限がかかり、ユーザーの詳細なトラッキングが難しくなりつつある時代です。そこで、ファーストパーティデータを活用して週次・月次でPDCAサイクルを回し、ROIを継続的に測定・改善するアプローチが注目されます。こうした施策は離脱率やCVRの増減と合わせて検証しやすく、ロイヤリティ形成にまで踏み込むと定性的な指標とも連動できます。
3. DX推進とデータドリブン施策
デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む企業ほど、ブランドロイヤリティやLTVを高める施策をデータドリブンで行う流れが定着しています。ROIはその最終的な評価軸になりやすく、「いかに少ない広告費・投資でより大きなリターンを得られるか」を検討する際に不可欠です。
こうした要因から、ROIが再び強く意識されるようになっており、コミュニティ運営やステップメールなどの手段との関連付けを探る企業も増加傾向にあります。
ROIのメリットと限界
ROIは、投資対効果を数値化するという明確なメリットを持つ一方、いくつかの限界も存在します。
メリット
投資効率の可視化
広告費を中心に、どの施策がどれほどの利益を生んでいるか一目で把握でき、企業の経営判断をサポートする。
社内外での説明力
上層部やステークホルダーに対して、施策の有用性を説明する際、ROIはシンプルで強力な指標になりうる。
短期的なPDCAの指針
週次・月次で計測することで、ABテストやEFO改善の効果がCVR増減にどう寄与したか、広告費の回収が適正に行われているかを逐次確認できる。
限界
定性的要素を反映しにくい
ロイヤリティ形成やユーザー満足度、コミュニティの結束など、長期的な効果は数値化が難しく、ROI計算では見落とされがち。
短期志向になりやすい
一時的に高いROIを出す施策ばかり選んでしまうと、中長期のブランド価値を損なう恐れがある。広告費抑制にとらわれすぎるとイノベーションを欠く場合も。
計算ベースが統一しづらい
何を「投資額」とみなし、何を「利益」と算定するかが企業やプロジェクトによって異なるため、横比較が困難。例えば人件費や開発費をどこまで含めるかの解釈がまちまち。
こうしたメリットと限界を踏まえつつ、ROIを唯一の基準とするのではなく、CXやNPS®など他の指標や定性調査と併せて総合的に評価することが望ましいとされます。
ROIと他の指標との組み合わせ
先に触れたように、ROIだけに頼ると「売上や利益に直結しやすい近視眼的施策」ばかりが選ばれてしまう傾向が出ます。しかし、ブランドロイヤリティやファーストパーティデータの蓄積、コミュニティ形成など、長期的に企業の競争力を高める要素は一度のROIでは測り切れません。そこで重要になるのが、複数指標の組み合わせです。
ROAS(Return On Ad Spend)
SNS広告や検索広告など、特定の広告施策への支出に対して売上金額をどの程度回収できたかを見る指標。ROIが純利益ベースで計算されるのに対し、ROASは主に売上高を用いるため、比較的短期での判断に使われがち。
LTV(LifeTime Value)
購入後にもリピート購入やアップセル、口コミ効果がある場合、LTVの向上をROIと合わせてモニタリングすると、中長期的なメリットが見えやすい。Cookie規制下でも、ファーストパーティデータで顧客行動ログを管理すれば長期価値を測定できる。
NPS®(Net Promoter Score)
ブランドやサービスを周囲に薦めたいと思うかどうかを数値化し、ロイヤリティ度合いを捉える指標。短期売上に表れなくても、ユーザーの熱量が高ければいずれ高いROIを生む可能性があることを示唆してくれる。
UX指標(離脱率、UI/UX評価など)
WebやアプリのUI/UXが良ければ購買行動に繋がりやすく、ROIを自然に向上させる。EFOやステップメールといった施策を導入する前後で離脱率を見比べ、ROI改善にどう寄与したかを推定することができる。
これらの指標とROIを同時に追うことで、「数字はいいが将来性のない施策」や「短期リターンは低いがブランド強化に繋がる施策」を一括して評価しやすくなります。
ROIと定性手法(デプスインタビューなどの)との併用の重要性
ROIは定量的な投資対効果を示す指標ですが、それだけでは広告費や施策費を投下しても期待どおりに成果が出ない要因が分からない場合があります。そこで、デプスインタビューなどの定性調査が補完的な役割を担います。
- デプスインタビューを通じて、ユーザーが商品を使わない理由や、最初は興味を持ったのに購入に至らない心理的障壁を把握することで、なぜCVRが上がらないのか、なぜROIが低迷しているのかの裏付けが得られる。
- 新たに生まれたサービスが斬新すぎてユーザーが理解できていないケースでも、PDCAサイクルを回しながらデプスインタビューのフィードバックを活かしてUIを改良すると、ROIが後から大きく伸びる可能性がある。
- コミュニティ内での反応を数値化しにくい状況でも、インタビューでロイヤリティ形成やシェア拡大の芽があるかどうかを発見すれば、投資判断を補強できる。
こうして定性調査とROIを組み合わせると、マーケティング施策の「数字の裏側」を掴めるため、長期的なブランディングと短期的な売上効率を両立する戦略が立案しやすくなります。
マクロミルグループでは西口一希氏が広めた「N1分析®」を提供しております。 「たった一人の顧客」からビジネスにインパクトする定性的インサイトを導き出すこの手法は、ROI運用の補完として機能させることができます。 ぜひ以下の記事を合わせてお読みください。
N1分析®とは?通常インタビューとの違い、メリット・デメリットから実施のポイントまで詳細に解説!
ROIの今後の展望とDX時代の可能性(短期ROIから『総合的ROI』へ)
DXが進み、Cookie規制や広告費の高止まりに悩む企業は、ROIを中心に広告戦略や施策選択を行う傾向が強まると考えられます。AIエージェントや大規模言語モデルの台頭により、SNS広告や検索連動型広告の成果測定も一層精密になるでしょうが、その分、ユーザーの多様な行動パターンを横断的に追う必要があります。
たとえば、コミュニティベースでの推奨行為(口コミ、メンションなど)が購入行動にどう波及するかを定量的に捉えるには、ファーストパーティデータを活用してNPS®やLTVと合わせて計測するアプローチが望ましいですが、それを最終的に収益に結びつけて見る指標としてROIが相変わらず有用な存在になります。
ただし、あくまでROIは投資対効果を金額ベースで捉える指標にとどまるため、今後は「短期 ROI」だけでなく「総合的な ROI(長期含む)」を追う必要があるでしょう。UI/UXの改良やロイヤリティ強化が定性的な要素を含む分、PDCAサイクルを何度も繰り返す中でROIの計測方法を複層化し、「広告費だけでなく、開発や運営全体を含めた実コストとリターン」を見極めるステージに入ると考えられます。
まとめ
ROI(Return on Investment)とは、投資額に対してどれほどの利益を生み出したかを示す、マーケティングや広告運用における基礎指標の一つです。従来は売上や利益を単純に投資額で割る計算方式が主流でしたが、Cookie規制や広告費の高騰、ファーストパーティデータの重要性が増した現在では、ROAS、LTV、NPS®など別の指標とも組み合わせながら、中長期的な観点で施策を検証するアプローチが定着しつつあります。
SNS広告や検索連動型広告など短期成果を追いやすい施策ばかり選んでしまうと、企業のブランドロイヤリティやコミュニティ形成の効果を見落とすリスクがあるため、UI/UX改善やステップメールなどの定性的な活動も踏まえた柔軟なROI活用が求められます。デプスインタビューなどの定性調査を加味すれば、なぜROIが上がらないのか、あるいは上昇傾向にあるのかといった原因を掴みやすく、PDCAサイクルを週次・月次の短いスパンで回す可能性が高まります。
今後、DXがより加速し、AIエージェントや大規模言語モデルが普及すると、ROIの計測と広告最適化はさらに自動化・高度化するかもしれません。とはいえ、ROIは投資対効果を単純な数値で示す指標であり、長期的なブランディングやコモディティ化の回避にはNPS®やLTVなどの追加指標もあわせて考える必要があります。結局、ROIを起点に、企業がどのようにコミュニティやユーザーとの繋がりを築き、継続的な関係を創出していくかが大きな差となるでしょう。
注:NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。