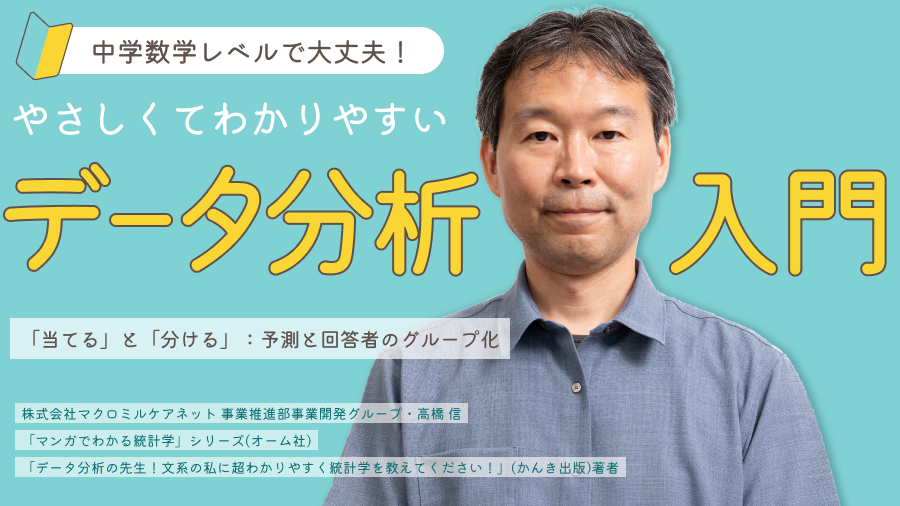「ユーザーにとって使いやすいものをつくりたい」
「インタビューでは好評だったのに、本番でつまずかれた」
「自分たちで試しても問題ないが、本当にユーザーもそう感じるのか?」
こうした問いに答えるために、多くの現場で導入されているのが「ユーザーテスト(User Testing)」です。
ユーザーテストとは、プロダクトやサービスの利用者が実際に操作する様子を観察・記録し、課題や改善点を明らかにする調査手法のことです。完成品だけでなく、プロトタイプやモックアップの段階から実施できるため、開発の初期フェーズから“気づき”を得ることが可能になります。
この記事では、ユーザーテストの定義、目的、主な手法、設計の流れ、分析のコツ、ありがちな失敗とその回避策までを、調査・UXリサーチの視点から実務的に解説していきます。
- ユーザーテストとは何か?その定義と位置づけ
- なぜユーザーテストが重要なのか?
- ユーザーテストの主な手法とその特徴
- ユーザーテストの設計ステップ
- 観察・記録・分析のコツ
- ありがちな失敗とその回避策
- まとめ:ユーザーテストは“つまずきから学ぶ”設計力
ユーザーテストとは何か?その定義と位置づけ
ユーザーテストとは、製品・サービスの実際のユーザーが、特定のタスクを実行する過程を観察し、その中で発生する“困りごと”や“感情の動き”を分析する調査手法です。
マーケティングリサーチにおけるインタビューやアンケートが「聞く」手法であるのに対し、ユーザーテストは「見る」手法にあたります。
主に以下のような用途で活用されます。
- UI・UX設計の仮説検証
- サイトやアプリのナビゲーション確認
- 新機能の理解度テスト
- 離脱要因の特定
- 業務システムの操作負荷の測定
ユーザー本人の視点・行動を通じて、設計側の思い込みや見落としを可視化するのが最大の特徴です。
なぜユーザーテストが重要なのか?
設計者や開発者がどれだけ細部にこだわっても、最終的にその製品やサービスを使うのは“ユーザー”です。そして、ユーザーの行動や感覚は、設計者の想定とは大きく異なることが多々あります。
ユーザーテストは、その“ズレ”を早期に発見し、開発や改善のサイクルを正しい方向に導くために欠かせない工程です。
① 実際の操作で課題をあぶり出せる
仕様書やUIデザインの段階では問題なく見えたものが、ユーザーの手に渡った瞬間、想定外のミスや戸惑いが起きることがあります。ユーザーテストはその“現場のリアリティ”を可視化する数少ない手法です。
② 言語化されない不満や違和感を発見できる
ユーザー自身が気づいていない“迷い”“気持ちのひっかかり”は、インタビューでは拾いきれないこともあります。テスト中の視線の動き、マウスの迷い、表情の変化など、非言語情報の観察が真のインサイトにつながります。
③ 開発初期から改善点を発見できる
プロトタイプの段階でも実施できるため、“失敗のコストが小さいうちに軌道修正できる”というのも、ユーザーテストの大きな強みです。
④ チーム全体のユーザー理解を促進する
ユーザーテストに立ち会うことで、開発者やデザイナーが“ユーザーの視点”を自分ごととして感じることができます。これがプロダクトの質を高め、組織の共通理解を育てる土壌になります。
ユーザーテストの主な手法とその特徴
ユーザーテストには、実施環境・対象・目的に応じてさまざまな手法があります。ここでは、代表的な形式を紹介します。
① モデレーター付きユーザーテスト(対面/オンライン)
調査者が同席し、ユーザーの行動を観察しながら、必要に応じて指示や質問を行う形式。行動の背景を深掘りしやすく、リアルタイムでの気づきも得られます。
| 特徴 | 質の高いインサイトが得られやすい |
|---|---|
| 留意点 | モデレーターのスキルに依存する |
② リモートユーザーテスト(非同時型)
ユーザーが自宅などの環境でタスクを実行し、その様子を録画して提出する形式。人数を多く集めたい場合や、実使用環境でのリアルな挙動を観察したい場合に適しています。
| 特徴 | 規模を拡大しやすく、自然な利用状況が見られる |
|---|---|
| 留意点 | 予期しないエラー時の対応が難しい、背景理解が限定的 |
③ シンクアラウド法(Think Aloud Protocol)
ユーザーに「今何を考えているか」を声に出しながら操作してもらう方法。操作の意図や迷いをリアルタイムで知ることができ、特に初期設計の検証に向いています。
| 特徴 | 思考プロセスを直接把握できる |
|---|---|
| 留意点 | ユーザーに負担がかかる、発話が苦手な人もいる |
④ アイ・トラッキング(視線計測)
視線の動きや注視時間を計測し、視認性や情報設計の妥当性を評価する手法。物理的な環境が必要だが、ビジュアル設計の定量評価に役立ちます。
| 特徴 | 客観的な視線データが得られる |
|---|---|
| 留意点 | 設備コストが高く、専門知識が必要 |
ユーザーテストの設計ステップ
ユーザーテストは、ただ“見ればよい”ものではありません。観察する前に“何を知りたいか”“何を課題とみなすか”を明確に設計しておくことで、初めて有効な気づきが得られます。以下は、ユーザーテストを行う際の基本的な設計ステップです。
① テストの目的を定義する
- 例:「初回利用時のナビゲーションの理解度を検証したい」
- 例:「予約フォームの完了率を阻害している要素を特定したい」
目的が明確でないと、観察ポイントがブレ、分析も曖昧になります。ひとつのテストで欲張らず、目的を絞るのが基本です。
② ユーザー像とタスクを設計する
- どのような属性の人に、どのような前提で使ってもらうのかを明示します
- タスクは「商品を1点購入する」「問い合わせフォームを送信する」など、具体的なアクションを設定します
タスクは“操作の順番”ではなく、“目的を達成してもらうシナリオ”で設計するのがコツです。
③ テスト環境を整える
- オンラインか対面かを選定
- デバイス(PC/スマートフォン/アプリなど)の指定
- 録画・録音ツール、観察者の配置、同席方法などを決定
現場でのテスト中に、記録やモニタリングができる体制を整えておくことも重要です。
④ 被験者の同意を取得する
- テストの目的、記録の有無、個人情報の扱いなどを事前に説明し、同意を得ます
- テスト中の発言や画面が記録される旨を明示し、不安を取り除く工夫をしましょう
⑤ テストの実施とレビュー
- モデレーターはできるだけ中立に振る舞い、ユーザーの自然な行動を尊重します
- テスト終了後すぐに“ホットレビュー”(観察者によるメモの共有)を行うことで、記憶が鮮明なうちに気づきを言語化できます
観察・記録・分析のコツ
ユーザーテストの本質は“観察”にあります。しかし、単に見ているだけではなく、「どこで迷ったか」「なぜその行動を取ったか」「表情や発話のトーンに違和感はなかったか」といった、細やかな読み取りが重要です。
① 行動+発言+文脈をセットで捉える
- 単に「戻るボタンを押した」ではなく、「不安そうな表情で確認画面に戻った」など、行動の背景を含めて記録します
- 発話だけでなく、沈黙、表情、視線、スクロール速度などの非言語情報も貴重なインサイト源です
② タスクごとの“つまずきポイント”を分類する
- タスクの達成率、所要時間、途中離脱、誤操作などを記録し、定量化も試みます
- 「戸惑いのあった箇所」「再操作が必要だった箇所」などをマッピングすると、改善点が明確になります
③ 仮説と照らし合わせて読み解く
- 事前に立てた仮説と、実際の観察結果を照らし合わせ、「想定どおりだった点」「意外だった点」に分けて分析します
- チームでレビューすると、視点の偏りを抑え、多角的に検討できます
ありがちな失敗とその回避策
ユーザーテストは、正しく設計・運用すれば非常に効果的な手法ですが、準備や進行に不備があると、誤った結論を導いてしまうこともあります。以下に、よくある失敗とその対策を紹介します。
① ユーザーに“操作指示”をしてしまう
→ 対策:「このボタンを押してください」と言ってしまうと、ユーザーの自然な行動が観察できなくなります。タスクは目的だけを伝え、操作方法は任せるのが基本です。
✕:ログイン画面を開いてください
○:このサービスにログインしてみてください
② テストの目的があいまいなまま実施してしまう
→ 対策:「なんとなく不安だから見ておこう」という動機では、観察がブレます。タスクと観察項目は明文化し、関係者と共有したうえで臨むべきです。
③ テスト人数だけを重視してしまう
→ 対策:定性調査であるユーザーテストは、「サンプル数」より「気づきの質」が重要です。5〜6人程度でも、共通した課題が見えれば十分に価値があります。
④ 観察者が多すぎて参加者が緊張する
→ 対策:画面越しでの同席や、モニタールームの活用、カメラ位置の工夫などで、ユーザーに“見られている感覚”を与えないよう配慮します。
まとめ:ユーザーテストは“つまずきから学ぶ”設計力
ユーザーテストとは、ユーザーの“迷い”“つまずき”“無意識の行動”を通じて、プロダクトやサービスの本質的な課題に気づくための設計手法です。
- UIやフローの改善に
- サービス導入の障壁発見に
- ナビゲーションや言葉の理解度の検証に
- 開発前のコンセプト確認に
調査・観察・対話の要素が融合したこの手法は、数字では見えない“本当の使われ方”に迫る強力なツールです。
ユーザーに聞くのではなく、
ユーザーに“やってもらう”ことで、
設計者は自分たちの思い込みから自由になります。
機能追加やデザイン変更の前に――
一度、ユーザーに触ってもらいましょう。
そこに、プロダクトの未来を変えるヒントがあるはずです。
著者の紹介
株式会社マクロミル
鳥居 慧
2009年に株式会社マクロミルに入社。
10年以上にわたり定量調査から定性調査まで幅広いリサーチサービスの運用部門に従事し、10,000件以上のプロジェクトに関与。
2024年、セルフ型のオンラインインタビュープラットフォーム「Interview Zero」を立ち上げ、プロダクト責任者として従事。