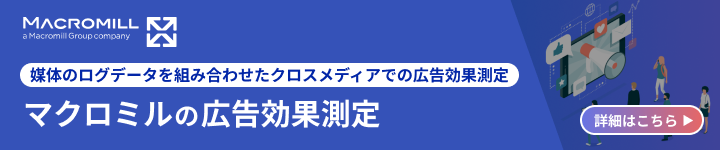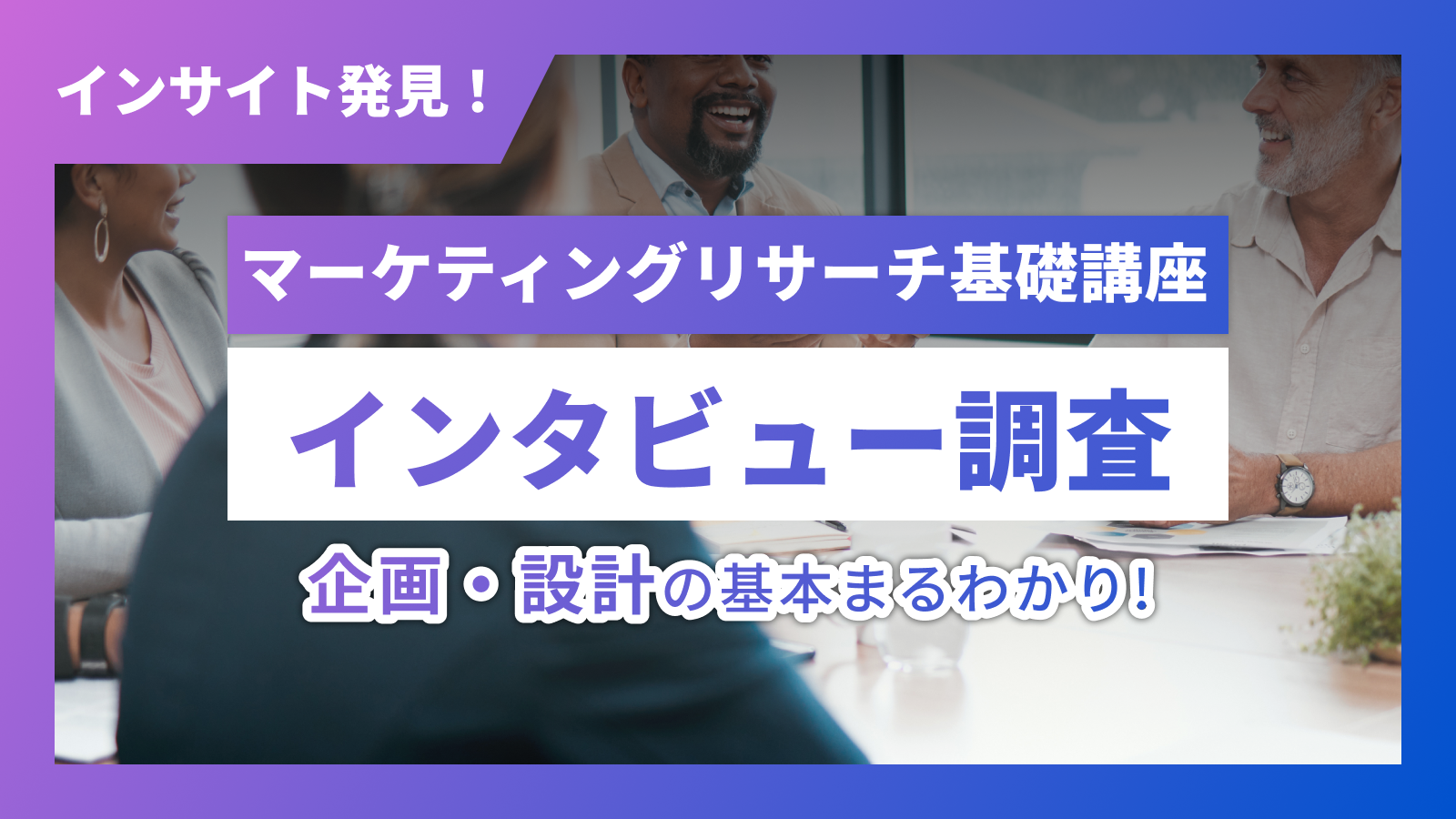OOH(屋外広告)とは?効果的な広告戦略を実現する方法を分かりやすく解説
公開日 :2023/4/14(金)
最終更新日:2025/3/19(水)
OOH(Out of Home)広告とは、文字通り「家の外」で目にするさまざまな広告媒体の総称です。たとえば駅や電車内のポスター、ビルの屋外看板、デジタルサイネージ(電子看板)、バスやタクシーの車体ラッピングなどが挙げられます。SNS広告や検索連動型広告のようにオンライン空間へ出稿するタイプとは異なり、物理的な空間に配置されるのが最大の特徴です。
OOH広告は、テレビCMや雑誌広告と同様、マスメディア的な範囲で多数の人々にアプローチできる手段として昔から活用されてきました。インターネットの普及に伴いデジタル広告が当たり前になった今でも、駅構内の大きなポスターや交通機関のラッピング広告は人目に触れやすく、短時間で強いインパクトを与えられる利点を持っています。広告費が高騰するデジタル広告とは異なるアプローチとして、認知度向上やブランドロイヤリティ醸成を狙う企業にとって欠かせない存在です。
ただし、OOH広告はオンラインのように詳細なトラッキングが難しく、ファーストパーティデータを直接結びつけにくい一面がありました。しかし近年では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が屋外広告の領域にも広がり、デジタルサイネージの導入や位置情報データとの連携などによって、マーケティング施策としての可能性が再評価されています。
OOH広告が再注目される背景
SNS広告や検索連動型広告が一般化する一方、Cookie規制の強化やユーザープライバシー保護の流れによってサードパーティデータの活用が制限されつつあります。そうした環境の変化が進むなかで、従来のオフライン媒体であるOOH広告が改めて注目されているのは興味深い状況です。大きな背景としては、以下のような要因が挙げられます。
1. リアルな接触機会の希少性
オンラインでの広告が溢れるなか、物理空間で視覚に直接訴求できるOOHの価値が相対的に高まっていると考えられます。誰もがスマートフォンを手にしている時代でも、駅や電車内で目にする大きな看板は、行動ログでは捉えきれない印象の記憶を残す効果が期待できます。
2. ブランドロイヤリティ醸成への寄与
広告費をかけてもSNS広告だけではブランドの世界観や迫力を伝えにくいケースがあります。OOH広告ではまず「物理的なサイズがデカい」という特徴を活かし、大胆なビジュアルや企業のメッセージを大規模に表現できるため、ブランドロイヤリティを強化するツールとしても再評価されています。
3. DX導入との相乗効果
デジタルサイネージ化が進み、OOH広告の表示内容をオンラインで遠隔制御したり、屋内でセンサーを用いて閲覧数や反応を推定したりする仕組みが登場しています。こうした技術を用いれば、ある程度のPDCAサイクルを回せるようになり、Cookie規制の影響が大きいオンライン広告の補完手段としても有効です。
4. リテールメディアによる流行
購買のラストタッチポイントである小売(リテール)業者が取り扱う「リテールメディア」の流行も、OOHが最注目された要因の一つです。リテールメディアにはデジタル広告やデジタルOOHの要素が含まれ、従来のサードパーティトラッキングが難化した影響で、小売店の持つファーストパーティデータの威力が発揮される投資先として、広告予算を引き寄せています。
OOH広告がデジタルメディアと連携しはじめることで、オフラインとオンラインの垣根を超えたマーケティング施策が可能になってきています。CVR(コンバージョン率)の測定やファーストパーティデータとの連携についてはまだ試行錯誤も多いですが、コミュニティ形成やブランディングの場としてのOOHのポテンシャルは無視できません。
OOH広告の主な種類
一口にOOH広告といっても、実に多様な媒体が存在します。大別すると以下のような種類にまとめられます。
1. 交通広告
電車やバスの車内・車外、駅構内、空港ロビーなどで展開される広告。電車の吊り広告やドア横ポスター、ラッピングバスなどが代表例。通勤・通学者、旅行者など多くの人が視認する場所に出せるため、比較的幅広い層に訴求できる。
2. 屋外看板
ビルの壁面広告、ネオンサイン、道路脇の大型看板(ロードサイドビルボード)などが該当。視認距離が長く、一目で企業ロゴやメッセージを認知してもらいやすい。交通量が多い場所に配置される場合、エリア全体の雰囲気づくりにも影響する。
3. デジタルサイネージ
従来は紙ベースだった看板をディスプレイやLEDパネルで表示する方式。時間帯や曜日、さらには天候などの条件に合わせて広告内容を変更できるため、PDCAサイクルと組み合わせれば広告効率の最適化が図れる。DXとの親和性が特に高い。
4. 屋内設置型メディア
ショッピングモールや病院、オフィスビルのエントランスなど、人が一定時間滞留する場所に設置されたモニターやポスターなどもOOHに含まれるとされることがあります。来場者の属性に合わせて情報を掲出できるのが特徴。
5. エレベーター広告
2024年から急速に流行したエレベーター広告は、従来の広告と違い密で身動きの取りづらい環境で投影されるため、嫌がられず、視線を引き付けやすいという特徴がある。
オンライン空間ではABテストやEFOなどによる改善が比較的容易ですが、OOH広告の場合は広告の差し替えや設置場所の確保にコストや手間がかかる一方、インパクトの強さという利点が活きるメディアとなっています。
OOH広告とオンライン広告の比較
共通点
広いリーチ
SNS広告や検索連動型広告がインターネット上で多数の人に届く一方、OOH広告も繁華街や交通量の多い場所で大衆に訴求できる。
イメージ形成
ブランドロイヤリティや認知度向上といったマーケティング課題に寄与する点では共通。どちらも、いかにユーザーの印象に残せるかが鍵となる。
相違点
1. トラッキングとデータ活用
オンライン広告はCookieを使った行動ログ分析が容易だったが、Cookie規制が強まる現代ではファーストパーティデータとの連携が主流に移行中。一方、OOH広告は直接的な行動ログが取得しにくいが、デジタルサイネージや位置情報データなどを組み合わせる試みが進む
2. 瞬間的な接触と視認状況
SNS広告はユーザーがスクロールしている最中に一瞬で通り過ぎることが多いが、OOH広告は移動中の人が物理的に目にするため、感覚的に「大きく目に飛び込む」インパクトを与えやすいとされる。広告費のかけ方や成果測定の方法論が異なるゆえに、単純比較が難しい部分もある。
3. PDCAサイクルの柔軟性
オンライン広告は出稿を停止したりクリエイティブを差し替えたりするのが容易だが、OOH広告は契約期間や設置物理コストがあり、頻繁な変更が難しい。ただし、デジタルサイネージならPDCAをある程度回せる可能性がある。
こうした比較から、OOH広告はデジタル施策を補完し、コミュニティ形成やブランドロイヤリティ向上を狙う企業にとって有効な選択肢となっているのです。
マクロミルでは、再流行の兆しを見せる「OOH広告」のメディアパワーを分析したレポートを発行しています。
無料でダウンロードいただけるので、ぜひ御覧ください。
参考:つい見てしまう広告媒体OOH(屋外広告・交通広告)のメディアパワーを徹底分析!
OOH広告を成功させるポイント
1. クリエイティブデザイン
視認時間が限られるため、大胆なビジュアルや短いキャッチコピーを使い、一目でブランドやメッセージを理解させる工夫が必要となります。色彩やフォントなどのデザイン要素も、広告費を有効に使うための戦略として欠かせません。
2. ロケーション選定
交通広告であれば通勤者の導線を考慮し、郊外のロードサイドビルボードなら車の流れを計算した場所に掲出するなど、「どの場所にどのような層が通るか」を調査し、ターゲットセグメントとマッチするポイントを選びます。
3. オンラインと組み合わせる
OOH広告上にQRコードを配置して、スマートフォンでアクセスすると特典ページやコミュニティ招待へ誘導するなど、オンライン広告との統合的運用が増えています。
4. DX視点でのデータ活用
デジタルサイネージの場合は表示を自由に差し替えられるだけでなく、センサーによって近づいた人数や視線を推定できるシステムもあります。Cookie規制の影響を受けずにリアル環境でデータを集め、ABテストのように広告内容を最適化するトライアルが少しずつ進んでいます。
OOH広告の課題とリスク
1. 効果測定の難しさ
オンライン広告と違い、クリックやCVRといった指標で直接的な成果を測りにくいのがOOH広告の難点です。ユーザーが広告を目にしたのかどうか、どれだけ記憶に残ったかなど、定量評価が不透明であるため、広告費との費用対効果を算出するのが難しい面があります。
2. 地理的制約とコスト
屋外看板の場合、立地や人口密度が成果に直結します。大都市圏の主要駅や繁華街に広告を出すには高いコストがかかり、また契約期間も長めになることが多いです。PDCAやABテストを頻繁に行いづらい点がリスクとなる可能性もあります。
3. 視覚的・環境的競争
駅や街中では多数のOOH広告が並んでいるため、「どれだけ注目を集められるか」が激しい競争となります。適切なクリエイティブがないと埋もれてしまい、せっかくの出稿が無駄になる恐れがあります。
OOH広告とコミュニティ活用
コミュニティ形成とOOH広告を組み合わせる事例も増えています。例えば、ある企業が新製品のローンチ時に大きな屋外看板を出しつつ、「SNSの専用ハッシュタグを付けて写真を投稿すれば特典がもらえる」というキャンペーンを展開。これによって、屋外看板を見た人が自発的にオンラインコミュニティへ参加し、口コミ(WOM)やブランドロイヤリティが高まる仕組みを作ったのです。
さらに、ロイヤルティプログラムと連携させることも可能です。OOH広告で認知を高めたあとに、SNS広告や検索連動型広告でリターゲティングし、ステップメールでファーストパーティデータを活用したフォローアップを行う。こうした流れを通じてCVRを改善するハイブリッドな施策は、Cookie規制下でもブランドのコミュニティ活性化を実現できます。
また、近年のオムニチャネル戦略では、店舗への集客や体験型イベントへの誘導をOOH広告で促し、イベント内でユーザーが製品に触れたりコミュニティと交流したりするスタイルが注目されています。その後、PDCAサイクルを回し、週次や月次で広告クリエイティブや設置場所を見直すことで、最適化を図る手法も徐々に整いつつあります。
OOH広告の展望
OOH広告は、DXや大規模言語モデルなどのテクノロジー進化により、これまでにない可能性を開きつつあります。デジタルサイネージの進化と位置情報データの活用が組み合わされば、時間帯や気象条件、さらにはターゲットの属性(匿名化された推定情報)に合わせて広告内容をリアルタイム変更する試みが一部で進行中です。
長年「配信の柔軟性が低い」とされてきたOOH広告も、このようなデータ連携とDXによって、一歩踏み込んだパーソナライズが可能になるかもしれません。オンラインでPDCAを回すように、屋外でも週単位、日単位、あるいは時間帯単位でクリエイティブを替え、効果測定を試みる企業が増えています。
さらに、マルチモーダル解析やAIエージェントが発展すれば、人々の視線や滞留時間などをより正確に推定し、広告費を最適配分するテクノロジーが生まれる可能性もあります。ただし、プライバシー保護やユーザーの嫌悪感を生まないような設計が前提となるため、倫理や法的側面の検討が継続的に必要でしょう。
まとめ
OOH(Out of Home)広告とは、屋外の物理空間に展開されるさまざまな広告媒体を指し、駅やバス、屋外看板、デジタルサイネージなどが代表例です。SNS広告や検索連動型広告といったオンライン施策が盛んな現在でも、OOH広告の視認性とインパクトは大きく、ブランドロイヤリティ形成や認知拡大に寄与する手段として重宝されています。
Cookie規制や広告費増加がもたらすオンラインの限界を補完する意味でも、OOH広告の存在感は見直されているところです。さらに、デジタルトランスフォーメーション(DX)が屋外広告にも浸透し、デジタルサイネージや位置情報と組み合わせてPDCAサイクルを回す事例も増加。コミュニティやファーストパーティデータを活かしてユーザーと深く結びつける施策が実現すれば、オフライン空間でも精度の高いマーケティングが可能となるでしょう。
とはいえ、オンラインのように詳細な行動ログが取得しづらいことや、設置コスト・期間の柔軟性が限られるといった課題も残ります。視線データや滞留推定など、マルチモーダル解析が進化すれば効果測定がより精密になる一方、プライバシー保護との折り合いも課題です。総じて、OOH広告はデジタル技術との融合を進めながら、ブランドの世界観や企業独自のメッセージを大規模に発信する貴重なメディアとして再評価され、コモディティ化しにくい強力な武器になり得ると言えます。