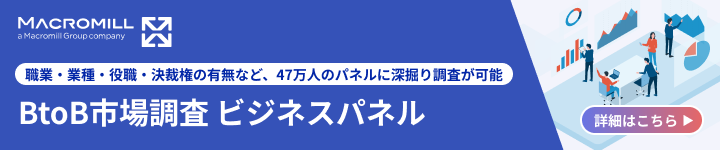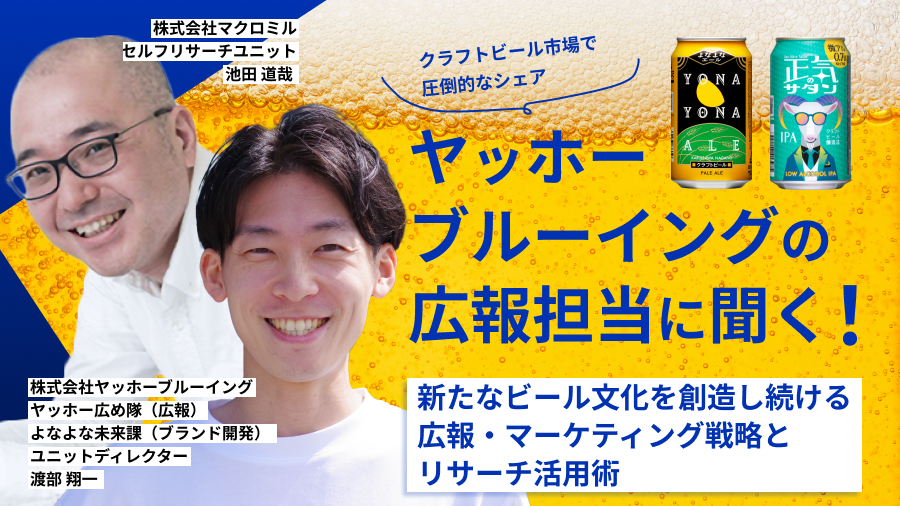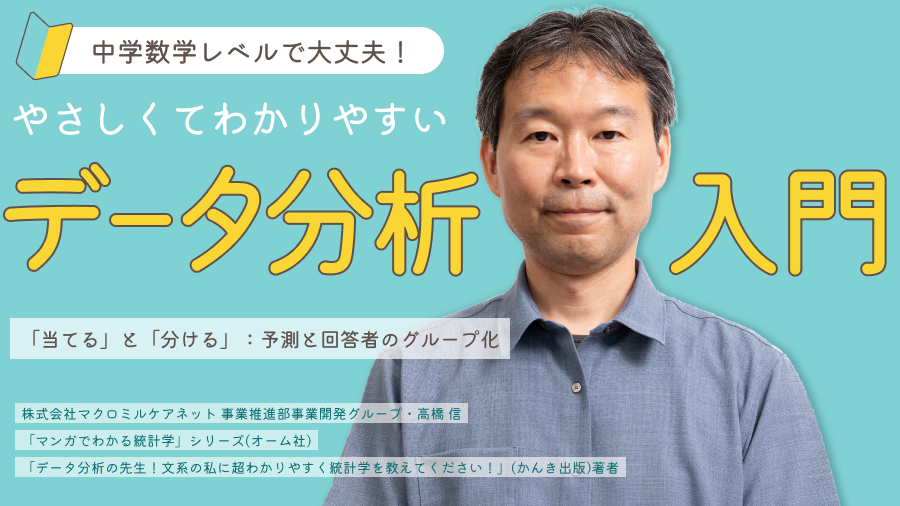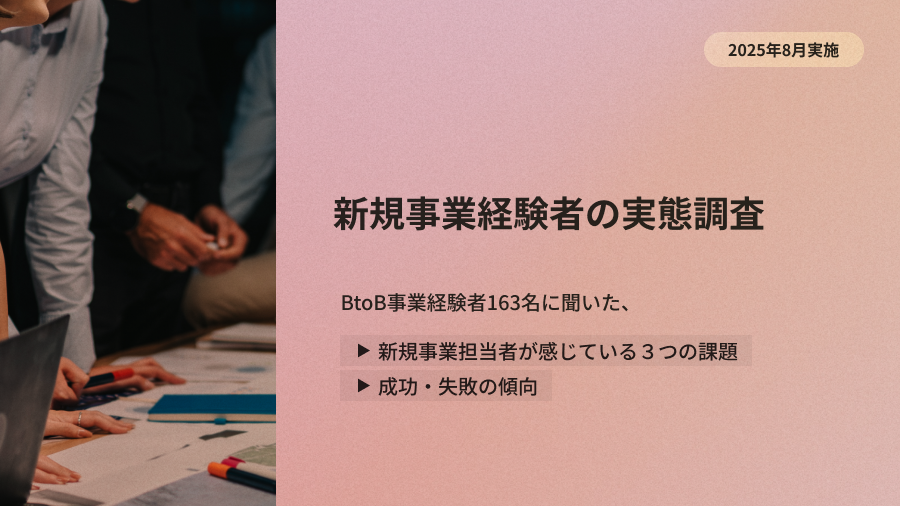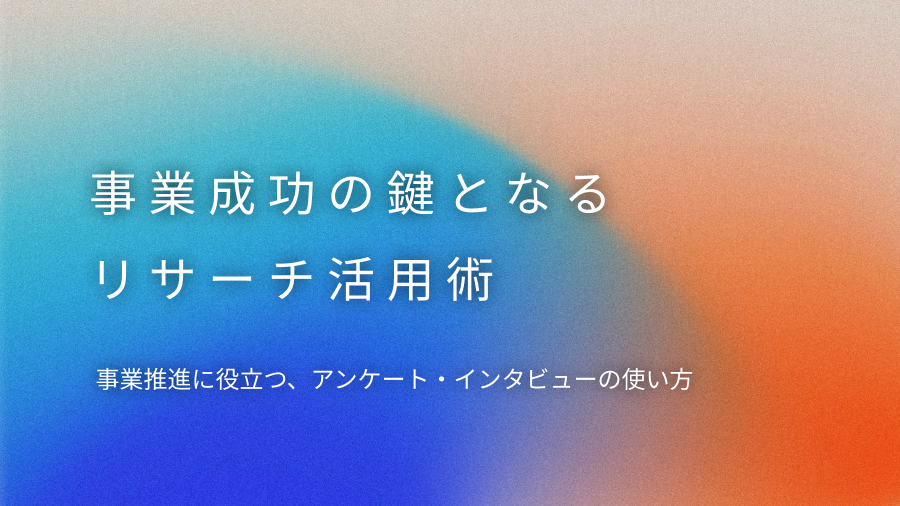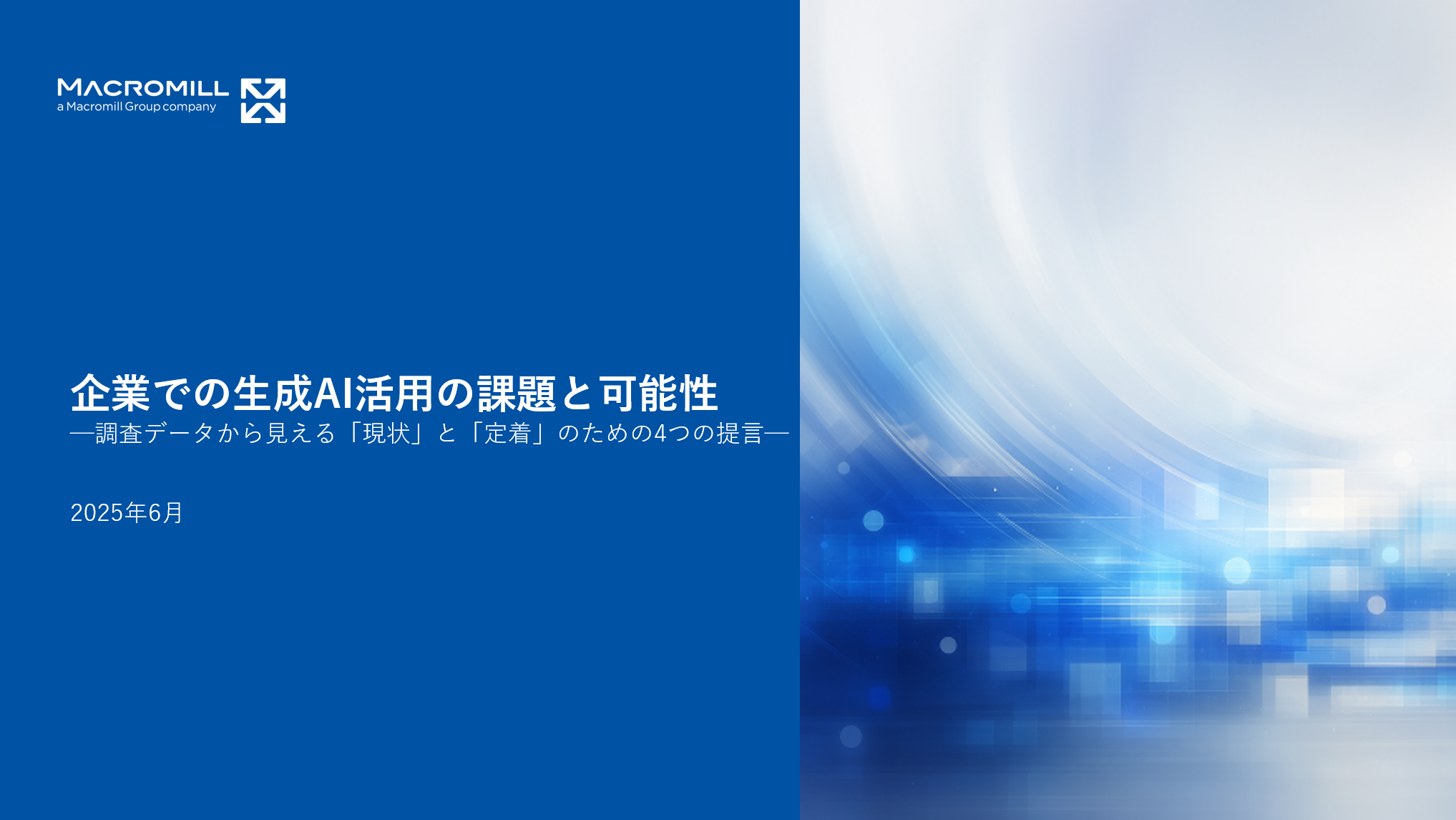MQL(Marketing Qualified Lead)とは?マーケティングと営業をつなぐリード評価の本質を解説
公開日:2025/8/29(金)
「リードは増えているのに商談が増えない」
「営業に渡しても反応が悪い」
「マーケからのリードは薄いと言われる」
BtoBマーケティングに携わる担当者であれば、こうした声を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。リード獲得がゴールだった時代は終わり、今は「商談に結びつくかどうか=リードの質」が問われる時代です。
そこで登場するのが「MQL(Marketing Qualified Lead)」という概念です。
MQLとは、マーケティング活動によって獲得された見込み顧客の中でも、「営業に引き渡すに値する」と判断された“確度の高いリード”のことを指します。MQLを正しく定義し、選別・育成・連携の仕組みを整えることで、リードの“量”から“成果”への転換が加速します。
このコラムでは、MQLの定義から、SQL(Sales Qualified Lead)との違い、判定基準、スコアリング設計、マーケティング施策との関係、運用上の課題と改善策、そして実際の活用事例までを、体系的に解説します。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- MQLとは何か?その定義と背景
- MQLとSQLの違いとは?
- MQLの判定基準:行動・属性・スコアリング
- MQLを生むコンテンツとナーチャリング設計
- MQLの運用ステップとSLAの考え方
- 成功事例:MQLが営業成果につながった企業の取り組み
- よくある課題と“質の高いMQL”を増やす改善策
- まとめ:MQLは“成果につながるリード”を育てるしくみ
MQLとは何か?その定義と背景
MQLとは、「マーケティング活動を通じて獲得した見込み顧客(リード)のうち、購買意欲や情報収集の姿勢などを一定の基準で評価し、“営業が接点を持つ価値がある”と判断されたリード」のことです。
語源は以下のとおりです。
- M(Marketing):マーケティング部門が獲得・管理する
- Q(Qualified):一定の基準により選別された
- L(Lead):見込み顧客
つまり、すべてのリードがMQLではなく、「質が高い」と判断されたごく一部がMQLとして営業に渡される、という考え方です。
背景には、以下のような課題が存在します。
- 獲得したリードが多すぎて営業が対応しきれない
- 営業から「優先度がわからない」「今すぐじゃない」と言われる
- マーケと営業が成果指標を共有できていない
MQLという“橋渡しの基準”を設けることで、マーケと営業の分断を解消し、商談化の精度を高めることができます。
MQLとSQLの違いとは?
MQLと混同されやすい概念として、「SQL(Sales Qualified Lead)」があります。MQLとSQLの違いを理解することは、マーケティングと営業の“連携の質”を高める上で極めて重要です。
MQL(Marketing Qualified Lead)
- マーケティング部門が「営業に渡す価値がある」と判断したリード
- Webサイト閲覧、資料ダウンロード、イベント参加、メール開封など、行動データと属性情報に基づき選別
- まだ“商談意欲”は明確でないが、検討初期段階にある可能性が高い
SQL(Sales Qualified Lead)
- 営業部門が「商談として成立する」と判断したリード
- インサイドセールスまたは営業がヒアリングを実施し、ニーズや導入検討の姿勢が確認されている
- 営業提案フェーズへと進むための条件がそろっている
相違点まとめ
| 項目 | MQL | SQL |
|---|---|---|
| 評価主体 | マーケティング | 営業/インサイドセールス |
| 判断材料 | 行動履歴+属性 | ヒアリング内容+意思決定情報 |
| 状態 | 興味・関心段階 | 検討・選定段階 |
| 主な接点 | Web、メール、セミナー | 電話、Web会議、訪問商談 |
| パス先 | インサイドセールス/営業 | フィールドセールス(商談化) |
このMQL→SQLの流れこそが、the model型営業組織やABM(アカウントベースドマーケティング)における中核プロセスであり、正しく設計・運用することで商談の“質と量”の両方を引き上げることが可能になります。
MQLの判定基準:行動・属性・スコアリング
MQLを定義する際、重要なのは「誰が・どのように・何をもとに判断するか」です。MQLの質が成果を左右する以上、その基準設計は極めて戦略的に行う必要があります。
属性情報(Fit)
- 企業規模(従業員数/売上)
- 業種/業界セグメント
- 部署・役職(決裁権の有無)
- 地域や市場ターゲットとの一致性
→ 自社にとって「顧客になりやすいかどうか」を評価します。
行動情報(Interest)
- 資料ダウンロード回数
- セミナー/ウェビナー参加有無
- 製品ページ閲覧の回数・滞在時間
- 比較資料/価格ページの閲覧履歴
- メールの開封・クリック履歴
→ 「どれだけ関心があるか」「検討度合いはどこか」を示します。
スコアリングによるMQLの自動化
多くの企業では、MA(マーケティングオートメーション)ツールを用いてスコアリングによるMQLの自動選別を行っています。
例:
- 資料DL:10点
- セミナー参加:20点
- 製品ページ閲覧(3回以上):15点
- 価格ページ閲覧:25点
- 合計スコアが70点以上 → MQLに認定
このように、属性×行動のスコア設計によってMQLの基準を「感覚」から「ルール」へと進化させることができます。
MQLを生むコンテンツとナーチャリング設計
質の高いMQLを継続的に生み出すには、マーケティング活動の中で「いかにリードの関心を高め、検討ステージを進められるか」が重要です。そのためには、“単なる資料提供”にとどまらず、戦略的なコンテンツ設計とナーチャリングシナリオが欠かせません。
MQL化につながりやすいコンテンツの種類
MQL判定に使われる行動は、“購買意欲”や“情報収集の真剣度”が高いコンテンツに触れているかどうかです。以下のようなコンテンツは、MQL化の判断材料として有効です。
- 導入事例集(=検討層が求める説得材料)
- 比較資料・価格ガイド(=選定フェーズのシグナル)
- 実践ノウハウのeBook(=導入前提での調査傾向)
- 製品デモ動画・無料トライアル申込(=“行動意欲”の明確化)
- 経営層向けのレポート(=社内検討材料として使用されやすい)
コンテンツは単なる“量”ではなく、“検討のステージ”に応じた“問いに応える深さ”がポイントです。
ナーチャリングシナリオの設計
見込み客がMQLに至るまでの過程を支援するのが、メール・広告・セミナーなどを使ったナーチャリングです。MAを活用し、以下のようなシナリオを設計します。
例:
- 資料DLから3日後 → 関連記事の紹介メール
- メール開封したら → 事例資料DLページへ誘導
- 製品ページを3回以上閲覧 → ウェビナーの招待メール配信
- ウェビナー参加後 → 営業に通知(MQL認定)
このように、「行動のトリガー」から「興味を深める導線」までを体系的に設計することで、顧客を“自然に”MQL化へと導くことができます。
MQLの運用ステップとSLAの考え方
MQLは「定義する」だけでは意味がありません。マーケティングと営業がMQLを起点に連携し、確実に成果につなげるためには、“渡し方”と“評価の仕組み”を整備する必要があります。
MQL運用の基本ステップ
- MAでMQL候補を自動抽出
- インサイドセールスがヒアリング
- 条件を満たせばSQLとして営業パス/満たさなければ再ナーチャリング
- 営業はSQLを商談化し、受注活動へ進行
- 商談結果をマーケへフィードバック → スコア設計やシナリオを改善
このように、MQLは“静的な基準”ではなく“動的なプロセス”として捉えることで、組織全体の営業活動が磨かれていきます。
SLA(Service Level Agreement)の設計
SLAとは、マーケティングと営業の“受け渡しルール”を明文化した合意事項です。
例:
- MQLの定義:スコア80以上+価格ページ閲覧済み+企業規模100名以上
- MQLパス後、営業またはインサイドセールスは24時間以内に対応
- SQL化しない場合は理由をマーケに返却し、再設計の材料にする
このように、定義・対応スピード・フィードバックまでを含めた運用があってこそ、MQLは“営業成果に効く評価軸”として機能します。
成功事例:MQLが営業成果につながった企業の取り組み
MQLを適切に定義・運用することで、リード対応の質が向上し、営業成果に直結するケースが数多くあります。ここでは、日本国内のBtoB企業における代表的な成功事例を紹介します。
事例①:SaaS企業A社 – 商談化率が3倍に向上
A社では、Web広告やセミナーで多くのリードを獲得していたものの、営業パス後の商談化率が10%を下回っていた。原因を探ると、MQLの定義が不明確で、営業が「今すぐではないリード」に無駄な時間を費やしていた。そこで、スコアリングを用いたMQL基準を導入し、資料DL、価格ページ閲覧、業種フィットなどで合計80点以上のリードのみをMQLとして営業にパス。その結果、MQLからの商談化率は30%超に跳ね上がり、営業の対応時間も大幅に削減。マーケと営業が共通KPIを持ったことで、部門間の信頼も深まった。
事例②:製造業B社 – ナーチャリングで眠っていたリードが受注に
B社では、展示会で名刺を獲得しても後続フォローがなく、数千件のリードが放置状態だった。MAを導入し、スコアリングによるMQL判定とシナリオメールによるナーチャリングを開始。価格ページや製品紹介ページの閲覧、資料再DLなどの行動をトリガーにインサイドセールスが接触し、営業に渡すMQLを再選別。約6か月後、ナーチャリング経由で10件以上の受注を獲得。「動かない」と思っていたリードがMQLとして再浮上し、成果につながった。
よくある課題と“質の高いMQL”を増やす改善策
MQLを導入してもうまくいかないケースには、共通する落とし穴があります。以下はその典型と、改善のヒントです。
MQLの定義が曖昧/属人的
「スコア80点以上」など定量的な基準がないまま営業にパスしてしまい、「なんでこれがMQLなの?」と現場に不信感が生まれるケース。
<改善策>
- スコアだけでなく「価格ページ閲覧+役職+業種」など複数要素で定義
- インサイドセールスによる“目視判定”と併用するステップを設ける
営業の反応が悪い(対応しない/不信感がある)
MQLを渡しても営業が放置してしまい、「結局反応ない」「連携できない」という状態に。
<改善策>
- SLAで“対応時間”を明文化(例:24時間以内に1回連絡)
- 営業側からのフィードバックループを設計(失注理由/課題の記録)
- 初期は「MQL→商談化→受注」のトレースを毎週分析・共有
数に偏りすぎて質が落ちている
「MQLをとにかく多く渡す」ことが目的化してしまい、結果として商談の質が低下し、営業が疲弊するパターン。
<改善策>
- 商談化率・受注率もKPIに含めることで“質のMQL”を評価
- MA/スコアリング設計を定期的に見直し、“貢献度の高いシグナル”を強化する
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
まとめ:MQLは“成果につながるリード”を育てるしくみ
MQLとは、単に「営業に渡す前のリード」ではありません。それは、マーケティング部門が“成果を生むための責任”を果たすための、戦略的な仕組みです。
- すべてのリードを追うのではなく、確度の高い相手に絞る
- マーケと営業が“共通の基準”で評価・判断・行動する
- リードを“育てて渡す”ことで、商談の質が上がる
MQLが正しく機能することで、組織全体の営業効率が上がり、フィールドセールスは提案に専念でき、マーケティングは「成果に貢献する部門」として社内での信頼を得られるようになります。
今、成果の上がらない営業体制や放置されるリードに悩んでいるなら――
MQLの定義と運用を見直すことが、組織全体の成長の第一歩になるかもしれません。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル