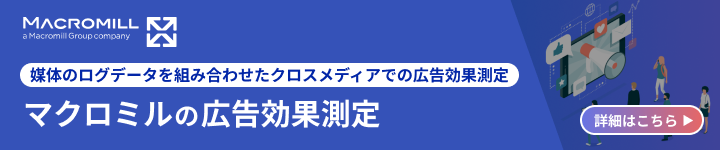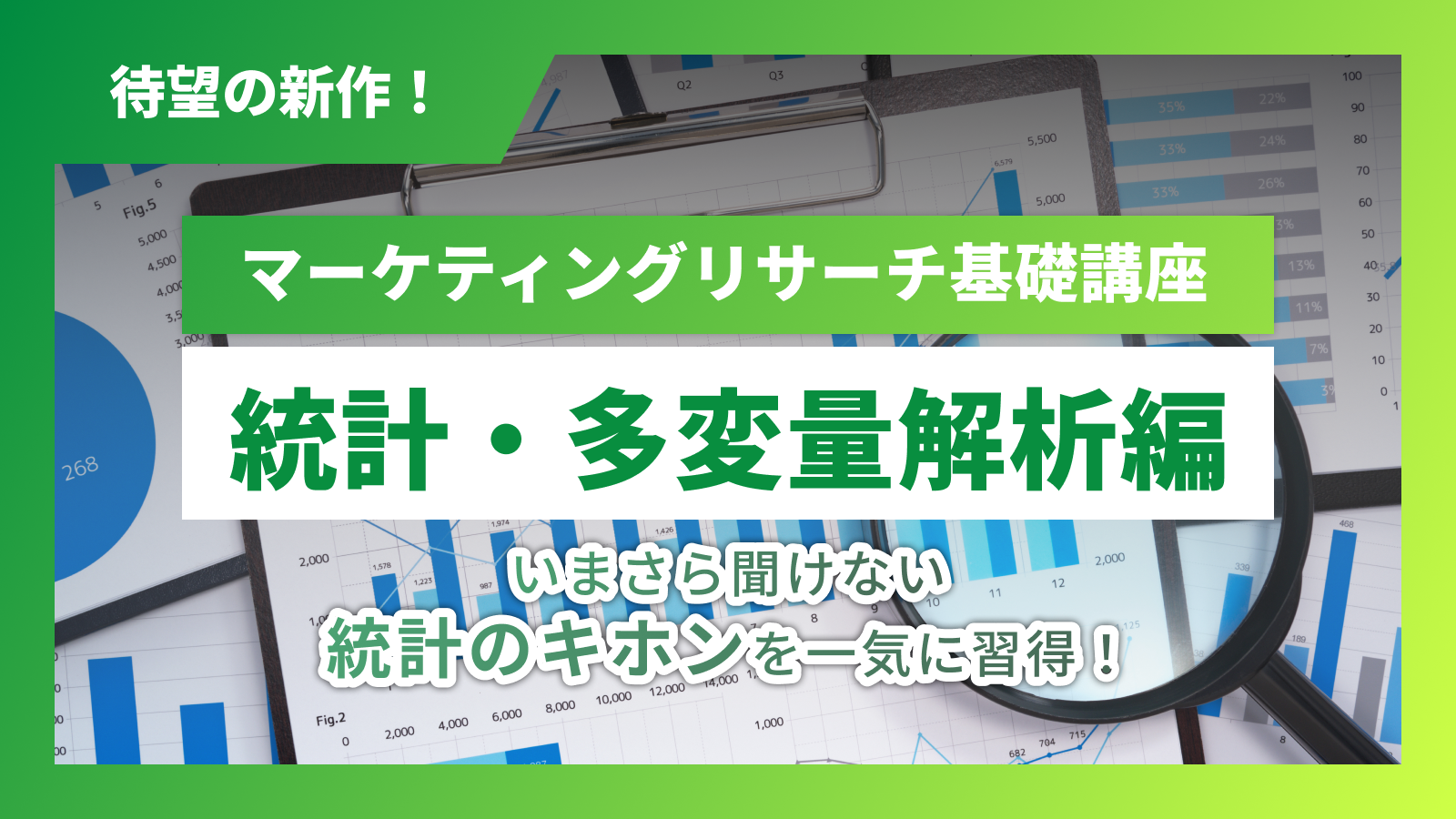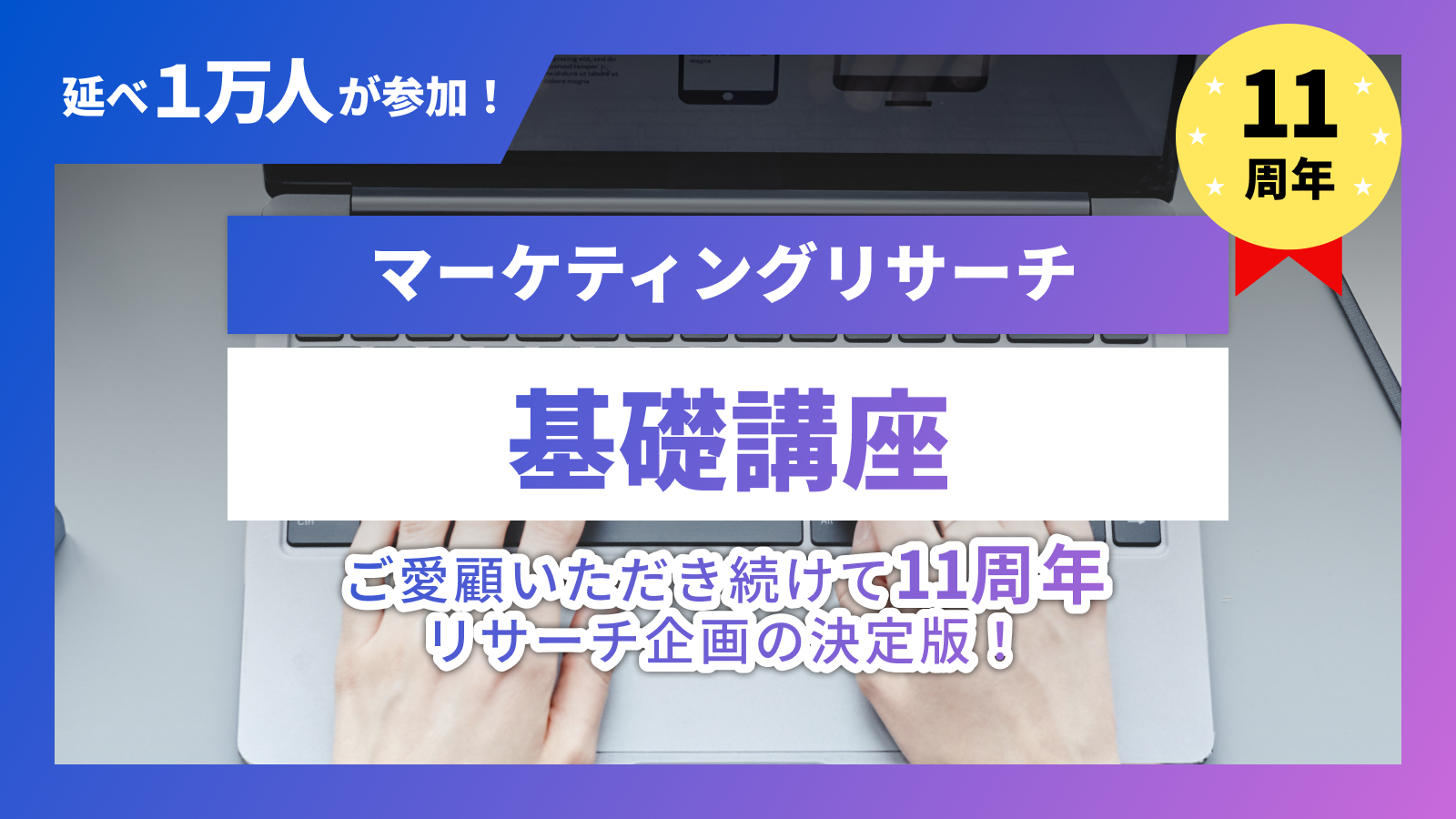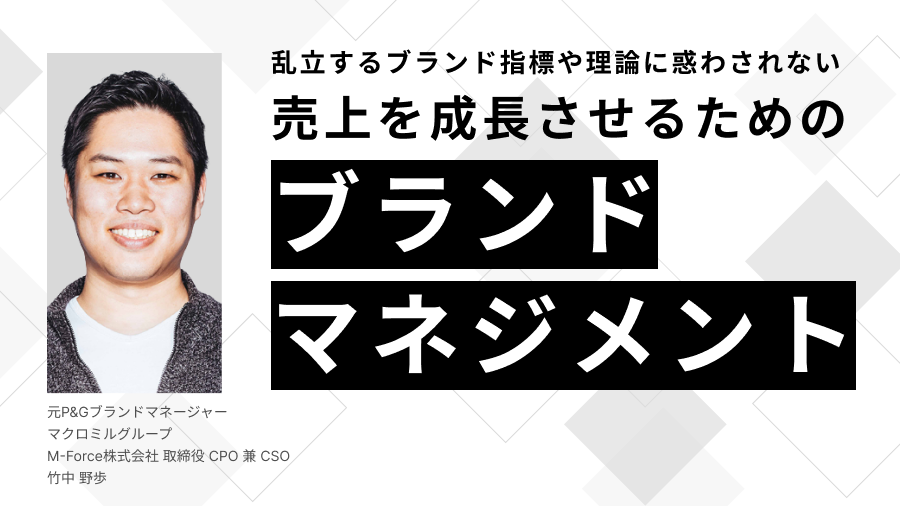「コミュニケーション」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。会話、メール、SNS、プレゼン、広告、デザイン、あるいは空気を読むこと——人によって答えはさまざまです。ですがマーケティングの世界では、こうした多様な手段をまとめて「価値を伝え、関係をつくる行為」として捉えます。言い換えれば、マーケティング活動の中核にはコミュニケーションがあり、それが上手くいくかどうかが企業と顧客、社会の関係性を決定づけます。
本コラムでは、コミュニケーションを「伝える技術」ではなく「共感をつくる設計」として捉え直し、マーケティングにおけるその役割・理論・実践・進化・未来について体系的に掘り下げていきます。
- コミュニケーションとは何か?伝達と共創のあいだ
- マーケティングとコミュニケーションの関係
- モデルと理論:伝わるとはどういうことか
- 現代マーケティングにおけるコミュニケーション設計の論点
- 実務で使えるフレームワークと考え方
- デジタル環境で変わるコミュニケーションの本質
- ケーススタディで見る成功と失敗
- 未来展望:コミュニケーションの「資本」化
- まとめ:コミュニケーションはマーケティングの“心臓”である
コミュニケーションとは何か?伝達と共創のあいだ
「コミュニケーション」の語源はラテン語の「communis(共有する)」にあります。つまり、本質的には一方的な“伝達”ではなく、相手との“共有”を目指す行為です。現代マーケティングでは、これを「意味の共有」と捉え、売り手と買い手が共に価値を発見するプロセスだと考えます。
たとえば、あるスポーツドリンクが「パフォーマンスを引き出す」と謳ったとしましょう。それを見た受け手が「トレーニング前に飲めば集中力が高まる」と理解するか、「疲れたときの回復に良い」と捉えるかは人それぞれです。つまり、発信者がどれほど意図を込めても、受け手がどう“意味づける”かによって成立するのがコミュニケーションなのです。
このように、マーケティングの文脈でコミュニケーションを語るには、情報を届けるだけではなく、意味を共有し、解釈をデザインする視点が不可欠です。
マーケティングとコミュニケーションの関係
マーケティングにおけるコミュニケーションは、「伝える手段」ではなく「ブランドと顧客の関係を築く設計」です。顧客とのすべての接点、つまりカスタマージャーニー上の認知・検討・購入・使用・共有の各フェーズにおいて、企業は何らかの形で顧客とやり取りをしています。
たとえば広告は明確な伝達手段ですが、店舗スタッフの表情、商品パッケージの配色、問い合わせメールへの返信速度、ECサイトのUI設計などもすべてが「無言のコミュニケーション」と言えます。これらが一貫していれば顧客は企業に対する信頼や好意を育てますが、矛盾していれば混乱や不信を招きます。
つまり、マーケティングにおいては「何を言うか」だけでなく「どこで、誰が、どう言うか」が極めて重要であり、組織として統合的なコミュニケーション戦略が求められるのです。
モデルと理論:伝わるとはどういうことか
マーケティングコミュニケーションの基本は、「送り手(sender)→メッセージ→媒体(channel)→受け手(receiver)」という線型モデルですが、現代ではこれだけでは不十分です。
なぜなら、受け手の背景・感情・文脈によって、同じメッセージでも全く異なる意味に解釈されるからです。たとえば、キャンペーンの「30%OFF」という表現は、「お得」と捉える人もいれば「在庫処分?」と警戒する人もいます。したがって、「受け手の世界観に合わせて意味が生成される」という解釈モデル(コンストラクティビズム)がより現実に即した理論となります。
また、ブランドは単なる「商品」ではなく「物語」であるとする「ナラティブマーケティング」も重要です。たとえば、アウトドア用品の購入者が製品スペックではなく「自然との共生を楽しむライフスタイル」に惹かれているように、企業が語るストーリーはそのままブランドの記憶となります。
現代マーケティングにおけるコミュニケーション設計の論点
一貫性(Consistency)
あらゆるタッチポイントでブランドの世界観や価値観がブレないことが重要です。広告はおしゃれなのに、店頭スタッフの接客が無愛想であれば、顧客の期待は裏切られます。一貫性のある言葉づかい・ビジュアル・態度が信頼の基盤となります。
共創性(Co‑creation)
顧客との双方向のやりとりを通じて価値を共につくるアプローチです。たとえば、SNSで商品開発案を募ったり、レビューから機能改善につなげたりすることで、顧客は“消費者”から“参加者”へと変化します。
文脈性(Contextuality)
メッセージは、受け取られるタイミングや場所によって意味が変わります。同じコピーでも、電車内の広告で見るのと、就寝前にスマホで見るのとでは、感じ方が異なります。ターゲットの生活リズムや心理状態を読み取る感性が求められます。
実務で使えるフレームワークと考え方
コミュニケーション戦略を実装する上で便利なのが「IMC(統合型マーケティングコミュニケーション)」という考え方です。これは、広告・販促・PR・SNS・コンテンツ・イベントなどすべてのチャネルを統合的に設計し、顧客に対して一貫した体験とメッセージを届ける手法です。
また、PEST(政治・経済・社会・技術)や3C(市場・顧客・競合)などの分析と組み合わせることで、外部環境と自社状況を踏まえた発信が可能になります。これらのフレームは、発信の「内容」よりも「前提」を整える役割を果たします。
さらに、「カスタマージャーニー×感情曲線」を組み合わせることで、情報だけでなく感情の動きに注目したコンテンツ設計が可能になります。「認知」時にワクワクを、「比較」時に安心を、「購入」時に納得を与えるよう、それぞれのフェーズに感情設計を加えると、共感度が格段に高まります。
デジタル環境で変わるコミュニケーションの本質
デジタル時代のコミュニケーションは、量・速さ・透明性の点でこれまでと比べものにならない変化をもたらしています。SNSやチャットはリアルタイムで反応が返ってくるため、「何を言うか」だけでなく「いつ・誰に・どう返すか」が重視されます。
また、テキストや動画、音声などのマルチモーダル表現が主流となったことで、「伝える力=表現の幅」となりました。ビジュアルや音楽、UI/UXの設計なども含めて総合的に「語る」ことが求められています。
さらに、生成AIの進化により、コンテンツは高速・大量に生成できるようになりましたが、「誰に対して、どんな物語を、どんなタイミングで語るか」という“文脈設計”は依然として人間のクリエイティビティが必要とされます。
ケーススタディで見る成功と失敗
ある日用品メーカーは、商品の特性を「時短」と訴求していましたが、SNSでの声を分析したところ「夜の癒し」に価値を感じているユーザーが多いことが判明しました。そこで広告コピーを「一日を閉じる、静かな時間」に変更したところ、購買数とブランド好感度の両方が上昇しました。メッセージそのものではなく、受け手の感情と生活文脈に寄り添った結果といえます。
一方、あるファッションブランドは、新作をTikTokでバズらせたものの、実店舗スタッフの態度が一貫せず「広告と中身が違う」という口コミが拡散。結果として、オンライン好感度とオフライン満足度のギャップが売上に悪影響を与えるという典型的な“分断型コミュニケーション”の失敗事例となりました。
未来展望:コミュニケーションの「資本」化
今後、企業の競争力は「何を所有しているか」ではなく、「どれだけ深い関係性を築いているか」にシフトしていくと考えられます。ブランドコミュニティ、SNS上の文脈理解、1to1の接客チャット、ファンとの共同企画など、すべてが“対話の資産”として蓄積され、企業の無形資産となります。
また、ウェルビーイング経済やエシカル消費が進む中で、「何を語るか」だけでなく「誰が語るか」「どんな姿勢で語るか」がブランドの信頼性を左右します。Z世代以降の生活者は、コンテンツの中身よりも“語り手の在り方”に敏感です。つまり、コミュニケーションは発信行為であると同時に、企業の姿勢と価値観を証明する行為でもあるのです。
まとめ:コミュニケーションはマーケティングの“心臓”である
コミュニケーションとは、単に情報を届けることではなく、価値観を共有し、関係性を築き、信頼を育てる営みです。マーケティングにおいては、すべての活動が何らかの形で顧客との対話であり、その積み重ねがブランドを形成していきます。
情報があふれ、言葉が溢れかえる時代だからこそ、伝えすぎず、読み取られすぎず、ちょうど良く伝わるバランスが求められます。広告、SNS、接客、UI、メール、商品設計——それらすべてを“一つの会話”として設計できたとき、企業と顧客の関係性はモノの売買を超えた信頼と共感へと変わっていきます。
コミュニケーションはマーケティングの手段ではなく、マーケティングそのものの中核にあります。言葉と意味、データと感情、声と沈黙の間に宿るものを見つめ直すことが、次の時代のマーケティングを強く優しく進化させる原動力になるのです。