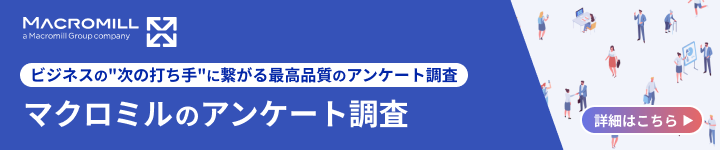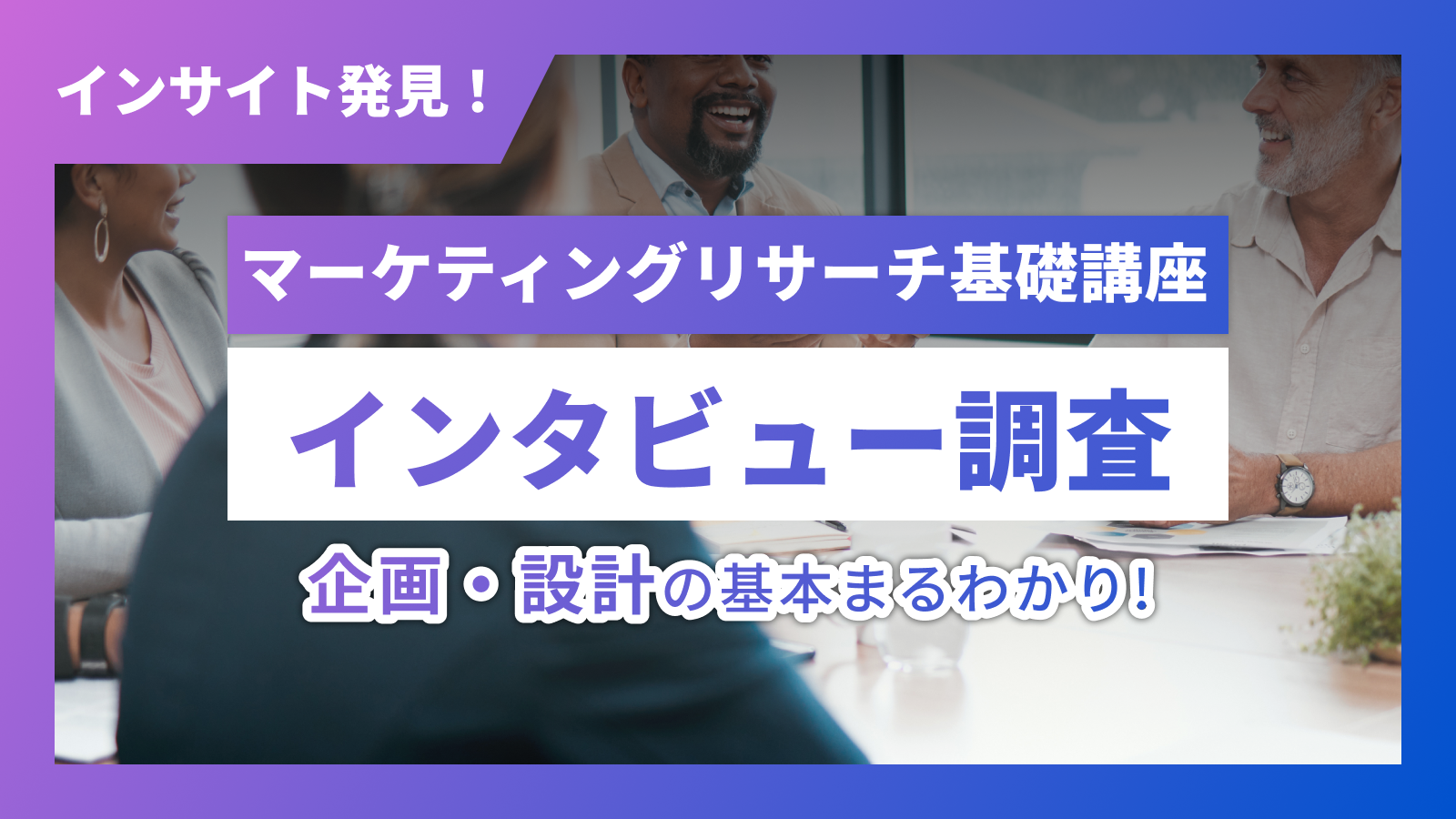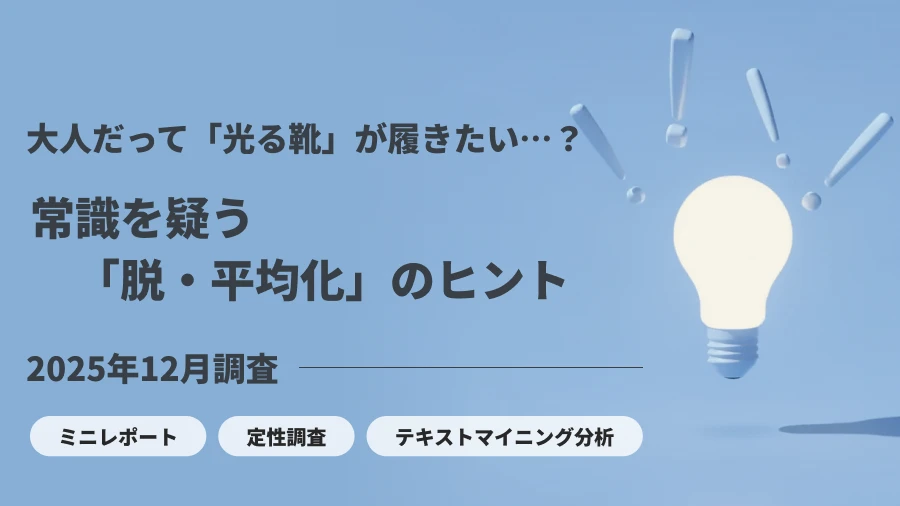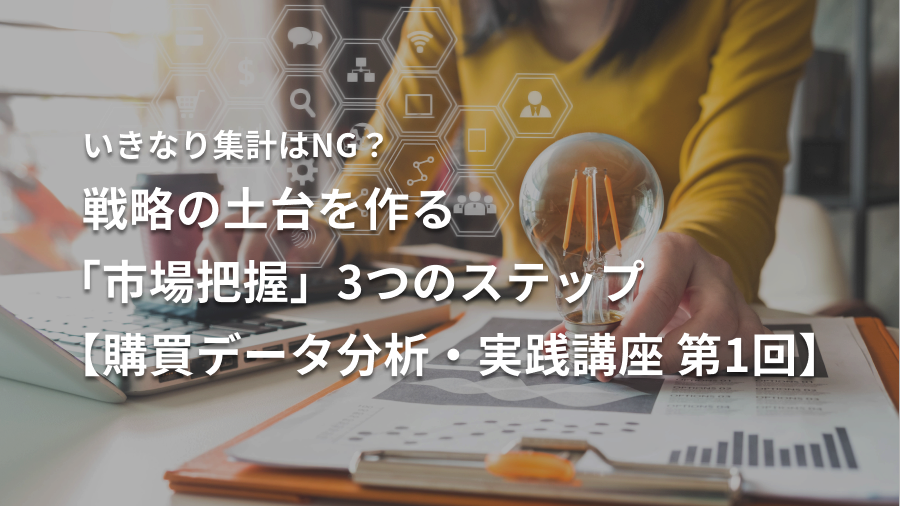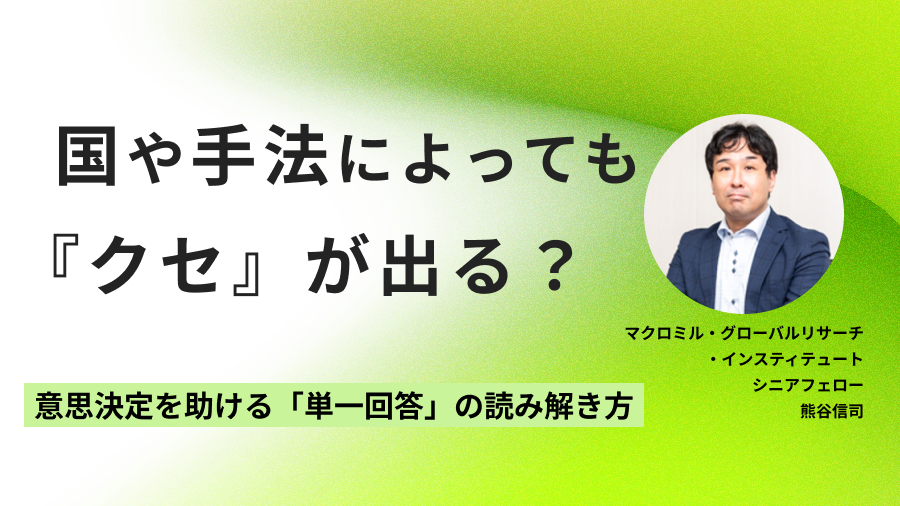少子化や晩婚化など、現代の社会構造は多様化しています。そのなかでも近年、改めて注目を集めているのが「DINKs(ディンクス)」というライフスタイルです。
DINKsとは「Double Income, No Kids(共働きで子どもがいない夫婦)」の略語で、もともとは1980年代に欧米で登場した言葉です。現代の日本でも、人口構成や働き方、価値観の変化によりDINKsは増加傾向にあります。
本コラムでは、DINKsの基本や消費傾向、マーケティングにおけるアプローチ方法などを解説します。
- DINKs(ディンクス)とは
- DINKsが増えている背景
- DINKsを選択するメリット
- DINKsを選択するデメリット
- マーケティング視点で見るDINKs層の消費傾向
- 【業界別】DINKs層へのアプローチ方法
- まとめ
DINKs(ディンクス)とは
まずは、DINKsというライフスタイルの正確な定義を確認しましょう。
- DINKsの基本的な定義
- DEWKsとの違い
DINKsの基本的な定義
DINKsとは、夫婦が共に安定した収入を得ながら、意識的に子どもを持たないというライフスタイルを選択した世帯を指します。DINKsを理解するうえで欠かせないのは、それが単に結果として子どもがいないのではなく、夫婦の合意による意図的な選択であるという点です。
キャリアの追求や趣味や自己実現への投資、夫婦二人の時間を大切にしたいなど、その理由は多岐にわたります。
DEWKsとの違い
DINKsとしばしば比較されるのが、DEWKs(Double Employed With Kids)、すなわち子どもを持つ共働き夫婦です。両者は、子どもの有無によって、家計の優先順位や時間の使い方、ライフプランの立て方が大きく異なります。
たとえば、子ども一人を大学卒業まで育てるには、2,000万円以上の費用が必要な場合があります。この巨額な支出がないDINKsは、DEWKsに比べて可処分所得が大幅に高くなるでしょう。そのため消費行動や住居の選択において、DINKsとDEWKsには違いが明確に表れます。
DINKsが増えている背景
現代の日本で、DINKsというライフスタイルを選択する夫婦が増加している背景には、複数の要因があります。ここでは、以下3つにわけて解説します。
- 共働き比率が増加している
- 多様なライフスタイルが選べるようになった
- 子育てコストなど将来への不安を感じる人が多い
共働き比率が増加している
DINKsが一般化した大きな要因としては、共働き世帯の増加です。『令和5年版 厚生労働白書』(厚生労働省)によると、専業主婦世帯が減少し続ける一方で共働き世帯は増え続け、1997年にその数が逆転しました。2022年時点では共働き世帯が1,262万世帯に達し、専業主婦世帯(539万世帯)の2倍以上となり、社会の多数派を形成しています。

この変化は、1986年の男女雇用機会均等法施行など女性の社会進出を促す法整備と、「夫は仕事、妻は家庭」という伝統的な価値観の変化が大きく影響しています。女性が経済的に自立しキャリアを追求することが現実的になった結果、出産や育児以外の人生設計も選択しやすくなったと考えられます。
多様なライフスタイルが選べるようになった
「結婚すれば子どもを持つのが当たり前」という画一的な幸福観が絶対的でなくなったことも、DINKs増加の要因です。
2024年の『少子化に関する意識調査』(日本財団)では、子どもを「持ちたくない・いなくてもよい」と考える人が26.3%にのぼり、子どもを持たないという選択がもはや少数派ではないことを示しています。

同調査で子どもを望まない理由として経済的負担に次いで、とくに女性では「自由な時間や生活を優先したい」との回答が上位にあがりました。キャリア形成や夫婦二人の時間を重視する価値観が、こうした選択の背景にあることがうかがえます。
子育てコストなど将来への不安を感じる人が多い
経済的な不安という現実的な課題も、DINKsという選択を後押ししています。長期にわたる経済の停滞や賃金の伸び悩みを背景に、子育てに伴う経済的負担を合理的に判断する夫婦が増えています。
『令和5年度 子供の学習費調査』(文部科学省)によると、子ども一人当たりの年間の学習費は、公立小学校で約34万円、私立ではその5倍以上の約183万円にものぼります。高等学校では、公立が約60万円であるのに対し、私立では100万円以上が必要です。
これらの高額な費用を、旅行や自己投資、あるいは老後資金の準備に充当できるDINKsのライフスタイルは、将来のリスクに対する合理的な選択肢の一つと考えられています。
参照:令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します│文部科学省
DINKsを選択するメリット
ここでは、DINKsの主要なメリットを具体的に解説します。
- 経済的なゆとりが生まれる
- 自由な時間を確保できる
- キャリア構築に専念できる
経済的なゆとりが生まれる
DINKs世帯の魅力は、経済的な余裕が生まれやすいことです。前述のとおり、子ども一人あたり2,000万円以上かかる可能性のある養育費や教育費が不要になるため、夫婦は自分たちの価値観や目標に沿って自由に資金を配分することが可能になります。
夫婦ともに安定した収入源があることで、世帯としての経済基盤が強固になり、生活の質を高めるための選択肢が広がります。
旅行やグルメ、趣味といった分野で、妥協せず体験を楽しむことができたり、スキルアップのための学習や資格取得などにお金を使うこともできるでしょう。
自由な時間を確保できる
DINKs夫婦が享受できる大きなメリットは、時間を自由に使えることです。子どもの世話や学校行事への参加、習い事の送迎といった時間的な制約が一切ないため、夫婦は自分たちのペースで日々の生活を自由に過ごせます。
とくに旅行計画においては、学校の長期休暇に合わせる必要がないため、料金が比較的安く、混雑も少ないオフシーズンを狙うことも可能でしょう。
また、夫婦それぞれが干渉されずに一人の時間を確保しやすいことも、精神的な充足感につながります。
キャリア構築に専念できる
DINKsという選択は、夫婦双方が出産や育児によるキャリアの中断なく、継続的かつ戦略的なキャリア形成を目指す際に有効です。
とくに女性にとって、20代後半から30代はキャリア形成における大切な時期と重なります。この時期に、出産による離職や育児と仕事の両立のためにキャリアのペースを落とす女性は多くいます。
DINKsのライフスタイルは、転勤や海外赴任といったオファーに対しても柔軟に対応できる点がメリットです。
DINKsを選択するデメリット
次に、3つの側面から、DINKsが直面しうるデメリットについても考察します。
- 老後への不安を感じることがある
- 世間体が気になることがある
- 子どもがいる友人と価値観があわなくなる場合がある
老後への不安を感じることがある
DINKs夫婦が直面する課題として、老後の生活に対する不安があげられます。子どもからの経済的、あるいは身体的なサポートを前提としないため、介護や病気の際に頼れる家族が限定されるという現実があります。
介護が必要になった場合、施設の利用料や専門的な介護サービスの費用は、公的な補助を除いて自己負担しなければなりません。こうした背景から、DINKs世帯には一般的な老後資金とされる2,000万円を大きく上回る、4,000~5,000万円程度の準備が推奨されることもあります。
また、金銭的な問題だけでなくパートナーに先立たれた後の精神的な孤独や、認知症になった際の財産管理といった課題にも、早期から備えておく必要があります。
世間体が気になることがある
個人の価値観が多様化したとはいえ、日本社会には依然として結婚すれば子どもを持つのが当然という家族観が根強く残っています。そのため、DINKs夫婦は周囲からの無理解や同調圧力によって精神的なストレスを感じる場面があるかもしれません。
一例として、以下のようなシーンに遭遇することが考えられます。
- 親や親戚から「孫の顔が見たい」といったプレッシャーをかけられる
- 職場や地域社会で「子どもはまだ?」といったプライベートな質問をされる
こうした経験が積み重なることで、親戚の集まりや職場での会話に疎外感を覚えたり、自分たちの選択に対する自信が揺らいだりすることもあるようです。
子どもがいる友人と価値観があわなくなる場合がある
ライフステージの変化は、親しい友人との関係にも影響を与えることがあります。友人たちが出産し親になるにつれて、会話の内容や関心の中心が自然と子育てに移っていくため、DINKs夫婦が話の輪に入りづらくなったり疎外感を覚えたりする可能性があります。
また、子育て中の友人は時間的な制約が多く、金銭感覚や休日の過ごし方についても考え方が大きく変わることもあるでしょう。その結果、金銭感覚や人生観があわなくなることがあります。
これはどちらが正しいという問題ではなく、ライフステージの違いから生じる自然な変化です。かつてのように気軽に時間を共有できなくなることに、寂しさを感じる場合もあるでしょう。
マーケティング視点で見るDINKs層の消費傾向
ここからは、マーケティング視点で見るDINKsの特徴について、解説します。
- 高単価の体験型消費に意欲的である
- 住宅やインテリアにこだわる傾向がある
- 外食やデリバリーの利用率が高い
- 将来への投資に積極的
企業がDINKsにアプローチする際のヒントを探ってみましょう。
高単価の体験型消費に意欲的である
DINKs世帯は、モノの所有よりも旅行やグルメ、エンターテイメントといった体験に価値を見出し、積極的に投資する傾向があります。子育て関連の支出がない分、可処分所得に余裕が生まれ、自分たちの満足度を高める高品質な体験への購買意欲が高まります。
また時間に縛られないため、旅行であれば混雑を避けた平日に、食事であれば予約の取りにくい名店を訪れるなど、質を重視した消費が可能です。ビジネスクラスを利用した海外旅行、星付きレストランでの食事、高級スパでのリラクゼーションなど、夫婦二人の生活を豊かにするために投資を惜しまない姿勢は、「プチ贅沢」市場を牽引する主要な要因となっています。
住宅やインテリアにこだわる傾向がある
DINKs世帯は、住環境を子育ての場としてではなく、夫婦二人のライフスタイルを表現する空間として捉える傾向が強いです。そのため、住宅やインテリアに強いこだわりを持ち、積極的に投資を行います。
デザイン性の高い家具や最新の家電、あるいは食洗機やディスポーザー(生ゴミ処理機)といった家事の効率を上げる高機能な設備に興味を持つ方も多いでしょう。在宅時間を快適に、そして美しく過ごすことへの投資意識が非常に高い層といえます。
外食やデリバリーの利用率が高い
共働きで多忙なライフスタイルを送るDINKs世帯は、外食やデリバリーサービスの利用率が他の世帯に比べて高いといわれています。
外食やデリバリーの利用は、単なる時短だけが目的ではありません。話題のレストランを訪れたり、高品質なデリバリーサービスを定期的に利用したりと、食を夫婦共通の楽しみやエンターテイメントとして位置づけている方もいるでしょう。
将来への投資に積極的
DINKs世帯は、現在の生活を充実させる一方で、将来への備え、とくに資産形成に対して非常に計画的かつ積極的です。老後の生活を子どもに頼ることができないという現実を深く認識しているため、早期から戦略的な資産運用に取り組む必要があります。
NISAやiDeCoといった税制優遇制度のほか、株式や投資信託による分散投資だけでなく、不動産投資などに関心を持つ層も少なくありません。
また、時間的な余裕を活かしてファイナンシャルプランナーに相談したり、投資セミナーに参加したりと、金融リテラシー向上にも熱心な方も多くいます。
【業界別】DINKs層へのアプローチ方法
本章では、不動産、旅行、金融の3業界を例に、DINKs層に効果的にアプローチするための具体的な戦略について解説します。
- 不動産業界:DINKs向け住宅の提案
- 旅行業界:ラグジュアリーな旅行プランの提案
- 保険・金融業界:資産運用できる商品の提案
DINKs層の独自のニーズと消費行動を理解し、的確な施策を実施することで、マーケティング効果を高めやすくなるでしょう。
不動産業界:DINKs向け住宅の提案
不動産業界がDINKs層にアプローチする際は、利便性とライフスタイルを核に据えた提案が効果的です。DINKsは駅からの距離を最優先に考え、2LDK程度のコンパクトな間取りでも高い満足度を示す傾向があります。
広さよりも質と設計にこだわり、ワークスペースや趣味空間、ホテルライクな設備の提案が有効です。また、子ども部屋の代わりに収納やシアタールームを充実させるニーズもあります。
旅行業界:ラグジュアリーな旅行プランの提案
旅行業界にとって、時間とお金に余裕があるDINKs層は子どものスケジュールに縛られないため、オフシーズンを狙った高品質な旅行を提案できます。
夫婦二人で海外や地方、短期リトリートまでDINKsは旅行頻度も高めの層です。静かで上質な滞在時間を過ごせる美術館やワイナリー、グランピングなど、没入できる非日常との相性が良好です。
保険・金融業界:資産運用できる商品の提案
世帯単位で資産運用を考える傾向が強く、共働き・子なし前提のライフプラン設計に対応した金融商品や保険設計の需要が高まっています。
子どもの教育費は不要ですがその分、老後の生活資金や介護への備えに対する意識が高いことが特徴です。
専門的な知識を持つファイナンシャルプランナーが、夫婦二人のライフプランに寄り添い、長期的な信頼関係を築くことで、他の金融機関との差別化につながるでしょう。
まとめ
DINKsは高品質なモノ・サービスを選択する傾向があることから、今後マーケティングを強化したいと考える担当者も多いでしょう。
マーケティングを立案する際には、DINKsの目線に立ち、本当に求めるもの(インサイト)に気づくことが重要です。
マクロミルではDINKsに対するアンケートを実施するなどリアルなデータ収集や分析を行うことが可能です。
データを用いたマーケティングにご興味をお持ちの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
マクロミルへのお問い合わせはこちらから>