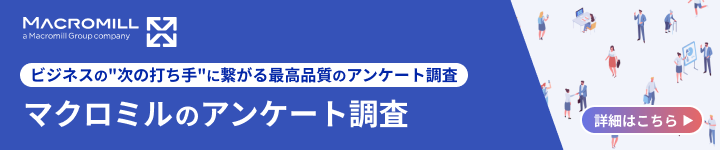アンケート調査を行う際、最適なサンプル数を選定することは重要です。必要なサンプル数を適切に計算することで、正確で信頼性の高いデータを得られます。この記事では、サンプル数の決め方や、計算方法について解説します。ぜひ参考にしてください。
参考:アンケート調査とは?種類や手順・進め方、ポイント、活用事例などを解説
- 「サンプル数」と「サンプルサイズ」の違いとは
- サンプル数を決めるポイント
- 回収サンプル数の決め方
- アンケートの有効回答率を向上させるポイント
- 必要サンプル数の計算方法
- アンケート調査で回収するサンプル数を確認する方法
- まとめ
「サンプル数」と「サンプルサイズ」の違いとは
サンプル数とサンプルサイズは異なる概念であり、よく混同されます。サンプル数は調査で収集するデータの総数を指し、サンプルサイズは1回のデータ収集で選ばれる1つの群の大きさを意味します。これらの違いを理解することで、調査をよりスムーズに進められます。
サンプル数を決めるポイント
サンプル数を決定する際には、誤差を考慮することが必要です。以下のポイントについて解説します。
誤差を理解する
アンケート調査において誤差は避けられない要素であり、誤差が大きくなると調査結果の信頼性が低下します。調査の信頼性を保つためには、サンプルサイズを適切に設定し、誤差を最小限に抑えることが大切です。
誤差5%でネットリサーチに必要なサンプル数を検討する
許容誤差が5%の場合は、400サンプルが目安です。なお、サンプルサイズを2倍にした際は、誤差が半分になるわけではないため、注意が必要です。
分析セグメントを考慮に入れる
サンプル数を決める際、特定のセグメントごとに十分なデータの収集が重要です。この分析は、対象をどのセグメントまで細分化するのかを考慮して、サンプルサイズを決定する方法です。ネットリサーチでは、セグメントの設定が結果に大きく影響を与える可能性があります。
回収サンプル数の決め方
必要なサンプルサイズを回収するためには、調査目的や信頼度を考慮することが必要です。回収サンプルサイズをどう決定するかについて解説します。
許容誤差の決定
誤差範囲がどれくらい許容できるかの決定は、サンプルサイズを決める際に非常に重要です。たとえば、誤差5%の場合、回答者の意見が±5%の範囲に収まると予測されます。調査の精度に応じて許容誤差を決めましょう。
信頼度の決定
信頼度は、調査結果が誤差範囲内で収まる確率を示します。信頼度95%であれば、同じ調査を100回実施した場合、そのうち95回は誤差範囲内で結果が一致することを意味します。信頼度95%以上が求められ、基準を満たすことで、調査結果の信頼性が高まるでしょう。
回答比率の確認
回答比率とは、調査対象者に対する実際に回答した人の割合です。事前に回答比率がわかっていればそのデータを活用し、わからない場合は50%を仮定して計算します。回答比率を確認することで、調査結果の精度を予測でき、次の調査計画にも役立ちます。
必要回収サンプル数の確認
調査目的に合わせて、回答比率や誤差を設定し、必要なサンプルサイズを見積もりましょう。サンプルサイズが不足すると、調査結果の信頼性が低くなる可能性があります。必要な回収サンプル数を事前に見積もることで、無駄のない調査設計が可能です。
信頼性のある最低限の回収サンプル数
信頼性のある調査結果を得るためには、最低限必要な回収サンプルサイズの確保が重要です。具体的なサンプルサイズについて解説します。
50サンプル
50サンプルの回収で得られる結果は、大まかな市場の把握には十分です。標本誤差約15%で、概算的な市場理解には適していますが、精度の高い分析には不十分といえるでしょう。迅速な結果が必要な場合や、精度を犠牲にしても速さを重視する場面には適しています。
100サンプル
100サンプルを回収することで、標本誤差約10%に抑え、比較的信頼性の高い結果を得られます。コストと精度のバランスを取る場合に適しています。
400サンプル
400サンプルを回収することで、標本誤差5%で、精度の高い調査結果が得られます。経営判断に基づく重要な意思決定に必要なデータを収集する際に推奨されます。
アンケートの有効回答率を向上させるポイント
アンケートの有効回答率を向上させるためには、いくつかのポイントがあります。主な5つのポイントを解説します。
アンケート回答者が負担を感じない内容にする
アンケートの回答者が負担に感じないようにするためには、設問数をできるだけ少なくし、回答時間を10分以内に収めることが重要です。選択肢を増やしすぎず、シンプルでわかりやすい質問を心がけましょう。自由回答やマトリクス形式の質問は避け、回答者にストレスを与えない工夫により回答率が上がります。
アンケートを回答しやすい形式や媒体にする
回答者が普段使用している媒体やデバイスの選択が不可欠です。スマートフォンで簡単に回答できるオンラインアンケートの採用で、回答のハードルを下げ、多くの回答を得られます。ターゲット層に適したプラットフォームの選択も有効です。
アンケート回答しやすいタイミングや時間帯で実施する
アンケートの回答率を向上させるためには、回答者が回答しやすいタイミングや時間帯を選びます。イベントやセミナーの直後にアンケートを実施すると、参加者の記憶が新鮮なため回答率が向上します。ターゲットの属性に応じて最適な時間帯を選ぶことで、効率的な回収が可能です。
アンケート回答のモチベーションを高める
回答者のモチベーションは、インセンティブを提供することで高められます。たとえば、デジタルギフトを用意することで、回答に対する意欲が高まるでしょう。ファンやコア顧客は、回答が会報を公式サイトに掲載するなど、目に見える形として残るインセンティブが好まれます。回答者にメリットを明確に伝えることで、前向きに回答してもらえる環境が整います。
アンケート回答者の不安を取り除く
アンケートに対して不安や警戒心を抱く回答者も少なくありません。アンケートの目的や実施する企業をはっきりと示し、個人情報の取り扱いについても丁寧な説明の実施が必要です。回答にかかる時間の目安を提示し、回答者が安心して参加できるような配慮があると、回答者の不安が和らぎます。
必要サンプル数の計算方法
アンケートの必要サンプル数を計算するためには、有効回答率の計算が不可欠です。有効回答率は、「(回収済有効回答数÷配布済のアンケートの数)×100」という計算式で求められます。たとえば、8,500件のアンケートを配布し4,000人から有効回答を得た場合の計算式は、「(4,000÷8,500)×100=47%」となります。
有効回答率を算出する際には、記載漏れや不適切な回答を除いた「有効回答数」に基づいて計算しましょう。信頼性の高いデータを得るためには、十分な回答数の回収が必要です。必要サンプル数を決めるときは、誤差範囲や信頼度を考慮し、適切なサンプルサイズの設定が求められます。
アンケート調査で回収するサンプル数を確認する方法
アンケート調査で必要なサンプルサイズを回収できるかどうかの確認は、調査の成功において重要です。調査対象者が広範囲であれば問題なく回収できますが、特定の職種やサービスの認知者など、対象が限られている場合は、回収が難しくなることもあります。この場合は、大規模なモニターを保有しているネットリサーチ企業への依頼がおすすめです。調査を円滑に進めるためにも、あらかじめ回収できるサンプルサイズを把握し計画的に進めましょう。
まとめ
アンケート調査のサンプル数を決定する際は、誤差や信頼度を適切に考慮することが重要です。目標とする誤差範囲に応じて必要なサンプル数を設定しましょう。信頼性の高いデータを得るための計算方法を理解し、調査結果の精度向上が求められます。
マクロミルは、マーケティングリサーチとデジタルマーケティングリサーチを駆使して、消費者インサイトを提供します。自社データと顧客データを組み合わせたデータ活用の支援や広告配信、CRMを含むマーケティング施策全般のサポートを行い、企業のマーケティング活動をトータルで支援します。アンケート調査の担当者は、ぜひお気軽にお問い合わせください。