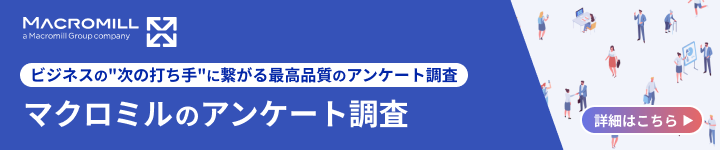アンケート調査票は、お客様の声を確実に集める「羅針盤」のような存在です。ただし、その設計方法ひとつで、得られる情報の質は天と地ほどの差が生まれてしまいます。本記事では、初心者でも実践できる調査票の作り方から、プロも使うテクニックまで分かりやすく解説します。
参考:アンケート調査とは?種類や手順・進め方、ポイント、活用事例などを解説
アンケート調査票とは?
アンケート調査票とは、調査対象者から必要な情報を収集するために体系的に設計された質問群のことです。定量・定性データの収集に活用します。
アンケート調査票の役割
アンケート調査票は、企業や研究機関が市場動向や消費者ニーズを把握するために使用するツールです。定量的なデータ収集だけでなく、自由回答形式を用いることで定性的な意見も収集できます。また、統一された質問項目により、多数の回答者から一貫性のあるデータを効率的に集められる利点があります。
調査票の設計が重要な理由
適切な調査票設計は、信頼性の高いデータ収集の基盤となります。回答者の理解度を高め、回答のしやすさを確保することで、回収率と回答精度の向上が期待できます。さらに、分析段階での作業効率を改善し、的確な結果解釈へとつながっていくでしょう。一方で、不適切な設計をしてしまうと、回答者への負担増加やバイアスが生じ、調査結果の信頼性が大きく損なわれてしまいます。
アンケート調査票の作り方における7つの手順
アンケート調査票の作成は、目的に応じた適切な設問設計が不可欠です。効果的な調査を実施するために、以下の手順に従って作成を進めていきましょう。
1. 調査の狙いを設定
調査の目的を明確にすることが、アンケート調査の設計の第一歩です。何を知りたいのか、どのような課題を解決したいのかを具体的に定義します。調査目的が曖昧だと、必要な情報が得られず、的確な分析ができなくなる可能性があるでしょう。目的に沿った質問項目を設定することで、回答者の負担を最小限に抑えながら、必要なデータを効率的に収集できます。
2. 必要な情報を洗い出し設問化
調査目的を達成するために必要な情報を洗い出し、具体的な質問項目へと落とし込みます。この段階では、1つの質問ではなるべく1つの内容だけを尋ねることを徹底し、複数の内容を詰め込まないようにします。また、回答者が迷わず答えられるよう、専門用語や曖昧な表現は避け、誰もが理解できる平易な言葉を選ぶことが大切です。
3. 回答形式の選定と設計
質問の内容に応じて、適切な回答形式を選択しましょう。主な回答形式には以下があります。
| 回答形式 | 特徴 | 適する場面 |
|---|---|---|
| 選択式 | 回答が容易、集計が簡単 | 定量的なデータ収集 |
| 評価尺度 | 程度や満足度の測定に適する | 意見や態度の測定 |
| 自由記述 | 詳細な意見が得られる | 具体的な改善点の把握 |
回答形式は、データの分析のしやすさと回答者の負担を考慮して選定します。特に、スマートフォンでの回答を考慮した設計が重要です。
4. 設問項目の取捨選択と絞り込み
アンケート調査の精度を高めるためには、設問項目を適切に選択し絞り込むことが必要です。調査の目的に直接関係のない質問は除外し、本当に必要な項目だけを残すようにします。回答者の負担を考慮して、回答時間が5分を超えないよう設問数を調整することが最も望ましいです。
質問の重要度を見極め、「もし1つしか聞けないとしたら、何を知りたいか」という視点で優先順位をつけましょう。
5. 質問の流れと配置を決定
質問の配置は、回答の質に大きく影響します。基本的な流れとして、簡単で答えやすい質問から始め、徐々に具体的な質問へと進めていきます。
各セクションの冒頭には、話題の転換を示す短い説明文を入れることで、回答者が自然に質問の流れを理解できるようになるでしょう。また、関連する質問はグループ化し、論理的なつながりを持たせることで、回答者の思考の流れを妨げないよう配慮します。
6. 設問文の表現を見直し
設問文は、明確で簡潔な表現を心がけます。専門用語や略語は避け、誰もが理解できる平易な言葉を使用しましょう。特に、二重否定や「のみ」「たった」などの不明確な限定表現は使用を控えます。また、「~と思いませんか?」のような誘導的な表現も避け、中立的な問いかけを心がけましょう。
7. プレテストと本番実施
本番実施前に、少数の回答者を対象としたプレテストを行うことが重要です。プレテストでは、質問の理解しやすさ、回答のしやすさ、所要時間などを確認します。特に以下の点に注意を払います。
- 確認項目
- チェックポイント
- 質問の明確さ
- 誤解を招く表現がないか
- 回答選択肢
- 全ての可能性をカバーしているか
- 所要時間
- 回答者の負担が適切か
プレテストで発見された問題点は修正し、本番を実施しましょう。
アンケート設問設計のコツ
効果的なアンケート調査を実施するには、設問設計が極めて大切です。回答者の負担を最小限に抑えながら、必要な情報を確実に収集できる設計が求められます。
適切な量に絞られた設問構成
アンケートの設問数は回答率と品質に大きく影響します。一般的に10〜15問程度が理想的とされ、回答時間は5〜10分以内に収めることをおすすめします。1つの設問では1つの内容のみを問い、回答選択肢も必要最小限に抑えましょう。設問を精査し、調査目的に直接関係のない質問は思い切って削除することで、より質の高い回答を得られます。
明確で理解しやすい質問表現
質問文は中学生でも理解できるレベルの平易な表現を心がけましょう。専門用語や業界用語は可能な限り避け、必要な場合は注釈をつけます。また、「よく」「たまに」といった曖昧な表現は具体的な頻度や数値で示すことが重要です。二重否定や長文は避け、質問の意図が一目で分かる簡潔な文章を心がけましょう。
誘導的でない中立的な問いかけ
回答者の本音を引き出すためには、中立的な立場からの質問が不可欠です。「この商品の優れている点」といった誘導的な表現は避け、「この商品の特徴」のように価値判断を含まない表現を使用します。また、質問文に回答のヒントとなる情報を含めないよう注意し、回答者の自由な意見を引き出せる工夫が必要です。
効果的な質問の順序設計
質問の順序は、回答のしやすさと回答精度に大きく影響します。一般的な質問から具体的な質問へ、簡単な質問から難しい質問へと段階的に進めていきましょう。関連する質問はグループ化し、回答者の基本情報などの設問は最後に配置します。また、重要な質問は回答者の集中力が高い序盤から中盤に配置することをおすすめします。
アンケート調査票作成時の注意点
アンケート調査票の作成では、回答者の視点に立った適切な設計が不可欠です。正確なデータを収集するために、以下の点に注意して作成しましょう。
設問文の表現・書き方のポイント
設問文は「いつ」「どこで」「何を」「どのように」といった具体的な表現で問いかけましょう。例えば「商品の使用頻度」ではなく「過去1か月間に、自宅でこの商品を使用した回数」のように具体化します。また、回答者の記憶が鮮明な「直近の経験」について質問することで、より正確なデータが得られます。質問の意図が明確になるよう、必要に応じて具体例を示すことも効果的です。
選択肢の設定ポイント
選択肢の数が多すぎると回答者が迷ってしまうため、5〜7個に収めることをおすすめします。例えば満足度を問う場合、「とても満足」「やや満足」「どちらでもない」「やや不満」「とても不満」の5段階が分かりやすい設定でしょう。さらに、選択肢の並び順は、ポジティブからネガティブ、もしくはその逆など、一貫性のある順序で配置することで回答のしやすさが向上します。
有効回答数を増やすための工夫
回答率を高めるには、アンケートの冒頭で目的と意義を明確に説明し、回答結果の活用方法も具体的に示すことが効果的です。また、回答所要時間を明示し、進捗バーを表示することで完了までの見通しを持ってもらいます。さらに、スマートフォン対応を徹底し、いつでもどこでも回答できる環境を整えることで、回答率の向上が期待できるでしょう。
アンケート調査ならマクロミル
アンケート調査を成功させるには、豊富な経験と専門知識を持つ会社に依頼することをおすすめします。マクロミルには、全国360万人以上の回答者データベースがあり、お客様の目的に合わせた調査が可能です。調査の進め方についても、経験豊富なスタッフが親身になってアドバイスを致します。
- アンケートの作り方から結果の見方まで、分かりやすくサポート
- 信頼できる回答者からの正確なデータ収集
- 結果をグラフや表で見やすく表示できる便利なツール提供
初めてアンケート調査を行う人でも安心して依頼できる環境が整っているため、確実な成果につながりやすいでしょう。
まとめ
良いアンケート調査を実施するためには、回答者の立場に立った質問作りが大切です。以下のポイントを意識して作成しましょう。
- 質問は10問から15問程度に抑え、答える時間は5分から10分以内に
- 難しい言葉は使わず、誰にでも分かる表現を選ぶ
- 回答を誘導するような質問は避け、公平な聞き方を心がける
- 答える選択肢は5つから7つ程度に絞り、迷わずに選べるようにする
また、本番の調査の前に必ずプレテストを行い、問題がないか確認することが重要です。これらの注意点を押さえることで、商品開発やサービス改善に役立つ、信頼性の高い調査結果を得ることができます。
アンケート調査における課題は、「マクロミル」までご相談ください。アンケートの作り方からアンケート結果の集計・分析まで、貴社のマーケティング活動をサポートいたします。