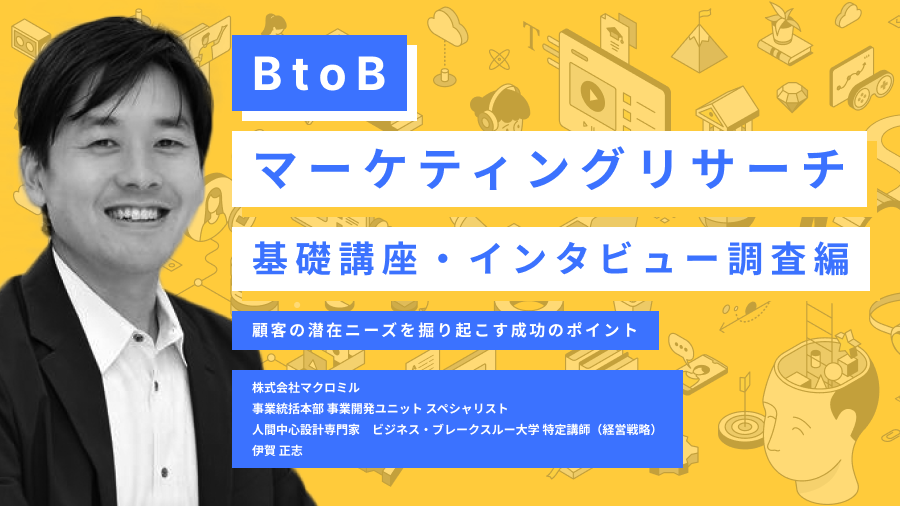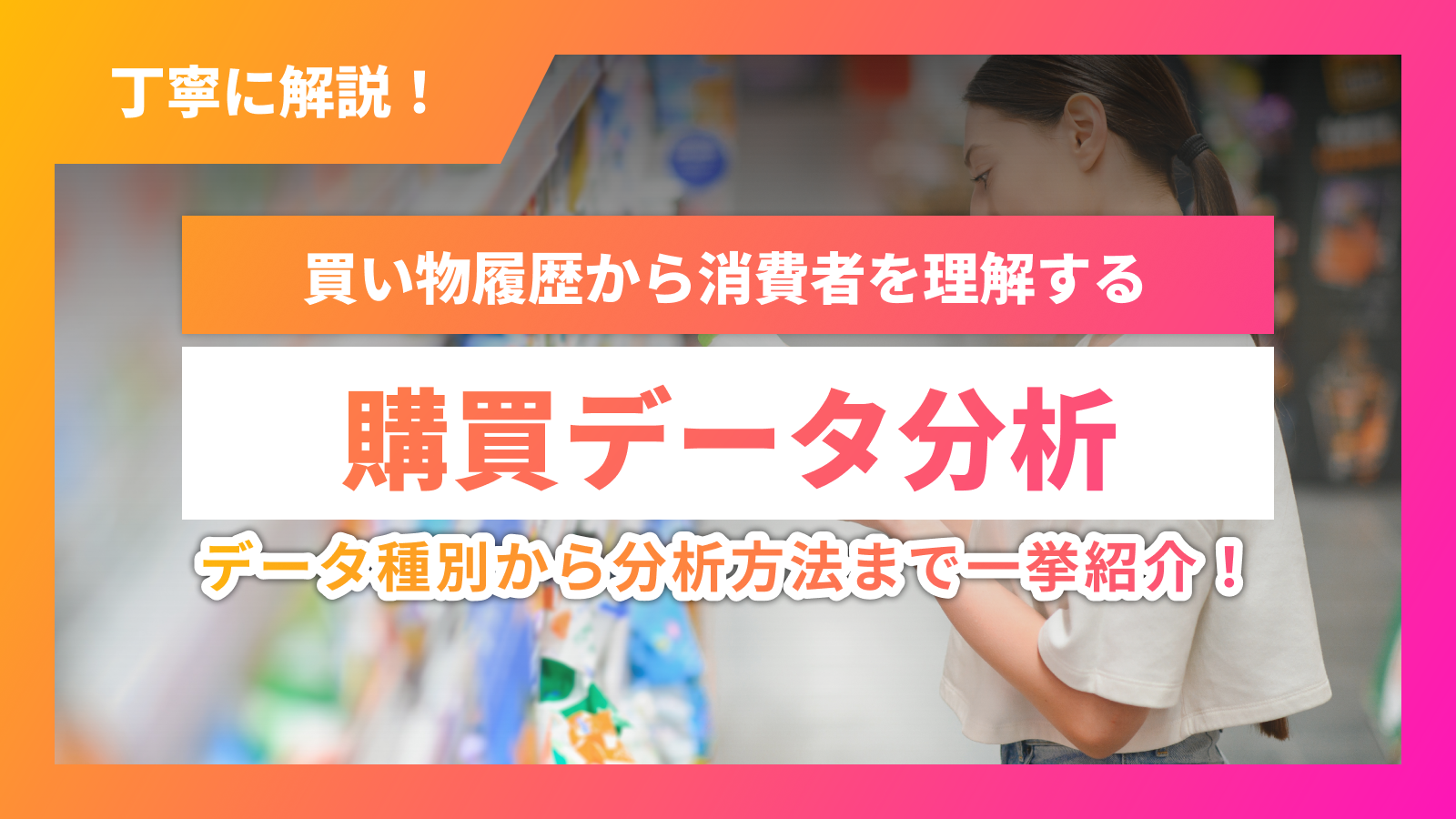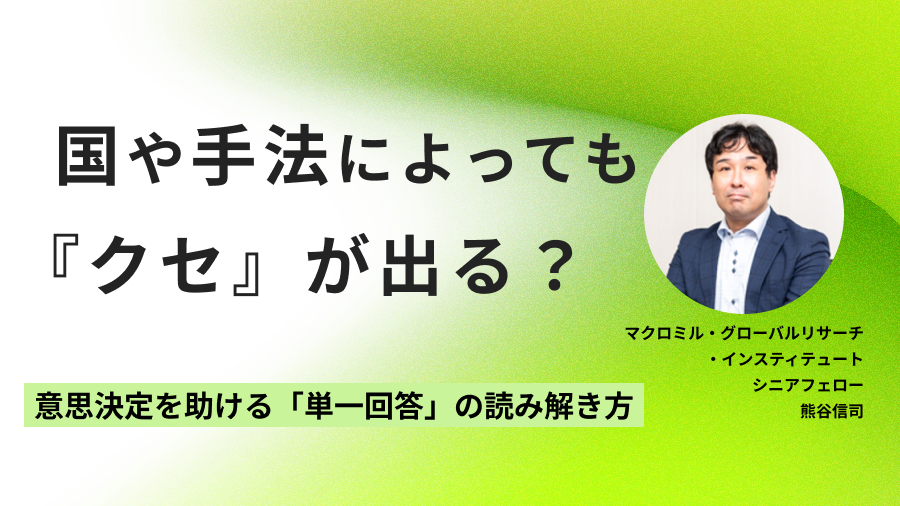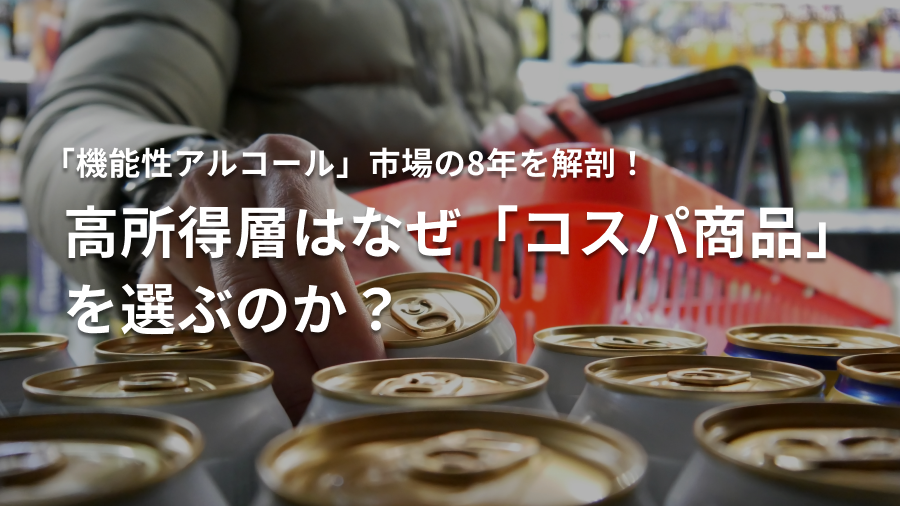WEBマーケティングとは?SEOやSNS広告、オウンドメディアなど多様な活用してWEB上でのプレゼンスを最大化する戦術
公開日 :2023/4/17(月)
最終更新日:2025/4/11(金)
WEBマーケティングとは、インターネット上のさまざまなチャネルやプラットフォームを活用して、商品・サービスの認知拡大、顧客獲得、ブランドロイヤリティの向上などを狙う総合的なマーケティング手法を指します。具体的には、ウェブサイトやSNS広告、検索エンジン最適化(SEO)や検索連動型広告(SEM)、メールマガジン、オウンドメディア運営、EFO(Entry Form Optimization)、ステップメールなど、多岐にわたる取り組みが含まれます。
- WEBマーケティングの基本概念
- WEBマーケティングの歴史と背景
- WEBマーケティングを構成する主要チャネル
- WEBマーケティングにおけるデータドリブン志向とPDCAサイクルの重要性
- WEBマーケティングにおけるUI/UX改善とEFOの連携
- SNS広告とコミュニティ運営の相乗効果
- WEBマーケティングの課題とリスク
- DX/AI時代のWEBマーケティングの展望
- まとめ
WEBマーケティングの基本概念
インターネットが普及していなかった時代には、主にテレビCMや新聞・雑誌広告といったマスメディアを中心にマーケティングが行われてきました(マスマーケティング)。しかし、消費者が情報をオンラインで収集するようになったことで、企業側もWEB上での接点(タッチポイント)をいかに最適化し、広告費を有効に使うかがカギとなりました。Cookie規制やプライバシー保護が進む一方で、SNS広告やファーストパーティデータの活用によってPDCAサイクルを回し、短期間でCVR(コンバージョン率)を高める戦略が多くの企業で実践されています。
また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の流れが加速する中、WEBマーケティングは単なる広告手法の一つにとどまらず、企業全体のデジタル施策を推進する要として機能しています。コミュニティとの対話や大規模言語モデル(LLM)の活用など、最新技術を取り入れた高度なマーケティングが可能になった一方で、Cookie規制の影響によるターゲティング広告の制限といった課題も生じており、柔軟な戦略設計が求められています。
WEBマーケティングの歴史と背景
インターネットが普及し始めた1990年代後半から2000年代にかけて、企業がウェブサイトを開設し、電子メールを用いたメールマガジンを配信するなどの施策が登場しました。次第に検索エンジンが台頭し、SEO(Search Engine Optimization)で自然検索の上位表示を狙う手法や、検索連動型広告(リスティング広告)で狙ったキーワードに広告を表示する戦略が一般化。これらがWEBマーケティングの基礎を築いたといえます。
その後、SNS(ソーシャルメディア)が世界的に普及すると、ユーザー同士の口コミ(WOM)やコミュニティを通じた拡散が大きな影響を持つようになり、企業がSNS広告やインフルエンサーマーケティングを積極的に取り入れる動きが広がりました。Cookieベースの行動ターゲティング広告や再ターゲティング(リターゲティング)も多くの企業で導入され、広告費を比較的効率的に使える手法として人気を集めました。
しかし近年、プライバシー保護の観点からCookie規制が強化され、サードパーティデータに頼るターゲティング広告が難しくなる傾向があります。この結果、ファーストパーティデータの収集・活用やコミュニティ運営を主体とした施策が見直され、短いPDCAサイクルでUI/UXを最適化しながら、ステップメールやEFOなどのテクニックを駆使してCVRを向上させる企業が増えてきました。DX推進によって社内外のデジタルリソースが統合されることで、より高度なデータドリブンなマーケティングが可能となる一方、広告費の上昇やコモディティ化などの課題もあり、競争がさらに激化しているのが現状といえます。
WEBマーケティングを構成する主要チャネル
WEBマーケティングは多数のチャネルを組み合わせて成果を上げるのが一般的で、具体的には以下のような手段があります。
1. SEO(検索エンジン最適化)
ウェブサイトのコンテンツや構造を整え、自然検索で上位表示を狙う施策。クローラーやアルゴリズムを意識したキーワード設計が必要だが、長期的な流入確保に寄与し、ブランドロイヤリティやコミュニティ形成にもつながりやすい。
2. 検索連動型広告(SEM)
検索エンジン上でユーザーが入力するキーワードに連動して広告を表示する施策。クリック課金(CPC)で広告費が変動しやすいが、適切なキーワードとクリエイティブを運用すればCVRを高める可能性がある。
3. SNSマーケティング
Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeなどのSNS広告やコミュニティ運営を通じてユーザーとの直接的な対話を生み出す。口コミ(WOM)が拡散しやすく、Cookie規制後のファーストパーティデータ重視にも適した手法。
4. オウンドメディア運営
自社ブログや情報サイト、動画チャンネルなどを構築し、継続的にコンテンツを発信。定期的な更新とSEO対策により、検索結果からの自然流入を狙いながら、ステップメールによるリードナーチャリングが可能になる。
5. メールマーケティング
EFOを意識したフォームでリードを取得し、ステップメールなどでコミュニケーションを深める。広告費をかけずにファーストパーティデータを蓄積しつつユーザーと長期的な関係を築ける。
これらのチャネルを適切に連携させることで、Cookie規制下でもブランドロイヤリティを育てつつ、広告費の効率化を実現するのが理想的なWEBマーケティングの形といえるでしょう。
WEBマーケティングにおけるデータドリブン志向とPDCAサイクルの重要性
WEBマーケティングでは、ユーザーの行動ログやコミュニティでの反応など、デジタル環境に残る多様なデータを収集し、施策の効果を定量化して改善を続けるデータドリブンアプローチが広く採用されています。具体的には週次・月次でのABテストやメルマガ開封率の測定、離脱率とコンバージョン率(CVR)の変化をトラッキングし、課題箇所を特定して修正を行うのが典型的な手順です。
さらに、ファーストパーティデータを活用すれば、より正確なユーザー像や行動パターンを把握できるため、Cookie規制の影響が相対的に少なくなるメリットがあります。MAツール(Marketing Automation)を用いれば、各段階(認知・興味・比較・購入・リピートなど)で適切なメッセージやステップメールをユーザーに届けることが可能です。
このPDCAサイクルを迅速かつ継続的に回すことで、WEBマーケティングで生じがちなコモディティ化を防ぎ、オリジナリティのある施策を打ち出せます。たとえば新しいコミュニティ活用の企画やユーザーエンゲージメント施策を試し、数字の変化を見ながら微調整を加えていけば、広告費を抑えつつ確実にブランドロイヤリティを醸成できるというわけです。
WEBマーケティングにおけるUI/UX改善とEFOの連携
WEBマーケティングで得られたリードやサイト訪問者を具体的な成果(CVR向上)につなげるには、UI/UXの改善が欠かせません。特に、EFO(Entry Form Optimization)はユーザーが入力フォームで諦めて離脱してしまう率(離脱率)を下げるための最適化手法であり、フォーム項目の見直しや入力補助、ステップ分割などが代表的な取り組みです。
ユーザーがSNS広告や検索連動型広告からLP(ランディングページ)に流入してきても、フォームが煩雑だったり、説明が不十分だったりすると、せっかく獲得したクリックを成果に結びつけられません。Cookie規制が進む中、高い広告費を投下して集客している場合は特に、EFOやUI改善を徹底することが投資効率を上げる重要なファクターです。
また、ブランドロイヤリティを高めるには、購入手続き後や登録プロセス後のステップメールなどで、ユーザーに満足感や継続利用のモチベーションを与えることも大切です。これらの細かな施策が総合的に効いてくるからこそ、WEBマーケティングで安定的に成果を出すことが可能になります。PDCAサイクルとデプスインタビューやフォーカスグループといった定性調査を組み合わせれば、よりユーザーの立場に立ったUI/UX改善が実現しやすくなるでしょう。
SNS広告とコミュニティ運営の相乗効果
SNS広告の強みは、ターゲティング精度やユーザーとの直接的なコミュニケーションにあります。しかし、Cookie規制で行動ターゲティングが制限されつつある今、コミュニティ運営によるファーストパーティデータの獲得や口コミ(WOM)の広がりが一層重要になってきています。広告費を多大に使わなくとも、コミュニティやブランドの世界観に共感したユーザーが自主的に情報を発信する循環ができれば、大規模言語モデル(LLM)などのAI分析を活かしながら効果的にPDCAを回せる可能性があります。
たとえば、ある企業がSNS上にコミュニティを作り、新商品についてユーザーから率直なフィードバックを収集するとしましょう。ここで得た意見を反映してUI/UXや告知ページを改良し、SNS広告のクリエイティブを更新すれば、次の広告出稿時にはCVRが上がり、結果的に広告費が最適化されるというシナリオが考えられます。オフラインとの連動(オムニチャネル)で顧客体験を強化すれば、さらにブランドロイヤリティを深めることも可能です。
WEBマーケティングの課題とリスク
WEBマーケティングは幅広いがゆえに、運用上の課題やリスクも存在します。Cookie規制の影響でサードパーティデータを使った詳細なターゲティングが難しくなれば、広告運用者がパフォーマンスを把握しづらくなる面があります。また、SNS広告は短期的に効果を見せやすい反面、クリックやCVRばかりを追求するとブランドイメージを損ねるクリエイティブや手法に走りがちなリスクも。
さらに、PDCAサイクルを回す際に、定量データを過度に重視して定性面—たとえばユーザーの深層心理やコミュニティの声など—を無視すると、根本的な課題を見落としてしまい、コモディティ化につながる恐れがあります。AIエージェントやABテストといった手法はあくまでツールであり、ユーザーに対する洞察力を持つ人間の視点が欠かせません。
セキュリティやプライバシーも留意すべきポイントです。ファーストパーティデータを扱う場合でも、個人情報の適切な取り扱いや法令遵守が求められます。ひとたび情報漏洩が起きればブランドロイヤリティに深刻な打撃を受けるため、企業としてのガバナンス体制を整えてから積極的にWEBマーケティング施策を展開することが重要です。
DX/AI時代のWEBマーケティングの展望
今後、WEBマーケティングはDX(デジタルトランスフォーメーション)の潮流とますます融合していくと考えられます。企業はオンラインだけでなく、オフラインのデータも含めて顧客行動を総合的に把握し、MAツールや大規模言語モデルを活用して、ユーザーニーズに合わせたサービスや商品を提案する道筋が自然とできるでしょう。SNS広告や検索連動型広告に頼るだけでなく、コミュニティ主導でブランドロイヤリティを築き、ファーストパーティデータをもとにUI/UXを改良してCVRを向上させる循環が理想的なモデルとして浸透していくはずです。
一方で、Cookie規制のさらなる強化やプライバシー関連法の改正により、サードパーティデータの活用範囲が狭まるリスクは引き続き存在します。その中で、自社のユーザー登録データやログイン情報を上手に活用し、広告費を無駄なく効率化しながらユーザーとの絆を深める必要が高まるでしょう。いかにバランスよく実施できるかが成功の鍵となり、マルチモーダル解析やAIエージェントが補完的に支える構図が想定されます。
まとめ
WEBマーケティング(Web Marketing)とは、インターネットを軸とした多様なチャネルと手法を使い、ユーザーとの接点を最適化してビジネス目標を達成するマーケティング戦略です。SEOやSEM、SNS広告、オウンドメディア、メールマーケティングなど、複数の施策を組み合わせ、Cookie規制や広告費の上昇にも適切に対応しながらPDCAサイクルを回すことで、CVRやブランドロイヤリティを高める効果が期待されます。
ファーストパーティデータやコミュニティを活用すれば、ユーザーの根本的なニーズを把握しやすく、オムニチャネルやDXといった次世代の施策ともスムーズに統合可能です。広告費を必要以上に使わずとも、ステップメールやEFOで離脱率を下げる工夫が可能となり、ユーザー心理に寄り添ったブランド構築が行えます。
今後は、AIエージェントや大規模言語モデルなどの先端技術と、定性・定量両面でのマーケティングリサーチを組み合わせる形で、WEBマーケティングがさらに進化していくと考えられます。市場環境が変化し続ける中、適切なデータ分析と柔軟な施策展開を行う「データドリブン・コミュニティ主導」のマインドセットが、WEBマーケティング成功の決定打となるでしょう。