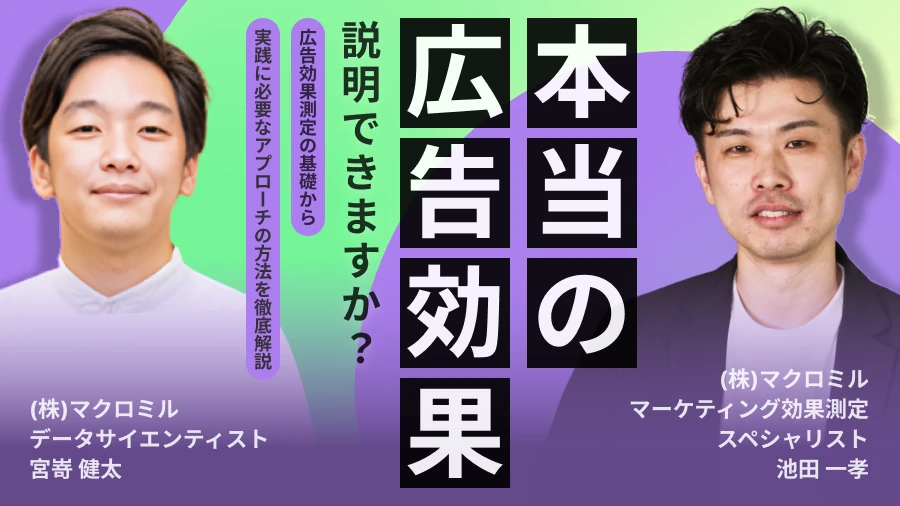シーズ(Seeds)とは?開発起点から生まれるアイデアとマーケティングへの活かし方
- タグ
- マーケティング
マーケティングや製品開発において、「ニーズ(Needs)」と並んでよく話題に上がる概念が「シーズ(Seeds)」です。ニーズが「顧客や市場が求める課題解決や要求」を指すのに対して、シーズは「企業や研究機関が保有する技術やアイデア、ノウハウ」を出発点とした製品開発アプローチを示します。
新しいビジネスを立ち上げたり、既存製品を高度化したりする際には、顧客ニーズを徹底的に調べる「ニーズ起点」の方法がよく取り上げられますが、一方で企業内部に眠る先進技術や独自ノウハウをベースに発想を広げる「シーズ起点」も有力な戦略となり得ます。実際には、ニーズとシーズを両輪として捉え、相互に結びつけることが大切です。
本稿では、シーズ(Seeds)とは何かを明確にしながら、その概念がどのように生まれ、どのようなプロセスで市場価値へと変換されるのかを掘り下げます。あわせて、マーケティング領域におけるシーズ活用のメリットや留意点、実践事例も紹介します。企業が持つ未開拓の技術やアイデアをどう商品化や事業化につなげるかを考えるうえで、シーズという視点を再確認してみましょう。
- シーズ(Seeds)とは何か
- シーズが重視される背景
- シーズとマーケティングの関係
- シーズを発掘・活用するプロセス
- シーズ起点のマーケティング戦略
- シーズを活かした成功事例
- シーズ起点の注意点と克服方法
- 今後の展望とまとめ
シーズ(Seeds)とは何か
シーズの基本定義
シーズとは、企業や研究者が保有する技術、アイデア、ノウハウなどの商品化・事業化の“種”となる要素のことを指します。研究開発で生まれた新素材や、新しいアルゴリズム、独創的な製法・製造技術、あるいは発明特許の形で存在しているものなど、多種多様な形態が考えられます。
この「シーズ起点」の考え方では、まだ顧客のニーズが顕在化していない段階、あるいは競合企業ですら気づいていない段階から新しいアイデアを商品化する余地がある点が特徴です。すでに手持ちの技術をいかに応用し、市場に価値を提供するかが開発・マーケティングの大きなテーマとなります。
ニーズ志向との対比
マーケティングと開発の現場では、ニーズとシーズは両極端のアプローチとして語られがちです。ニーズとは「市場が抱える課題や欲求」を指し、顧客リサーチや市場調査に基づいて商品設計を進めるのがニーズ志向と呼ばれます。一方でシーズは「企業や研究者の側にすでに存在する技術や素材」を軸に、まだ見えていない新市場を作り出そうとするのがシーズ志向です。
ニーズ志向は顧客に確実に刺さりやすい反面、斬新性やブレイクスルーを生む余地が限られる場合があります。一方でシーズ志向は、大きなイノベーションを起こす可能性がある一方、顧客不在になってしまうと「使える技術だが需要がない」という状況に陥るリスクもあります。現代では、この二つの志向をいかにバランス良く融合させるかがポイントです。
シーズが重視される背景
イノベーション創出と技術開発の進化
近年、世界的に競争が激化する市場では、差別化の手段として“イノベーション”がキーワードになっています。新しい製品カテゴリーや、全く新たなソリューションを切り開くためには、既存製品の延長線上にない発想が必要です。そこでは、まだ認知されていない新技術やアイデア(シーズ)が大きな可能性を秘めているといえます。
例えば、AIやIoT、バイオテクノロジー、ロボット工学など、先端テクノロジー領域の発展スピードは非常に速く、企業や研究所が続々と新たなシーズを生み出しています。これらがうまく市場ニーズと結びつけば、一気にブームとなるケースもあり得ます。
研究機関やベンチャー企業との連携
シーズは、大企業内の研究所だけでなく、大学や公的研究機関、そしてベンチャー企業など、多様なプレイヤーから生まれます。特に近年はオープンイノベーションの流れが強まっており、大企業がスタートアップのシーズを取り込んで新事業を開発したり、大学発ベンチャーが研究シーズを事業化するなど、連携モデルが活発化しています。
こうした背景から、シーズをいかに早期に見つけ出し、協業を通じて形にするかが、企業競争力の大きな要因になりつつあります。
シーズとマーケティングの関係
発明から製品化への橋渡し
シーズを保有していても、市場が求める形に加工しなければ事業としては成立しません。ここでマーケティングが果たす役割は「技術やアイデアに、どのような価値やコンセプトを与え、顧客に届けるか」をデザインすることです。
優れた技術がありながら「どの顧客層にアピールするか」「どう使ってもらうか」のイメージが欠けていると、技術が活かされないまま終わる可能性が高くなります。マーケティングが橋渡し役となり、シーズを「分かりやすいユーザーベネフィット」に転換する作業が重要です。
ニーズとのバランスをどう取るか
シーズだけで突っ走ると、実際の需要が無い「自己満足的な発明」に陥るリスクがあります。一方、ニーズに寄りすぎると大きな飛躍や新市場の創出が難しく、価格競争に巻き込まれがちでもあります。したがって、理想はシーズを起点としつつも、市場のニーズや潜在的な課題をうまく取り込むハイブリッドなアプローチです。
たとえば、市場のフィードバックを見ながら技術の適用範囲を調整したり、潜在ニーズをあえて先回りして顕在化させるマーケティング手法を用いるなど、両面からのアプローチが求められます。
シーズを発掘・活用するプロセス
社内リソースの把握と知的資産の棚卸し
まずは自社が持つ技術や特許、ノウハウを洗い出すステップから始まります。大企業の場合、研究所や各事業部に分散している技術資産が多く、「実はA事業部の技術をB事業部に応用できる」などのシナジーを見逃しているケースが少なくありません。
こうした社内リソースを可視化し、どの技術がどのような強みを持つのかを明確にすることで、新製品コンセプトのヒントを得やすくなります。知的資産経営の観点からは、特許や商標の棚卸しを行い、保有技術の市場価値やライセンス活用の可能性を定期的に見直すことも大切です。
オープンイノベーションと共同開発
社内に限らず、他企業や大学・研究機関、ベンチャーとの連携を活用する方法も増えています。オープンイノベーション・プログラムを通じてスタートアップの新技術(シーズ)を取り入れたり、大学の研究成果を共同研究で実用化に近づけたりといった取り組みも一般的になりました。
こうした外部リソースの活用には、シーズを提供する側と受け取る側の利害調整や、知的財産の管理など、注意すべきポイントがありますが、うまく機能すれば大きな飛躍につながる可能性があります。
シーズ起点のマーケティング戦略
製品コンセプト設計のポイント
シーズをもとに製品コンセプトを作る際には、まず技術やアイデアのコアバリューが何なのかを明確にします。それが「従来品の10倍の速度で処理できる」「特殊な環境下で性能を維持できる」など、具体的な数値や特徴で示せるとわかりやすいでしょう。
次に、それらの技術的な強みをどの顧客層・産業領域に最も有効に適用できるのかを考えます。場合によっては複数の用途が想定されるため、用途ごとの市場規模や参入障壁、競合状況を比較し、最も成功確率の高い市場からアプローチする方法もあります。
ターゲット市場の選定と価値提案
技術の汎用性が高い場合、あれもこれもと手を広げがちですが、最初は絞り込みが重要です。ターゲットを具体化し、「何が彼らの課題なのか」「その課題をシーズによってどう解決できるのか」を価値提案としてまとめます。
この段階でニーズとの整合を図りながら、「シーズがどのようにニーズを満たすか」をストーリーとして構築することが重要です。ブランドメッセージや製品名、デザインなども、価値提案を伝えるうえで欠かせない要素となるでしょう。
投資回収とリスクヘッジ
シーズ型の開発は、ニーズ型に比べてリスクが高いとされます。なぜなら、市場が存在するかどうか不確実な段階で投資を行うためです。そこで、開発プロセスをフェーズごとに区切って投資額をコントロールし、技術検証(PoC)や試作段階の評価を得ながら次のステップへ進むアプローチがよく用いられます。
また、特定市場における成功例を作ってから横展開を図るなど、段階的な成長戦略を描くことでリスクを分散しやすくなります。
シーズを活かした成功事例
大手メーカーの技術シーズ活用
たとえば、自動車部品メーカーが保有していた高精度センサー技術を、家庭向けの防犯デバイスに転用し、新規事業として立ち上げたケースなどが挙げられます。当初は自動車部品の製造ラインで使用するセンサーでしたが、その高感度が家庭用防犯カメラのモーション検知に活かせるという発想で事業領域を広げ、成功を収めた例です。
スタートアップ企業の革新事例
AIやブロックチェーンなど、先端技術をシーズにしたスタートアップも数多く見られます。特に海外では大学発ベンチャーが基礎研究の段階から投資を受け、市場と連携しながら事業化するモデルが盛んです。日本でも近年はユニコーン企業が増えてきており、技術シーズを強みに急成長を遂げるスタートアップが注目されています。
産学連携で生まれた新規ビジネス
大学の研究室で開発された新素材が、大手化学メーカーと共同で製品化される事例も珍しくありません。大学の研究者が特許を保持し、企業がその特許をライセンス契約で獲得して量産体制を整える、または共同研究プロジェクトを立ち上げて技術を成熟させる。こうした形で実用レベルまで育て上げられたシーズが、数年後に市場を席巻する例もあります。
シーズ起点の注意点と克服方法
技術主導になり過ぎるリスク
シーズ型の落とし穴として最も多いのが、「素晴らしい技術だが誰も買わない」という状況です。技術的には画期的でも、ユーザーにとっては「そこまで高性能は必要ない」「価格に見合わない」など、購入動機が生まれないケースがよくあります。
これを防ぐには、開発初期からマーケティング担当やユーザー調査の専門家を巻き込み、コンセプトや価格帯、使用シーンを丁寧に検証することが欠かせません。最低限の市場リサーチを行いながら、徐々に技術を磨き込むアプローチが理想です。
市場投入時の時間軸と育成策
研究開発から実際に商品化するまでには、長い時間がかかることが多いのもシーズ型アプローチの特徴です。企業内部の承認プロセスが長かったり、技術的課題の克服に思わぬ時間がかかったりと、スピード感が求められる現代では難しさも伴います。
また、いざ市場投入しても、ユーザーがその価値を理解するまで時間がかかる場合があります。そうした場合、教育的なプロモーションやトライアルの提供、業界標準を取るためのアライアンスなど、長期的視野で市場を育てる施策が必要です。
ユーザー目線の不足を補う仕組み
シーズを大きく育てるには、「ユーザビリティを高める」「インタフェースを直観的にする」「最終的にどう使われるか」を常に想定する力が欠かせません。
例えば、アジャイル開発やデザイン思考の手法を取り入れ、試作品をユーザーに早期にテストしてもらったり、フィードバックを小刻みに反映することで、“研究室の中だけで完結する技術”の状況を避けやすくなります。社内だけで考えすぎず、外部のユーザーや有識者を巻き込むことが大切です。
今後の展望とまとめ
シーズ(Seeds)は、イノベーション創出の原動力ともいえる概念です。企業が既に持っている技術や研究成果、または新しく生まれつつあるアイデアを起点に、新しい市場価値を生み出す可能性を秘めています。しかし、その可能性を本当に開花させるには、市場・顧客(ニーズ)と結びつけるマーケティングの発想が欠かせません。
シーズ志向は大きなブレイクスルーをもたらす一方で、開発期間や投資リスクが高いという性質も持ち合わせます。そのため、リスクマネジメントや段階的な検証プロセスをしっかり設計する必要があります。さらに、技術を理解し、それをユーザーに伝えるためのデザイン力やコミュニケーション力が求められるでしょう。
近年はAIやブロックチェーン、量子コンピュータなど、今後社会を大きく変えうる先端テクノロジーが数多く誕生しています。それらのシーズを取り込みながら新市場を創出する取り組みは、まさに国家レベルや企業連携を巻き込んだ壮大な動きになっています。オープンイノベーションや産学連携の加速により、シーズ志向のビジネスチャンスはますます拡大するでしょう。
シーズを起点としたアプローチは、ニーズ主導にはない独特の強みとリスクを併せ持ちます。自社の開発現場や研究リソースを見直し、どのようなシーズが眠っているのかを把握し、それをマーケティング戦略と結びつけることで、新規事業やイノベーションの種を育てていく可能性が広がるはずです。
マーケティングを行う立場の方は、社内外の研究者やエンジニアと協力しながら、技術の持つポテンシャルを引き出すことに挑戦してみてください。小さな種が、市場を大きく変える一大事業へと成長するかもしれません。