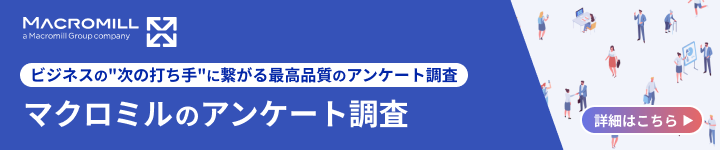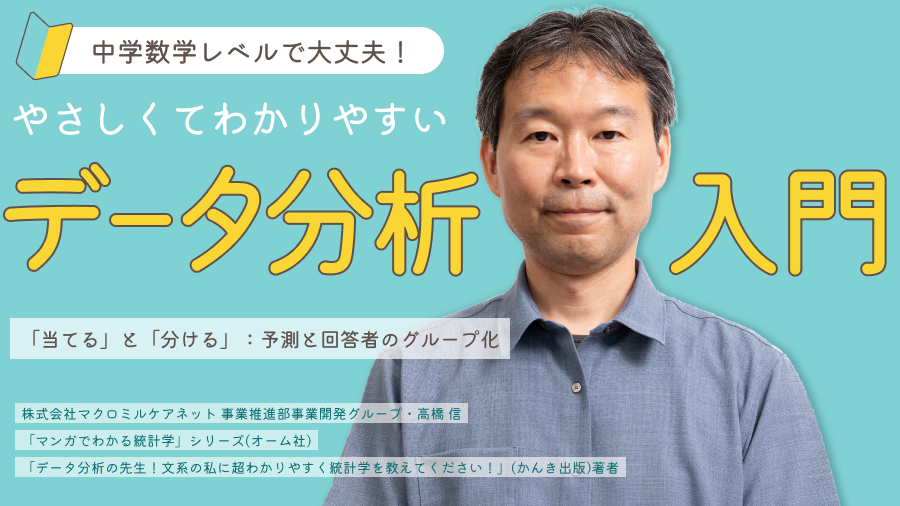2023年7月24日、世界中のユーザーに親しまれてきたTwitterは、突如として「X」へと名称変更されました。ただのブランドリニューアルにとどまらず、ロゴ・カラー・機能・理念すべてが刷新され、かつての“つぶやきの場”とは異なる姿を見せはじめています。
本コラムでは、TwitterからXへの移行にともなう変化を、次の観点から網羅的に解説します。
- 名称・ロゴ・ブランドポジションの変更
- 投稿仕様やUIの変化
- 広告・収益化モデルの変化
- アルゴリズムと可視性のルール変更
- “公共空間”としての役割の変化
- 今後の展望とマーケティング活用の示唆
単なるロゴ変更ではなく、“機能の脱Twitter化”とでも呼ぶべき本質的な再設計が進んでいる今、Xはどこへ向かおうとしているのか――その全体像を探ります。
- なぜTwitterは「X」になったのか?
- ビジュアルと名称の変更:ロゴ・色・用語の再定義
- ポストTwitter化:投稿・UI・機能はどう変わったか
- 広告・収益化モデルの刷新とその影響
- アルゴリズムの変化と“見られ方”のルール再編
- 社会インフラとしてのTwitterは失われたのか?
- 今後の展望とマーケティング施策への示唆
- まとめ:Xは「ポストSNS」の扉を開くのか
なぜTwitterは「X」になったのか?
背景①:イーロン・マスクによる買収と構想
Twitterの「X化」は、2022年のイーロン・マスク氏による買収劇に端を発します。彼は当初から「X.com」という名の“万能アプリ(Everything App)”構想を描いており、Twitterはその実現に向けた土台と位置づけられていました。
買収後のブランド変更は、短期的な炎上を招いた一方で、長期的には“決済・動画・検索・AI統合”など、マルチ機能プラットフォームへの進化を見据えたステップでもあります。
背景②:ユーザー数と広告収益の鈍化
FacebookやInstagramなどのSNSに比べ、Twitterの成長は頭打ちになっていたとも言われています。TikTokのような強力な動画体験も提供できておらず、広告主離れも進行していました。ブランド刷新は、この停滞状況を打開する一手でもあったのです。
ビジュアルと名称の変更:ロゴ・色・用語の再定義
2023年7月、Twitterは突如としてロゴを青い鳥から「X」のモノクロアイコンへと切り替えました。以降、名称や用語も次々と変更され、かつての“Twitter文化”に親しんでいたユーザーにとって大きな揺さぶりとなりました。
ロゴの刷新とブランドカラーの脱“青”化
かつての青い鳥のアイコンは、「つぶやき」「軽やかさ」「オープンさ」を象徴していました。それに対して、新しい「X」ロゴは、シンプルで力強く、どこか中立的かつ抽象的な印象を与えます。
背景色もブラックが基調となり、UI全体の色調がダークトーンに統一されることで、まるで“メディア”や“マーケットプレイス”のような佇まいに変わりました。
用語の変更:「ツイート」はもう存在しない
名称変更にともない、「ツイート」「リツイート」「フォロー」といった固有の語彙も次々と置き換えられました。
| 旧用語 | 新名称 |
|---|---|
| ツイート(Tweet) | ポスト(Post) |
| リツイート(Retweet) | リポスト(Repost) |
| いいね(Like) | 同名だがハートマークは存続 |
| フォロー(Follow) | 一部「サブスクライブ」へ置換中 |
こうした名称変更は、旧Twitterの文化的・歴史的アイデンティティから距離を取ると同時に、「X」という新たな方向性への再構築の一環と考えられます。
URLやドメインの変化
Webブラウザ上では「x.com」へのリダイレクトも実施され、完全に「twitter.com」から切り替わっています。外部共有やリンク挿入の際、混乱を招くケースもあるため、ビジネス運用者には注意が必要です。
ポストTwitter化:投稿・UI・機能はどう変わったか
ブランドだけでなく、サービスそのものも“Twitter的”な性質から離れはじめています。
文字制限の緩和と有料ユーザーの優遇
- 無料ユーザーの投稿上限:従来の280文字を維持
- 有料ユーザー(X Premium):最大25,000文字(段階的に拡大)
- 画像、動画、リンク、ハッシュタグなどの挿入機能も強化
長文投稿が可能になったことで、ミニブログからロングフォームメディアへのシフトが進行中です。
UIの再構成:リーチより収益を意識した設計へ
- フォローよりも“おすすめ”中心のタイムライン
- アナリティクス強化による“インプレッション型報酬”への誘導
- クリエイター向け収益管理機能の導入(再生数連動の報酬モデル)
従来の「つながり」よりも「届ける/稼ぐ」ための構造に変化しています。
投稿の“発見性”に影響する変化
- ハッシュタグの影響力は限定的に
- 検索結果はログイン前と後で異なり、アルゴリズム依存度が増加
- フォロワーよりも“おすすめ表示ロジック”の影響が大きくなった
インフルエンサーやビジネスアカウントにとっては、「どうすれば届くか」を読み解く難易度が上がっています。
広告・収益化モデルの刷新とその影響
TwitterからXへの転換は、収益構造にも大きな変化をもたらしました。従来の広告中心モデルから、投稿者側にも収益が還元される“クリエイター経済”型へと軸足を移しつつあります。
Premiumプランの導入とサブスクリプションの拡大
X Premium(旧Twitter Blue)は、月額課金によって以下の特典を得られる仕組みです。
- 投稿上限の拡大(文字数/動画尺)
- 優先表示(アルゴリズム上の可視性向上)
- 投稿ごとの収益分配(インプレッションに応じた広告収益)
- 認証バッジ(青いチェックマーク)の付与
従来は“企業広告で稼ぐ場”だったTwitterが、“投稿者が直接稼げる場”としてリポジションされていることがわかります。
企業広告主の“離反”と再接近
イーロン・マスク氏の買収直後、多くの大手広告主が政治的・倫理的理由から出稿を停止しました。しかし、2024年に入り、ターゲティング精度や分析機能が改善されたことを受け、一部で再開の動きも見られます。
とはいえ、「ユーザー投稿に広告が表示される=ブランドリスク」と捉える企業も多く、完全復帰には至っていません。
小規模クリエイターの活性化と“荒稼ぎ構造”の課題
- 投稿1件で数十万円を稼ぐユーザーも出現
- 一方で“扇情的”“分断的”投稿のほうが高収益になりやすい傾向も
プラットフォームとしての“健全性と利益性”のバランスが、今後の成長にとって重要な課題となっています。
アルゴリズムの変化と“見られ方”のルール再編
Xのもうひとつの大きな変化は、「何が表示されるか」「誰に届くか」を決定づけるアルゴリズムの仕組みです。以下に、ポストTwitter時代の“見られ方”の特徴を整理します。
「おすすめ」中心のタイムライン
- 従来の“フォロー中心”ではなく、興味・関心ベースで投稿が表示される構造に変化
- AIによる文脈解析が反映されるため、フォロワー数と表示回数の相関が薄くなった
投稿の“収益性”が可視性に影響
- インプレッション数が収益に直結するため、「拡散されやすい=稼げる=優先表示されやすい」という循環が生まれている
- 誇張・炎上・極論がアルゴリズム的に“優遇”されやすくなり、構造的に過激化が促進される懸念もある
外部リンク付き投稿の減衰傾向
- 外部リンクを含む投稿(特にニュース/YouTube/他SNS)は“露出が抑えられる”傾向にあると一部報告あり
- X内にとどまる投稿(画像・動画・長文テキスト)のほうがリーチが安定しやすい
これらの傾向を踏まえ、Xを情報発信チャネルとして活用するには「アルゴリズムの癖」を読み解くリテラシーが不可欠です。
社会インフラとしてのTwitterは失われたのか?
かつてのTwitterは、災害時のライフライン、政治報道の速報源、企業や自治体の公式発信チャネルなど、社会インフラ的な役割を果たしてきました。しかし、Xへの移行によって、こうした「信頼される情報空間」としての機能にも変化が起きています。
公共性と透明性の低下
Xでは「認証バッジ」が有料化されたことで、かつての“本人確認済みアカウント”という意味合いが希薄化しました。信頼性のある情報源とそうでないアカウントとの区別がつきにくくなった結果、以下のような現象が報告されています。
- フェイクニュースの拡散スピードが上昇
- 本物の自治体アカウントより、煽動的な投稿が先に表示される
- 通報や運営への問い合わせのハードルが上がった
アカウント凍結/制限の基準が不透明化
旧Twitterでは、ポリシーに基づいたガイドライン違反への対応が比較的明示されていましたが、Xでは凍結・表示制限のルールが非公開のまま変更されることもあり、批判が相次いでいます。
- ジャーナリストの投稿が“不可視化”された例
- アルゴリズムによる“シャドウバン”の疑いが増加
- 特定政治的言説への対応に一貫性が見られない
公共利用の“代替先”が模索されている
国連機関、公共放送、医療団体などがXからMastodonやThreads、公式Webサイトに発信の主軸を移す動きも加速しています。完全な代替には至っていませんが、X一強時代は明らかに終わりつつあります。
今後の展望とマーケティング施策への示唆
Xは今もなお“試行錯誤の最中”にあるプラットフォームです。現時点では方向性が定まりきっていないがゆえに、リスクと可能性の両面をはらんでいます。
「Everything App」構想は実現するのか
イーロン・マスク氏が掲げるXの最終形は、「SNS/決済/動画/AI/検索/マーケットプレイス」を統合した“万能アプリ”です。中国のWeChatが一例として挙げられますが、欧米および日本市場において同様の形が受け入れられるかは未知数です。
広告以外のマネタイズ手法の拡充
- Premium会員
- 収益分配(クリエイター報酬)
- 動画投稿の収益化
- オンライン決済との連携
こうしたマネタイズが安定すれば、プラットフォームとしての“再構築”は可能ですが、ユーザー体験を損なわずに収益を得る設計ができるかどうかが分水嶺です。
マーケティング活用の再設計が必要
Xはもはや「Twitter時代の延長」では使えません。たとえば以下のような変化が求められます。
- トレンド入り狙いから、AIに“見つけてもらう”投稿設計へ
- 拡散よりも“滞在時間”や“エンゲージメント”重視の内容設計
- 投稿単位ではなく、アカウント全体をメディアと捉えた戦略へ
また、リンク投稿のリーチ低下やハッシュタグ効果の変化を踏まえると、「X単体で完結する情報設計」が今後の基本になります。
まとめ:Xは「ポストSNS」の扉を開くのか
TwitterからXへの変化は、単なる名称やロゴの変更ではありません。それは、SNSという枠組みの再定義であり、“発信者の経済圏”を生み出そうとする設計思想の転換です。
ユーザーの声を短く届ける“公共広場”から、収益と拡張性を備えた“情報インフラ”へ
この転換は、ユーザーにとっても、企業にとっても、“発信の設計”そのものを見直すきっかけになります。
今後Xが「万能アプリ」として完成するのか、「一時の実験」で終わるのかはまだ不透明です。しかし確実なのは、「Twitter時代の常識は、もう通用しない」ということです。
過去の慣習ではなく、現在の文脈に応じた“使い方の再設計”が、これからのX活用の前提条件となるでしょう。