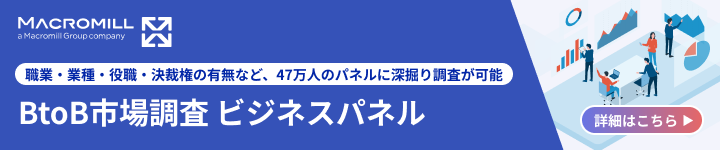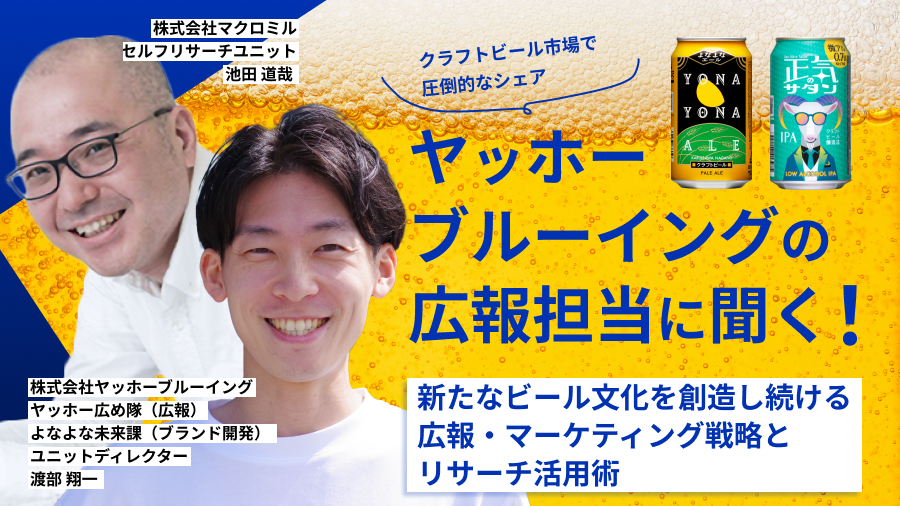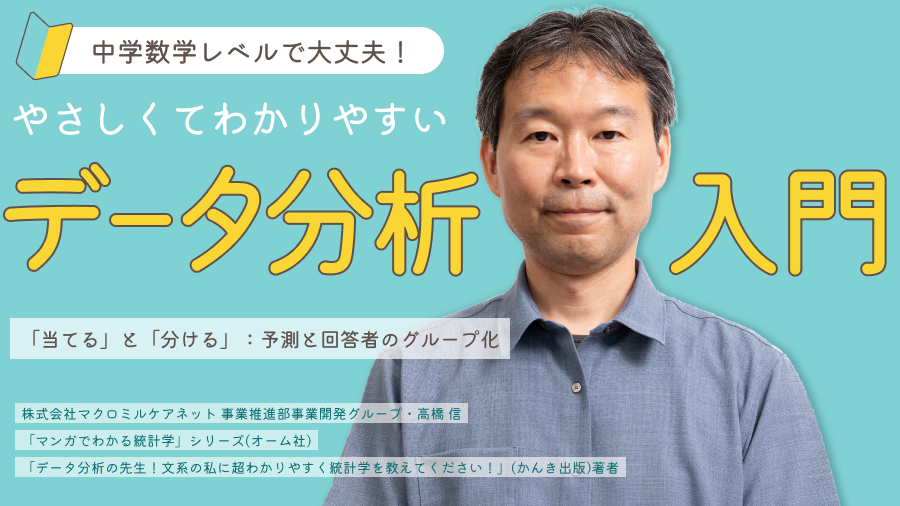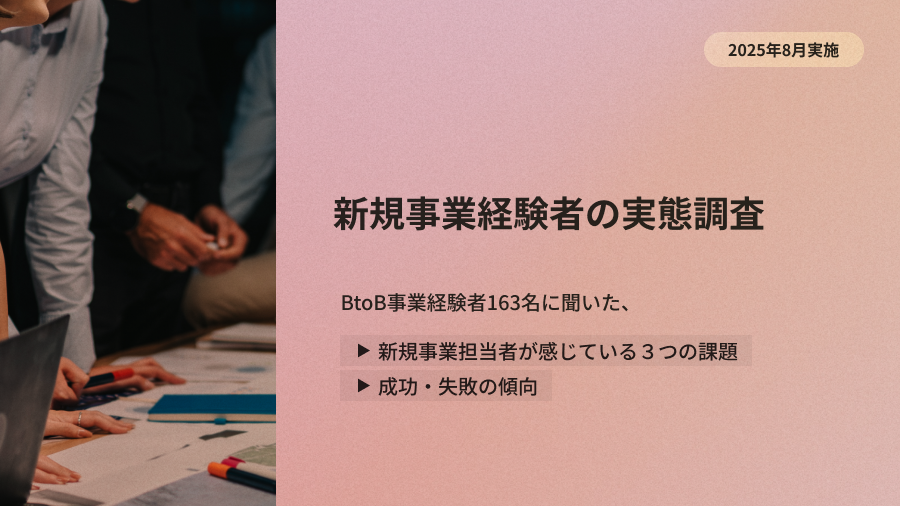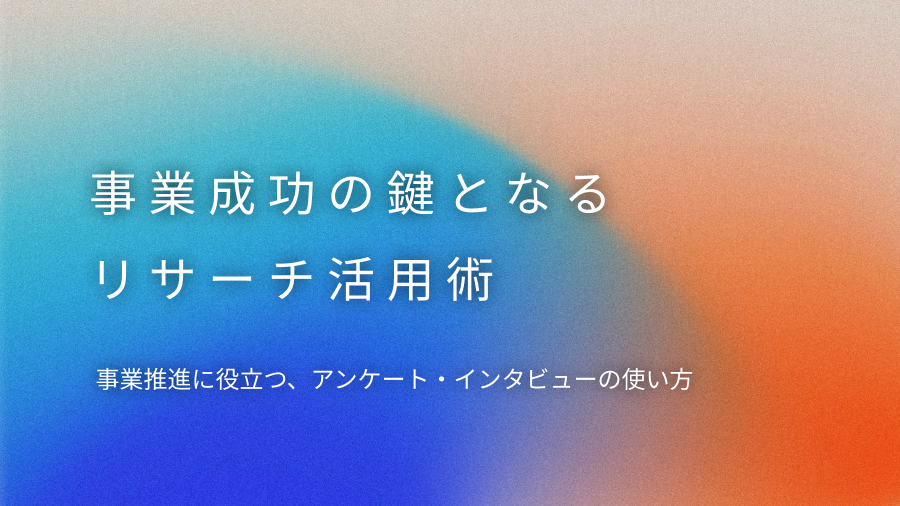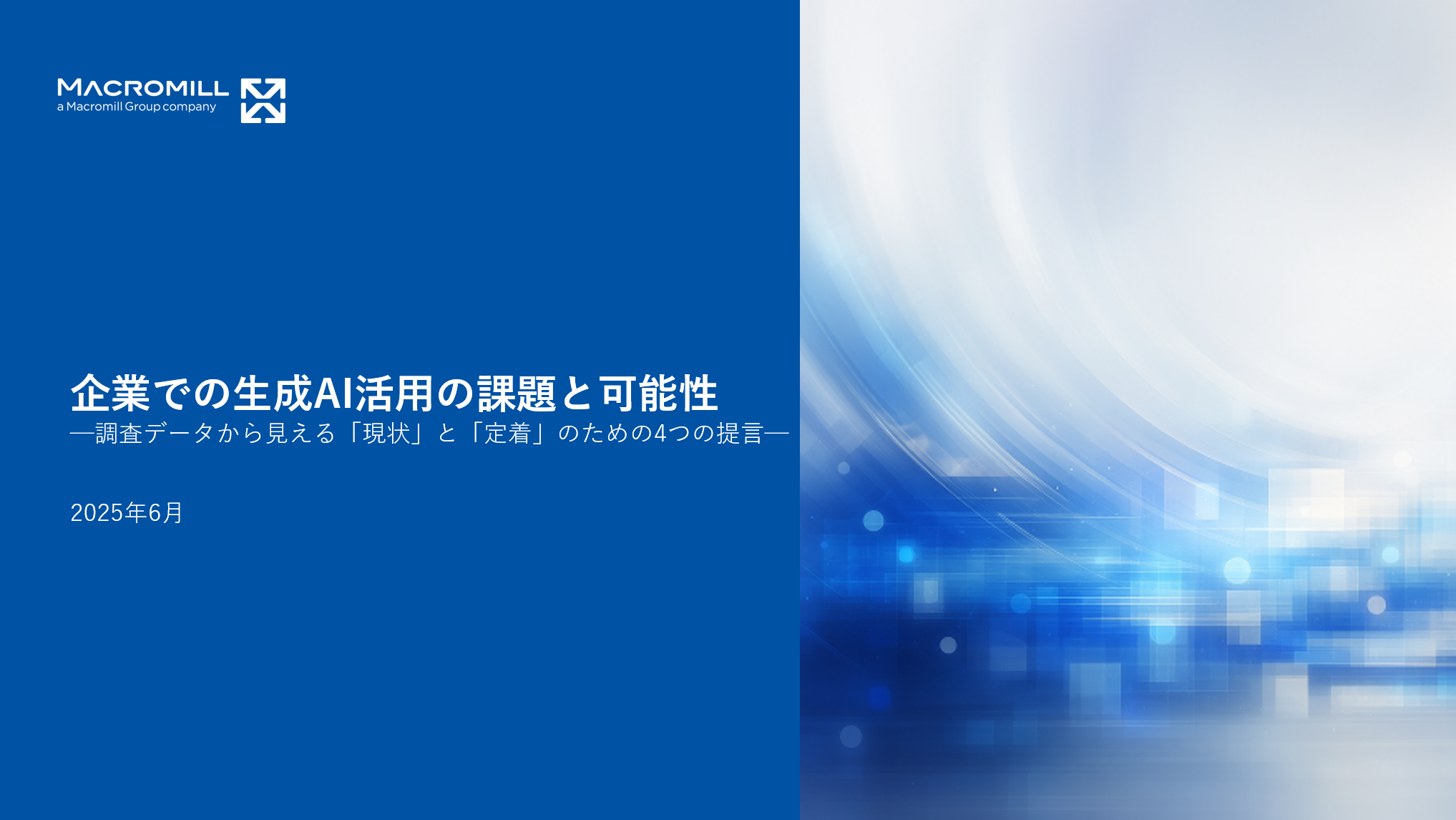あなたの会社には、こんな見込み顧客はいないでしょうか?
- ホワイトペーパーはダウンロードしたが、その後音沙汰がない
- セミナーに参加したが、商談にはつながっていない
- 過去に問い合わせがあったが、いまは動いていない
こうした「いますぐ顧客ではない」相手に対して、どのように関係を築き、購買意欲を高め、最終的に商談化へとつなげていくのか――その鍵を握るのが、ナーチャリング(Nurturing)です。
BtoBの購買プロセスは長期的かつ複雑で、顧客は製品を知ってから実際に導入するまでに数週間から数ヶ月、場合によっては年単位の検討を重ねます。つまり、いま売れなくても「将来売れるかもしれない」顧客との関係性をどう保ち、どう育てるかが、営業効率と売上に大きな影響を与えるのです。
本コラムでは、ナーチャリングの定義から、なぜ必要とされるのか、どのような手法があり、どんな企業が成果を出しているのかまでを、体系的に解説していきます。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- ナーチャリングの定義と目的
- なぜいまナーチャリングが重要なのか?
- ナーチャリングの3つの柱(タイミング・コンテンツ・パーソナライズ)
- 代表的な手法とツール活用(メール・セミナー・スコアリング・MA)
- 営業との連携で成果を最大化するために
- 成功事例:育成によって受注率が変わった企業の取り組み
- KPI設計と改善のポイント
- 今後の展望:AI、意図予測、長期リレーション構築
- まとめ:信頼の蓄積が未来の売上をつくる
ナーチャリングの定義と目的
ナーチャリングとは、「見込み顧客との関係性を継続的に構築し、購買意欲を高めていくマーケティング活動」のことを指します。直訳すれば「見込み客の育成」です。
重要なのは、ナーチャリングの対象が「すぐには買わない人」である点です。多くの企業が、今すぐ購入するホットリード(Hot Lead)ばかりを追いがちですが、実際にはほとんどの見込み顧客はまだ情報収集段階や課題認識段階にあります。
そのため、以下のような目的でナーチャリングが行われます:
- 検討フェーズを進めてもらう(情報提供によって課題を明確にする)
- 信頼関係を構築する(企業や製品に対する心理的ハードルを下げる)
- 競合との差別化ポイントを理解してもらう(比較検討の支援)
- 商談タイミングを見極める(スコアリングによりホット化の兆しを捉える)
つまり、ナーチャリングとは「顧客の“決断”を支援するプロセス」であり、それが結果的に営業の生産性を高める強力な武器となるのです。
なぜいまナーチャリングが重要なのか?
マーケティングや営業の現場では、「リードは取れているのに受注につながらない」という声がよく聞かれます。その背景には、顧客の購買行動の変化があります。
かつては、営業が情報提供の“起点”でした。製品の特徴や価格、事例などは営業担当者から聞くのが一般的だったため、企業側は「情報を持っている」だけで優位に立てました。
しかし現在では、インターネットで情報があふれ、顧客は“自分で調べてから”営業に会いに来ます。調査によれば、BtoBの購買行動のうち約60〜70%は、営業と接触する前にすでに進んでいると言われています。つまり、顧客は営業の前に、Webサイト、ホワイトペーパー、セミナー、SNSなどを通じて自分なりに答えを探しているのです。
このような変化の中で、営業だけに頼った「点のアプローチ」では成果が出にくくなっています。むしろ、「まだ買う気がない人と、どう関係を築き、信頼を積み上げていくか」が、最終的な受注率やLTVに大きく影響するのです。
ナーチャリングは“売り込み”ではありません。見込み客の検討行動に寄り添い、必要な情報を適切なタイミングで届ける「導きのマーケティング」なのです。
ナーチャリングの3つの柱(タイミング・コンテンツ・パーソナライズ)
ナーチャリングが成果につながるかどうかは、大きく3つの要素にかかっています。
1. タイミング:行動と関心の“いま”をとらえる
同じ顧客であっても、「どの段階にいるか」で届けるべき情報は変わります。課題認識段階では“課題の言語化”を促すような資料、比較検討段階では“自社の優位性”を示す事例や価格表、導入直前なら“ROIや稟議支援資料”が求められるでしょう。
そのためには、以下のような「行動トリガー」を活用することが有効です:
- 特定のページを複数回閲覧した
- メールを一定回数開封している
- 資料AからBへと移行している(検討ステージの上昇)
これらの“行動シグナル”に応じて、次の情報を設計することが成果につながります。
2. コンテンツ:検討の「問い」に応える設計
ナーチャリングにおけるコンテンツとは、「顧客の意思決定に伴走するガイド」です。ただし、“なんとなく作る”だけでは効果は期待できません。重要なのは「ステージ別設計」です。
- 潜在層向け:課題に気づかせる(例:業界動向レポート)
- 顕在層向け:選定判断を支える(例:製品比較表、導入事例)
- 稟議層向け:社内説明の支援(例:ROI資料、FAQ)
顧客は「読んだら次に何をすべきかわかる」コンテンツに価値を感じます。つまり、コンテンツは単なる“資料”ではなく、“導線”であるべきなのです。
3. パーソナライズ:セグメントに応じた体験設計
同じ業界の企業でも、企業規模や導入フェーズによって課題や関心は異なります。ナーチャリングでは、リードの属性(業種、職種、役職、検討度)に応じたセグメント分けと、それに基づいたパーソナライズが重要です。
たとえば、次のような設計が考えられます:
- 中小企業向けにはコスト削減を前面に
- 大企業には全社展開やセキュリティを重視した情報を
- 現場担当には操作性や導入支援に関する情報を
- 経営層には定量的成果(ROI、成功事例など)を
このような「相手の立場で最適な話をする」設計こそが、ナーチャリング成功の鍵なのです。
代表的な手法とツール活用(メール・セミナー・スコアリング・MA)
ナーチャリングを実行する際、どのような手段を使うかは企業のフェーズや業種によって異なります。ただし、代表的な手法には共通した“目的”があります。それは、「信頼を育みながら、購買意欲を高める接点を継続的につくること」です。ここでは、特にBtoB領域で多く活用されている4つの手法を紹介します。
① メールマーケティング
もっとも普及しているナーチャリング手法のひとつです。ホワイトペーパーやセミナーのダウンロード時に取得したアドレスに対して、段階的に情報提供を行う「ステップメール」や、行動に応じた「トリガーメール」などが活用されます。
ポイントは、「セールス色を出しすぎないこと」です。売り込みよりも、“あなたの課題に役立つ情報があります”というスタンスで、顧客の意思決定を支援することが成果につながります。
② ウェビナー・セミナー
BtoBでは、ウェビナーが「教育型ナーチャリング」の中心的手段として機能します。特に、検討初期にあるリードに対しては「学びの場」を提供することで、“課題に気づいてもらう”効果が期待できます。
また、セミナー終了後のアンケートや行動ログから、興味関心度を把握することもできるため、次の施策にもつなげやすいのが特徴です。
③ スコアリング
ナーチャリングが進んだリードが「どの程度ホット化しているか」を判断するための指標です。MA(マーケティングオートメーション)などのツールで、行動に応じて点数を付与し、スコアが一定に達したら営業へパスする――この設計があれば、営業は“温まった相手”に集中してアプローチできます。
例:
- 資料Aの閲覧 → +10点
- セミナー参加 → +20点
- 製品ページ3回以上閲覧 → +15点
- 価格ページ閲覧 → +25点
④ MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用
ナーチャリング施策を支える土台として、MAツールの活用は不可欠です。メール配信、スコアリング、セグメント別シナリオ設計、営業連携までを一元管理できることで、属人的な運用から脱却できます。
代表的なツール:
- Salesforce Pardot(Account Engagement)
- Marketo Engage
- HubSpot
- SATORI
- BowNow
営業との連携で成果を最大化するために
ナーチャリングが機能するかどうかは、「営業との連携」にかかっていると言っても過言ではありません。マーケティングが育てたリードが営業に“ちゃんと引き渡されていない”、あるいは“営業がナーチャリングの意味を理解していない”という状況では、せっかくの努力が水泡に帰してしまいます。
ここで重要なのは、「MQL(マーケティングクオリファイドリード)」と「SQL(セールスクオリファイドリード)」の定義です。どのような状態になったら営業に引き渡すのか、その基準を明文化し、部門間で合意しておく必要があります。
たとえば、
- MQLの定義:スコア80点以上かつ業種・職種がターゲット内
- SQLの定義:営業が接触後に商談化の可能性ありと判断したリード
また、以下のような“組織的な接続点”を設けると、よりスムーズな連携が可能になります。
- 月1回の営業・マーケ合同ミーティング
- 営業からのリード評価フィードバックをMAへ連携
- 商談化率のデータをもとにナーチャリングシナリオを改善
ナーチャリングとは「顧客との関係構築」だけでなく、「社内の信頼関係の構築」も求められる活動なのです。
成功事例:育成によって受注率が変わった企業の取り組み
事例①:SaaS企業A社 – スコアリングによる営業連携強化
A社では、リード獲得後に営業がすぐにコンタクトしていたが、成果につながらず、営業部門のリードへの信頼も低下していました。
そこでスコアリングを導入し、一定点数に達したリードのみを営業にパスする運用に変更。さらに、点数の高いリードには別途シナリオで“温める”コンテンツを配信。その結果、商談化率は15%から38%に上昇。営業の受注件数も前年比140%となり、部門間の信頼も改善しました。
事例②:IT企業B社 – セミナーを軸にしたステップメール施策
B社では月1回のウェビナーに集客した後、参加者に対して段階的に情報提供するステップメールを設計。初回は業界トレンド、2回目は事例、3回目は導入のメリットとROI、4回目で営業への相談を促す内容とし、開封率40%以上を維持。その結果、ウェビナー経由での受注率が2倍以上に。特に「自社から問い合わせをくれた」リードが増え、営業の工数削減にもつながりました。
KPI設計と改善のポイント
ナーチャリングの効果を可視化し、継続的に改善していくには、適切なKPIの設計が欠かせません。ただし、単に「メール開封率」や「資料DL数」だけを見ても、ナーチャリング全体の成果は評価できません。重要なのは、“商談化”や“受注”とのつながりを意識したKPI設計です。
代表的なKPI項目
- メール開封率/クリック率:コンテンツの訴求力の目安
- ナーチャリング中のMQL化率:温まり度合いの指標
- ナーチャリング経由の商談化率:営業成果への貢献度
- 商談あたりの営業接触回数:ナーチャリングによる工数削減効果
- LTV(顧客生涯価値):ナーチャリングから育った顧客の長期価値
たとえば、「ナーチャリングを経たリードの受注率が高い」「営業に渡した後の商談滞留率が下がった」といった数値が出ていれば、それはナーチャリングが機能している証拠です。
改善のアプローチ
改善のヒントは、数値だけでなく“行動ログ”にも隠れています。たとえば、メールは開かれているのにリンクがクリックされていないとしたら、タイトルと本文は響いているがCTAが弱い可能性があります。
また、スコアリング設計が適切かどうかを検証するために、「スコアが高い=本当に商談化しているか」を営業と一緒に振り返ることも有効です。
ナーチャリングのKPI設計は、営業との“共通言語”にもなります。数値を介して対話ができる仕組みこそが、マーケティングと営業の信頼をつなぐ橋渡しになるのです。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
今後の展望:AI、意図予測、長期リレーション構築
ナーチャリングは、これからますます進化していきます。とくに注目されているのは、「AIによるインテント予測」と「中長期的な信頼構築の戦略化」です。
AIとスコアリングの高度化
従来のスコアリングは、設定したルールに基づく“事前設計加点式”が一般的でした。しかし、AIを活用することで、「過去に受注したリードの行動パターン」や「失注したケースとの違い」などを学習し、“今後受注する確率が高いリード”を予測できるようになっています。
これにより、「誰に・いつ・何を」届けるかの精度が飛躍的に向上します。
関係性を“資産化”する考え方
また、ナーチャリングは短期施策ではなく、「関係性を積み上げるマーケティング資産」として捉え直す動きも広がっています。
たとえば、
- 1年前にDLしたリードが再びメールを開封し始めた
- ナーチャリングで得た情報が営業の提案時に活用された
- 顧客化した後も役立つ情報提供を継続し、アップセルへつながった
このように、ナーチャリングは「受注で終わる」のではなく、「顧客とのリレーションを深化させ、次の価値創出につなげる」戦略基盤になりつつあるのです。
まとめ:信頼の蓄積が未来の売上をつくる
ナーチャリングとは、ただ情報を送り続けることではありません。それは、見込み顧客の課題や関心に寄り添い、信頼を築き、意思決定の背中をそっと押す――そんな“丁寧な伴走”のマーケティングです。
- 今すぐ買わない人にも敬意を持って接する
- 検討段階に応じた適切な情報を届ける
- コンテンツは「読むもの」ではなく「動かすもの」として設計する
- 営業と共通KPIで語り合い、連携を深める
- 成果が出るまで続ける“戦略としての継続性”を持つ
信頼は、一朝一夕では生まれません。しかし、それが積み重なったとき、営業の受注率は上がり、顧客との関係は深化し、企業のブランドは“選ばれる理由”になります。ナーチャリングは、見えにくく、地味に思える活動かもしれません。でもそれは、未来の売上を着実に支える、BtoBマーケティングの“本丸”なのです。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル