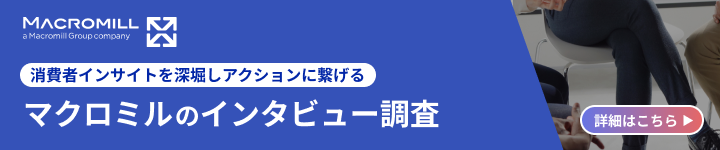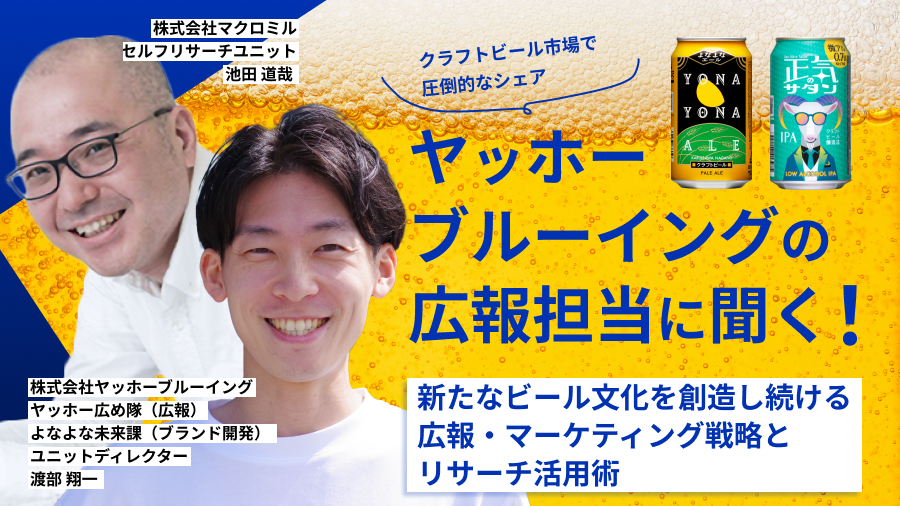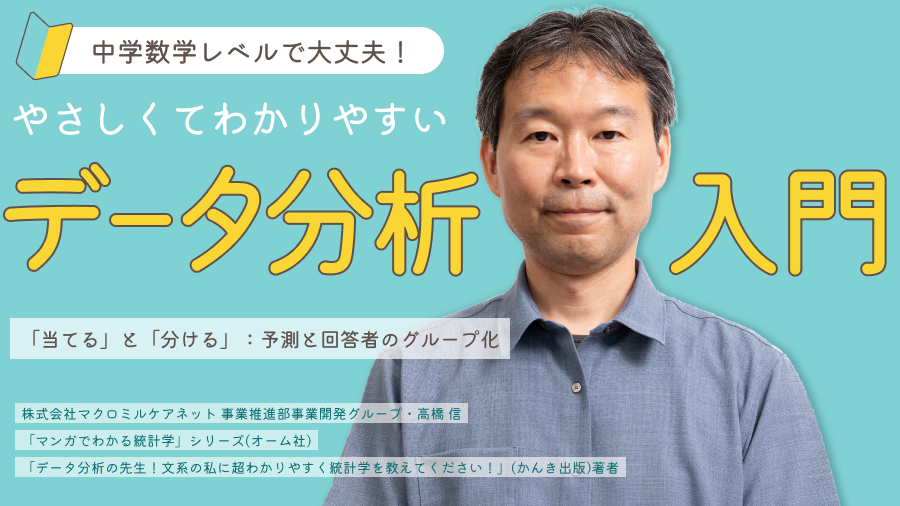定性調査とは?基本から定量調査との違いや比較・メリット・手法まで解説
公開日 :2023/4/20(木)
最終更新日:2025/3/7(金)
定性調査という言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容や手法を知らないという人は珍しくありません。この記事では定性調査の基本情報から手法、メリット・デメリット、成功のポイントなどを解説しています。定性調査に関わる可能性のある人は一通りの情報を得て、業務の参考にしてください。
定性調査の基本情報
概要や目的、定量調査との違いを解説します。
定性調査とは
定性調査とは、数値に表せない言葉や行動などの情報を調査することです。そのため、対象者の言葉や行動、インタビュアーが感じた仕草や印象などが調査対象となります。代表的なものとして複数人を対象とするグループインタビューや、1対1で行うデプスインタビューが挙げられますが、さまざまな実施方法があり、目的に合致する方法を選択することが重要です。
定性調査の目的
定性調査は、さまざまな情報を得ることが目的です。たとえば、商品・サービスの購入に至ったプロセス、商品・サービスを使用する状況、広告を見た際の印象、自社の商品・サービスを選択した要因などです。
これらを把握することで、マーケティング領域では新たなニーズや改善点の発見や、消費者インサイトの把握などにつながります。定性調査では対象者と対面して、直接会話をしていくことで調査します。
定性調査と定量調査との違い
定量調査とは、調査結果が数値で表現できる調査のことです。たとえば、質問に「はい」と答えた人と「いいえ」と答えた人、それぞれの割合を表すことは定量調査に該当します。一方、定性調査は数値で表せない言葉や行動などを調査するものです。
また、目的も異なります。定量調査は満足度や認知率、効果などを数値で検証したい場合に適しています。定性調査は事柄の背景や原因などを把握したい場合に適しています。
定性調査の基本的な手法
一口に定性調査と言っても、さまざまな調査方法があります。基本的な5つの手法を解説します。
グループインタビュー
3~8人ほどのグループ単位で、インタビューを実施する手法です。複数の対象者を同じ場所に集め、テーマについて自由に発言してもらうなかで話し合う姿を調査します。多くの場合モデレーターと呼ばれる司会者がおり、スムーズに進行します。1回で多くの意見を集められたり、複数のグループを比較できたりというメリットがあります。
デプスインタビュー
デプスインタビューは、インタビュアーと対象者が1対1で会話する手法です。インタビュアーが質問して対象者が答え、それを掘り下げていきます。1人を念入りに調査するため多くの時間が必要ですが、対象者の本音を得られたり、他者に影響されにくかったりするメリットがあります。パーソナルな情報を得たい場合にも適しているでしょう。
行動観察調査(エスノグラフィー)
行動観察調査とは、対象者の日常生活に同行し、近くから対象者を観察して気になることがあればインタビューする手法です。対象者の、無意識の行動や癖などを把握できます。対象者と行動をともにするため、深い質問がしやすいでしょう。ただし、調査環境が回答に影響するため、調査場所を選ぶ必要があります。
訪問調査
訪問調査とは、商品・サービスを利用している対象者の自宅に訪問して、使用環境や使い方などを調査する手法です。対象者が住む地域や自宅の雰囲気、対象者の特徴、家族による視点などを調査できます。また、対象者の生活を確認し、家族構成や雰囲気などを知れるため、無意識の行動を把握したい場合に適しているでしょう。
ワークショップ
ワークショップとは対象者を集め、テーマに沿って実施する体験型スキームです。対象者は当事者として参加するため、達成感とともに当事者意識を抱きやすくなります。企業や商品・サービスへ愛着を抱いてもらえる機会となるでしょう。参加者が話しながら進めるため、その際の会話も調査対象となります。
定性調査のメリット
定性調査によってどのような効果が得られるのか、おもな3つのメリットを解説します。
ユーザーのリアルな声を入手できる
インタビューで聞いたユーザーのリアルな声や視点を入手することで、開発や改善の際に活用できます。ユーザーの視点で便利な機能や好まれる見た目など、企業の目線とは違った声により新たな発見を得られるでしょう。
商品開発のためのアイデアにつながる
定性調査はユーザーの声を直接聞けるため、新たな商品・サービスのアイデアにつながる可能性があります。得たアイデアを商品開発につなげられると、ユーザーのニーズに合致する商品・サービスが誕生するかもしれません。
ユーザーの深層心理を調査できる
定性調査によって、ユーザーの深層心理を調査できます。具体的には、商品・サービスを購入した要因や使用している理由などです。気になった内容があればその場で深掘りできるのは、定性調査の強みです。
定性調査のデメリット
定性調査にはデメリットも存在するため、理解したうえで実施することが重要です。おもな2つのデメリットを解説します。
偏りのあるデータになってしまうことがある
定性調査は人数が限られるため、自社のターゲットに限定すると対象者の年齢や職業が偏るおそれがあります。その場合は得られるデータも偏りがちです。対象者はさまざまな視点を持つ人を選ぶ、定性調査で見つけたインサイトを定量的に検証するなど、偏りを補完するようなプロセスを考えることが重要です。
調査やデータの集計に時間がかかる
定性調査は数値ではなく言葉や行動などが回答となるため、集計に時間がかかります。また、データとして管理するのにも適していません。調査前から得られた結果の活用方法と優先順位を決めておくとよいでしょう。
定性調査は定量調査と組み合わせるとより効果的
定性調査と定量調査は調査方法や得られるデータが異なるため、目的に応じて使い分ける方法が一般的です。しかし、2つの調査を組み合わせることで、有用性のあるデータを得られることもあります。組み合わせた2つのパターンについて解説します。
定性調査を先に実施するパターン
先に定性調査を実施して仮説を立て、定量調査で仮説を検証するパターンです。一般的に、定量調査の実施前には仮説を立て設問を作成します。
ところが、調査対象への知識が不十分だと、仮説が不正確で的外れな設問となるケースがあります。設問が適切でなければ、精度の高い調査結果は得られません。先に定性調査を実施することで対象者についての知識や理解が進み、仮説の精度を上げられるでしょう。
定量調査を先に実施するパターン
先に定量調査を実施しておおまかな傾向を掴み、定性調査で深掘りするパターンです。定量調査で得たデータから精度の高い仮説を立て、特定のターゲット層を把握できた場合、対象者へのインタビューで掘り下げた質問を実施します。
定性調査では表面的な部分だけではなく潜在的な意識に迫れるため、従来とは違う発見によって商品・サービスの新たなアイデアや改善案へつながる可能性があるでしょう。
定性調査を成功させるポイント
定性調査の成功には、事前の準備と調査時の臨機応変さが重要です。3つのポイントを解説します。
調査目的を明確にする
実施前の時点で、調査目的は明確にしておきましょう。また、関わる人たちの間で共有しておくことも欠かせません。調査目的が明確でなければ、対象者の選定やインタビューの内容決定時に誤った選択をするおそれがあります。
インタビューフローを作成する
定性調査でのインタビュー前には、必ずインタビューフローを作成します。インタビューフローとは、質問の内容や構成をまとめたものです。質問内容は関わる人たちで確認し、質問すべき内容を網羅できるよう意識しましょう。
臨機応変に対応する
インタビューフローの作成は重要ですが、必ずしもそのとおりに実施する必要はありません。対象者の回答で気になった部分は深掘りする、臨機応変さが求められます。加えて、対象者との信頼関係を築くことも意識しましょう。
まとめ
数値に表せない内容を調査できる定性調査では、大勢に実施する従来の調査方法では得にくい対象者の深層心理に迫ることが可能です。ただし、精度を上げるには事前の知識や準備などが欠かせません。メリットだけではなくデメリットまで理解し、商品・サービスのアイデアや改善策に活用しましょう。
株式会社マクロミルでは、マーケティングリサーチとデジタルマーケティングリサーチを中心に、多様な社会・消費者ニーズを分析し、クライアントに的確な消費者インサイトを提供しています。定性調査の実施をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。