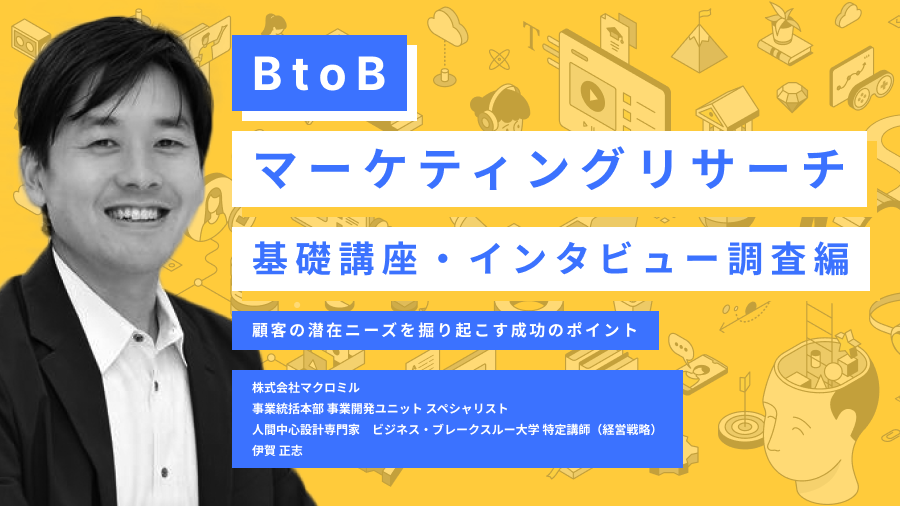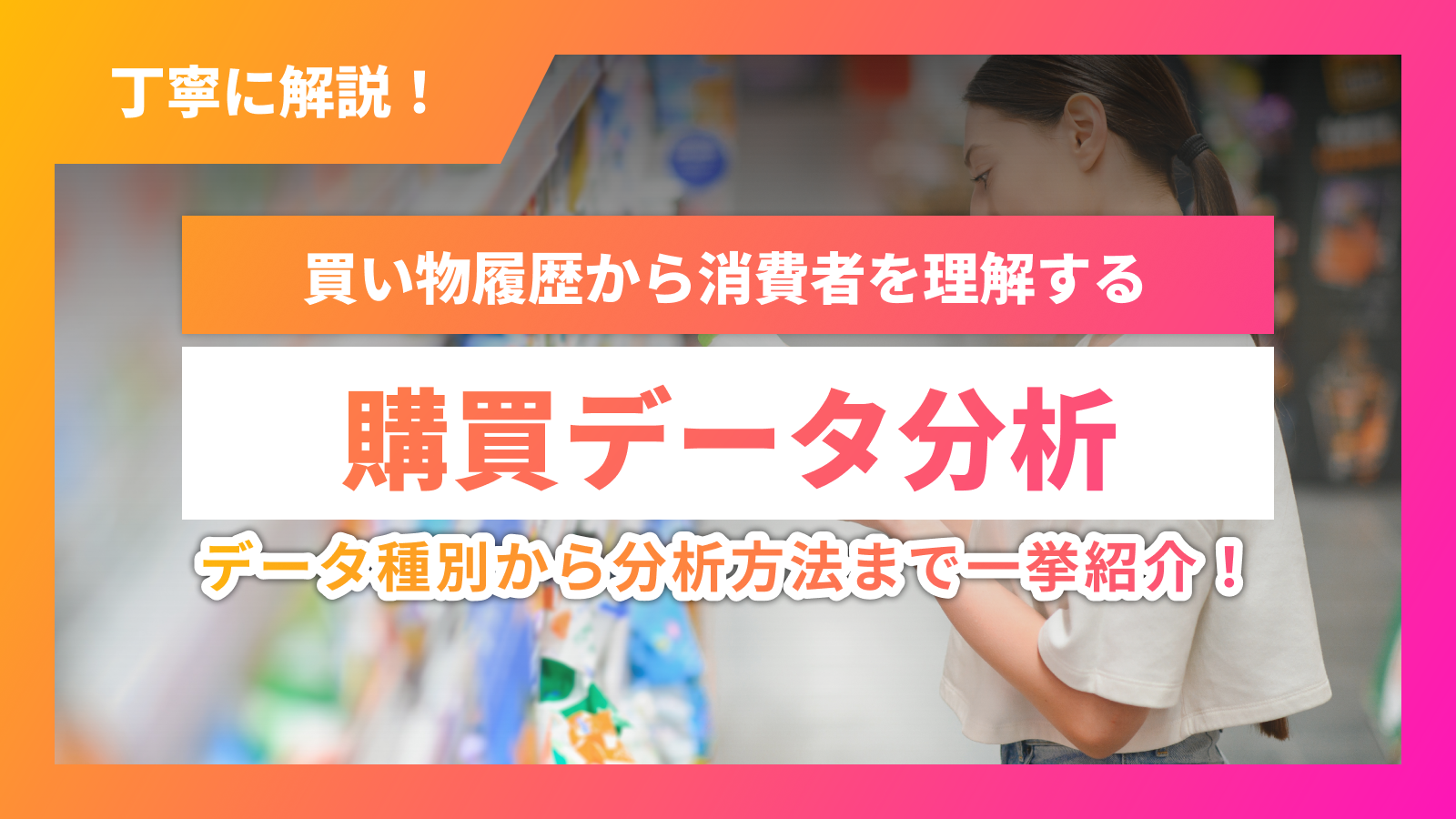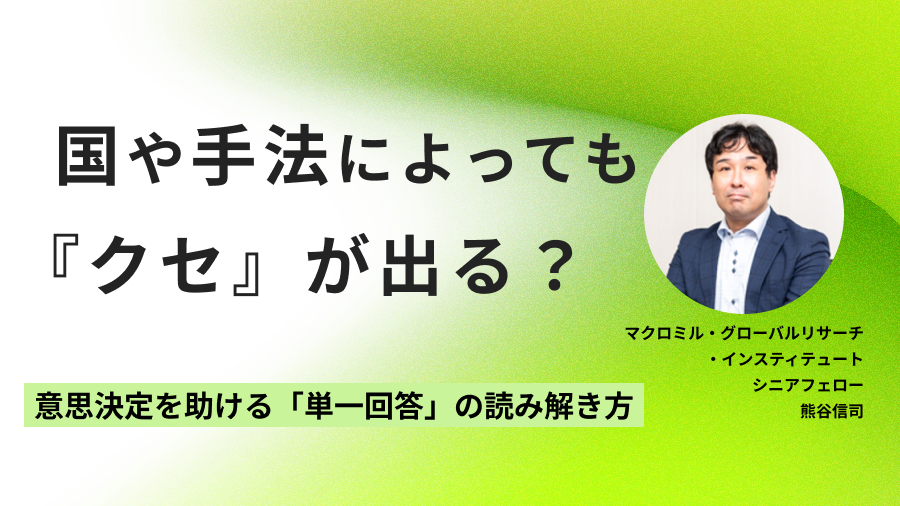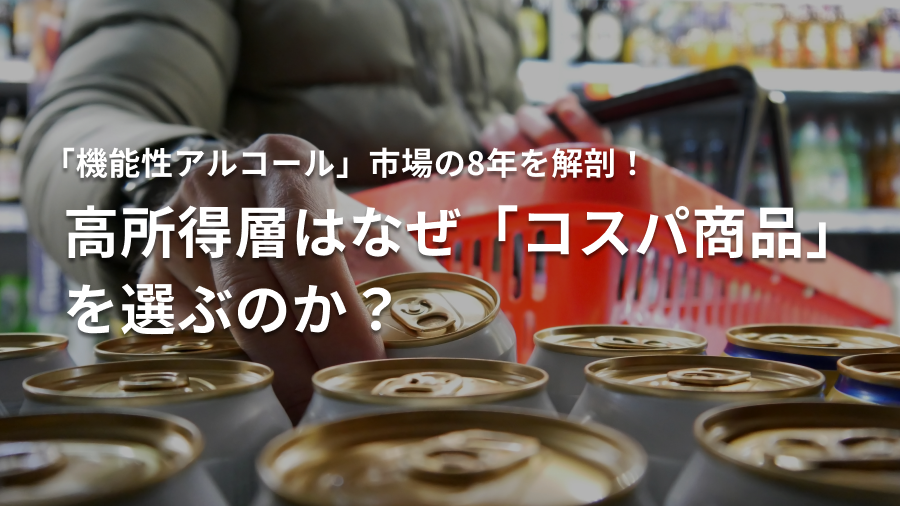オンラインインタビューとは?調査手法のメリットとN1分析への活用を徹底解説
公開日:2025/7/18(金)
オンラインインタビューとは、文字通り「インターネットを介して行われるインタビュー」のことを指します。ビデオ会議ツールや音声通話アプリなどを通じて、離れた場所にいる相手とリアルタイムに会話を行い、情報を収集する手法です。新型コロナウイルスの影響など社会的背景も相まって、オンラインでのやり取りが一般的になったことで急速に普及し、現在では多くの企業や研究機関が調査手法として取り入れています。
一見すると「対面で行うインタビューとあまり変わらないのでは?」と思われるかもしれません。しかし実際には、オンライン環境ならではのメリットやデメリット、コツや注意点が存在します。また、インタビュー調査の一環としてN1分析®を実施する際にも、オンラインインタビューの特徴を踏まえた設計が求められます。本記事では、インタビュー調査に焦点を当てながら、オンラインインタビューの基礎や実施の流れ、メリットと課題、N1分析®*との関連までを詳しく解説します。
- オンラインインタビューの特徴
- オンラインインタビューのメリット
- オンラインインタビューのデメリット・課題
- オンラインインタビューの実施における流れ
- オンラインインタビューのコツ
- オンラインインタビューの注意点:プライバシーと倫理
- N1分析におけるオンラインインタビューの活用
- まとめ:オンラインインタビューの価値とN1分析への応用
オンラインインタビューの特徴
オンラインインタビューは、場所や時間の制約が少ないという大きな特徴を持ちます。対面のインタビューでは、インタビュー対象者(インタビューイー)をオフィスや会議室へ招く必要があるため、移動コストがかかったり、日程調整が難しかったりすることが多々あります。一方、オンラインインタビューであれば、インタビューイーもモデレーター(インタビュアー役)も自宅で気軽に参加できるため、スケジュール調整が比較的容易です。
また、新たなツールの登場によって、Webカメラとマイクを備えたパソコンやスマートフォンだけあれば、誰もが簡単にインタビューに参加できるようになりました。ビデオ会議システムの普及はもちろんのこと、通信環境も整備が進んでおり、以前では考えられなかった高品質な映像と音声をリアルタイムでやり取りできるようになっています。このような技術的進歩は、オンラインインタビューを活用するうえでの大きな追い風となっています。
オンラインインタビューのメリット
オンラインインタビューがここまで注目されるようになったのは、以下のようなメリットがあるためです。
地理的制約がほぼない
従来であれば会場近郊の対象者のみをリクルーティング対象とするケースが多かったですが、会場来場が困難な方(会場近郊外居住の方、幼児の親御様など)もリクルーティングが可能となりました。より多くの方から選考できるようになり、募集条件が厳しいインタビュー調査も実施が可能となります。
スケジュール調整が容易
インタビューに必要なのは、オンライン会議ツールと安定したインターネット環境、そして互いの時間が合うことだけです。対面の場合のように部屋や交通手段を確保する必要がないため、スケジュール調整が容易になります。
コスト削減
移動費や会場費がかからない分、調査にかかるトータルのコストを削減できます。特に大規模な調査や複数回のインタビューを予定している場合、オンライン化によるコストメリットは大きくなります。
オンラインインタビューのデメリット・課題
一方で、オンラインならではのデメリットや課題もあります。実際にオンラインインタビューを実施する際には、以下の点に注意が必要です。
実物を使いながら行うインタビュー
試用・試飲・試食等の評価調査や、グルーピングやカードソーティング、コラージュ等の手法を使う調査を実施する場合は対面で行う必要があります。
対面よりも感情を読み取りにくい
ビデオ通話を使っていても、実際に同じ空間で話しているのと比べると、どうしても表情や仕草、雰囲気などの情報が得にくいという面があります。対面であれば感じられる微妙な空気感や相手の態度変化などを捉えづらいかもしれません。
通信環境への依存
インタビューの質は、通信環境に大きく左右されます。通信が不安定な場合、音声や映像が途切れたり、質問と回答がかみ合わなくなったりすることがあります。これは調査の正確性にも影響を及ぼすため、双方が安定した環境を確保することが望まれます。
オンラインインタビューの実施における流れ
ここでは、オンラインインタビューを具体的にどのように進めればよいのか、その一般的な流れを紹介します。
1. インタビューの目的の明確化
まずは調査の目的を明確にします。インタビューを実施する背景となるマーケティング課題は何か、インタビュー後にどのような成果を得たいかを明らかにしておきます。
2. インタビュー回答者の設定
どのような回答者から情報を得たいのかを設定します。回答者(ターゲット層)が明確であるほど、より有意義な調査設計が可能です。
3. スケジュールや費用感の設定
インタビューを実施する際には、実施時期やインタビュー対象となる人数、そしてインタビューの所要時間を事前に設定する必要があります。これらの要素によって費用が変動する可能性があるため、費用感を考慮しながら調整を行うことが重要です。
4. 対象者の選定
インタビュー対象者を募集し選定していきます。調査会社に依頼する、自社社員に依頼する、家族や知人に依頼する、Interview Zeroのようなセルフツールを利用するなど、さまざまなアプローチが可能です。それぞれのメリット・デメリットを確認しながら、対象者を募集・選定してください。
5. インタビューフロー作成
聞きたい項目を精査し、聞く順番と大まかな時間配分を決めておきます。ただし、対象者の回答に応じてヒアリング内容を柔軟に変えられるよう、細かく決めすぎないことが重要です。また、答えやすい一般的な質問から徐々に重要な質問へと進める構成にすると効果的です。
6. インタビューの実施
インタビューが始まったら、まずは簡単な挨拶、調査目的、守秘義務、忌憚なき意見を述べてほしい旨をお伝えします。その後、回答者がリラックスできるように軽い雑談やウォーミングアップから入り、作成したインタビューフローに沿ってヒアリングを進めます。
7. まとめ(ラップアップ)
インタビュアーと見学したメンバー同士で、発言の読み取り・解釈をすり合わせ、インタビューの目的に沿って次のアクションプランについて議論を行います。また、複数回インタビューを行う場合は、インタビュー後にインタビューフローの修正が必要かどうかを確認します。
オンラインインタビューのコツ
オンラインインタビューに特別なスキルは不要ですが、回答者の話を丁寧に真剣に聞く姿勢が重要です。オンラインインタビューであっても、モデレーターの役割は従来の対面インタビューとほぼ同じです。
ラポールの形成は必須
本題に入る前にラポールを形成します(「このインタビュアーは話しやすい」と思ってもらえる雰囲気・空気づくり)。最初に簡単な自己紹介を行い、インタビューの目的、内容の漏洩防止、忌憚ない意見を述べてほしい旨を伝えましょう。その後、回答者に休日の過ごし方や趣味などを尋ね、声を出すことや具体的に話すことに慣れてもらいます。
ペーシングとリード
回答者が話しやすいようにペースを合わせ(ペーシング)、必要に応じて次の話題へ進める(リード)技術を使います。相手のペースを大事にし、声の大小やリズムを相手に合わせることで、回答者との一体感が生まれます。
アクティブリスニング
相手の話を真剣に聞くことをアクティブリスニングと呼びます。真剣に聞いていれば自然に質問が湧いてきますし、相手も「理解されている」と感じて話し続けてくれます。聞く際には【 相槌を打つ(例:「なるほど!」「そうなんですね!」「知りませんでした」「参考になります!」)】【決めつけない】ことを意識しましょう。 また、沈黙を嫌い無理に言葉を繋げたり、聞き出そうとするのは避けましょう。沈黙があっても相手が話し出すまで待つことが重要です。
回答者への姿勢
忙しい中、自分にメリットがあるかどうかわからないにも関わらずインタビューに応じてくれた回答者に対して、最大限の敬意を払います。こちらの言いたいことがあっても遮らずに相手の話を最後まで聞く、自社の商品について否定的な意見を言われても反論しないことが重要です。また、先入観を持って決めつけたり、自分の仮説を確認するための質問をするなどの行為は避けましょう。
オンラインインタビューの注意点:プライバシーと倫理
オンラインインタビューでは、インタビュー映像や音声がデジタルデータとして残るため、取り扱いに注意しなければなりません。プライバシー侵害やセキュリティリスクを回避するためにも、以下のポイントを押さえましょう。
同意書(コンセントフォーム)の準備
録画や録音をする場合は、事前に対象者から文書またはオンラインフォームを通じて同意を得るのが理想的です。利用目的や保管期限、データの取り扱い方法などを明記することで、トラブルを防ぎます。
セキュアな環境の選択
ミーティングURLが部外者に知られないようにしたり、パスワードを設定したりするなど、ツールのセキュリティ設定を十分に行いましょう。無料ツールの場合は、通信の暗号化やデータ保存場所なども確認しておくと安心です。
守秘義務の徹底
調査で得た情報は外部に漏らさないよう、関係者間で取り決めを行います。特にN1分析®のように個人を深く掘り下げる場合は、個人情報やセンシティブな内容が含まれることが多く、慎重な扱いが求められます。
N1分析におけるオンラインインタビューの活用
インタビュー調査といえば、複数名でのフォーカスグループインタビューや、一定数の被験者を集めて定量的調査をしつつあわせて行うインタビュー調査を思い浮かぶかもしれません。しかし近年注目されているのがN1分析®という手法です。N1分析®とは、サンプル数が1名(N=1)であっても、深く掘り下げることで得られる個人の深層心理や具体的な行動パターン、購買や利用に至るまでの文脈を詳細に捉えることを可能にするアプローチです。
なぜN1分析が注目されるのか
近年、N1分析®が注目されている理由の一つは、顧客を深く理解することが求められる時代背景にあります。従来のグループインタビューでは、複数の参加者の意見を収集することで全体的な傾向を把握することが可能でしたが、個々の顧客の内面に迫るには限界がありました。
一方、N1分析®では、顧客個人の潜在的なニーズ、価値観、感情、具体的な行動の背景にある思考プロセス、深層心理など購買や利用に至るまでの文脈を詳細に捉えることが可能です。このような個別の洞察を重視するN1分析®は、顧客一人ひとりの詳細な理解を基盤とし、よりパーソナライズされた戦略や施策を立案するための重要な手法として注目されています。
N1分析とオンラインインタビューの相性
N1分析®のように深く掘り下げる調査を行う場合、オンラインインタビューは特に有効な手段となります。理由としては以下の2点が挙げられます。
回答母数が多い
Webカメラとマイクを備えたパソコンやスマートフォンがあれば全国どこからでも参加ができるため、多くの方の中から回答者を選考することができます。そのため、より希望する募集条件に合致する回答者と出会える確率が高まります。
リラックスした環境
対象者が自宅など落ち着ける場所から参加できるため、対面調査よりも心理的な負担が減りやすいケースがあります。モデレーターが上手に雰囲気をつくることができれば、より率直な意見や感情を引き出せるでしょう。
まとめ:オンラインインタビューの価値とN1分析への応用
オンラインインタビューは、場所や時間の制約を緩和し、コストを抑えながら多様なインタビュー調査を可能にする手法であり、特にN1分析®のように一人の対象者を深く掘り下げる調査において大きなメリットをもたらします。
コロナ禍を明けたことで、調査目的やターゲットに応じて「オンラインインタビュー」と「対面インタビュー」を使い分けることが現在主流となっており、企業のマーケティング活動においても、より迅速かつ手軽に消費者の声を聴くためにアジャイル型リサーチを取り入れる動きが広がっています。
オンラインインタビューは、対面インタビューでは難しい迅速かつ手軽な調査を可能にする点で、アジャイル型リサーチに非常に適しており、引き続き有用なインタビュー手法として選択され続けるでしょう。N1分析®もインタビューの発言とAIツールを掛け合わせることで、インタビュー結果を効率的かつスピーディに分析する流れが今後の主流となると考えられます。
※N1分析®は、マクロミルグループが保有する商標です。ライセンス提供はしておりませんため、当社(マクロミルグループ)以外は正規の提供者ではありませんのでご注意ください。
著者の紹介
株式会社マクロミル
鳥居 慧
2009年に株式会社マクロミルに入社。
10年以上にわたり定量調査から定性調査まで幅広いリサーチサービスの運用部門に従事し、10,000件以上のプロジェクトに関与。
2024年、セルフ型のオンラインインタビュープラットフォーム「Interview Zero」を立ち上げ、プロダクト責任者として従事。