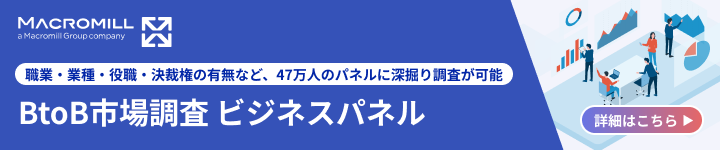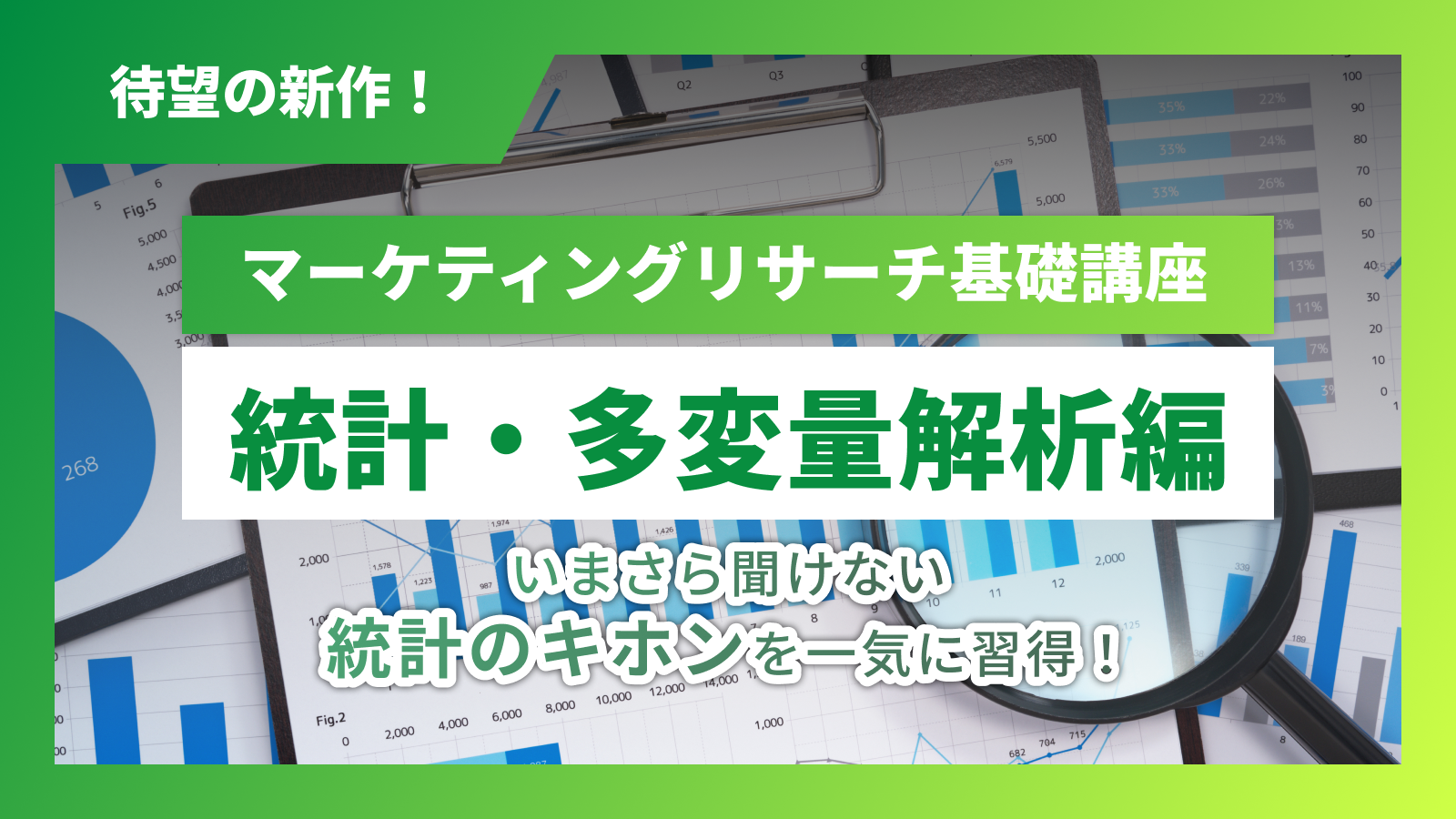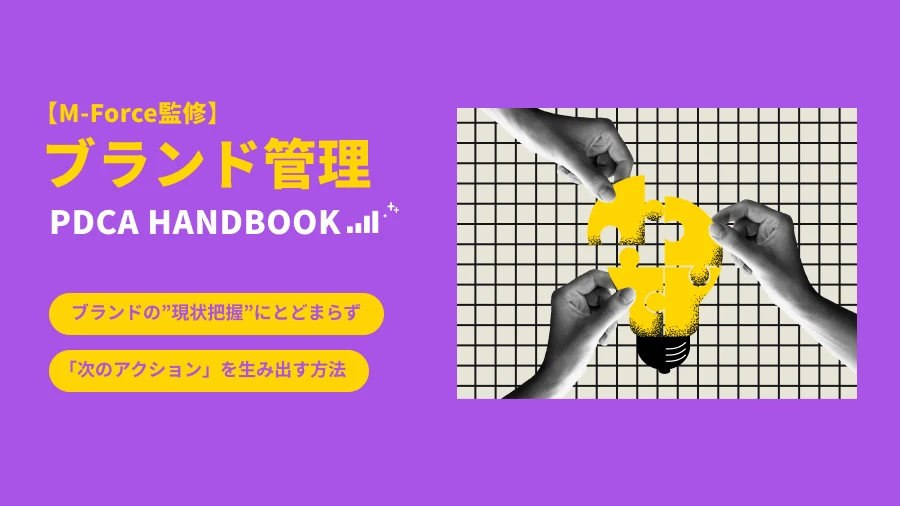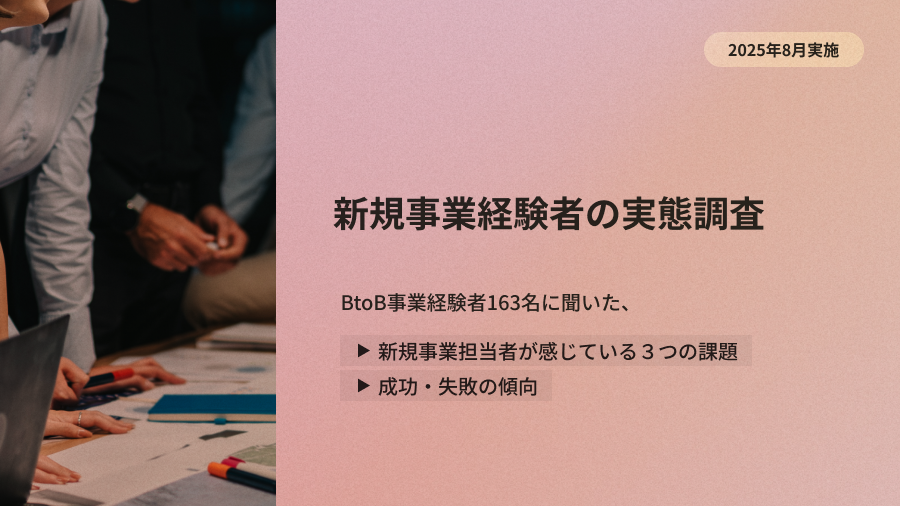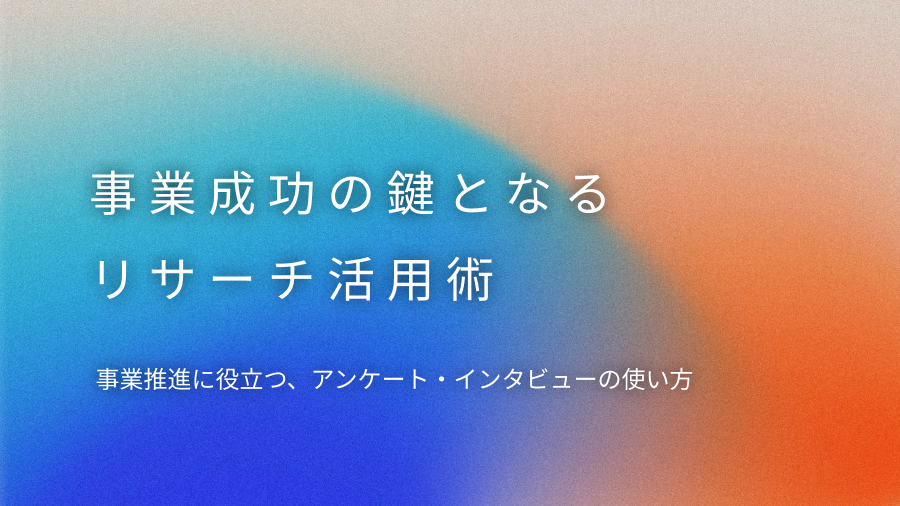「マーケティング」と聞くと、まず思い浮かべるのは一般消費者を相手にしたBtoC(Business to Consumer)の世界かもしれません。テレビCM、SNS、店頭販促――いずれも私たちの日常と接点のある“消費の現場”です。しかし、実は私たちの目に触れないところで、膨大なビジネスが企業間で日々行われています。製造業の部品供給、ITベンダーのシステム提案、法人向けの研修サービス…。こうした“企業を相手にした取引”の中でも、マーケティングは極めて重要な役割を担っています。
BtoBマーケティングは、BtoC以上に論理的で長期的な視点が求められる世界です。一つの商談が成立するまでに、複数の関係者が関与し、膨大な情報が行き交い、何度も比較検討が繰り返されます。つまり「営業だけ」では決して成り立たないのです。マーケティングが“見込み顧客の意思を動かす設計”を担うことで、営業が効率的に商談化・受注につなげられるようになります。
本コラムでは、「そもそもBtoBマーケティングとは何か?」という本質から、その構造、戦略、実践例、そして近年注目される最新トレンドまでを包括的に解説していきます。
【BtoB事業に関わる方必見!課題別アプローチ方法の資料を公開中】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- BtoBマーケティングの定義
- BtoCとの違いはどこにあるのか?
- なぜBtoBの購買は複雑なのか?意思決定構造を読み解く
- STP戦略とカスタマージャーニー:設計で勝負が決まる
- コンテンツマーケティングの役割:検討プロセスの伴走者として
- マーケティングと営業の連携:分業ではなく協業へ
- アカウントベースドマーケティング(ABM)の可能性
- テクノロジーとBtoBマーケティング:MA、SFA、CDPの活用
- 成功事例から学ぶBtoBマーケティングの実践
- まとめ:営業とマーケティングの境界線を越えて
BtoBマーケティングの定義
「BtoB」とは「Business to Business」、つまり企業と企業の間で行われる取引を指します。そして「BtoBマーケティング」とは、その企業間取引を成約へと導くためのあらゆるマーケティング活動のことを意味します。製品やサービスを開発し、それを適切な相手に届けるためのプロセス全体を設計し、見込み顧客の“情報探索→比較検討→意思決定”という行動を支援する一連の仕組みです。
たとえば、あるSaaS企業が会計事務所向けに新しいクラウドサービスを販売したいと考えた場合、彼らはただ営業を送り込むだけでは不十分です。ターゲットの企業にまず製品を知ってもらい、業界特有の課題にどのように貢献できるのかを丁寧に伝え、信頼を獲得して初めて、商談のスタートラインに立てるのです。
つまり、BtoBマーケティングとは「相手の会社に売る」というよりも、「組織内で意思決定されるプロセス全体を設計し、働きかける」ことに他なりません。
BtoCとの違いはどこにあるのか?
BtoBマーケティングの全体像を理解するうえで、まず押さえておきたいのがBtoCとの構造的な違いです。対象が“法人”になるということは、単に「相手が会社」というだけではありません。購買の意思決定構造やプロセス、評価軸そのものが大きく異なるのです。
たとえば、BtoCの場合、意思決定者は基本的に1人で、衝動買いや感情に左右されることもしばしばあります。価格や利便性、ブランドイメージなどが購買に大きな影響を及ぼします。
一方、BtoBでは以下のような特徴が見られます:
- 意思決定者が複数人にわたる(現場担当者、部門責任者、経営層など)
- 意思決定までに時間がかかる(社内稟議・検討フローがあるため)
- 論理的な根拠や実績が重視される(ROI、セキュリティ、運用実績など)
- 顧客ごとにニーズが異なりやすい(カスタマイズや業界特化が求められる)
こうした違いを理解せずに、BtoCと同じような訴求やチャネルを使っても、成果につながることはありません。むしろ、顧客が求めているのは「共感」よりも「信頼」や「根拠」なのです。
なぜBtoBの購買は複雑なのか?意思決定構造を読み解く
BtoBマーケティングにおける最大の特徴のひとつが、「購買の意思決定に関わる人数と工程が多い」という点です。たとえば、営業支援ツールの導入を検討している企業があるとしましょう。このツールの選定には、営業部門だけでなく、情報システム部門、経理部門、場合によっては経営層までが関与することになります。
こうした購買のプロセスを構造的に見ていくと、次のようなステークホルダーが登場します:
- 実際に業務を行う「利用者」
- 導入の是非を判断する「管理職」
- 予算を決裁する「財務・経営層」
- セキュリティや運用の可否をチェックする「情報システム部門」
このように、1つの導入判断の裏側には、複数の関係者による“社内合意形成”が存在します。さらに、それぞれの立場で重視するポイントも異なります。利用者は「使いやすさ」を、経営層は「費用対効果」を、IT部門は「セキュリティ要件への適合性」を重視します。
つまり、BtoBマーケティングとは、「複数の人の納得」を設計する営みであるとも言えます。そのためには、単一のメッセージを繰り返すのではなく、相手の立場に応じた情報提供や価値訴求が必要です。
【BtoB事業に関わる方必見!課題別アプローチ方法の資料を公開中】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
STP戦略とカスタマージャーニー:設計で勝負が決まる
こうした複雑な購買構造を前提とするBtoBマーケティングでは、「誰に・何を・どうやって」届けるかという設計がすべての起点となります。その基本的な枠組みが、STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)です。
まず、セグメンテーションでは、業種、企業規模、課題の成熟度、意思決定構造といった軸で企業を分類します。次に、その中から自社が最も価値を提供できる領域をターゲットに設定。そして、他社にはない独自の価値を打ち出すことで、ポジショニングを確立します。
たとえば、同じ「人事部門向けシステム」であっても、「従業員数500名以上の製造業向け」に特化することで、より高い訴求力を発揮できるケースは少なくありません。
そしてもう一つ重要なのが、カスタマージャーニーの設計です。これは、顧客が初めて課題に気づいてから、最終的に製品・サービスを導入するまでの“思考と行動の流れ”を可視化するフレームです。
一般的には、以下のようなフェーズに分かれます:
- 潜在課題の認知(例:「業務が属人化していて非効率だな」)
- 情報収集・学習(例:「SaaSで効率化できるのでは?」)
- 比較検討(例:「A社とB社で何が違うのか?」)
- 社内説得・稟議(例:「ROIを示す根拠資料が必要」)
- 契約・導入
- 評価・拡張
この流れに対して、各ステージでどんなコンテンツを用意し、どのようなチャネルで届けるかを戦略的に組み立てることで、顧客の“検討行動”を前に進めることができるのです。
コンテンツマーケティングの役割:検討プロセスの伴走者として
BtoBマーケティングにおいて、いまや欠かせない存在となっているのが「コンテンツマーケティング」です。これは、顧客の意思決定プロセスに寄り添う情報(コンテンツ)を継続的に提供し、自社への信頼と興味を育てるアプローチです。
特に重要なのは、「いま買う気はないが、情報を探している層」へのアプローチです。BtoBの多くの製品やサービスは、顧客がすぐに意思決定できるものではありません。数か月、あるいは数年単位で情報を比較検討し、ようやく導入に至るケースもあります。そこで、見込み顧客が検索しそうなキーワードに対応する記事や資料を用意し、彼らが課題を認識し、理解を深めるためのガイドとして機能することが求められます。
たとえば、次のようなコンテンツが典型的です:
- 課題整理ガイド(例:「脱・属人化を実現する3つの方法」)
- 導入事例(例:「A社が6か月で成果を出せた理由」)
- 比較資料(例:「他社製品との機能・価格比較一覧」)
- 専門家インタビュー(例:「業界動向とこれからの課題」)
これらは単に「情報提供」ではなく、検討の次のステップへと進ませる“橋渡し”の役割を担います。つまり、コンテンツとは「静的な資料」ではなく、「顧客の行動を変える導線」として設計されるべきなのです。
マーケティングと営業の連携:分業ではなく協業へ
BtoBマーケティングを語るうえで避けて通れないのが、「営業」との関係です。特に日本企業では、営業主導でビジネスが動いているケースが多く、マーケティングは“名刺集め”や“展示会要員”と見なされがちです。しかし、現代のBtoBにおいては、マーケティングと営業が連携しなければ成果は出ません。
なぜなら、顧客の購買行動そのものが変化しているからです。かつては「営業に問い合わせて情報を得る」のが当たり前でしたが、今は顧客の多くが、意思決定の6〜7割を「営業に会う前」に済ませています。Googleで検索し、業界メディアを読み、ホワイトペーパーをダウンロードし、競合との比較もある程度終えたうえで、ようやく営業にコンタクトするのです。
つまり、営業が会いに行く前に、マーケティングがいかに“接点”を作り、適切な“理解と期待”を育てているかが、商談化率を大きく左右します。
このような背景から、マーケティングと営業の協業は次のようなプロセスで組まれることが理想です:
- マーケティングがターゲット企業の関心を喚起し、リードを獲得
- 行動履歴やスコアリングによって、関心度の高いリードを絞り込む
- ホットリードのみを営業にパスし、商談へと接続
- 営業は、リードが閲覧した資料や関心テーマを踏まえて提案
- 商談結果のフィードバックをマーケティングに返し、改善へ活かす
この連携を実現するためには、CRMやSFA、MAといったツールの導入と運用設計が不可欠です。しかし、最も大切なのは「両者が同じ成果指標を追っている」こと。単なる部門間連携ではなく、ひとつのチームとして“受注”というゴールを共有することが成功の鍵になります。
アカウントベースドマーケティング(ABM)の可能性
BtoBマーケティングがより戦略的に進化するなかで、注目を集めているのが「アカウントベースドマーケティング(ABM)」という考え方です。これは、不特定多数への広域アプローチではなく、「特定の企業や業界、部門」にフォーカスして、マーケティングと営業が一体となって深く入り込む手法です。
たとえば、「上場している製造業で、DX推進を掲げている企業」のように、ピンポイントで狙いたい企業群があるとします。ABMでは、そうした企業に向けて、専用のLP(ランディングページ)を用意し、業界特化のコンテンツを配信し、営業がアプローチの糸口をつかみやすくする――といった施策を講じます。
ABMの特徴は、「量」ではなく「質」に重きを置く点です。従来のリード獲得型マーケティングが“母数を増やす”ことを目的にしていたのに対し、ABMは“特定の有望企業との関係性を深める”ことを目的とします。つまり、商談化率や受注率の向上に直結するアプローチなのです。
特に、以下のようなケースではABMが大きな効果を発揮します:
- 高単価で導入ハードルの高い商材を扱っている
- 営業リソースが限られており、効率的なアプローチが必要
- 対象市場が限られている、あるいはすでに絞られている
- 顧客企業内での関係構築を深めて拡販したい
ABMを成功させるには、マーケティングと営業がターゲット企業を共有し、進捗状況や接点履歴を密に連携する必要があります。加えて、1社ごとの課題や背景を把握し、カスタマイズされた提案やコンテンツを提供する丁寧さが求められます。ABMとは、いわば“1社に対して1ブランドを作る”くらいの覚悟をもって取り組むマーケティングなのです。
テクノロジーとBtoBマーケティング:MA、SFA、CDPの活用
BtoBマーケティングは年々複雑化しており、それを支えるテクノロジーの重要性もますます高まっています。なかでも中核をなすのが、以下の3つのソリューションです。
1. MA(マーケティングオートメーション)
MAは、見込み顧客に対する情報提供やナーチャリング(育成)を自動化・最適化する仕組みです。資料ダウンロードやセミナー参加といった行動履歴に応じて、パーソナライズされたメールを送ったり、スコアリングによってホットリードを判別したりと、営業の支援につながる施策を実現します。
2. SFA(セールスフォースオートメーション)
SFAは営業活動を記録・分析するツールです。顧客との接点、提案内容、商談ステージなどを可視化し、営業チーム全体でナレッジを共有できます。また、進捗や課題を把握することで、経営判断の精度向上にも貢献します。
3. CDP(カスタマーデータプラットフォーム)
CDPは、Webサイトの閲覧履歴、メールの開封状況、セミナー参加など、様々なチャネルで得られた顧客データを統合するプラットフォームです。これにより、ある見込み顧客が「どのような情報に関心を持っているのか」「いつ・どこで接触したのか」といった全体像を把握することが可能になります。
これらのツールは、単体で使うのではなく、統合的に活用することで真価を発揮します。たとえば、CDPで得た行動データをMAに連携してメール配信のタイミングや内容を最適化し、その結果をSFAで営業と共有するといった形です。
ただし、テクノロジーはあくまで“道具”です。重要なのは、どんな成果を出すためにどのような設計思想でツールを使うか。マーケティング戦略と連動してこそ、テクノロジーは本当に力を発揮します。
成功事例から学ぶBtoBマーケティングの実践
BtoBマーケティングは抽象的な議論に終始しがちですが、現場では「成果が出るかどうか」がすべてです。ここでは、国内外の企業で実践された代表的な事例を通して、どのような戦略が成果を生んだのかを見ていきます。
事例①:製造業向けSaaS企業のリード育成戦略
あるSaaS企業は、工場の業務効率化を支援するクラウドサービスを提供していました。営業の課題は「問い合わせはあるが、商談化しない」という点。原因を探ると、情報収集段階の見込み客が多く、営業に渡すには“時期尚早”だったのです。
この企業は、見込み客の行動履歴に応じて3つの層に分類し、それぞれに異なるメールコンテンツを配信。さらに、行動スコアが一定を超えた見込み客だけを営業に引き渡す運用に変更した結果、商談化率が3倍、受注率が2倍に改善しました。
事例②:ABMによる大手企業への深耕アプローチ
BtoB広告代理店のA社は、顧客単価が高く、対象となる企業数が限られていました。従来の広告施策では母数が広すぎて費用対効果が合わず、営業のモチベーションも低下していたのです。そこで導入したのがABM戦略。重点ターゲット企業を30社に絞り、各社に特化した業界レポートや提案書を作成し、セールスとマーケティングが一体でアプローチ。結果、6か月で8社と商談が成立し、そのうち4社が受注に至りました。
事例③:MA活用による展示会フォローの高度化
イベント出展後のフォローアップに課題を抱えていたIT機器メーカーでは、MAを活用して展示会来場者への自動メールシナリオを設計。閲覧コンテンツに応じて追加資料の案内や事例紹介を配信し、Web上の行動データからホットリードを特定。営業部門では、MAで得られた閲覧履歴をもとに「◯◯という業務課題に関心がある」と事前に把握したうえで訪問・提案が可能となり、展示会からの受注件数が前年比で約160%に増加しました。
【BtoB事業に関わる方必見!課題別アプローチ方法の資料を公開中】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
まとめ:営業とマーケティングの境界線を越えて
BtoBマーケティングとは、単なる“集客手法”ではありません。それは「企業間の信頼関係を構築し、価値共創を実現するための全体設計」とも言えます。
- 顧客の意思決定構造を理解し
- 論理と信頼に基づく訴求を設計し
- 営業と協力して受注へとつなげる
- データとテクノロジーを活用し改善を回し続ける
- そして、目先の導入だけでなく、顧客の未来を一緒に描く
そのためには、マーケティングと営業の“分業”ではなく“協業”が不可欠です。両者が共通の指標をもち、ひとつのチームとして動くことで、はじめて真のBtoBマーケティングは機能します。
あなたの企業にとっての「理想の顧客」とは誰か?その顧客が“いまどんな課題を抱えているか”?その問いに向き合うことが、BtoBマーケティングの出発点です。現場の悩みや行動に寄り添いながら、論理的かつ人間的なマーケティングを実践していきましょう。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル