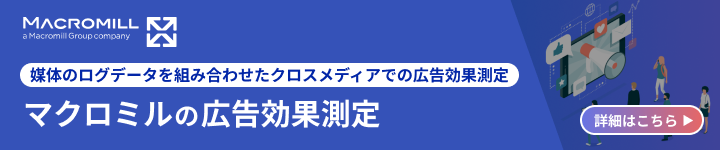ブランドリフト調査とは?メリットや実施方法、注意点を解説
公開日 :2023/8/14(月)
最終更新日:2025/10/31(金)
YouTube広告やディスプレイ広告を出稿したものの、クリックやコンバージョンといった直接的な成果につながらず、「この広告、本当に効果があるのだろうか?」と疑問に思った経験はありませんか。
Web広告の世界では、かつてはクリック数や購入数が効果測定の主流でした。しかし、ブランドイメージの向上を目的とする広告が増えた現在、旧来の指標だけでは広告の真の価値を測ることはできません。
そこで重要になるのが、広告によるブランドの認知度や好意度、購買意向といった消費者の心理を可視化する「ブランドリフト調査(態度変容調査)」です。
この記事では、ブランドリフト調査の基本的な概念からメリット、実施方法、相性が良い商材、注意すべきポイントまで、網羅的に分かりやすく解説します。
- ブランドリフト調査とは
- なぜブランドリフト調査が必要なのか?
- 態度変容に寄与できたかどうかは、どう判断する?
- ブランドリフト調査を行うメリット
- ブランドリフト調査の実施方法
- ブランドリフト調査と相性がいい商材
- ブランドリフト調査で注意すべきポイント
- マクロミルでブランドリフト調査を行うことのメリットは?
- まとめ
ブランドリフト調査とは
まずは、ブランドリフト調査の基本的な概念を解説します。
- ブランドリフト調査の基本的な意味
- セールスリフト調査との違い
ブランドリフト調査の基本的な意味
ブランドリフトとは、広告キャンペーンがブランドの認知度や好意度、購買意向といった消費者の心理に与えた影響を定量的に測定する調査手法です。
コンバージョン(購入、申込みなど)などの直接的な行動だけでは捉えきれない、広告の心理的な効果を可視化することを目的とします。
調査は、ランダム化比較試験(RCT)を用いて、「広告に接触するグループ」と「広告に接触しないグループ」にアンケートを実施します。ブランドリフト調査の基本的な手順は以下のとおりです。
- グループ分け:調査対象者を、広告に接触するグループ(接触群)としないグループ(非接触群)に無作為に分ける
- アンケート:両グループに同じ内容のアンケート(ブランド認知度、好意度など)を実施する
- 効果測定:回答結果の差を「リフト値」として算出する(この差が、広告接触による純粋な効果と見なされる)
たとえば、広告接触群の認知度が60%、非接触群が40%なら、差である20パーセンテージポイントがリフト値(効果が得られた指標)となります。
この手法は、季節変動や競合の動向といった広告以外の外的要因を統計的に排除できるため、広告と消費者の態度変容との因果関係を客観的なデータで証明できます。
セールスリフト調査との違い

ブランドリフト調査が消費者の心の変化(態度変容)を測るのに対し、セールスリフト調査は実際の購買行動(売上への貢献)を測定する点に明確な違いがあります。
ブランドリフト調査とセールスリフト調査の違いは、以下のとおりです。
| 調査の種類 | ブランドリフト調査 | セールスリフト調査 |
|---|---|---|
| 測定対象 | 認知度、好意度、購入意向などの態度変容 | 売上、購入率などの購買行動 |
| マーケティングファネル | 認知・興味関心(アッパー・ミドル) | 購入・申込(ロワー) |
| 主な手法 | アンケート調査(接触群と非接触群の比較) | 購買データと広告接触データの連携分析 |
| 分析の視点 | 広告が消費者の認識に与えた影響 | 広告が実際の売上に与えた純増分 |
| 適した目的 | ブランディング、認知度向上 | 販売促進、ダイレクトレスポンス |
両者は優劣の関係ではなく、マーケティングの目的やフェーズに応じて使い分けるべきものです。
なぜブランドリフト調査が必要なのか?
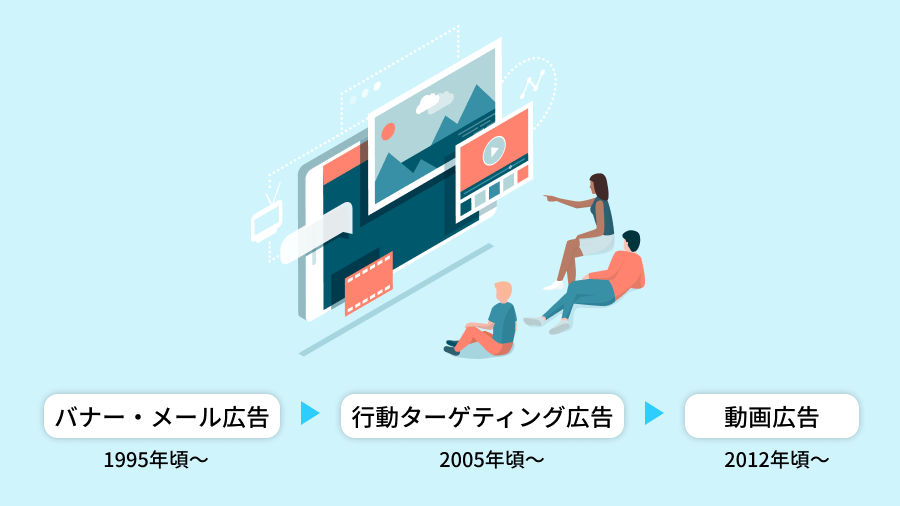
ブランドリフト調査の必要性を解説するにあたり、まずWeb広告の歴史について見ていきましょう。
1995年頃から「バナー広告」「メール広告」が始まったあと、リスティングやアフィリエイトといったダイレクト指標・成果報酬型の広告が多くなりました。
2005年頃から、行動ターゲティング広告(behavior Targeting)やアドネットワークが出現しはじめましたが、同じくダイレクト指標に寄った広告です。この辺りから、媒体レポート(IMP/CTR/CVR/CPIなど)もしっかり定義されはじめます。
具体的には「100万円Web広告を出稿したら、どのくらい直接指標で良い効果が得られるか」などのデータが、シビアにトラッキングされるようになりました。そのシビアさから、益々ダイレクト系クライアントの刈り取り目的出稿が台頭していったのです。
変化が起きたのは2012年頃からの動画広告がはじまってからになります。当時の動画広告は、各プラットフォーマーの静止画バナー枠に、GIFアニメのようなインバナー形式で動画が流れるものでした。ここからYouTube広告に変化していきます。
態度変容に寄与できたかどうかは、どう判断する?

これまでは、Web広告をテレビCM素材をYouTubeのインストリーム枠に配信してみても、ダイレクト指標だけで判断するとまったく効果が出ない場合、「広告をやる必要があるのか?」「効果をどう考えたらいいのか?」という声が出ていました。
そこで、どのように評価すべきかを検討していくなかで「態度変容に寄与できたか?」という点が新しい指標になっていきます。態度変容に寄与できたか判断するために、購入や、利用の手前の「中間指標」として、認知や興味喚起のきっかけになったかを調査で確認します。
テレビCMに対しても、意識調査で効果測定を行って結果を振り返ることは、これまでに多数ありました。しかしWeb広告の場合、「少ない予算で・狙った人たちに」リーチしているので、意識調査を行おうとしても動画広告を見た人が出現しないという問題が発生します。そのため、ログ判定と調査を組み合わせる手法が最適解となって成立したのです。
ブランドリフト調査を行うメリット
ここでは、ブランドリフト調査をマーケティング戦略に組み込むことで得られる、2つの具体的なメリットを掘り下げて解説します。
- 自社ブランドの消費者認知を正しく把握できる
- 広告の改善点を発見でき、ブランド戦略が立てやすくなる
調査を行うことで、これまで感覚的に評価されがちだったブランディング広告の価値を、経営層や他部署にも分かりやすい数値という共通言語で示せるようになります。
自社ブランドの消費者認知を正しく把握できる
季節や競合の動向といった外的要因の影響を排除し、自社の広告による純粋な効果を正確に把握できる点も大きなメリットです。
一般的な認知度調査では、市場全体の盛り上がりなど、広告以外の要因が結果に影響を与えます。
しかし、ブランドリフト調査は広告の接触群と非接触群を比較するため、これらの外的要因の影響を排除できます。両グループ間の差は、純粋な広告効果そのものを反映していると解釈できるのです。
さらに、単なる認知度だけでなく、以下のような多角的な視点から消費者心理を詳細に分析できます。
- ブランド認知度
- 広告想起率
- ブランドへの好意度
- メッセージの理解度
- 比較検討の状況
- 購入意向
これにより、自社ブランドが消費者にどう受け止められているかを、より正確に把握できます。
広告の改善点を発見でき、ブランド戦略が立てやすくなる
キャンペーンの成否判定だけでなく、今後の広告戦略を改善するための具体的なヒントを得られる点もメリットです。
ブランドリフト調査では、以下のような分析ができます。
| 分析の種類 | 内容 |
|---|---|
| デモグラフィック分析 | 広告がとくに強く響いた年齢・性別・地域などを特定する |
| ファネル段階別分析 | 「広告は覚えてもらえたが、コアなファン化ができていない」など、マーケティングファネル上の課題を発見する |
| クリエイティブ別分析 | 最も効果の高かった広告パターンを分析する |
| フリークエンシー分析 | 最適な広告表示回数を探る |
たとえば「キャンペーン全体の結果は振るわなくても、特定の年齢層にだけは効果が出ていた」といった発見から、ターゲット戦略の見直しにつなげることが可能です。
調査結果を活かしてPDCAサイクルを回すことで、ブランド戦略全体の精度を継続的に高められます。
ブランドリフト調査の実施方法
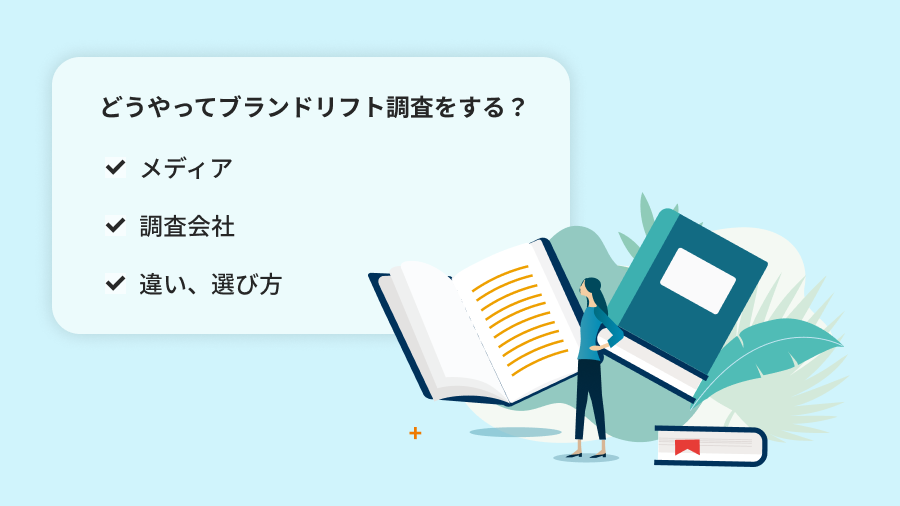
ここでは、ブランドリフト調査を実際に実施するための具体的な方法を3つのアプローチに分けて紹介します。
- 自社でアンケートを実施する
- 広告配信プラットフォームを利用して調査する
- リサーチ会社に依頼する
ブランドリフト調査には相応のコストがかかりますが、予算が限られている場合でも、工夫次第で実施することは可能です。
自社でアンケートを実施する
予算が限られている場合や、まずはスモールスタートで効果測定の文化を醸成したい企業にとっては、自社のリソースを活用してアンケートを実施することは有効です。
具体的な手法には、以下があげられます。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| サーチリフト分析 | ・キャンペーンの前後で、自社ブランド名などの検索数がどう変化したかを比較する方法 ・検索数の増加は、消費者の興味関心が高まった間接的な証拠と見なせる |
| ダイレクトトラフィックの観測 | ・Webサイト解析ツールで、ブックマークやURL直接入力による流入を観測する方法 ・この数値の増加は、ブランド想起率が向上している可能性を示唆する |
| SNSの投票機能の活用 | ・SNSの投票機能を使ったブランド想起率の目安を把握する方法 ・例:「〇〇と聞いて思い浮かぶブランドは?」といった簡易的な質問をして反応を確認する |
| 購入後アンケート | ・自社ECサイトなどで顧客の認知経路を収集する方法 ・例:「どこでこの商品を知りましたか?」などの質問を設置する |
統計的な厳密性には欠けるケースもありますが、マーケティングの方向性を判断するための参考データとして十分に価値があります。
まずはこうした低コストの手法からはじめて、ブランドリフト調査の有用性を社内で示し、将来的な本格調査への予算確保につなげていくというアプローチが現実的でしょう。
広告配信プラットフォームを利用して調査する
主要な広告プラットフォームが提供する、広告配信と連携した調査機能を利用する方法です。
アンケート形式には主に以下の2種類があります。
| 形式 | インバナーサーベイ | リードバナーアンケート |
|---|---|---|
| 概要 | 広告バナー内で直接アンケートに回答する形式 | 広告バナーをクリック後、専用ページで回答する形式 |
| メリット | 回答の手間が少なく、高い回答率が期待できる | 質問数や形式の自由度が高く、詳細なデータを収集できる |
| デメリット | 質問数が1~3問程度に限定される | ページ遷移による離脱で回答率が低くなる傾向がある |
プラットフォームのデータで広告の接触・非接触ユーザーを正確に特定できるため、信頼性の高いデータを得られるのが大きな利点です。
ただし出稿金額が高額になることが多く、比較的大規模なキャンペーンに適しています。
リサーチ会社に依頼する
高品質で信頼性の高い調査を行いたい場合には、専門のリサーチ会社に依頼する方法が有効です。
専門業者に依頼する場合のメリット・特徴として、以下があげられます。
| 専門業者に依頼するメリット・特徴 | 概要 |
|---|---|
| クロスメディア効果の測定ができる | テレビCM、デジタル広告、交通広告など、複数メディアを横断した効果を同一の尺度で測定できる |
| 高度な統計分析ができる | 傾向スコア分析などの手法で、ユーザー属性の偏りを補正し、より精度の高い分析が行える |
| 自由度の高い調査を設計できる | 企業の独自のマーケティング課題に合わせて、アンケートの質問項目を自由にカスタマイズできる |
リサーチ会社に依頼すると調査設計から高度な分析、戦略的なレポーティングまで、一貫したサービスを受けられます。
高品質である一方でコストもかかるため、大規模な新商品ローンチや企業のブランドイメージを左右する重要なキャンペーンに適していると言えるでしょう。
ブランドリフト調査と相性がいい商材

ここでは、ブランドリフト調査がとくにその真価を発揮する商材タイプについて解説します。
- 購入や利用までの検討期間が長い商品
- 市場での認知を広げたい新商品
自社の扱う商品やサービスが、これから紹介する特徴に当てはまるかどうかを確認してみてください。
購入や利用までの検討期間が長い商品
ブランドリフト調査と相性が良いのは、主に「高関与商材」(消費者が購買までに情報収集・比較検討に時間をかける商材)と呼ばれる部類のものです。
- 自動車
- 不動産
- 金融商品
- 高級ブランド
- 家電(高価格帯)
- 教育サービス
- BtoBサービス
これらの商材は、消費者が認知してから情報収集、比較検討を経て購入に至るまでのプロセスが長く複雑です。そのため、一度の広告接触で購入に直結することはあまりなく、短期的な売上をセールスリフト調査では広告の価値を捉えきれません。
ブランドリフト調査は、この効果を的確に測定します。たとえば、「このブランドは信頼できる」「次の買い替え候補に加えたい」といった心理的な変化を捉えることで、ブランディング活動が着実に未来の顧客を育てていることを証明できます。
これらの心理的変化は、将来の購買につながる重要な先行指標となるでしょう。
市場での認知を広げたい新商品
市場での認知度がほぼゼロから始まる新商品や新規参入ブランドも、ブランドリフト調査と相性が良いでしょう。
新商品は、「知ってもらうこと(認知度獲得)」と「覚えてもらうこと(広告想起率向上)」がキャンペーンの主目的となります。ブランドリフト調査は、これらの指標の変化を的確に捉えられます。
クリック数などでは測れない「知ってもらう」という成果を、ブランドリフト調査なら正しく評価できるためです。
ブランドリフト調査で注意すべきポイント
ブランドリフト調査を成功させるには、以下の4点が重要です。
- 調査目的を明確に設定する
- サンプル数を一定数確保する
- 回答者の属性をバランスよく含める
- 質問文はニュートラルに作成する
調査目的を明確に設定する
成功の最初のステップは、「何のために調査を行うのか」を明確にすることです。
目的は、自社のマーケティングファネルの段階に応じて設定しましょう。以下はそれぞれの段階における目的や指標の例です。
| ファネル段階 | 主な目的 | 主要指標 |
|---|---|---|
| 認知段階 | 新商品のローンチ、新市場への参入 | 広告想起、ブランド認知度 |
| 興味・関心段階 | ブランドイメージの向上、競合との差別化 | 好意度、メッセージ連想 |
| 比較・検討段階 | 購入の後押し、第一想起の獲得 | 比較検討、購入意向 |
たとえば、新商品のキャンペーンでいきなり「購入意向」を追うのではなく、まずは「ブランド認知度」を測るほうが効果的な場合があります。
目的を明確にしたうえで、測定する指標を1~3つ程度に絞り込めば、焦点の定まった効果的な調査ができます。
サンプル数を一定数確保する
調査結果に統計的な信頼性を持たせるには、十分な数のアンケート回答(サンプルサイズ)が不可欠です。サンプル数が不足すると、結果が偶然の誤差なのか、本当に意味のある差なのかを判断できなくなります。
一般的に、広告の接触群・非接触群のそれぞれで最低でも数百は必要で、数千のサンプルを用意することが理想です。予算が限られる場合には、指標を1つに絞り、十分なサンプル数を確保すると有効です。
回答者の属性をバランスよく含める
広告の接触群と非接触群は、広告に接触したか否か以外の属性(年齢、性別、興味関心など)ができるだけ均質でなければなりません。
元々関心が高い人々の意見と、一般的な人々の意見を比較すれば、広告の効果がなくても差が生まれるのは当然です。この差を広告の効果として誤って解釈してしまうと、過大評価することになります。
このような偏りはセレクションバイアス(選択バイアス)と呼ばれ、調査結果を大きく歪める原因となります。この状態を避けるには、調査設計時に属性のバランスをチェックしたり、専門のリサーチ会社を活用したりする方法が有効です。
質問文はニュートラルに作成する
アンケートの質問文は、回答者を特定の方向に誘導しない、中立的で分かりやすい言葉で作成する必要があります。
一例:健康志向の新しいお茶の広告を見た人へのアンケートを実施する場合
| 種類 | 質問の例文 | 解説 |
|---|---|---|
| 悪い例 | 「体に良い成分がたっぷりで、スッキリすると話題の新商品『〇〇茶』を、飲んでみたいと思いますか?」 | ・「体に良い」「スッキリする」というポジティブな情報を先に与え、回答を誘導してしまっている ・回答者はプレッシャーを感じ、本心とは違う回答をする可能性がある |
| 良い例 | 「新商品『〇〇茶』の広告を見て、この商品を飲んでみたいと思いましたか?」 | ・情報は商品の客観的な部分に留めて、回答を誘導しないようにする ・これにより広告の効果を正確に測定できる |
回答者が「こう答えるべきかな?」と考えてしまうような、情報や印象操作を含んだ質問は避けましょう。
またすべての質問文は、誤字脱字がなく、平易な言葉で簡潔に書かれていることが前提です。回答者がストレスなく、ありのままの意見を表明できるように設計することが、信頼性の高いデータを収集できるコツです。
マクロミルでブランドリフト調査を行うことのメリットは?
マクロミルのデータ提供サービスは、Web広告のブランディング効果を可視化できる効果検証が可能です。
ファネル上位を構成するターゲット層や新規ユーザーの認知・ブランドリフトをどれだけ促進させられたか、興味層・購入検討層がどれだけ増加できたかなどの細かいデータを収集・分析できます。
【メディアが提供するブランドリフト調査と、マクロミルの違い】
- 自由度の高い設計ができる
- 調査回答品質が担保できる(アンケートモニタとして適切に管理された人たちが回答するため)
- メディア横断した評価ができる
【他調査会社が提供するブランドリフト調査と、マクロミルの違い】
- 業界最大級のパネル数
- 測定精度の高さ
- 調査設計・分析についてプロフェッショナルが多い
まとめ
ブランドリフト調査とは、広告がどれだけ態度変容に寄与できたかを把握するための調査です。調査を通じて、広告の費用対効果を明確にしたり、消費者からの純粋なブランドイメージを把握したりできるだけでなく、データにもとづいた具体的な改善点を発見できるなど、多くのメリットがあります。
しかし、ブランドリフト調査を効果的に実施するには、十分なサンプル数を確保したり、適切なアンケート項目の設定をしたりといった工夫が必要です。
「マクロミル」では、ブランドリフト調査に関するさまざまなご相談を承っています。具体的な実施方法やマーケティング戦略への活用方法など、お気軽にご相談ください。