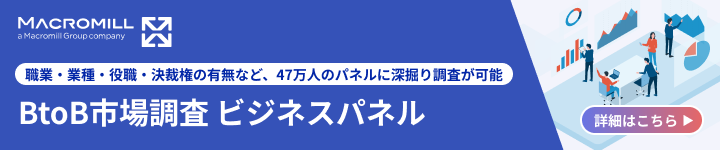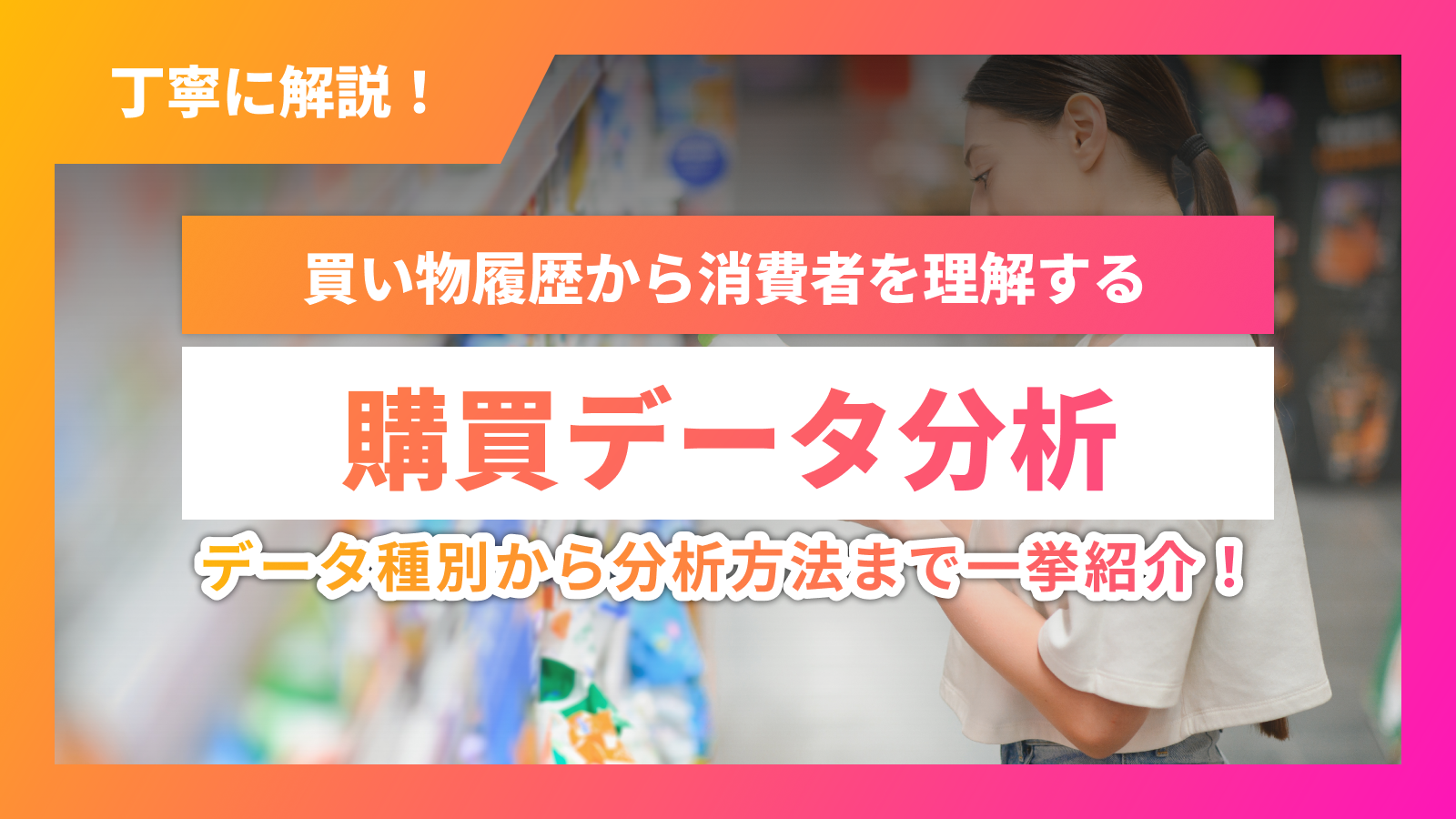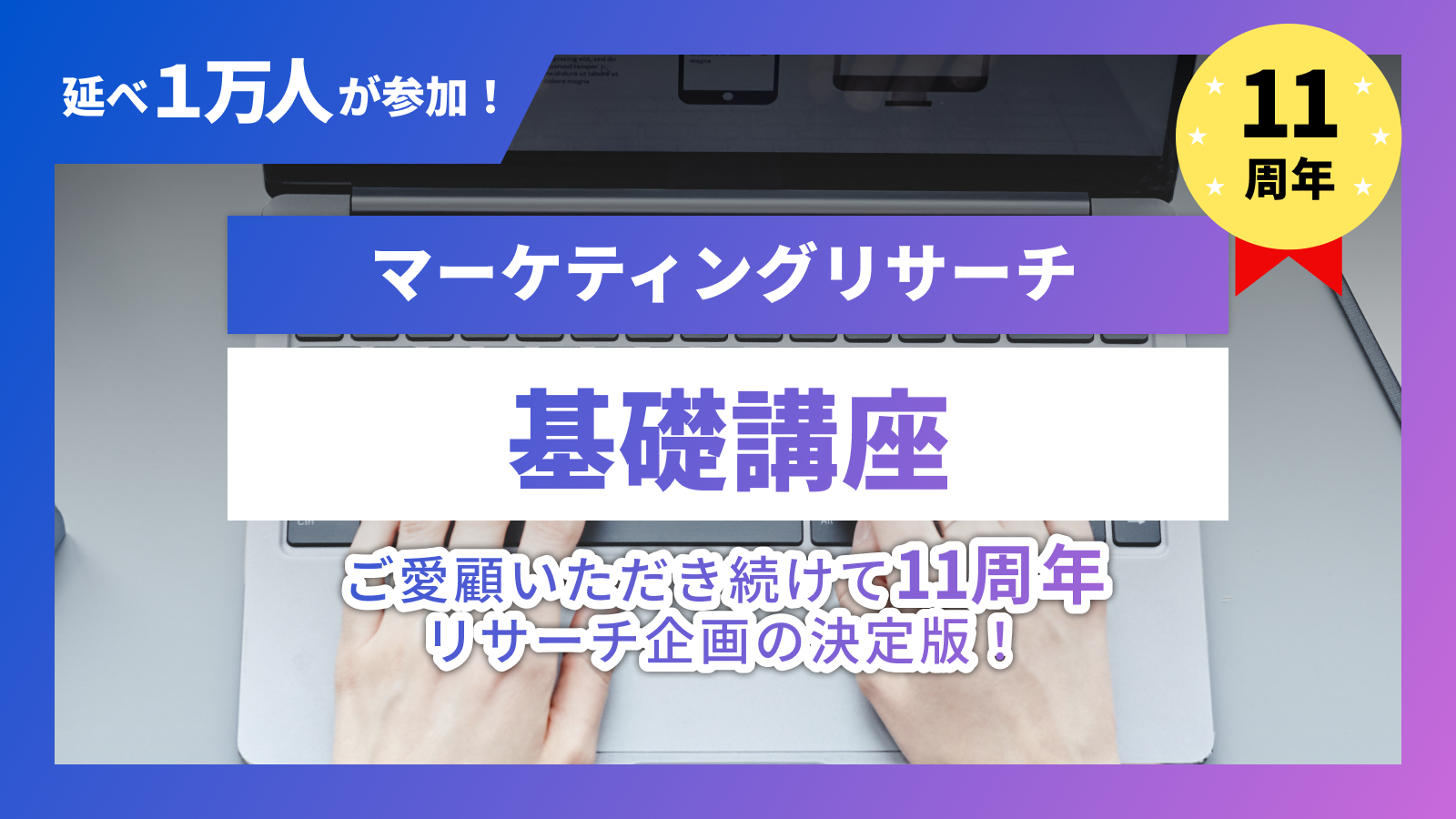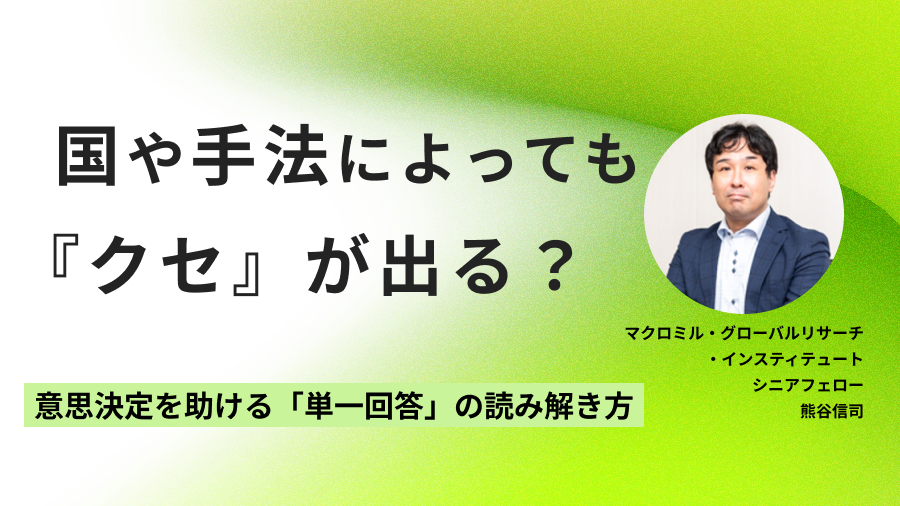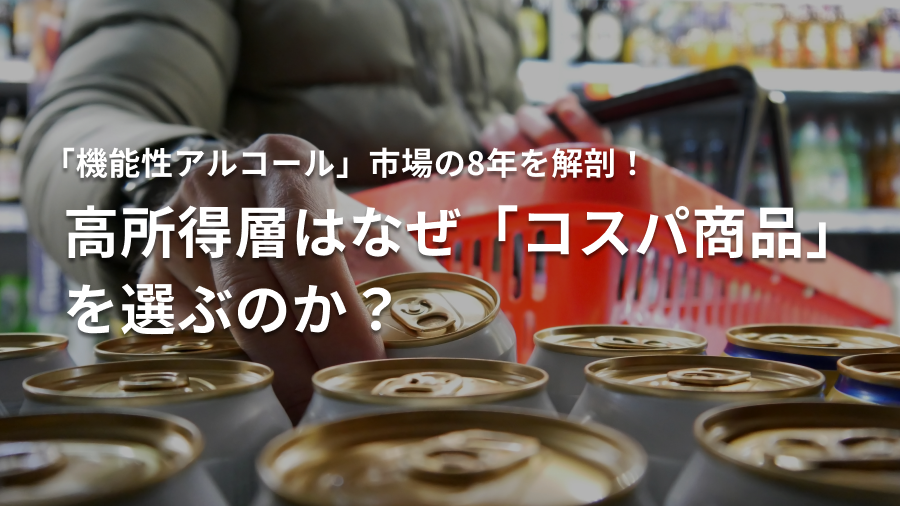スコアリングとは?BtoBマーケティングにおける定義・設計方法・活用事例を徹底解説
公開日:2025/8/1(金)
営業が「この人は熱い!」と感じてアプローチしてみたら、まったく商談にならなかった。
一方で、特に注目していなかったリードが、競合に奪われていた――。
こうした“機会損失”は、営業とマーケティングの間で日常的に起こっています。原因のひとつは、見込み客(リード)の「温度感」や「購買意欲」が、属人的な判断に委ねられていることです。
そこで登場するのが「スコアリング」です。
スコアリングとは、見込み客の行動や属性に点数を付けて定量的に評価し、商談化や受注の確度を見える化する手法です。スコアが高いリードほど購買意欲が高く、営業が優先的にアプローチすべき対象として浮かび上がります。
本コラムでは、B2Bマーケティングにおけるスコアリングの定義、設計の考え方、成功のコツ、代表的なツール、運用の課題、成功事例までを包括的に解説していきます。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
- スコアリングとは何か?その定義と役割
- なぜB2Bにスコアリングが必要なのか?
- スコアリングの2大軸:属性スコアと行動スコア
- スコアリング設計のステップと考え方
- 活用シナリオ:スコアに応じたマーケティングと営業アクション
- スコアリング運用の落とし穴と改善策
- 代表的なツール(MA・SFA・CRM)との連携方法
- 成功事例から見る、スコアリングの効果と成果
- まとめ:見えない熱意を、見える行動に変える
スコアリングとは何か?その定義と役割
スコアリングとは、リード(見込み客)の購買確度や関心度を、定量的な数値として可視化する手法です。マーケティングオートメーション(MA)やCRMなどのシステムを用いて、リードの属性や行動に対して点数を付け、累積スコアに応じて営業アクションの優先順位を判断します。
たとえば:
- メールを開封したら+5点
- 資料をダウンロードしたら+10点
- 価格ページを閲覧したら+20点
- 役職が“部長”以上なら+15点
このように、あらかじめルール化した基準に従って加点・減点を行い、「ホットなリード」「まだ検討段階のリード」などを数値で分類していきます。
目的は明確です。「営業が今アプローチすべき相手を見つけやすくする」こと。そして、「マーケティングの成果を営業につなげるパス精度を高める」ことです。
なぜB2Bにスコアリングが必要なのか?
B2Bのマーケティング・営業活動において、スコアリングが重要視される背景には、いくつかの構造的な要因があります。
購買プロセスが長く、関与者が多い
B2Bでは、購入までの意思決定が複雑です。検討期間が数か月〜1年に及ぶことも珍しくなく、担当者・上長・経営層など複数人が関与するのが一般的です。そのため、「いますぐ買いたい人」ばかりをターゲットにするのではなく、「育てれば買うかもしれない人」を見極めて継続的にアプローチする必要があります。
営業リソースには限界がある
すべてのリードに営業が手間をかけることは現実的ではありません。スコアリングによって「商談化しやすいリード」「今はまだ育成すべきリード」を分類することで、営業効率を最大化できます。
マーケと営業の連携をスムーズにする
スコアリングは、マーケティングがどのような基準でMQL(Marketing Qualified Lead)を判断しているかを“見える化”する手段でもあります。共通言語を持つことで、営業との信頼関係が深まり、リードパスの精度が高まります。
スコアリングの2大軸:属性スコアと行動スコア
スコアリングは、大きく分けて「属性スコア」と「行動スコア」の2つの軸で構成されます。これらを組み合わせることで、リードの“質”と“温度感”の両方を判断できます。
属性スコア
リードが自社にとって「顧客になりやすい条件を満たしているか」を評価します。
例:
- 業種がターゲット業界である:+10点
- 役職が課長以上:+20点
- 企業規模が年商10億円以上:+10点
- 関東エリアに所在:+5点
これにより、「関心は高くてもそもそも商材に合わない相手」を見極めることができます。
行動スコア
リードがどれくらい興味を持っているか、どの段階にいるかを測る指標です。
例:
- メール開封:+5点
- 資料DL:+15点
- 価格ページの閲覧:+25点
- セミナー参加:+30点
- お問い合わせフォーム入力:+50点
行動スコアは「今この瞬間に熱量があるかどうか」を把握できるため、営業タイミングの判断材料として非常に有効です。
スコアリング設計のステップと考え方
スコアリングは設計次第で成果が大きく変わります。ここでは、基本的な設計ステップを紹介します。
STEP1:スコアリングの目的を明確にする
例:
- MQLの質を高めたい
- 営業に渡すタイミングを最適化したい
- 商談化率の高いパターンを可視化したい
目的によってスコアの重みや評価指標が変わるため、まずはゴールを明確にします。
STEP2:商談化しやすい行動・属性を洗い出す
過去に受注した案件の特徴を分析し、「どんな行動・属性を持っていたか」を抽出します。Google Analytics、MAツール、営業ログなどをもとに、勝ちパターンをデータで整理します。
STEP3:加点・減点ルールを定義する
行動や属性に点数を設定し、一定の基準で加減点します。
例:
- 製品紹介ページの閲覧:+10点
- ホワイトペーパーDL:+15点
- メール配信からの未開封が続く:−10点
- メール配信停止:−50点
STEP4:スコア別の営業アクションを定義する
スコアに応じて対応の優先度を変えるルールを設けます。
例:
- 80点以上:インサイドセールスが即時対応
- 50〜79点:ナーチャリング継続
- 〜49点:一時保留または再スコアリング対象
このように、「判断基準としてのスコア」だけでなく、「次の行動につながるスコア」にすることが肝要です。
活用シナリオ:スコアに応じたマーケティングと営業アクション
スコアリングの真価は、“得点そのもの”ではなく、「その情報をどう活用して行動に結びつけるか」にあります。以下では、スコアに応じてどのようなアクションが取れるのか、典型的なシナリオをご紹介します。
高スコア(例:80点以上)→ 営業即時対応
購買意欲が高いと判断されるリードには、インサイドセールスや営業が即座にアプローチを行います。この際、以下のような準備をすると成功率が高まります:
- 事前にWeb閲覧履歴を確認(関心テーマの把握)
- 開封されたメール内容を把握(どのコンテンツに興味があるか)
- ダウンロード済みの資料をもとに話題を展開
中スコア(50〜79点)→ ナーチャリング継続
この層は興味はあるものの、まだ導入には至らない“検討中”の段階です。主な対応としては:
- セミナーへの再招待
- 専門家インタビューや比較資料のメール配信
- 動画コンテンツや事例集などで解像度を上げる
スコアを見ながらタイミングを見計らい、ホット化を促進します。
低スコア(〜49点)→ 保留またはライトタッチフォロー
関心が低いか、ターゲットとして適合していない可能性があります。ただし、業界やテーマによっては将来性のある層であることも。
- メールマガジンへの登録継続
- トレンド解説など間接的に価値提供できるコンテンツの配信
- スコアが一定期間動かない場合は再スコアリングへ
スコアリング運用の落とし穴と改善策
スコアリングは強力な武器になる一方、設計や運用に課題があると“使われない仕組み”になってしまいます。ここでは、よくある失敗とその対策を整理します。
スコア設計が曖昧すぎる
「なんとなく加点している」「重みが属人的」といった状態では、営業が信頼しなくなります。
<改善策>:
過去の商談化リードを分析し、再現性のある行動・属性に基づいてスコアを設計しましょう。営業と定期的にレビューする場を設け、実態とのギャップを埋めていくことが重要です。
ツール内で完結しすぎていて営業が見ていない
スコアが可視化されていても、営業が活用していなければ意味がありません。
<改善策>:
SFAやSlack、メール通知など、営業の使っているツールに“見える形”で情報を流す設計がポイントです。たとえば、「スコア90点超のリードが出現したら通知を飛ばす」といった運用を組みましょう。
高スコアなのに商談化しないパターンが多い
特定の行動にスコアを付けすぎている場合、実態と乖離した“過剰評価”が発生します。
<改善策>:
スコアリングは“設計して終わり”ではなく、“運用しながら磨く”ものです。失注パターンや無反応パターンの分析を通じて、重み付けを定期的に見直しましょう。
代表的なツール(MA・SFA・CRM)との連携方法
スコアリングの設計や運用は、ツールによって実現されます。以下は代表的なMA、SFA、CRMの役割とスコアリングとの関係です。
MA(マーケティングオートメーション)
- リードの行動履歴(メール開封、資料DL、Web閲覧など)を記録
- スコアリングルールを設定・自動化
- 営業へのアラートや通知も可能
例:Marketo、Pardot、HubSpot、SATORIなど
SFA(セールスフォースオートメーション)
- 営業担当者が進捗管理・対応履歴を記録
- MAから送られてきたスコアを参照し、優先順位を判断
- 商談ステージやクロージング状況と連携できる
例:Salesforce、kintone、Zohoなど
CRM(顧客関係管理)
- 顧客の属性、購買履歴、サポート履歴などを一元管理
- MAやSFAと連携して360度の顧客理解を可能にする
- 顧客ランクやLTVを基にスコアリングと併用できる
例:Salesforce、HubSpot CRM、Sansanなど
連携のポイントは、「どのツールに情報を集約し、どの部門が何を見て行動するか」を明確に設計することです。
成功事例から見る、スコアリングの効果と成果
実際にスコアリングを導入し、成果につなげている企業にはいくつかの共通点があります。それは、ツールを導入したことよりも、「活用の仕方」にこだわっているという点です。ここでは代表的な成功事例を紹介しながら、スコアリングの効果を具体的に見ていきましょう。
事例①:SaaS企業A社 – 営業対応スピードが2倍に、商談化率1.8倍
リード数が増えすぎて営業が追いきれなくなっていたA社は、行動スコアリングを導入し、スコア80点以上のホットリードのみを営業にパスする仕組みを構築。
結果、営業1人あたりの対応件数は半減したが、商談化率は1.8倍に。営業は「確度の高いリードに集中できる」ようになり、提案の質も向上した。
事例②:BtoBメディア運営B社 – スコア×セグメントでメール開封率が3倍に
B社では、リード全体に一斉送信していたメルマガを、スコアに応じてコンテンツを出し分ける設計に変更。
たとえば、価格ページ閲覧者(スコア70点以上)には導入事例を送信し、ホワイトペーパー未読者(スコア30点未満)には業界動向レポートを送信。
結果、メール開封率は従来の8%から24%へと3倍に跳ね上がった。
事例③:ITベンダーC社 – MA×CRM連携で受注単価が30%向上
C社は、過去に営業失注したリードに対してもスコアを継続蓄積し、「再関心化したタイミング」で営業がアプローチできる仕組みをMAとCRMで連携構築。
再アプローチ成功率が高まり、受注単価も平均より30%高い結果に。「見込み客の興味は消えたのではなく、眠っていただけだった」と担当者は語る。
【課題別に整理したアプローチ方法の資料を公開中!】
B2Bマーケティングのプロセスガイドを詳しく見る>
まとめ:見えない熱意を、見える行動に変える
スコアリングとは、単なる数字遊びではありません。
それは、見込み客の“興味の温度”という本来は見えにくい要素を、定量的に把握し、ビジネスの意思決定やアクションに結びつけるための強力な仕組みです。
- マーケティングは、誰に情報を届け、どう育てるかを見極め
- インサイドセールスは、確度の高いリードを選別し
- 営業は、商談の可能性が高い相手に集中できる
こうした全体最適を可能にする“共通言語”こそが、スコアリングです。
リードが増えることは嬉しい一方で、「誰に、いつ、どうアプローチするか」の判断が曖昧なままでは、機会損失も増えていきます。
スコアリングは、その曖昧さを取り除き、「見込み客の行動データに基づいた意思決定」を可能にします。
未来の顧客は、すでにあなたのWebサイトやメールの中にいるかもしれません。
その“気配”を捉える仕組みとして、スコアリングはBtoBマーケティングの中核となる考え方なのです。
著者の紹介
株式会社マクロミル マーケティング部門ユニット長
橘 亮介
コーポレート及びプロダクトマーケティングのマネジメントを管掌。2015年からインサイドセールスの企画設計/KPI管理、KPIマネジメント、イベントマーケティング、WEBマーケティング、コンテンツ企画、MA導入・運用やインフルエンサー活用など、幅広い領域を経験後、2022年以降はマネジャーとしてマーケティングROIの管理や組織設計、全社マーケティング設計に従事。
BtoB市場調査は
マクロミルのビジネスパネル